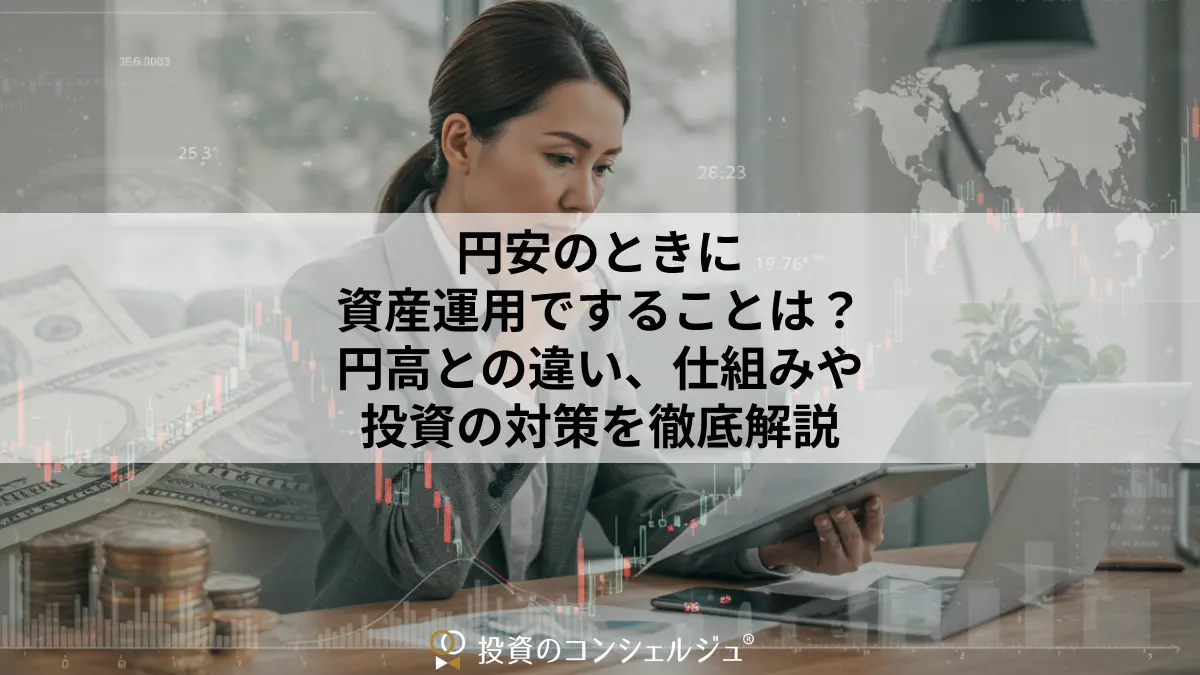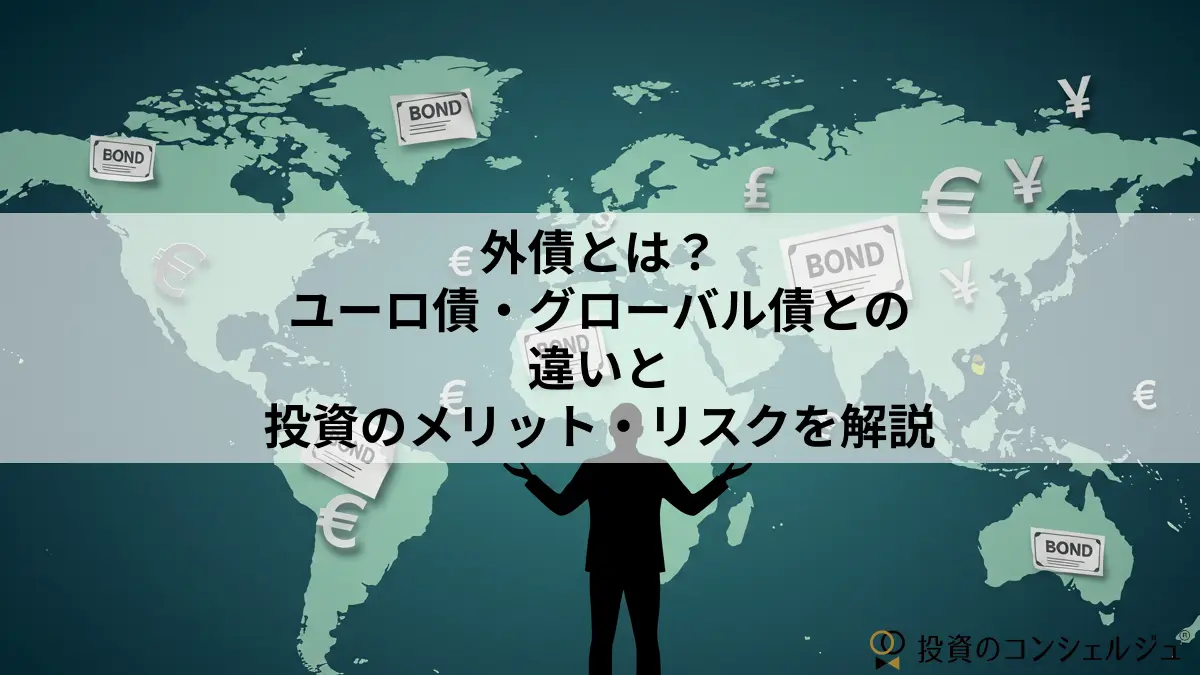為替ヘッジとは?仕組みやあり・なしの違いやメリット・デメリットを徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.08.01
更新:
2025.08.01
外国株式や外貨建て債券への投資を検討する際、避けて通れないのが為替変動リスクです。特に最近は日米金利差の影響で為替相場が大きく変動しており、将来的な円高や円安の影響を不安視する声も増えています。そこで注目されるのが為替ヘッジですが、「そもそも為替ヘッジとは?」「どんな仕組みでリスクを抑えるのか?」「コストやデメリットは?」という疑問も尽きません。本記事では、為替ヘッジの基本的な仕組みから実際に必要なコスト、メリット・デメリットまでを具体的に解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、為替ヘッジの基本的な仕組みである「為替予約」の意味と、為替リスクをどのように抑えるのかが具体例で理解できます。さらに、日米金利差が影響するヘッジコストの考え方や、円高・円安それぞれの局面でのメリット・デメリットまで整理でき、あなた自身の投資スタイルやリスク許容度に合った「ヘッジあり/なし」の判断基準が明確になります。海外資産への投資判断を一歩前に進めるための知識が得られます。
為替ヘッジとは?為替変動リスクから資産を守るための仕組み
海外資産に投資する際、避けて通れないのが為替変動リスクです。為替ヘッジは、このリスクを抑えて資産価値を安定させるための防御策。ここでは、為替ヘッジの基本的な仕組みや目的を説明します。
「将来の為替レートを予約する」のが為替ヘッジの仕組み
為替ヘッジとは、為替レートが変動することによる損失リスクを避ける(ヘッジする)ための手法です。
海外の株式や債券など、外貨建ての資産に投資していると、円高が進むだけで資産の円換算価値は目減りしてしまいます。為替ヘッジは、こうした為替変動による資産価値のブレを小さくする目的で行われます。
最も代表的な方法は「為替予約」です。これは「将来の特定の日に、あらかじめ決めた為替レートで外貨を円に交換する」と約束する取引を指します。例えば「1年後に1ドル=140円で交換する」と予約しておけば、実際に円高が進んで1ドル130円になったとしても、約束した140円で交換できるため資産価値の下落を防げます。
このように、将来の為替レートを固定することで、為替変動のリスクを抑えるのが為替ヘッジの基本的な仕組みです。
なぜヘッジする?目的は「リターンの安定化」と「円高への備え」
為替ヘッジの最大の目的は、為替の動きに左右されず、安定した投資成果を目指すことです。
外貨建て資産の価値は為替レートで大きく変動します。資産そのものが値上がりしても、円高になれば利益が減ったり、元本割れしたりする可能性があります。為替ヘッジは、こうした円高による資産価値の目減りを防ぐための有効な手段です。投資家は為替の動きを過度に心配せず、投資対象そのものの分析に集中できるというメリットもあります。
ただし、重要な注意点もあります。為替ヘッジは円高リスクを抑える一方、円安が進んだ場合に得られるはずだった利益(為替差益)も放棄することになります。リスクを抑える代わりに、大きなリターンも狙えなくなるトレードオフの関係にあるのです。
なぜ為替ヘッジは必要?知らないと損する「為替変動リスク」とは
海外資産への投資では、資産自体の値動きだけでなく、円高・円安といった為替の動きがリターンを大きく左右します。これが「為替変動リスク」です。ここでは、為替変動が資産価値にどう影響するのか、そしてなぜヘッジが必要になるのかを解説します。
為替ヘッジを使うメリットや注意点は以下Q&Aでも説明しています。
為替変動リスクとは?円高なら資産が目減り、円安なら利益増と、為替がリターンを左右
日本の投資家が外国資産に投資する場合、リターンは「資産自体の値動き」と「為替の動き」という2つの要因で決まります。この為替の動きによる円換算評価額のブレが「為替変動リスク」です。
例えば、1ドル140円の時に100ドル(14万円)の米国資産に投資したとします。1年後、資産のドル価格が変わらなくても、為替レートが1ドル130円の円高になれば資産は13万円に減ってしまいます。逆に1ドル150円の円安になれば15万円に増えるのです。
このように、為替の動きだけで損益が発生します。実際に2022年には急激な円安が進み、為替ヘッジをしていなかった投資では、資産の値上がりに加えて大きな為替差益が得られ、リターンが飛躍的に向上しました。
為替変動リスクの影響については以下Q&Aでも説明しています。
為替ヘッジはリスクの振れ幅を抑える「防御策」
しかし、円安が利益をもたらす一方、円高に振れれば逆効果となります。先の2022年の例でも、その後の円高局面では、資産の利益が為替差損で打ち消されるケースがありました。為替変動リスクは、リターンを増やすことも減らすこともある「両刃の剣」なのです。
このリスクに対処する方法が為替ヘッジです。為替ヘッジを行えば、円高や円安による評価額の変動幅を小さく抑え、リターンを安定させることができます。
円高による損失を防ぎたい場合はヘッジが有効です。ただし、ヘッジをすると円安による利益も得られなくなります。この「ヘッジあり」と「ヘッジなし」の違いを理解することが、為替リスクを考える上での基本です。
為替ヘッジの仕組みとコストを解説!なぜ費用がかかるのか?
為替ヘッジは為替変動リスクを緩和する安心材料ですが、実はコストがかかります。その費用の正体は、日本と投資先国との「金利差」。ここでは、為替ヘッジの基本的な仕組みから、なぜコストが発生するのか、そして投資信託ではどのように反映されるのかを、分かりやすく解説します。
主な仕組みは「為替予約」:将来の交換レートを現時点で固定する取引
為替ヘッジで最も一般的に使われるのが「為替予約」という手法です。これは、将来の交換レートを現時点で約束する取引で、銀行などと行います。
例えば「1年後に1ドル=140円で交換する」と契約すれば、将来円高になっても資産価値の下落を抑えられます。これは、外貨資産を持つと同時に、将来その外貨を売る(円を買う)予約をすることで、受け取る円の額を固定するイメージです。
個人投資家がこの取引を直接行うのは難しいため、通常は「為替ヘッジあり」の投資信託を選びます。投資信託なら、運用会社が投資家に代わってヘッジ取引を行ってくれるため、手軽にヘッジの効果を得られます。
ヘッジコストの正体は「金利差」:自分でできる計算方法も紹介
為替ヘッジには「ヘッジコスト」という費用がかかります。このコストの正体は、日本と投資先国との「短期金利の差」です。
例えば、日本より金利の高い米ドル資産に投資する場合、その金利差がコストとして発生します。逆に、投資先の金利が日本より低ければ、金利差が収益(ヘッジプレミアム)になることもあります。しかし、現在の日本の低金利状況を考えると、海外資産への投資では基本的にコストが発生すると理解しておきましょう。
なぜ金利差がコストになるのか?
為替予約のレートは、現在の為替レートに両国の金利差を反映して決まります。金利の高い通貨を売って金利の低い円を買うヘッジ取引では、金利差の分だけ将来の交換レートが不利(円高方向)に設定されます。この不利になった差額が、実質的なヘッジコストになるのです。
2025年8月現在、米国は利下げ局面にありますが、日本の金利も依然として低水準なため、日米の金利差は大きいままです。この金利差が、ドル円のヘッジコストが年率数パーセントと高止まりする要因となっています。
仮に米国債券の利回りが年4.5%でも、ヘッジコストが年3.5%かかると、実質的なリターンは年1.0%まで低下してしまいます。ヘッジコストが高いと、せっかくの利息収入がほとんど相殺されてしまう点には注意が必要です。
ヘッジコストはいつ、どのように引かれるのか?
このヘッジコストは、手数料として別途請求されるわけではありません。為替予約の決済レートを調整する形で、投資信託の基準価額に間接的に反映されます。
具体的には、ヘッジコスト分が日々、信託財産から差し引かれるイメージです。そのため、コストが高いほど基準価額の伸びが抑えられます。ヘッジコストは各国の金利情勢で変動するため、投資対象国と日本の金利動向に注目しておくとよいでしょう。
為替ヘッジのメリット・デメリット
為替ヘッジは円高リスクを抑える強力な手段ですが、万能ではありません。リターンが安定する大きなメリットがある一方、コスト負担や円安時の利益を逃すといったデメリットも。ここでは、ヘッジの光と影を具体的に解説し、賢い選択をサポートします。
為替ヘッジのメリット:為替変動を気にせず安定運用できる
為替ヘッジ最大のメリットは、為替の動きに一喜一憂せず、落ち着いて資産運用に取り組める点です。円高による資産の目減りを防ぎ、投資先の分析に集中できるため、特に安定志向の投資家にとって大きな安心材料となるでしょう。
メリット1:為替変動によるリターンのブレを抑えられる
ヘッジをすると、円高や円安による損益のブレを小さくできます。為替相場の影響が限定的になるため、リターンは主に投資対象の資産価格(株価など)で決まります。結果として運用が安定し、特に急激な円高による資産価値の目減りを防げる点は大きな利点です。
メリット2:為替を気にせず投資判断に集中できる
為替ヘッジをしていれば、投資判断の際に為替相場の行方を過度に考慮する必要がなくなります。外国の株式市場や債券市場の分析といった、投資先本来の価値判断に集中できるため、初心者にとっても分かりやすい運用が可能です。
為替ヘッジのデメリット:コスト負担と円安時の機会損失
一方で、為替ヘッジには無視できないデメリットも存在します。ヘッジにはコストがかかるためリターンが圧迫されるほか、もし円安が進んだ場合には、得られたはずの為替差益を逃す「機会損失」が発生する点には注意が必要です。
デメリット1:ヘッジコストでリターンが目減りする
最大のデメリットは、ヘッジコストの負担によって運用成績が下がってしまう点です。ヘッジありの投資信託では、ヘッジなしに比べてコスト分だけリターンが差し引かれます。特に、日本と投資先国との金利差が大きい局面ではコストが高くなるため注意が必要です。
デメリット2:円安による為替差益を逃してしまう
ヘッジをする場合、円安による為替差益を得ることができません。投資期間中に大幅な円安が進んだとしても、ヘッジによって為替変動の影響を遮断しているため、その恩恵は受けられません。これは、ヘッジなしなら得られたはずの利益を逃す「機会損失」となります。
結局どっちがいい?「あり」「なし」の使い分け方
結局のところ、為替ヘッジありは「コストを払い、円安メリットを諦める代わりに、為替リスクを避けて安定性を取る」戦略です。一方、ヘッジなしは「円高リスクを背負う代わりに、コストをかけず円安メリットを狙う」戦略と言えます。
どちらが有利かは、その時々の相場環境によって変わります。例えば、円高が進んだ局面ではヘッジありが有利ですが、長期的な円安トレンドではヘッジなしの方が高い成績を上げることも珍しくありません。
そのため、直近の成績が良いからという理由だけで選ぶのは危険です。過去の実績を見る際は、その背景にある為替の動きを理解し、今後の見通しと照らし合わせて判断することが重要です。
為替ヘッジ「あり・なし」はどっちがいい?3つの判断基準
ヘッジの「あり」と「なし」、どちらを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。絶対的な正解はありませんが、自分に合った選択はできます。ここでは「投資期間」「リスク許容度」「為替相場の見通し」という3つの判断基準から、最適な選択を導き出す方法を解説します。
為替ヘッジあり・なしの違いの実例は以下記事でグローバルAIファンドをテーマに解説しています。
判断基準1.投資期間:長期なら「ヘッジなし」、短期なら「ヘッジあり」が基本
短期的な運用では、ヘッジありで円高リスクを抑えるのが安心です。例えば1年以内に使う予定の資金なら、期間中の価格安定を優先すべきでしょう。短期間ならヘッジコストが大きく積み上がる心配も少ないです。
逆に長期投資では、コストをかけないヘッジなしも有力な選択肢です。長い目で見れば為替レートの変動はプラスにもマイナスにも働くため、為替リスクも込みでリターンを狙う戦略が考えられます。ただし、投資先の金利が極端に高い場合は、長期でもヘッジコストがリターンを大きく圧迫する点には注意しましょう。
判断基準2.リスク許容度:安定志向なら「ヘッジあり」、積極志向なら「なし」
為替変動による資産のブレをどれだけ許容できるかも重要な判断基準です。「元本割れは避けたい」「安定的に運用したい」という方は、コストを払ってでもヘッジありでリスクを抑えるのが合理的です。
一方で、「多少の変動は気にしないからリターンを最大化したい」という積極的な方は、ヘッジなしで為替差益を狙う選択が向いています。ご自身の性格に合わせて、安定志向ならヘッジあり、積極志向ならヘッジなし、と方針を決めましょう。
判断基準3.為替相場の見通し:円高を予想するなら「ヘッジあり」が有効
今後の為替動向をどう予想するかも判断材料になります。「これから円高が進みそうだ」と考えるなら、ヘッジありで資産価値の目減りを防ぐのが理にかなっています。
逆に「円安が続くだろう」と思うなら、ヘッジなしで為替差益を狙うのが有効な戦略です。もちろん、為替の予想はプロでも難しいものですが、自分なりの相場観があるなら、それに沿って選択する価値は十分にあります。
投資信託で為替ヘッジを選ぶ方法:ファンド名の見分け方と購入時の注意点
為替ヘッジの方針が決まったら、次はいよいよ投資信託選びです。NISAなどで商品を選ぶ際、どうすれば「ヘッジあり」「なし」を間違えずに選べるのでしょうか?ここでは、ファンド名の見分け方から購入時の注意点まで、具体的な手順を解説します。
ファンド名と目論見書で「ヘッジの有無」を確認する方法
投資信託でヘッジの有無を選ぶには、まずファンド名を確認するのが基本です。ヘッジを行うファンドには、名称に「為替ヘッジあり」や「(Hあり)」などと明記されています。逆に、名称に何も記載がなければ「ヘッジなし」であることが一般的です。
購入前には、必ず目論見書(投資信託の説明書)にも目を通しましょう。目論見書では、より正確なヘッジ方針を確認できます。例えば、資産の全てをヘッジするのか、一部のみを対象とする「部分ヘッジ」なのかといった詳細も記載されています。
これらの情報は、証券会社のウェブサイトや取引画面でも分かりやすく表示されていることが多いので、ご自身の考えに合った商品か、間違えずに選択するよう注意してください。
ファンド選びではコストとリターンの総合的な比較を
ファンドを選ぶ際は、過去の価格推移や利回りを比較するのも参考になります。その際、為替ヘッジの有無がリターンにどう影響したかを考えることが重要です。
また、ヘッジコストの影響度は資産クラスによっても異なります。例えば、元々の利回りが低い債券ファンドではコストの影響が大きくなりがちです。一方で、値動きの大きい株式ファンドでは、為替の要因が相対的に小さくなることもあります。こうした特性も踏まえ、総合的に判断しましょう。
この記事のまとめ
為替ヘッジは、海外資産を円高リスクから守るための有効な手段ですが、ヘッジコストが発生するため、必ずしもメリットばかりではありません。円高への不安が強く短期的にリスクを抑えたい場合はヘッジあり、長期で投資し、円安メリットを享受したい場合はヘッジなしという考え方が一般的です。投資判断に際しては、現在の金利差によるヘッジコストを正確に把握し、自分の投資期間やリスクへの考え方と照らして適切な選択をしましょう。迷う場合は専門家への相談も有効です。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
為替ヘッジ
為替ヘッジとは、為替取引をする際に、将来交換する為替レートをあらかじめ予約しておくことによって、為替変動のリスクを抑える仕組み。海外の株や債券に投資する際は、その株や債券の価値が下がるリスクだけでなく、為替の変動により円に換算した時の価値が下がるリスクも負うことになるので、後者のリスクを抑えるために為替ヘッジが行われる。
為替予約(フォワード契約)
為替予約(フォワード契約)とは、将来の特定の日に、あらかじめ取り決めた為替レートで外貨を売買することを約束する契約のことをいいます。主に企業が海外との取引に伴う為替変動リスクを避けるために利用する手段で、たとえば半年後に100万ドルの支払いがある場合、今のレートでその取引を予約しておくことで、将来の円安・円高にかかわらず、支払い額を固定することができます。このように、為替予約は外貨建て取引の金額をあらかじめ確定させることで、収支やコストの見通しを安定させる効果があります。一方で、為替の変動によって有利になる可能性も同時に放棄するため、リスク回避を重視する際に選ばれる手法です。資産運用や国際ビジネスにおける重要なリスク管理の一環として広く利用されています。
ヘッジコスト
ヘッジコストとは、為替や金利などの市場変動リスクを抑えるために先物取引やスワップ取引などでポジションを置き換える際に発生する費用の総称です。たとえば外貨建て資産を円で評価する投資家が為替リスクを避けるために為替ヘッジをかける場合、将来の円・外貨交換レートを予約する代わりに金利差や手数料に基づくコストが発生します。 このコストは通貨間の金利差が大きいほど高くなり、投資収益の差し引き後リターンに直接影響します。資産運用の成果を正しく評価するには、表面的な収益だけでなくヘッジコストを加味してネットリターンを把握することが大切です。
ヘッジプレミアム
ヘッジプレミアムとは、為替リスクなどのリスクを避けるために行うヘッジ取引において、投資家が追加で支払うコストや、逆に受け取れる利益のことを指します。たとえば、外国の資産に投資するときには、為替レートの変動によって損失を被る可能性があります。そのリスクを避けるために通貨の先物取引などを使ってヘッジを行うと、ヘッジのコストが発生する場合があります。これが「ヘッジプレミアム」です。場合によっては、逆にヘッジを行うことでプラスのリターンが得られることもあり、その差益もヘッジプレミアムと呼ばれます。通貨の金利差や市場の需給によって変動するため、投資の戦略を立てる際には注意が必要です。
円高
円高とは、ほかの国の通貨と比べて相対的に日本の円の価値が高くなること。海外から商品を購入すること(輸入)が有利で、海外に商品を販売すること(輸出)が不利になる。 (例) 1ドル=100円が1ドル=50円になる →以前よりも少ない円で1ドルを得ることができるので、円の価値が高くなっており、円高である。
円安
円安とは、ほかの国の通貨と比べて相対的に日本の円の価値が低くなること。海外から商品を購入すること(輸入)が不利で、海外に商品を販売すること(輸出)が有利になる。 (例) 1ドル=100円が1ドル=150円になる →以前よりもたくさんの円がないと1ドルを得られなくなっており、円の価値が低くなっているので、円安である。
為替差損益
為替差損益とは、外貨建ての資産を日本円に換算する際に生じる為替レートの変動による損益を指します。たとえば、1ドル=130円のときに米ドルで資産を購入し、売却時に1ドル=140円で円に戻した場合、為替差によって10円分の為替差益が発生します。逆に、売却時に円高が進行し1ドル=120円になっていれば、10円分の差損が発生することになります。この為替差損益は、外国株式、外貨建て投資信託、外債、外貨預金など、外貨を用いた資産運用において常に発生し得る重要なリスク要因です。 資産の値動きが堅調であっても、為替相場の変動によって最終的な円ベースのリターンが目減りすることがあるため、投資判断の際には為替リスクも含めて総合的に考慮する必要があります。たとえば、円安が進行すれば円換算での評価額は増えますが、円高になれば逆に資産価値は減少します。為替差損益は、こうした為替変動を通じて投資成果に直接的な影響を与える存在であり、為替動向の把握や資産配分の調整、ヘッジ戦略の活用などが求められます。 NISA口座での運用においても為替差損益は無視できません。NISAでは、外国株式や外貨建て投資信託の売却益が非課税となるため、為替差益も含めた全体の売却益が非課税対象となります。つまり、為替差によるプラスのリターンも税金がかからずそのまま受け取れるというメリットがあります。ただし、逆に為替差損が発生しても、それを他の利益と損益通算したり、繰り越して控除することはできません。NISAでは損失の税務活用ができないため、為替リスクを取る際は慎重な判断が必要です。 税務や会計上では、為替差損益には「実現損益」と「評価損益」があります。実現損益とは、外貨建て資産を実際に売却し円に換えた際に確定する損益であり、通常の課税対象となります。一方、評価損益とは、保有中の外貨建て資産を期末などに円換算した際に一時的に生じる為替差損益であり、個人投資家の場合、課税対象にはなりません。法人ではこの評価損益を会計上反映させるケースもありますが、個人の確定申告ではあくまで実現ベースでの損益が対象です。 このように、為替差損益は資産運用における見落としがちなリスク要素でありながら、運用成果に与えるインパクトは決して小さくありません。為替相場の予測は困難であるため、為替ヘッジ付き商品の活用や、複数通貨への分散投資、円建て資産とのバランス調整などを通じて、想定外の為替変動にも対応できる設計が望まれます。投資判断を行う際には、表面的なリターンだけでなく、その背後にある通貨変動の影響にも目を向けることが重要です。
投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。運用によって得られた成果は、各投資家の投資額に応じて分配される仕組みとなっています。 この商品の特徴は、少額から始められることと分散投資の効果が得やすい点にあります。ただし、運用管理に必要な信託報酬や購入時手数料などのコストが発生することにも注意が必要です。また、投資信託ごとに運用方針やリスクの水準が異なり、運用の専門家がその方針に基づいて投資先を選定し、資金を運用していきます。
基準価額
基準価額とは、主に投資信託の商品価格を表すもので、投資信託1口あたりの価値を示しています。毎営業日に一度計算され、投資信託が保有している株式や債券などの資産の時価総額から、運用にかかる費用を差し引いた金額を、発行済みの総口数で割って算出されます。 投資信託の購入や売却の際には、この基準価額が参考になりますので、価格の動きに注目することが大切です。ただし、基準価額は市場価格とは異なり、リアルタイムで変動するわけではないため、翌営業日の価格になることが多い点にもご注意ください。
目論見書(プロスペクタス)
目論見書(プロスペクタス)とは、株式や債券などの金融商品を発行する際に、その内容やリスク、資金の使い道などを詳しく説明するための書類のことをいいます。これは、投資家が商品について正しく理解し、投資判断を行うための重要な資料です。目論見書には、発行体の財務情報、事業内容、募集する金額、利回りや償還期間などが記載されており、金融商品取引法に基づいて作成されます。投資初心者にとっては、少し専門的で読みづらく感じるかもしれませんが、購入する前にリスクや条件を確認するためにとても大切な情報源となります。
金利差
金利差とは、異なる国や通貨、あるいは異なる金融商品の間で適用される金利の違いを指す言葉です。たとえば、日本の金利が0.1%でアメリカの金利が5.0%であれば、その差である4.9%が金利差になります。この金利差は、為替相場や資産運用の判断に大きな影響を与えます。 たとえば、金利の高い国に投資すればより多くの利息が得られるため、資金がその国に集まりやすくなり、通貨が高くなる傾向があります。一方で、為替リスクや経済状況の違いにも注意が必要です。個人投資家にとっては、外貨建て預金や外国債券などの運用で金利差が収益に直結するため、しっかり理解しておくことが重要です。
機会損失
機会損失とは、ある選択をしたことによって、別の選択肢で得られたはずの利益を失うことを指します。例えば、低金利の預金に資金を預けている間に、高利回りの投資商品で運用する機会を逃す場合などが該当します。資産運用においては、慎重になりすぎて投資を見送ることで得られたはずのリターンを逃さないよう、適切なリスク管理を行うことが重要です。
リスク許容度
リスク許容度とは、自分の資産運用において、どれくらいの損失までなら精神的にも経済的にも受け入れられるかという度合いを表す考え方です。 投資には必ずリスクが伴い、時には資産が目減りすることもあります。そのときに、どのくらいの下落まで冷静に対応できるか、また生活に支障が出ないかという観点で、自分のリスク許容度を見極めることが大切です。 年齢、収入、資産の状況、投資経験、投資の目的などによって人それぞれ異なり、リスク許容度が高い人は価格変動の大きい商品にも挑戦できますが、低い人は安定性の高い商品を選ぶほうが安心です。自分のリスク許容度を正しく理解することで、無理のない投資計画を立てることができます。