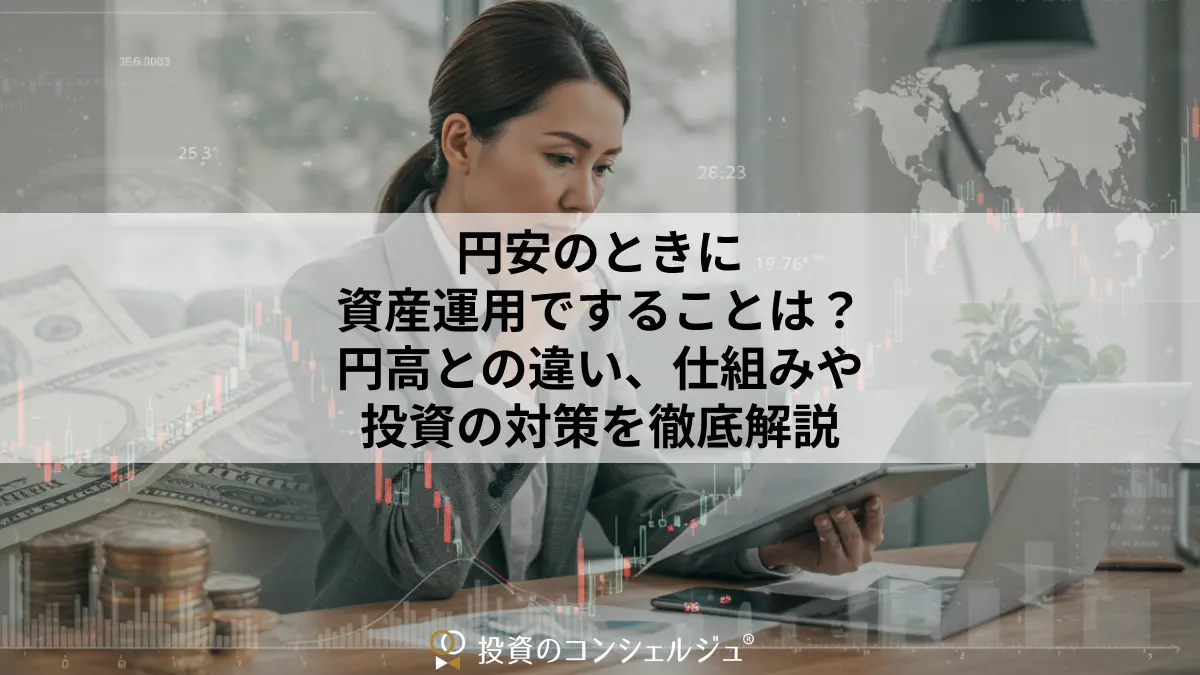サムライ債とは何か?円建てで海外投資できる債券の基本と活用法
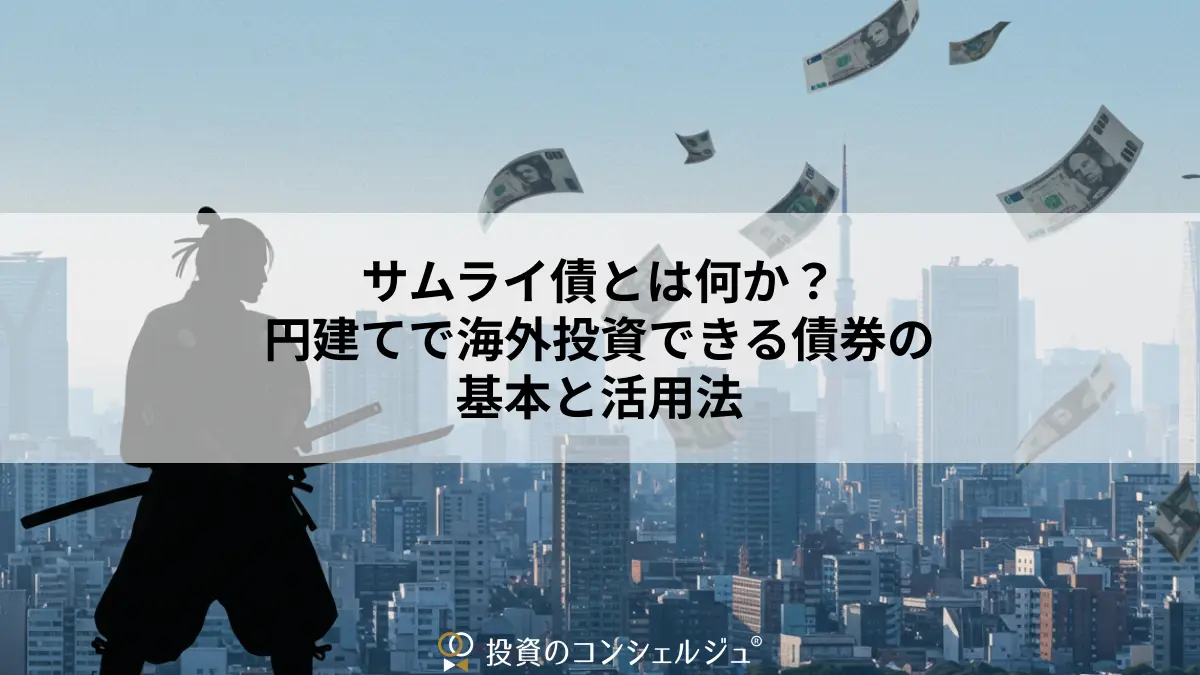
サムライ債とは何か?円建てで海外投資できる債券の基本と活用法
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.09
更新:
2025.07.01
「外債に興味はあるけれど、為替リスクが気になる…」そんな方に注目されているのが「サムライ債」。日本円で海外の政府や企業に投資できるこの債券は、為替変動の不安を避けつつ、国際的な分散投資を実現できる魅力的な手段です。この記事では、円建てで利回りを確保できるサムライ債の仕組みやメリット・注意点をわかりやすく解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事では、サムライ債の仕組みから購入方法、メリット・注意点までをわかりやすく整理しています。「円で海外に投資するとは?」「為替リスクなしでどう分散できるのか?」といった疑問が解消されるだけでなく、ESG債や投資信託を通じた間接的な投資方法も紹介。さらに、最低投資金額や税制、流動性など実務に役立つ情報も網羅しており、知識として理解するだけでなく、実際の投資判断に踏み出す具体的な視点が得られる内容です。
サムライ債とは?
サムライ債は、海外の政府や企業などが日本国内で円建てで発行する債券で、発行から利払い、償還までのすべてが日本円で行われるのが特徴です。1970年にアジア開発銀行が初めて発行して以来、多くの国や企業がこの仕組みを活用しており、日本市場における重要な資金調達手段のひとつとなっています。
発行体にとっての最大のメリットは、日本の投資家から直接、円建てで資金を調達できる点です。特に、円でのプロジェクト資金や債務返済などのニーズがある場合に、為替リスクを避けつつ安定的な資金を得る手段として有効です。
一方で、日本の投資家にとっては、為替変動リスクを負うことなく、海外の政府や企業の信用に基づいた債券に投資できる点が魅力です。発行体にはインドネシアやメキシコといった各国政府のほか、海外の企業や金融機関も含まれており、投資先の選択肢は年々広がりを見せています。
サムライ債のメリットと注意点
サムライ債は、外国の政府や企業などの非居住者が、日本円建てで日本の投資家に向けて発行する債券です。円建てでありながら、海外の発行体に投資できるという特徴を持ち、為替リスクを回避しつつ、国際分散投資を実現できる商品として注目されています。
特に、外貨建て資産に慎重な投資家にとって、「円で投資できる外債」という立ち位置は大きな魅力となります。以下では、サムライ債の主なメリットと注意点を整理してご紹介します。
サムライ債に投資するメリット
為替リスクを回避しながら海外に投資できる
サムライ債は日本円建てで発行され、利息や元本の受け取りもすべて円で行われます。そのため、為替レートの変動によって資産価値が目減りする心配がなく、為替リスクを取りたくない投資家でも安心して取り組めるのが最大の特徴です。
発行体が外国の政府や企業であるため、円建てのまま国際的な信用リスクをポートフォリオに取り入れられるのも魅力のひとつです。
このような特性から、サムライ債は円建て資産を基本に置きつつ、国際分散効果を狙いたい富裕層や中長期の安定運用を志向する個人投資家に特に適しています。
海外の信用リスクを通貨リスクなしで分散できる
サムライ債では、発行体は海外であっても通貨は円で完結するため、為替リスクを取らずに国や地域ごとの信用・地政学リスクを分散することが可能です。たとえば、日本国債や国内企業債と組み合わせることで、より広い範囲の信用リスクを取り込むことができます。
国内債券よりもやや高めの利回りが期待できる
発行体の信用力や市場環境によって異なりますが、サムライ債は日本の投資家を引きつけるため、同格の国内債券よりもやや高めの利回り(クーポン)が設定されるケースが少なくありません。 特に低金利環境下では、円建てで利回りを高めに確保できる選択肢として検討に値します。
ただし、利回りの高さは信用リスクや市場需給に裏打ちされたものであるため、常に魅力的とは限らず、個別の銘柄ごとの見極めが必要です。
ESG債にも円建てで投資可能
近年では、グリーンボンドやブルーボンドといったESG債の一形態として、サムライ債が活用されるケースも増えています。 たとえば、インドネシア政府やルーマニア政府が発行するESGサムライ債は、円で投資できるESG商品として注目されており、為替リスクを伴わずに社会的意義のある投資を行いたい投資家にとって魅力的な選択肢となります。
サムライ債に投資する際の注意点
発行体情報の入手が難しい場合がある
サムライ債の発行体は外国の政府や企業であるため、日本国内企業の債券に比べて、信用力や財務状況に関する情報が得にくいことがあります。たとえば、開示資料が英語中心であったり、日本語での分析レポートが少なかったりするため、投資判断に必要な情報が十分に揃わないケースもあります。格付機関の評価や証券会社の資料などを活用しながら、慎重に判断する必要があります。
中途売却しにくい銘柄もある(流動性リスク)
サムライ債の中には、発行規模が小さく、満期まで保有されるケースが多いため、市場での売買があまり活発でない銘柄もあります。そのため、途中で売却しようとしても、買い手が見つからず、想定よりも低い価格での売却となる可能性があります。
これはサムライ債全体の特性というよりは、銘柄ごとの事情や市場環境に左右されるリスクです。中途売却を想定している場合は、あらかじめ証券会社などで流動性について確認しておくことが安心材料になります。
サムライ債はこんな投資家に向いている
サムライ債は円建てでありながら、国際的な投資機会にアクセスできるユニークな商品です。通貨リスクを避けつつ、外債に関心がある投資家にとっては、有力な選択肢となり得ます。一方で、発行体に関する情報の把握や、銘柄ごとの流動性リスクには注意が必要です。メリットとリスクのバランスを踏まえつつ、個別銘柄ごとに丁寧に検討する姿勢が求められます。
サムライ債の投資方法
円建てで海外政府や企業に投資できるユニークな商品として、サムライ債は富裕層から個人投資家まで幅広い層の注目を集めています。外貨建て資産に慎重な方でも為替リスクを抑えつつ、海外の成長や利回りを取り込める点が魅力です。一方で、発行体の情報収集が難しい場合や流動性に差があるなどの課題も存在します。
サムライ債を購入する場合、主に公募形式で発行される債券を証券会社を通じて取得する方法が一般的です。募集期間中に申し込む新発債だけでなく、既に市場に流通している既発債を二次市場で買い付けることもできます。
公募サムライ債購入前の確認ポイント
最低投資金額の確認
サムライ債は、通常1,000万円や1億円といった大口でしか購入できません。しかし一部の証券会社では、在庫として保有している債券を100万円単位まで小口化して販売している場合があります。ただし、こうした小口販売がいつでも行われているわけではなく、銘柄や証券会社の在庫状況によって取り扱いが異なります。実際に購入を検討する際には、最低投資金額を必ず確認し、自分の資金規模やリスク許容度に合った投資かどうか見極めるようにしましょう。
発行体の信用リスク
発行体が外国の政府や企業である場合、国内債券に比べて情報開示の形式や量が異なり、英語での開示資料が多いなどのハードルが存在します。格付機関のレーティングや証券会社のレポートを活用し、発行体の信用力をしっかり把握しておきましょう。
二次市場での流動性
サムライ債の中には、発行規模が小さいものや、あまり有名でない国や企業が発行するものもあります。そうした債券は、市場での売買(=途中で売ること)があまり活発でないことがあります。そのため、途中で売ろうと思っても買い手が見つからず、希望より安い価格でしか売れない可能性がある、という「流動性リスク」があるのです。
中途売却を考えている場合は、事前に証券会社やアドバイザーに「この債券は売りやすいか?」を確認したり、過去にどれくらい売買されていたか(取引実績)を調べておくと安心です。
税制面の確認ポイント
サムライ債の利息には、国内債券と同様に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されます。発行体が外国の政府や企業であっても、日本国内で発行される円建て債券であるため、基本的には日本の債券と同じ税制が適用されます。また、発行体の本国が日本と租税条約を結んでいる場合でも、通常のサムライ債では日本での源泉徴収のみで完結するケースが一般的です。ただし、投資対象や取引スキームによっては税務上の扱いが異なる場合があるため、事前に証券会社や税理士に確認しておくと安心です。
投資信託を通じたサムライ債投資
サムライ債を直接買わず、投資信託を利用して間接的に投資する方法もあります。プロの運用会社が複数の債券を組み合わせるため、小口資金でも分散投資しやすいのがメリットです。しかし、サムライ債だけを集中的に運用するファンドはほとんど存在しない点に注意が必要です。
国内債券ファンド
国内債券を投資対象とするファンドの一部に、サムライ債が組み込まれている場合があります。円建て商品を中心にポートフォリオを組成しているので、為替リスクを取りたくない投資家にとって選択肢になりやすいでしょう。
以下は、国内債券を主要投資対象とするファンドの一部で、運用方針上サムライ債を含める場合がある代表例です。ただし、時期や運用判断によって組入状況は変化し、必ずしも多くのサムライ債を保有しているわけではありません。
野村日本債券ファンド(野村アセットマネジメント)
国内の公社債を幅広く投資対象とするファンド。運用方針には「海外発行体による円建て債券(サムライ債等)」も含まれています。実際の組入比率は運用環境や方針次第で大きく変わるため、最新の目論見書・運用報告書で要確認。
大和住銀DC国内債券ファンド(大和アセットマネジメント)
確定拠出年金(DC)向けに設定された国内債券ファンド。条件を満たす円建て債券のひとつとしてサムライ債を組み入れる可能性があります。一般販売向けの類似ファンドとは組入銘柄が異なる場合がある点に注意。
三井住友・日本債券ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
日本の国債や社債、地方債などを広く投資対象とするファンド。サムライ債の含有も運用上可能とされています。実際にどれだけサムライ債を保有しているかは、運用会社の判断や市場動向によります。
みずほ日本債券ファンド(アセットマネジメントOne)
国内の債券全般をカバーするファンドで、サムライ債も円建て債券の一種として組み入れる場合があります。過去の運用報告書を確認し、サムライ債の保有状況をチェックすることをおすすめします。
グローバル債券ファンド・国際機関債ファンド
世界各国の債券を広く取り入れるファンドで、サムライ債が含まれる場合があります。外貨建て債券と合わせて運用するケースが多いため、為替リスクやファンドの運用方針をよく確認しましょう。サムライ債への投資割合がごく一部にとどまる場合もあるため、目論見書や運用報告書で組入比率をチェックすることが大切です。
この記事のまとめ
サムライ債は、「円で投資できる外債」として、為替リスクを避けながらもグローバルな分散効果を得られる貴重な選択肢です。しかし、発行体の信用分析や市場での流動性、購入時の最低金額など、実際の投資判断にはいくつかの専門的な知識と注意が求められます。特に中長期で安定した運用を目指す方にとっては、「どの銘柄が自分に合っているか」「どのタイミングで買うべきか」といった判断が重要です。こうした判断を一人で行うのが不安な場合は、資産運用に詳しい専門家に相談することで、自分に最適なポートフォリオ設計が可能になります。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連する専門用語
サムライ債
サムライ債とは、日本の国内市場で、外国の企業や政府などが日本円建てで発行する債券のことをいいます。発行体は海外の団体ですが、日本の法律に基づいて発行され、日本の投資家が購入できる仕組みになっています。そのため、日本の投資家にとっては、為替リスクがない状態で海外の信用力をもつ発行体に投資できるという特徴があります。外国企業にとっては、日本市場から資金を調達する手段のひとつです。「サムライ」という名称は、海外から見た日本らしさを表現した呼び名として使われています。
円貨建て債券
円貨建て債券とは、日本円で元本や利息が支払われる債券のことをいいます。日本国内の企業や政府が発行するだけでなく、海外の発行体が日本円で発行する場合も含まれます。投資家にとっては、為替変動の影響を受けにくいため、リスクを抑えた運用がしやすいというメリットがあります。一方、発行体にとっては、日本市場から円建てで資金を調達できる手段のひとつです。円貨建て債券は、特に日本国内の投資家にとって、通貨の変動リスクを避けながら安定的な収益を期待できる商品として利用されています。
為替リスク
為替リスクとは、異なる通貨間での為替レートの変動により、外貨建て資産の価値が変動し、損失が生じる可能性のあるリスクを指します。 たとえば、日本円で生活している投資家が米ドル建ての株式や債券に投資した場合、最終的なリターンは円とドルの為替レートに大きく左右されます。仮に投資先の価格が変わらなくても、円高が進むと、日本円に換算した際の資産価値が目減りしてしまうことがあります。反対に、円安が進めば、為替差益によって収益が増える場合もあります。 為替リスクは、外国株式、外貨建て債券、海外不動産、グローバルファンドなど、外貨に関わるすべての資産に存在する基本的なリスクです。 対策としては、為替ヘッジ付きの商品を選ぶ、複数の通貨や地域に分散して投資する、長期的な視点で資産を保有するなどの方法があります。海外資産に投資する際は、リターンだけでなく、為替リスクの存在も十分に理解しておくことが大切です。
利回り
利回りとは、投資で得られた収益を投下元本に対する割合で示し、異なる商品や期間を比較するときの共通尺度になります。 計算式は「(期末評価額+分配金等-期首元本)÷期首元本」で、原則として年率に換算して示します。この“年率”をどの期間で切り取るかによって、利回りは年間リターンとトータルリターンの二つに大別されます。 年間リターンは「ある1年間だけの利回り」を示す瞬間値で、直近の運用成績や市場の勢いを把握するのに適しています。トータルリターンは「保有開始から売却・償還までの累積リターン」を示し、長期投資の成果を測る指標です。保有期間が異なる商品どうしを比べるときは、トータルリターンを年平均成長率(CAGR)に換算して年率をそろすことで、複利効果を含めた公平な比較ができます。 債券なら市場価格を反映した現在利回りや償還までの総収益を年率化した最終利回り(YTM)、株式なら株価に対する年間配当の割合である配当利回り、不動産投資なら純賃料収入を物件価格で割ったネット利回りと、対象資産ごとに計算対象は変わります。 また、名目利回りだけでは購買力の変化や税・手数料の影響を見落としやすいため、インフレ調整後や税控除後のネット利回りも確認することが重要です。複利運用では得た収益を再投資することでリターンが雪だるま式に増えますから、年間リターンとトータルリターンを意識しながら、複利効果・インフレ・コストを総合的に考慮すると、より適切なリスクとリターンのバランスを見極められます。
発行体
発行体とは、債券や株式などの金融商品を市場に出して資金を調達する側のことを指します。債券であれば、お金を借りる側であり、投資家から集めた資金を使って事業活動や設備投資などを行います。発行体には、国や地方自治体、企業、政府機関などさまざまな種類があります。投資家にとっては、発行体の信用力や財務状況がその金融商品の安全性や利回りに大きく影響するため、誰が発行しているのかをしっかりと確認することが重要です。信頼できる発行体であれば、安定した利息や元本の返済が期待できます。
信用リスク(クレジットリスク)
信用リスクとは、貸し付けた資金や投資した債券について、契約どおりに元本や利息の支払いを受けられなくなる可能性を指します。具体的には、(1)企業の倒産や国家の債務不履行(いわゆるデフォルト)、(2)利払いや元本返済の遅延、(3)返済条件の不利な変更(債務再編=デット・リストラクチャリング)などが該当します。これらはいずれも投資元本の毀損や収益の減少につながるため、信用リスクの管理は債券投資の基礎として非常に重要です。 この信用リスクを定量的に評価する手段のひとつが、格付会社による信用格付けです。格付は通常、AAA(最上位)からD(デフォルト)までの等級で示され、投資家にとってのリスク水準をわかりやすく表します。たとえば、BBB格付けの5年債であれば、過去の統計に基づく累積デフォルト率はおおよそ1.5%前後とされています(S&Pグローバルのデータより)。ただし、格付はあくまで過去の情報に基づいた「静的な指標」であり、市場環境の急変に即応しにくい側面があります。 そのため、市場ではよりリアルタイムなリスク指標として、同年限の国債利回りとの差であるクレジットスプレッドが重視されます。これは「市場に織り込まれた信用リスク」として機能し、スプレッドが拡大している局面では、投資家がより高いリスクプレミアムを求めていることを意味します。さらに、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の保険料率は、債務不履行リスクに加え、流動性やマクロ経済環境を反映した即時性の高い指標として、機関投資家の間で広く活用されています。 こうしたリスクに備えるうえでの基本は、ポートフォリオ全体の分散です。業種や地域、格付けの異なる債券を組み合わせることで、特定の発行体の信用悪化がポートフォリオ全体に与える影響を抑えることができます。なかでも、ハイイールド債や新興国債は高利回りで魅力的に見える一方で、信用力が低いため、景気後退時などには価格が大きく下落するリスクを抱えています。リスクを抑えたい局面では、投資適格債へのシフトやデュレーションの短縮、さらにCDSなどを活用した部分的なヘッジといった対策が有効です。 投資判断においては、「高い利回りは信用リスクの対価である」という原則を常に意識する必要があります。期待されるリターンが、想定される損失(デフォルト確率×損失率)や価格変動リスクに見合っているかどうか。こうした視点で冷静に比較検討を行うことが、長期的に安定した債券運用につながる第一歩となります。
格付機関
格付機関とは、企業や国、債券などの信用力を評価し、「信用格付」と呼ばれる等級をつける専門の機関のことをいいます。信用格付は、投資家がその企業や国が借りたお金をきちんと返せるかどうかを判断するための重要な指標となります。たとえば、格付が高ければ「信用度が高く、返済の可能性が大きい」とみなされ、逆に格付が低ければ「リスクが高い」と判断されることになります。代表的な格付機関には、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ(S&P)、フィッチ・レーティングスなどがあります。投資初心者にとっても、債券や企業の安全性を見極めるうえで、格付機関の評価はとても参考になります。
公募債
公募債とは、多くの投資家を対象に広く募集される形式で発行される債券のことをいいます。企業や地方自治体、国などが資金調達のために発行し、証券会社などを通じて一般の投資家に販売されます。特徴としては、不特定多数に対して情報が公開されるため、透明性が高く、誰でも購入しやすいという点があります。公募債は、企業などの資金調達手段としてよく使われており、社債や地方債、国債など、さまざまな種類があります。投資初心者でも比較的安心して購入しやすい債券として、資産運用の一環として活用されることが多いです。
ESG債
ESG債とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といった要素に配慮した取り組みに使われることを目的として発行される債券のことをいいます。企業や政府などが、環境保護活動や社会的課題の解決、透明性の高い経営体制の構築といったプロジェクトに必要な資金を集めるために発行します。具体的には、再生可能エネルギーの開発や教育支援、地域社会への貢献などに使われるケースが多く見られます。ESG債は、投資によって経済的な利益だけでなく、社会的な貢献も意識した「責任ある投資」をしたいと考える人々に注目されています。投資初心者にとっても、自分の資金が良い社会づくりに役立つという実感が持ちやすい金融商品といえます。
目論見書(プロスペクタス)
目論見書(プロスペクタス)とは、株式や債券などの金融商品を発行する際に、その内容やリスク、資金の使い道などを詳しく説明するための書類のことをいいます。これは、投資家が商品について正しく理解し、投資判断を行うための重要な資料です。目論見書には、発行体の財務情報、事業内容、募集する金額、利回りや償還期間などが記載されており、金融商品取引法に基づいて作成されます。投資初心者にとっては、少し専門的で読みづらく感じるかもしれませんが、購入する前にリスクや条件を確認するためにとても大切な情報源となります。
運用報告書
運用報告書とは、投資信託などの金融商品について、一定期間ごとの運用状況や成果、保有資産の内容、運用方針の変更点などをまとめて投資家に知らせるための書類です。投資信託を管理・運用している運用会社が作成し、通常は半年または1年ごとに発行されます。報告書には、基準価額の推移や分配金の実績、市場環境の変化なども記載されており、投資家が自分の資産がどのように運用され、どのような成果が出ているのかを確認する手助けになります。初心者にとっても、自分の資産がどこに投資され、どのような結果を生んでいるのかを理解するうえで、非常に役立つ資料です。
流動性リスク
流動性リスクとは、資産を売却したいときに市場で買い手が見つからず、希望する価格で売却できないリスクのことを指します。特に市場が混乱した場合や、取引量の少ない資産では、このリスクが顕著になります。例えば、不動産や未上場株式、流動性の低い債券などは、売却に時間がかかることが多く、想定よりも低い価格での取引を余儀なくされる場合があります。金融機関や企業にとっては、必要な資金を調達できずに支払いが滞る可能性があることを意味し、経済危機や市場の急激な変動時には特に注意が必要です。投資ポートフォリオを構築する際には、資産の換金しやすさを考慮し、現金や流動性の高い資産とのバランスを取ることが重要とされます。
既発債
既発債とは、すでに発行され市場に流通している債券のことを指します。新規に発行される新発債と区別され、既発債は発行時に決定された金利、償還期間、利払い条件などの契約内容が固定されているため、その後の市場環境の変化に応じて価格が変動する特徴があります。 投資家は、既発債を市場で売買する際に、発行時の条件と現行の金利状況などを考慮してリスクとリターンを判断する必要があります。また、既発債の市場動向は、金融全体の金利環境や信用リスクの変動を反映するため、経済の健全性や市場動向の分析においても重要な指標となっています。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
租税条約
租税条約とは、国と国との間で取り決められる「税金に関する国際的な協定」です。たとえば、日本に住む人が外国の株式などに投資したとき、利益に対して日本とその国の両方で税金を取られてしまう可能性があります。これを「二重課税」と言います。 租税条約があると、この二重課税を防ぐ仕組みが整えられていたり、源泉徴収税率(配当や利子にかかる税率)が軽減されたりします。こうした仕組みにより、国際的な投資がしやすくなるため、資産運用においてとても重要な存在です。
投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。運用によって得られた成果は、各投資家の投資額に応じて分配される仕組みとなっています。 この商品の特徴は、少額から始められることと分散投資の効果が得やすい点にあります。ただし、運用管理に必要な信託報酬や購入時手数料などのコストが発生することにも注意が必要です。また、投資信託ごとに運用方針やリスクの水準が異なり、運用の専門家がその方針に基づいて投資先を選定し、資金を運用していきます。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産運用における投資対象の組み合わせを指します。分散投資を目的として、株式、債券、不動産、オルタナティブ資産などの異なる資産クラスを適切な比率で構成します。投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを設計し、リスクとリターンのバランスを最適化します。また、運用期間中に市場状況が変化した場合には、リバランスを通じて当初の配分比率を維持します。ポートフォリオ管理は、リスク管理の重要な手法です。