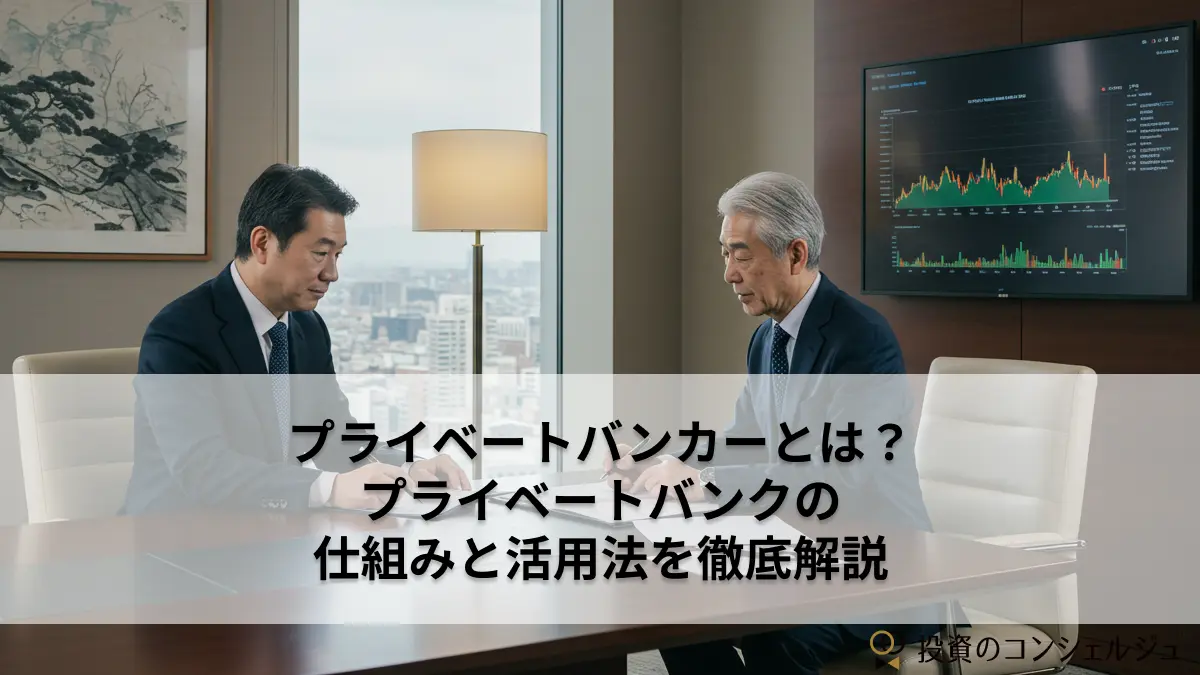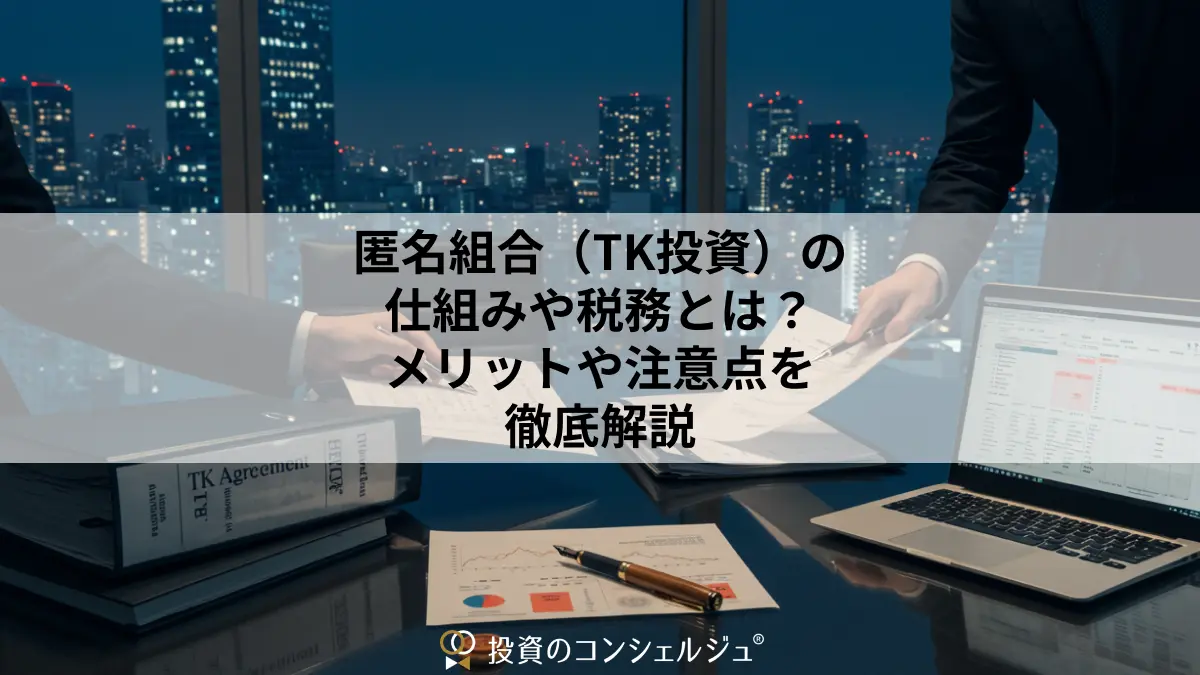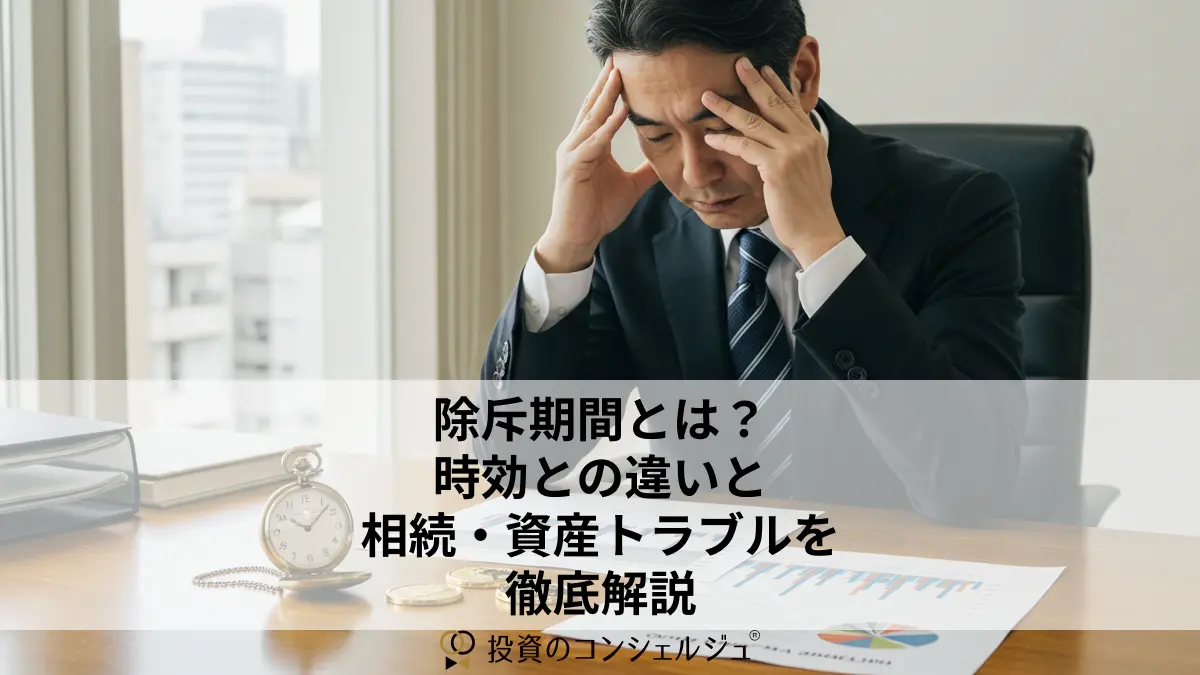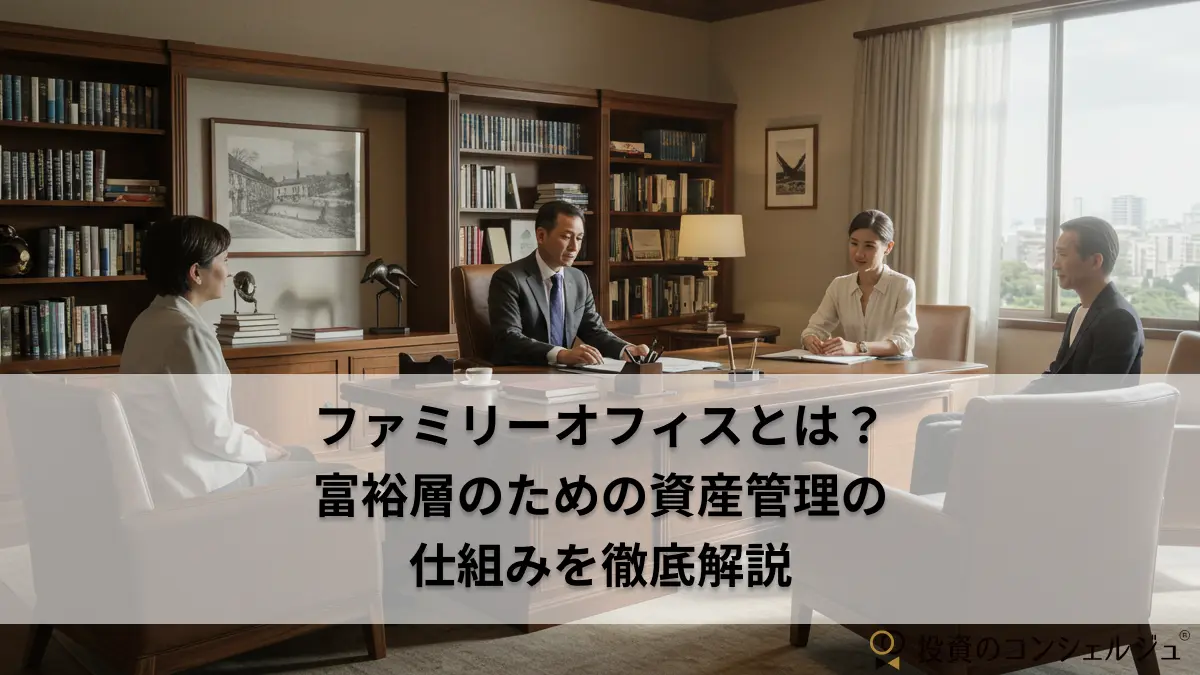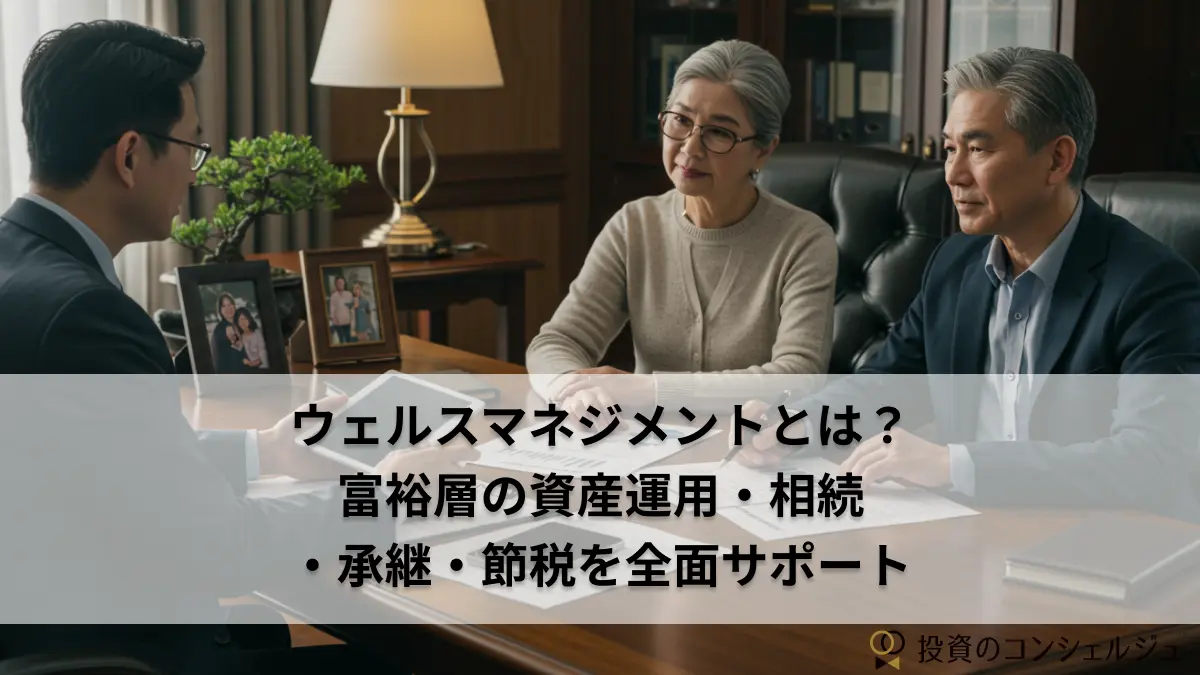
ウェルスマネジメントとは?富裕層の資産運用・相続・承継・節税を全面サポート
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.02
更新:
2025.07.04
資産を増やすだけでなく、最適に管理・運用し、次世代へとスムーズに引き継ぐにはどうすればよいのでしょうか? そこで注目されるのが「ウェルスマネジメント」です。単なる投資アドバイスにとどまらず、税務対策や相続・事業承継、不動産運用など、富裕層の資産管理を総合的にサポートする専門サービスとして、世界的に重要性を増しています。本記事では、ウェルスマネジメントの基本から、各金融機関の提供するサービスの違いまでを詳しく解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、ウェルスマネジメントの本質と、その活用方法について深く理解できるようになります。単なる資産運用と何が違うのか、どのような専門家が関わるのか、さらには国内外の金融機関によるサービスの違いまで網羅しているため、富裕層向けの資産管理戦略の全体像をつかむことができます。特に、投資だけでなく、税務対策や相続、事業承継、不動産活用まで含めた総合的なサポートの重要性が明確になり、自身や家族の資産管理に対する視野が広がるでしょう。将来の資産形成や継承を考えるうえで、最適な選択肢を見つけるための第一歩として、この記事が役立つはずです。
ウェルスマネジメントとは?
ウェルスマネジメントは、個人や家族の資産を総合的に管理・運用するサービスです。単なる投資や資産運用にとどまらず、相続対策や税務計画など、クライアントの人生設計全般に関わる包括的なアドバイスを提供します。具体的には、まず資産の現状を分析し、クライアントの年齢、家族構成、収入、将来の目標などを考慮したうえで、最適な資産配分を提案します。
投資商品の選定においては、リスク許容度や投資期間を踏まえ、株式、債券、不動産、保険商品などを組み合わせたオーダーメイドのポートフォリオを構築することが特徴です。
また、相続・事業承継対策として、不動産の活用や信託の設定、生命保険の活用など、税務面でも効果的な手法を取り入れます。
さらに、定期的なポートフォリオの見直しや、市場環境の変化に応じた資産配分の調整を行い、最適な運用を継続します。
近年では、ESG投資やインパクト投資など、社会的価値を考慮した投資手法も採用されており、単なる資産の増加だけでなく、持続可能な社会への貢献を意識する流れが強まっています。
このように、ウェルスマネジメントは財務面だけでなく、ライフプラン全般を包括的に支援する専門的なサービスとして、特に富裕層を中心にその重要性が高まっています。
ウェルスマネジメントのサービス内容
ウェルスマネジメントとは、個人の資産を総合的に管理・運用する専門サービスです。各分野の専門家と連携し、クライアントの状況に応じた最適なサポートを提供します。
資産運用コンサルティング(投資戦略の設計)
資産運用の中心となるコンサルティングでは、クライアントの資産状況やリスク許容度を分析し、最適な投資戦略を提案します。
提供内容
- 国内外の株式、債券、オルタナティブ投資を組み合わせたポートフォリオ設計
- 市場環境の変化に応じた定期的なリバランス(資産配分の見直し)
- 長期的な資産形成を見据えたアドバイス
税務・法務対策(資産の保全と最適化)
資産を守り、最適な形で継承するために、税理士や弁護士と連携し、税務・法務戦略を構築します。
提供内容
- 国内外の税制を考慮した資産管理
- 相続税・贈与税対策の立案
- 法的リスクを軽減する契約・信託の活用
相続・事業承継対策
資産を円滑に次世代へ引き継ぐための計画策定を支援します。
提供内容
- 相続税負担を抑えるための資産組み換え
- 事業承継計画の策定と後継者育成
- 遺言・信託の活用によるスムーズな承継
不動産コンサルティング
不動産は、資産形成や相続対策、事業承継において重要な役割を果たします。クライアントの目的に応じた最適な戦略を提案します。
提供内容
- 収益物件の取得・売却に関するアドバイス
- 既存不動産の有効活用および税務対策
- 相続対策としての不動産活用(賃貸経営、不動産信託の活用など)
- 海外不動産投資や節税対策のサポート(税理士・弁護士と連携)
保険コンサルティング(リスク対策)
万が一のリスクに備え、生命保険や損害保険を活用した資産保全策を提案します。
提供内容
- 生命保険を活用した相続税対策・資産継承プラン
- 不動産オーナー向けの火災・賃貸リスク保険
- 事業オーナー向けの賠償責任保険
- 高額資産(美術品・貴金属等)の損害対策
- 老後資金の補完や医療・介護費用に備えた保険活用
ウェルスマネジメントとプライベートバンキングの違い
ウェルスマネジメントは、投資運用だけでなく、税務対策や相続、不動産管理などを含む総合的な資産管理サービスです。証券会社やIFAなどが提供し、比較的幅広い富裕層が利用できます。オーダーメイドの資産戦略が特徴です。
プライベートバンキングは、銀行が提供する超富裕層向けの金融サービスで、預金・貸付・投資管理などが中心。最低資産額の基準が高く、銀行内のリソースを活用した安定した運用が強みです。
| ウェルスマネジメント | プライベートバンキング | |
|---|---|---|
| 提供機関 | 証券会社、IFA、信託銀行など | 銀行 |
| 対象者 | 富裕層(比較的幅広い) | 超富裕層(最低1億円以上が一般的) |
| サービス範囲 | 投資運用、税務対策、相続、不動産管理など総合的 | 預金、貸付、投資管理など銀行中心 |
| 特徴 | 柔軟な資産管理と戦略的アドバイス | 銀行のリソースを活用した金融サービス |
ウェルスマネジメントとアセットマネジメントの違い
ウェルスマネジメントとアセットマネジメントは、資産管理に関するサービスとして提供されていますが、大きな違いがあります。
アセットマネジメントは、主に金融資産の運用に特化したサービスであり、投資信託や年金基金などの運用を通じて、リターンの最大化を目指します。
運用戦略の策定、ポートフォリオの構築、リスク管理が主な業務となり、多くの場合、機関投資家や投資信託を通じた個人投資家向けに画一的なサービスを提供します。
一方、ウェルスマネジメントは、個人や家族の資産全体を包括的に管理するサービスです金融資産の運用だけでなく、不動産、事業資産、知的財産など、顧客が保有するすべての資産を対象とし、税務対策、相続・事業承継計画、保険設計なども含めた総合的なアドバイスを提供します。
ウェルスマネジメントに関わる専門家と必要資格
ウェルスマネージメントに携わるためには、絶対に必要な資格はありません。ただし、専門的な資格を保有することによって、顧客への信頼度は上がります。以下、ウェルスマネジメントを行うにあたって持っていた方が良い資格について紹介をします。
CFP(Certified Financial Planner)
CFPは、ウェルスマネジメントにおける国際的に認知された最高峰の資格です。金融、税務、不動産、保険、相続など6分野の専門知識が求められる資格です。資格取得には、AFP資格の保有を前提に、各分野の試験に合格し、最終的に実践的な事例試験をクリアする必要があります。顧客の財務状況を総合的に分析し、ライフプランに沿った最適な資産管理・運用のアドバイスを提供できる専門家としての能力が証明されます。
証券アナリスト
証券アナリストは、企業の財務分析や投資判断を行う専門家であり、主に証券会社や運用会社で活躍する金融のプロフェッショナルです。日本では、日本証券アナリスト協会が認定する検定会社員(CMA:Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)が代表的な資格となっています。資格取得には、証券分析、ポートフォリオ・マネジメント、企業分析、経済・金融といった分野の試験に合格する必要があります。第1次試験、第2次試験があります。
これらの資格は必須ではありませんが、持っていた方がウェルスマネジメントの業務につきやすいですし、顧客の信頼を得やすいです。
主要金融機関のウェルスマネジメントサービス比較
主要金融機関のウェルスマネジメントのサービスを比較してみました。
| 名称 | 対象顧客 | サービス内容 | 拠点 | |
|---|---|---|---|---|
| 野村證券 | ウェルス・マネジメント部門 | 金融資産1億円以上 | 資産運用に強み。 相続や不動産に関しては野村信託銀行と協働 | 全国の支店 |
| 三井住友銀行 | ウェルスマネジメントグループ | 金融資産1億円以上 | 総合コンサルに強み。 日興証券・SMBC信託銀行と協働 | 全国の支店 |
| UBS証券 | UBS SuMi TRUST | 金融資産10億円以上 | 資産運用に強み。 相続や不動産に関しては三井住友信託銀行と協働 | 本店部署 |
ウェルスマネジメントに関しては、一般的に情報が公開されていないものが多いので、もしウェルスマネジメントのサービスを受けたければ、サービスを受けたい金融機関に多くのお金を預けておく必要があります。
野村證券のウェルスマネジメントの特徴
野村證券のリテール部門は大きく変化し、現在はウェルスマネジメント部門と呼ばれています。
ウェルスマネジメントでは、税理士、弁護士、不動産の専門家などと連携し、必要に応じて支援チームを編成します。例えば、野村證券本体が提供できるのは資産運用業務のみですが、関連会社の野村信託銀行と協力することで、相続や不動産の提案も行えます。
このように、専門家とチームを組み、資産の保全や承継をサポートすることがウェルスマネジメントの特徴です。各支店の専門担当者が富裕層向けに資産運用を提案するだけでなく、野村信託銀行と協力し、相続や不動産のコンサルティングも行う点が強みとなっています。
この記事のまとめ
ウェルスマネジメントは、単なる投資ではなく、資産全体を最適に管理し、将来に備えるための包括的な戦略です。実際に資産運用を始めるには、専門知識と戦略が不可欠です。市場や税制は常に変化するため、的確な判断には専門家の助言が重要です。
まずは現在の資産状況や将来の目標を整理し、ウェルスマネジメントに精通した専門家に相談してみましょう。証券会社やIFA、信託銀行など、さまざまな金融機関が富裕層向けの資産管理サービスを提供しています。早めに行動することで、適切な運用プランを立て、将来の資産形成や継承の準備を進めることが可能です。今こそ最初の一歩を踏み出しましょう。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
富裕層
富裕層とは、高額な資産を保有し、投資や資産運用を積極的に行う個人を指す。一般的には、金融資産1億円以上を持つ人々が該当するとされ、さらに超富裕層(資産5億円以上)などの分類もある。彼らは資産の保全・運用だけでなく、事業承継、相続対策、節税対策、慈善活動などにも関心を持つことが多い。金融機関やプライベートバンク、ファミリーオフィスなどの専門機関と連携しながら、資産を効率的に管理し、長期的な財産維持・成長を目指す。
ウェルスマネジメント
ウェルスマネジメントとは、一定以上の資産を保有する個人やその家族に対して提供される、総合的な資産管理サービスのことを指します。 ここでいう「総合的」とは、単に資産を運用するだけでなく、税金対策、相続対策、保険の活用、ライフプランの設計など、複数の分野にまたがる支援を一体的に行うという意味です。資産の構成や目的は人それぞれ異なるため、個別の事情に応じてカスタマイズされたアドバイスが求められます。 このサービスは、通常、金融・法律・税務などの専門家がチームを組んで提供します。例えば、資産を運用して増やすだけでなく、それに伴って発生する税負担を軽減するための対策や、次世代にスムーズに資産を引き継ぐための相続設計も同時に検討されます。生命保険を活用して納税資金を確保したり、遺産分割のトラブルを避ける仕組みを整えたりすることも、ウェルスマネジメントの重要な要素です。 こうしたサービスは、特に資産規模が大きくなるほど必要性が増します。資産が一定の規模を超えると、「どのように増やすか」だけでなく、「どう守るか」「どう引き継ぐか」「どう使うか」といった視点が不可欠になります。ウェルスマネジメントは、こうした多面的なニーズに応えるための、長期的・戦略的なコンサルティングサービスといえるでしょう。 一般的には富裕層を対象としたサービスと位置づけられていますが、近年では資産形成の初期段階から専門的な支援を求める人も増えており、ウェルスマネジメントの考え方そのものが広がりを見せています。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
事業承継
事業承継とは、企業の経営権や資産を後継者に引き継ぐプロセスを指します。経営者の高齢化が進む中、円滑な承継を実現するためには、早期からの計画と準備が欠かせません。 事業承継には、大きく分けて「経営の承継」と「資産の承継」の二つの側面があります。経営の承継では、後継者の選定や育成、経営戦略の継承が重要です。一方、資産の承継では、株式や事業用資産の移転に加え、相続税や贈与税などの税務対策が必要となります。 事業承継の方法には、主に三つの選択肢があります。一つ目は、親族内承継で、経営者の子どもや親族に事業を引き継ぐ方法です。この場合、相続税や贈与税の負担を考慮し、適切な財務戦略を立てることが求められます。二つ目は、従業員承継(MBO)で、役員や従業員が事業を引き継ぐ方法です。資金調達が課題となることがあるため、金融機関や専門家の支援を受けることが有効です。三つ目は、第三者承継(M&A)で、他社や投資ファンドに事業を売却し、継続させる方法です。後継者が見つからない場合の有力な選択肢となります。 事業承継を成功させるためには、早期の計画策定が重要です。理想的には5~10年前から準備を始め、株式や財務の整理、相続税・贈与税の負担軽減を進める必要があります。また、後継者の育成も欠かせません。経営者としての知識や経験を身につけるための支援を行い、スムーズな引き継ぎを目指すことが求められます。さらに、税理士、弁護士、M&Aアドバイザーなどの専門家の活用も有効です。 事業承継は、企業の存続だけでなく、従業員の雇用や取引先との関係維持、さらには地域経済にも大きな影響を与えます。そのため、計画的に進めることで、企業価値の維持・向上を図ることが重要です。
信託
信託とは、お金や不動産などの財産を信頼できる相手(受託者)に託し、特定の目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。財産を託す人を「委託者」、管理する人を「受託者」、利益を受け取る人を「受益者」といいます。 たとえば、親が子どもの教育資金を信託したり、高齢の親の認知症対策として資産管理を家族に委ねたりするケースがあります。このような個人間で活用される信託は「家族信託」と呼ばれ、相続対策や資産承継の手段として近年注目されています。 一方、資産運用の世界では「商事信託」として、信託銀行や運用会社が多数の投資家から集めた資金をまとめて運用する「投資信託」が一般的です。さらに、海外では、受益者への分配内容を受託者が裁量で決められる「ディスクリショナリートラスト(裁量信託)」という形態もあります。 信託は目的や状況に応じて柔軟に設計できる制度であり、大切な資産を計画的に管理・承継するための有力な選択肢となります。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産運用における投資対象の組み合わせを指します。分散投資を目的として、株式、債券、不動産、オルタナティブ資産などの異なる資産クラスを適切な比率で構成します。投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを設計し、リスクとリターンのバランスを最適化します。また、運用期間中に市場状況が変化した場合には、リバランスを通じて当初の配分比率を維持します。ポートフォリオ管理は、リスク管理の重要な手法です。
リスク許容度
リスク許容度とは、自分の資産運用において、どれくらいの損失までなら精神的にも経済的にも受け入れられるかという度合いを表す考え方です。 投資には必ずリスクが伴い、時には資産が目減りすることもあります。そのときに、どのくらいの下落まで冷静に対応できるか、また生活に支障が出ないかという観点で、自分のリスク許容度を見極めることが大切です。 年齢、収入、資産の状況、投資経験、投資の目的などによって人それぞれ異なり、リスク許容度が高い人は価格変動の大きい商品にも挑戦できますが、低い人は安定性の高い商品を選ぶほうが安心です。自分のリスク許容度を正しく理解することで、無理のない投資計画を立てることができます。
ESG投資
ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮して行う投資のことです。従来、企業の投資価値は主にキャッシュフローや利益率などの財務情報を基に判断されてきましたが、近年は、環境負荷の低減、社会的責任の遂行、健全な経営体制といった非財務情報も投資判断の重要な指標となっています。 ESGの概念は、2006年に国連が機関投資家向けに「責任投資原則(PRI)」を提唱したことをきっかけに広まりました。ESG要素を投資プロセスに組み込むことで、長期的なリスクを抑えながら持続可能なリターンの向上が期待されます。特に、ESGに積極的に取り組む企業は、規制対応力やブランド価値の向上につながるため、将来的な成長性や安定性の面で投資家の関心を集めています。
インパクト投資
投資による財務的リターンだけでなく、社会や環境への良い影響(インパクト)を重視します。例として、再生可能エネルギーへの投資があります。
独立系アドバイザー(IFA)
IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、日本語では「独立系フィナンシャルアドバイザー」と呼ばれる資産運用の専門家を指す。内閣総理大臣より金融商品仲介業の登録を受け、1つ以上の証券会社と業務委託契約を締結し、投資家に対して資産運用のアドバイス業務や金融商品の仲介を行う。
オルタナティブ投資
オルタナティブ投資とは、伝統的な投資対象である株式や債券以外の資産への投資を指します。主な投資対象には、不動産、インフラ、プライベートエクイティ(未公開株式)、コモディティ(商品市場)、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、貴金属、仮想通貨などが含まれます。 この投資手法の主な特徴として、伝統的な市場との相関が低いため、ポートフォリオ全体のリスク分散効果が期待できることが挙げられます。また、投資対象や手法の選択肢が広がることで、より柔軟な投資戦略を構築することが可能になります。 ただし、オルタナティブ投資には留意点もあります。一般的に流動性が低い場合が多く、また専門的な知識が必要とされることから、長期的な投資視点を持って取り組む必要があります。
プライベートバンキング(PB)
プライベートバンキングとは、富裕層の個人顧客向けに提供される資産運用サービスのことです。資産管理、相続対策、税務アドバイス、投資戦略など、顧客のニーズに合わせた総合的な金融サービスが含まれます。通常、専門のファイナンシャルアドバイザーが個別に対応し、長期的な資産形成や保全をサポートします。
証券アナリスト
証券アナリストとは、株式や債券などの金融商品について、企業の業績や市場の動向を分析し、投資判断の助言を行う専門家です。企業の財務情報や業界動向を詳しく調べ、投資家向けにレポートを提供します。証券アナリストの分析は、個人投資家や機関投資家の資産運用において重要な参考資料となります。
CFP(Certified Financial Planner)
CFPとは、「サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー(Certified Financial Planner)」の略で、世界24か国以上で導入されている国際的なファイナンシャルプランナーの上級資格です。日本では日本FP協会が認定しており、AFPという基礎資格を取得したうえで、さらに専門的な学習と試験を経て得られる資格です。 CFPは、資産運用、保険、税金、年金、不動産、相続といった幅広い分野において、顧客のライフプランに基づいた中長期的な提案を行います。金融機関や保険会社、独立系のファイナンシャルプランナーとして活躍する人が多く、信頼性の高い専門家として評価されています。資格の維持には継続的な学習も求められ、常に最新の知識でアドバイスできる体制が整っています。
CMA(Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)
CMAとは、「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)」の略で、企業の財務内容や経済情勢、金融市場などを専門的に分析する高度な資格です。 取得には、日本証券アナリスト協会が主催する講座の修了と試験の合格が必要で、金融業界で高い専門性を証明する資格とされています。CMAの有資格者は、証券会社や運用会社、保険会社などで、企業分析、投資判断、資産運用戦略の立案などに関わるプロフェッショナルとして活躍しています。