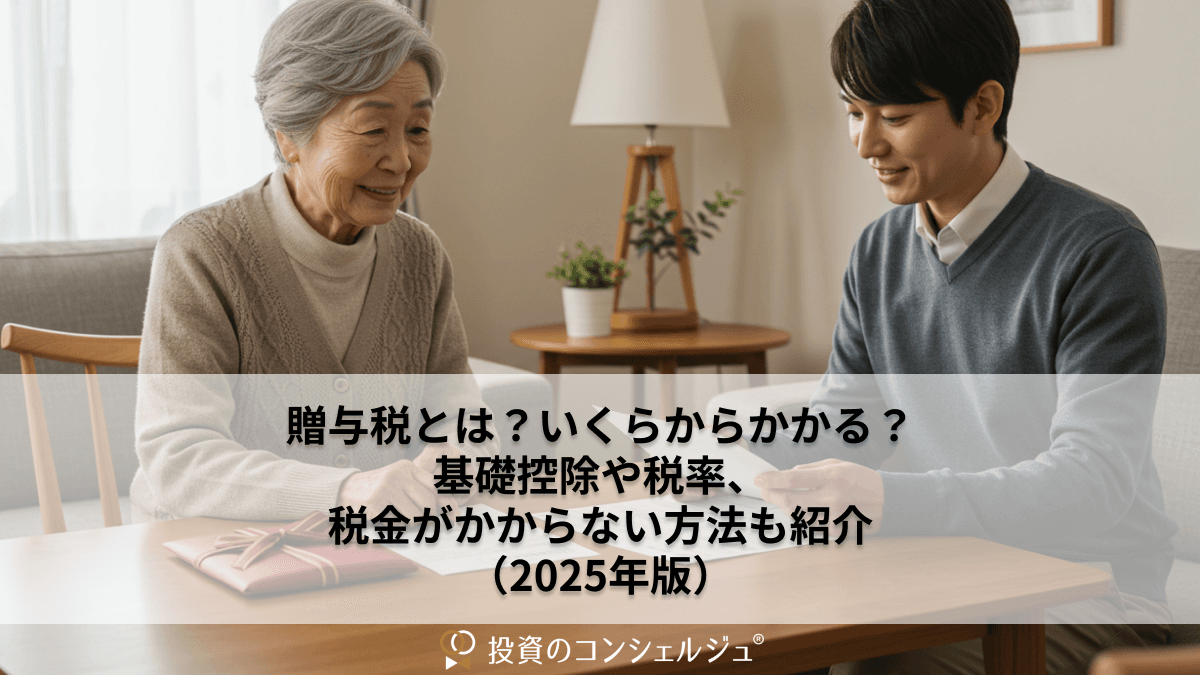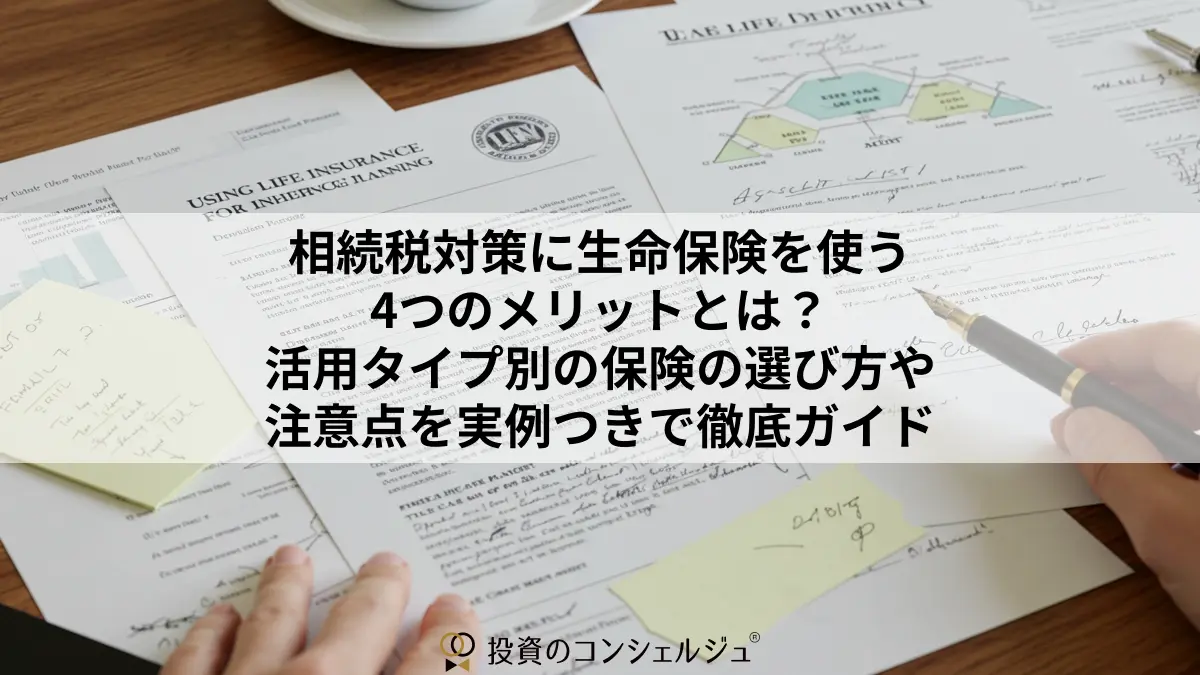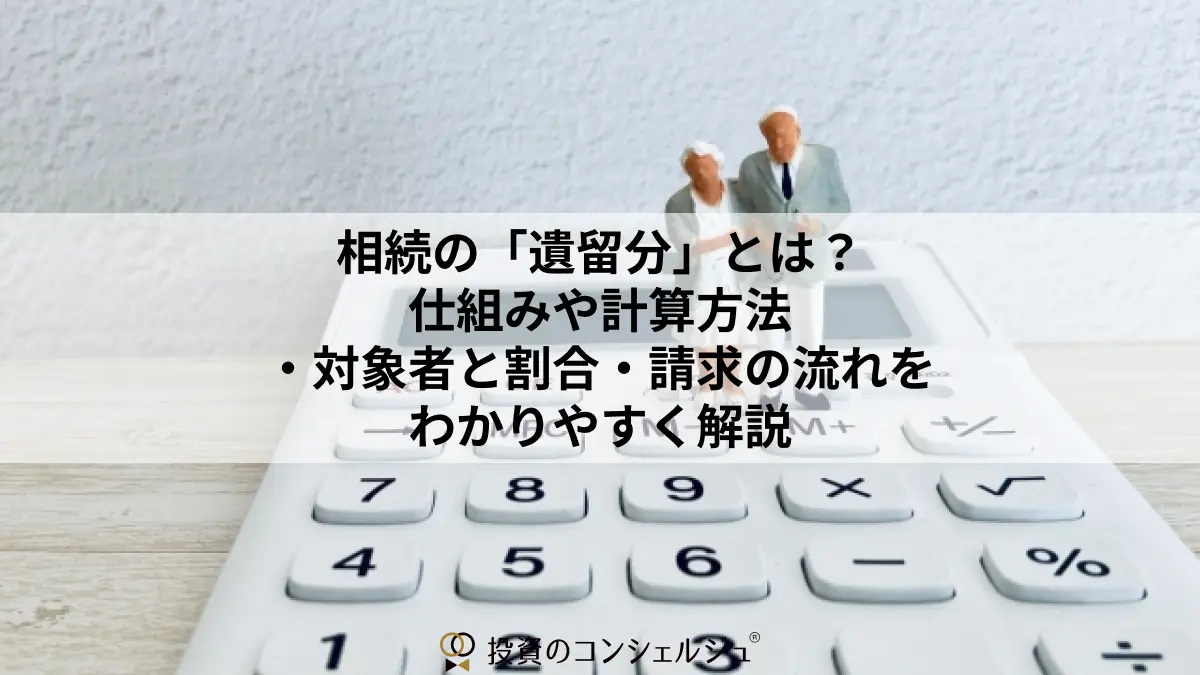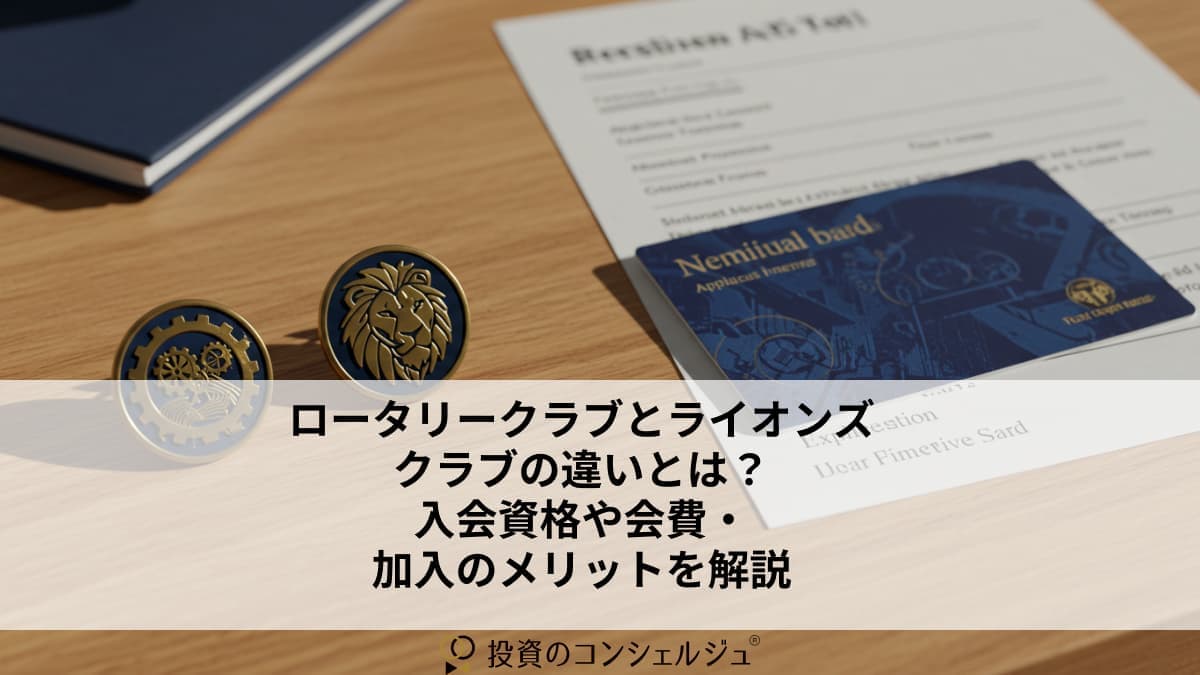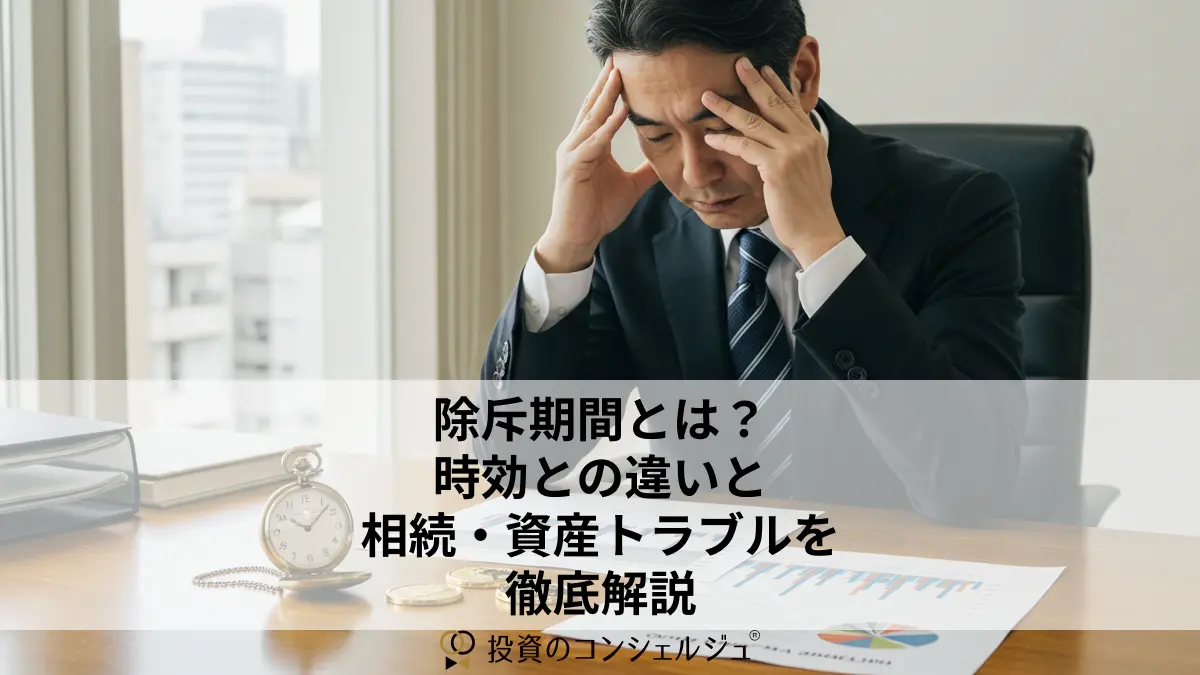相続の相談は誰にすべき?専門家ごとの役割と相談先の選び方
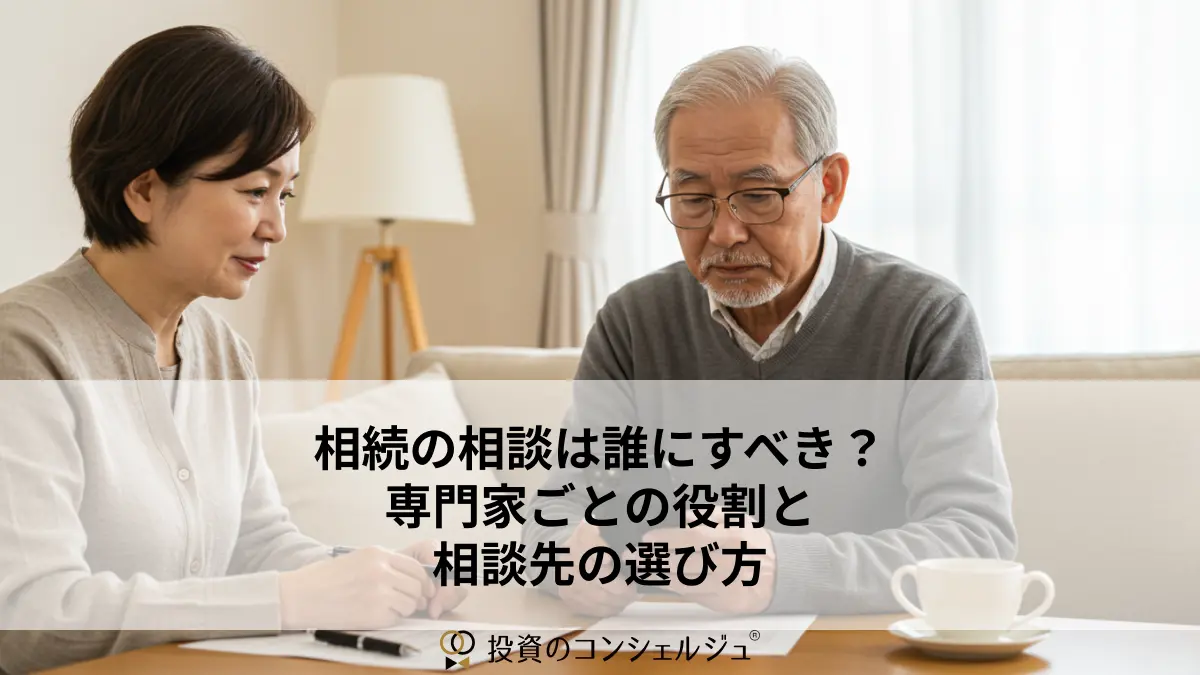
相続の相談は誰にすべき?専門家ごとの役割と相談先の選び方
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.14
更新:
2025.09.17
相続は人生でそう何度も経験するものではなく、誰に相談すべきか迷いやすい手続きです。内容によって適任の専門家は異なり、判断を誤ると時間や費用のロスにつながります。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えると申告義務があり、さらに2024年からは相続登記が義務化されました。
本記事では、弁護士・税理士・司法書士・行政書士の役割や特徴、依頼の目安を整理し、状況に応じた相談先を見極めるための指針を解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、相続の状況ごとに「誰に相談すべきか」が明確になります。たとえば、揉め事があれば弁護士、相続税の申告が必要なら税理士、不動産の名義変更は司法書士、争いがなく低コスト重視なら行政書士が適任です。
さらに「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えると相続税申告が必要で、登記は2024年から義務化といった重要ポイントも理解でき、個別依頼とワンストップの選択基準まで整理できます。
相続はどういうときに、どの専門家に相談すればいいの?
相続手続きは、状況によって必要となる専門家が異なります。「誰に相談すればいいのかわからない…」という方も多いですが、相続の内容(不動産の有無、争いの有無、税金の有無など)によって、最適な専門家は変わります。
相続に関わる主要な専門家4種(弁護士・税理士・司法書士・行政書士)の対応業務と特徴は以下の通りです。この後、各章で詳細を説明します。
専門家別|相続手続きの対応範囲と相談の目安
| 専門家 | 主な対応業務 | 対応できない・注意点 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | ・遺産分割協議の代理 ・調停・訴訟対応 ・相続放棄・限定承認の申述 ・法的トラブル対応 ・相続人/財産調査 | ・相続税申告は不可 ・不動産登記は実務ではあまり行わない ・費用が高め | ・揉め事・紛争がある ・連絡の取れない相続人がいる ・法的リスクが高い |
| 税理士 | ・相続税申告書作成・提出 ・遺産評価・節税アドバイス ・税務相談・特例活用助言 | ・調停・訴訟など裁判手続き不可 ・不動産登記不可 | ・相続税が発生する(遺産が多い) ・節税対策が必要 |
| 司法書士 | ・相続登記(不動産の名義変更) ・遺産分割協議書作成支援 ・相続人/財産調査 ・会社役員変更登記 | ・調停・訴訟不可 ・税務相談不可(税理士資格がない場合) | ・不動産を相続する ・相続人間で争いがない |
| 行政書士 | ・戸籍収集・財産調査 ・遺産分割協議書・遺言書文案作成 ・預貯金・自動車名義変更手続き支援 | ・調停・訴訟不可 ・相続税申告不可 ・不動産登記不可 | ・争いがなく税金も発生しない ・コストを抑えてスムーズに進めたい場合 |
弁護士:相続トラブルの法的解決のプロ
弁護士は法律全般の手続きに対応できる国家資格者であり、相続においては主に紛争の解決や法的手続きの代理を担います。
他の専門家とは異なり、弁護士だけが依頼者を代理して、遺産分割の交渉や家庭裁判所での調停・訴訟に臨むことが可能です。
相談すべきケース:遺産分割協議などで相続人同士の揉め事や法的な紛争がある場合
遺産分割協議で相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、遺言の内容に不満があって相続人間で争いが起きている(あるいは起こりそうな)場合は、弁護士への相談を検討しましょう。たとえば「遺言書の有効性を巡って揉めている」「特定の相続人による財産の使い込み疑惑がある」といったケースだけでなく、相続人の一人と連絡が取れないなどの状況でも、弁護士が介入することでスムーズな解決を図れます。
弁護士ができること|交渉代理から法的手続きまで
他の専門家とは異なり、弁護士だけが依頼者を代理して、遺産分割の交渉や家庭裁判所での調停・訴訟に臨むことが可能です。
遺産分割の交渉・調停・訴訟の代理
相続人同士で直接話し合うのが難しい場合、依頼者の代理人として交渉を行います。交渉で解決しない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟手続きに移行し、法的な解決を目指します。
相続放棄や限定承認の申述手続き
他の士業では対応できない家庭裁判所への相続放棄申述(相続放棄の手続き)や限定承認手続きについても、代理人として手続きを進めることが可能です。
相続人・財産調査や遺産分割協議書の作成
弁護士は戸籍収集による相続人調査や財産調査、遺産分割協議書や遺言書の作成支援なども行うため、法律に関する手続き全般を幅広くサポートできます。
依頼する際の注意点|対応できない業務と費用
弁護士への依頼を検討する際は、専門外の業務と費用感を把握しておくことが重要です。
相続税申告や不動産登記は専門外
弁護士は税務の専門家ではないため、相続税の申告や税務相談には対応できません。また、法律上は不動産登記も可能ですが、実務として行わない事務所が多いため、相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は高額なため、紛争リスクに応じて検討
弁護士への依頼は他の専門家より高額になりやすい傾向があり、数十万円から数百万円規模の費用を見込む必要があります。「費用がかかっても法的に確実な解決を図りたい」「揉め事のリスクが高い」場合に適しています。
税理士:相続税申告と税務対策のプロ
税理士は税務の専門家であり、相続税の申告や節税相談を担う重要な存在です。相続財産の評価計算や相続税申告書の作成・提出を代理できるのは税理士(または税理士資格保有者)だけであるため、相続税が発生する場合は基本的に税理士への依頼が必要となります。
相談すべきケース:相続税の申告義務がある場合
相続税の基礎控除額(非課税枠)は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算され、この金額を超える遺産を相続する場合は申告が必要です。相続財産の評価計算や相続税申告書の作成・提出を代理できるのは税理士だけであるため、相続税が発生する場合は基本的に税理士への依頼が必須となります。
税理士ができること|相続税申告から節税アドバイスまで
申告期限は被相続人(亡くなった方)の死亡から10ヶ月以内と定められているため、早期の相談が重要です。
相続税申告書の作成・提出
遺産全体を踏まえた適正な相続税額を計算し、税務署へ提出する申告書を作成・提出します。
特例活用や二次相続を見据えた節税対策の助言
どの不動産を誰が相続するかで税額が変わるため、自宅土地の評価減(小規模宅地等の特例)など、最適な特例の活用を助言します。これにより「特例を使い忘れた」「税金を払い過ぎた」といった失敗を防げます。
依頼する際の注意点|紛争解決や登記手続きは不可
相続に精通した税理士であれば、必要に応じて他の専門家(弁護士や司法書士など)を紹介し、連携して一連の手続きを進めてくれるケースもありますが、税理士自身が紛争解決や登記を行うことはできません。
司法書士:不動産の名義変更・登記手続きのプロ
司法書士は登記手続きの専門家で、不動産の相続登記(名義変更)を代行するケースが非常に多い職種です。
相談すべきケース:遺産に不動産が含まれる場合
被相続人名義の土地や建物などが遺産に含まれる場合は、法務局での所有権移転手続きが必要となり、司法書士に依頼するのが一般的です。
2024年から相続登記は義務化!放置すると過料の対象に
2024年の法改正により、相続登記の申請が義務化され、相続から原則3年以内に申請を行わなければなりません。怠ると過料の対象にもなるため、早めの対応が求められます。
司法書士ができること|登記を中心に周辺業務もカバー
司法書士は登記以外にも、相続関連業務をある程度カバーできます。
遺産分割協議書の作成や相続人調査のサポート
不動産を相続する場合、まず相続人全員で遺産の分配を決める必要がありますが、司法書士に依頼すれば、協議書の作成から登記申請までまとめてサポートしてもらえます。
会社の役員変更登記などにも対応
被相続人が会社役員だった場合には、役員変更登記(取締役の死亡による役員抹消登記)も司法書士の業務範囲です。
依頼する際の注意点|紛争解決や税務相談は専門外
司法書士には裁判所での手続き代理権がないため、相続をめぐる調停や訴訟には対応できません。また税理士資格を持たない場合は相続税申告も行えないため、税金が発生する場合は税理士との連携が不可欠です。不動産の相続登記が必要で、かつ揉め事がないケースではコストパフォーマンスに優れた選択肢となります。
行政書士:書類作成・行政手続きサポートのプロ
行政書士は官公庁に提出する書類作成を中心業務とする専門家で、相続分野では各種書類作成や手続き代行のサポート役として活躍します。
相談すべきケース:争いがなく、費用を抑えて手続きしたい場合
行政書士に依頼するメリットは、書類作成や手続き代行を比較的低コスト(数万円〜十数万円程度)で依頼できる点にあります。相続人間で争いがなく、相続税も発生しないようなシンプルなケースに適しています。
行政書士ができること|書類作成と各種名義変更
具体的には、戸籍収集による相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更などを幅広く対応します。
遺産分割協議書・遺言書文案の作成
相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書の文案を作成します。
預貯金や自動車の名義変更
銀行・証券会社の残高証明取得や、預貯金口座の払い戻し、自動車の名義変更手続きなどを代行します。
依頼する際の注意点|紛争・登記・税務には対応不可
行政書士には裁判所での手続き代理権や登記申請代理権がないため、遺産分割調停や不動産の相続登記、相続税申告はできません。これらの手続きが必要な場合は、それぞれ弁護士、司法書士、税理士との連携が必須となります。
専門家に個別で依頼するか、ワンストップで相談するか
相続手続きを進めるうえで、「自分で必要な専門家を探し、個別に依頼する方法」と、「銀行や信託銀行、IFAなどの総合窓口でワンストップサービスを利用する方法」の2つが代表的な選択肢として挙げられます。以下では、それぞれの特徴や向いているケースをまとめています。
個別相談をした方がいい人はこういう人
必要な専門家だけを選んで依頼したい人
相続内容に応じて、「税金の申告だけ税理士に頼む」「登記は自分で行う」といった柔軟な選択が可能です。無駄な費用を抑え、必要なサポートだけを受けたい方に向いています。
自分で相手を選びたい・直接やり取りしたい人
たとえば知人の紹介や過去の実績、相性などを重視して専門家を選べます。一人ひとりと直接契約するため、担当者が変わりにくいのも安心材料です。
連絡調整やコーディネートを自分で行っても苦にならない人
複数の専門家に依頼する場合、書類や情報のやり取りなど、各方面との連絡調整は依頼者自身が主導するのが原則です。自分の希望を細かくコントロールしながら進めたい人には、むしろやりやすい方法と言えます。
相続がシンプルで、連携の必要が少ないケース
不動産登記のみ・相続税申告のみといった単一の課題であれば、個別依頼ができ手間も費用も最小限で済みます。ただし紛争・税金・不動産など複数の要素が絡む場合は、各専門家への連絡や情報共有が煩雑になる点に注意しましょう。
ワンストップで相談した方がいい人はこういう人
手続きが複雑で、多方面にまたがる相続を抱えている人
銀行や信託銀行、IFAなどに相談すれば、相続登記から税務申告、財産調査まで複数の専門家との連携を一括で任せられます。依頼者は総合窓口の担当者とやり取りすればよいため、手間を大幅に削減できます。
資産運用や不動産活用などを総合的に提案してほしい人
金融機関系や中立的なIFAであれば、相続手続きだけでなく資産運用・生前贈与・不動産売却など、多岐にわたるアドバイスを受けられます。相続財産が大きく、今後の資産管理や活用まで含めて検討したい方に向いています。
多少費用がかかっても、まとめて楽に進めたい人
ワンストップサービスは便利な反面、手数料が割高になる傾向があります。しかし「手続きが複雑すぎて自分で管理するのは大変」「早く片付けたい」と考える方にとっては、有力な選択肢となるでしょう。
この記事のまとめ
相続は人生に何度もあるものではなく、だからこそ事前の準備と的確な相談が重要です。この記事を読んで「どの専門家に何を頼めばいいか」が分かった今こそ、信頼できる専門家との対話を始める好機です。
特に相続には法務・税務・登記といった複雑な分野が絡むため、自分だけで完結させようとせず、早めの相談がトラブル回避につながります。
「どこに頼んでいいかわからない」「専門家同士の連携まで考えると不安」という方は、IFAや信託銀行などのワンストップ型窓口に一度相談してみましょう。最初の一歩が、将来の大きな安心につながります。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
相続
相続とは、人が亡くなった際に、その人が所有していた財産や権利、さらには借金などの義務を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことを指します。相続の対象となるのは、不動産、預貯金、有価証券などの資産に加え、住宅ローンや借入金などの負債も含まれるため、慎重な対応が求められます。 相続が発生すると、まずは誰がどの財産をどの程度受け取るかを決める「遺産分割」の手続きが必要になります。この分配は、民法で定められた割合に基づく「法定相続」によって進めることもあれば、亡くなった方が遺言書を残していた場合は、その内容に従って行われることもあります。 資産運用の観点では、相続によって得た財産をいかに管理し、長期的に活かしていくかが重要なテーマとなります。たとえば、相続した不動産を売却して資産を分散投資に振り向けるケースや、相続した株式をそのまま長期保有する戦略など、相続後の運用方針によって将来の資産価値が大きく変わる可能性もあります。 また、相続には相続税の申告・納付期限や、不動産の名義変更、金融機関での手続きなど、時間的制約と法的手続きが伴うため、早めの準備と専門家のサポートが不可欠です。資産を次世代へスムーズに引き継ぎ、無駄なコストやトラブルを避けるためにも、生前からの対策と継続的な資産設計が求められます。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
登記(登記手続き)
登記とは、会社の設立や変更、財産の所有権などの法的事項を公的な記録として登録する手続きのことを指します。会社の登記は法務局で行われ、商号、本店所在地、役員構成などが記録されます。これらの登記情報は誰でも確認でき、取引の透明性を確保するために重要な役割を果たします。 投資家にとっても、登記情報は企業の実在性や信用を確認するための客観的な根拠のひとつであり、投資判断の信頼性を高める助けになります。また、不動産投資においても、登記を通じて所有権や担保権の状態を確認できます。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
独立系アドバイザー(IFA)
IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、日本語では「独立系フィナンシャルアドバイザー」と呼ばれる資産運用の専門家を指す。内閣総理大臣より金融商品仲介業の登録を受け、1つ以上の証券会社と業務委託契約を締結し、投資家に対して資産運用のアドバイス業務や金融商品の仲介を行う。
信託銀行
信託銀行とは、銀行業務に加えて信託業務を行う金融機関のことで、資産の管理・運用・承継を専門的に取り扱う。個人向けには遺言信託や資産承継のサポート、法人向けには年金信託や不動産管理などを提供する。特に、富裕層に対する資産保全や相続対策の面で重要な役割を果たし、長期的な資産管理の手段として活用される。信託契約を通じて、顧客の資産を安全に管理し、特定の目的に沿った資産運用が可能となる。
過料
過料とは、法律や条例に違反した際に科される金銭的な制裁の一種で、刑罰ではなく行政上の処分として課されるものです。罰金や科料と異なり、過料の支払いによって前科が付くことはなく、あくまで法令違反に対する行政的なペナルティという位置づけになります。 たとえば、税務申告を期限内に行わなかったり、不動産の登記や相続手続きが遅れた場合などに、過料が科されることがあります。資産運用や相続においては、期限や手続きの不備によって思わぬ過料が発生するケースもあるため、事前にスケジュールや要件を確認し、適切に対応することが重要です。 また、法人で資産を保有している場合には、過料が税務上損金として処理できるかどうかも実務上の注意点となります。結論として、過料は原則として損金算入が認められていません。これは、法人税法において違法行為に基づく支出を税務上の費用として扱わないという考え方に基づいており、罰金や過料、科料などの制裁金はすべて損金不算入とされています。したがって、過料の支払いは実質的に企業や個人の資産を直接的に減少させる費用となり、税務上の負担軽減にはつながらない点に注意が必要です。 資産運用や相続対策を行う上では、こうした手続きミスや期限超過による過料のリスクをあらかじめ認識し、予防策を講じておくことが賢明です。特に法人や資産管理会社を活用している場合は、税務上の扱いも含めて専門家と連携しながら進めることが望まれます。