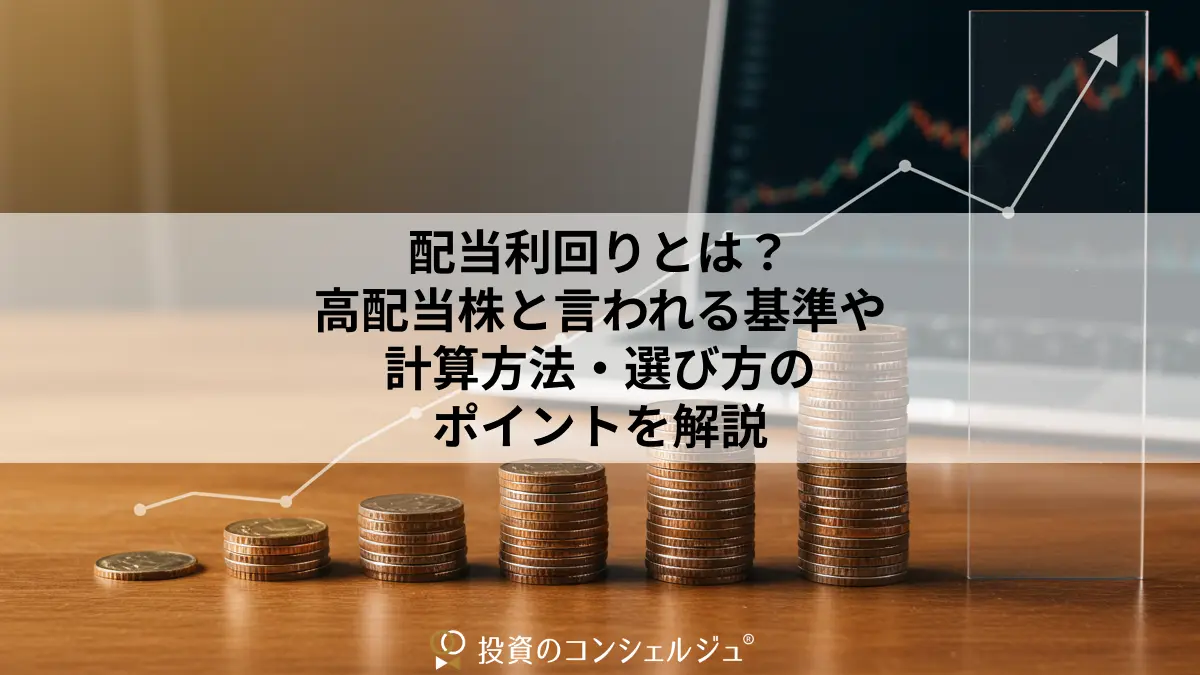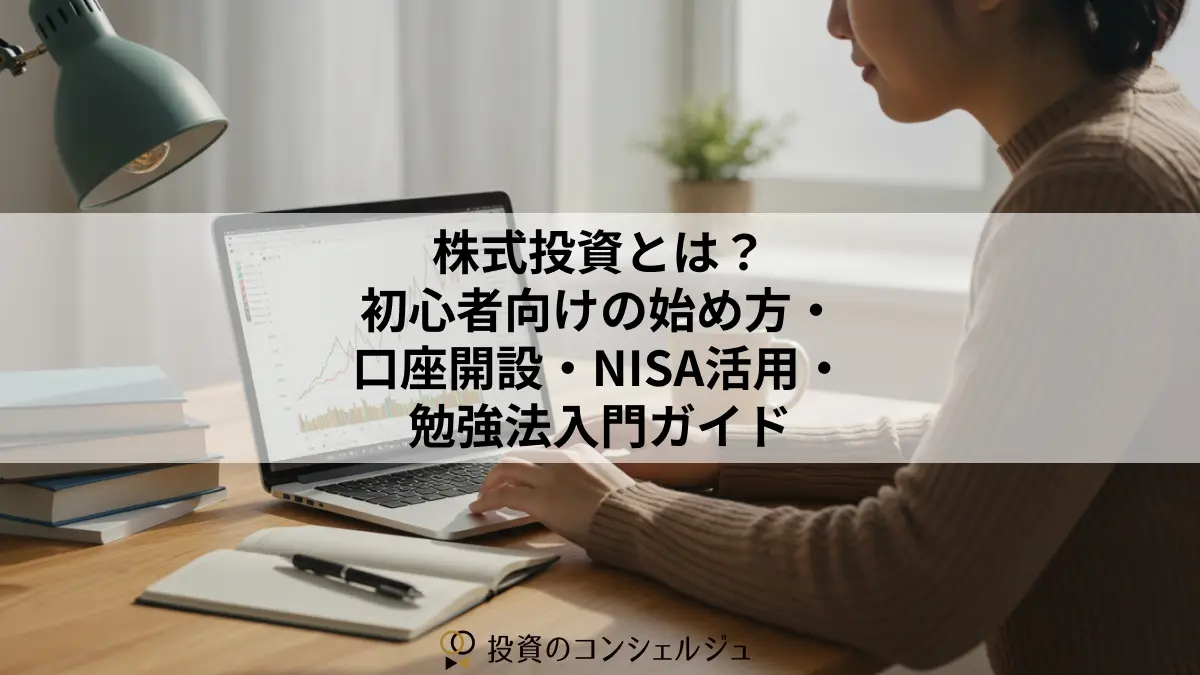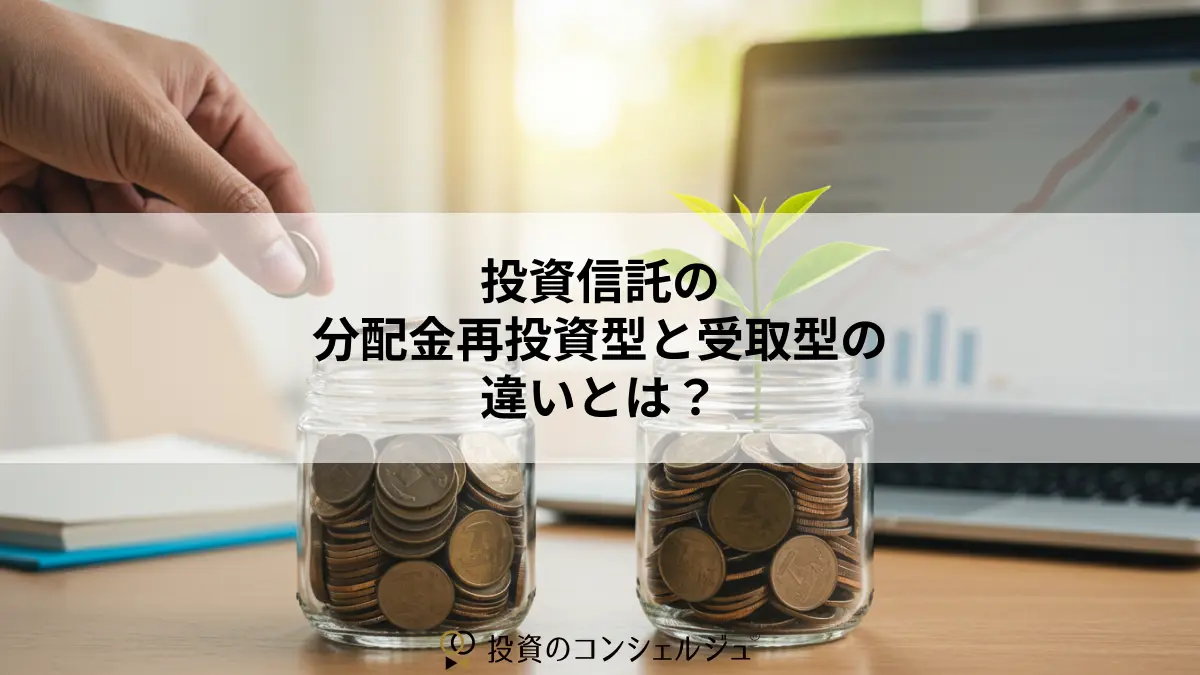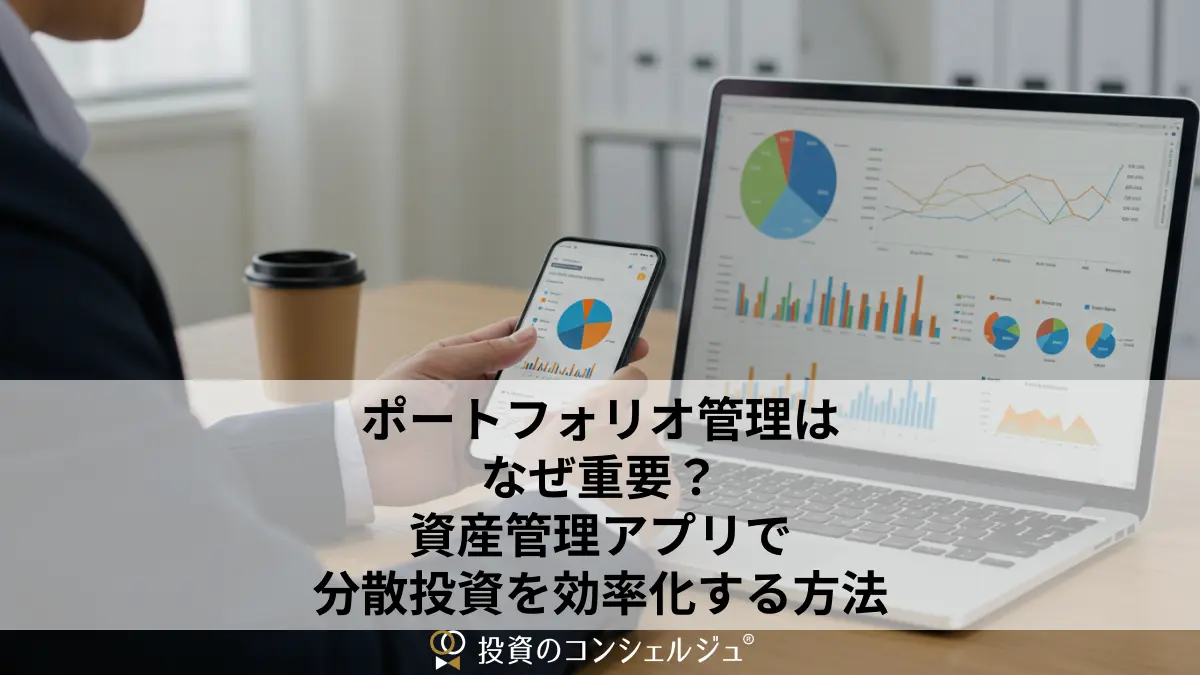株の利回りとはどのように計算しますか?
回答受付中
0
2025/08/09 08:19
男性
30代
株を購入すると「利回りが〇%」という表現をよく目にしますが、具体的にどのような計算式で求められているのかがわかりません。利回りの計算方法やその考え方について教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
株式投資における「利回り」とは、投資した金額に対してどれだけ利益を得られるかを表す指標です。銀行預金の利息と似た考え方ですが、株の場合は主に「配当金」や「株価の値上がり益(キャピタルゲイン)」によって利益が得られるため、これらを踏まえて利回りを計算します。
まず、最もよく使われるのが「配当利回り」です。これは、1株あたりの年間配当金を現在の株価で割って求めます。たとえば、株価が1,200円の銘柄が年間60円の配当を出していれば、配当利回りは5%になります。配当利回りには、過去の実績に基づく「実績利回り」と、企業が発表する予定に基づく「予想利回り」があります。
次に、「キャピタルゲイン利回り」も重要です。これは、株を買ってから売るまでにどれだけ値上がりしたかを計算します。たとえば、1,000円で買った株を1年後に1,150円で売れば、15%の利回りが得られたことになります。ただし、これは売却して初めて確定する利益であり、保有中の評価益(含み益)とは異なります。
これらを合わせた「総合利回り(トータルリターン)」が、実際の投資成果に近い指標です。たとえば、1,000円で購入した株が1年後に1,100円になり、さらに配当として30円を受け取った場合、配当利回り3%とキャピタルゲイン利回り10%を足して、総合利回りは13%になります。
利回りを考える際にはいくつか注意点もあります。まず、配当金や売却益には通常20.315%の税金がかかります(NISA口座を使えば非課税)。また、保有期間が短い場合は年率換算して比較する必要があります。加えて、売買手数料や、ETFなどの場合の信託報酬など、コストも考慮しなければなりません。さらに、インフレ率も踏まえて「実質利回り」を意識することが重要です。
利回りは、銘柄選びやポートフォリオの見直し、配当の再投資戦略など、資産運用のさまざまな場面で活用できます。特に初心者の方は、まず配当利回りから理解し、徐々に総合利回りでの評価に慣れていくのがおすすめです。長期投資では、利回りの積み重ねが将来の資産形成に大きな影響を与えます。
関連記事
関連する専門用語
配当利回り
配当利回りは、株式を1株保有したときに1年間で受け取れる配当金が株価の何%に当たるかを示す指標です。計算式は「年間配当金÷株価×100」で、株価1,000円・配当40円なら4%になります。 指標には、実際に支払われた金額で計算する実績利回りと、会社予想やアナリスト予想を用いる予想利回りの2種類があります。株価が下がれば利回りは見かけ上上昇するため、高利回りが必ずしも割安や安全を意味するわけではありません。 安定配当の見極めには、配当性向が30~50%程度であること、フリーキャッシュフローに余裕があることが重要です。また、権利付き最終日の翌営業日には理論上配当金相当分だけ株価が下がる「配当落ち」が起こります。 日本株の配当は通常20.315%課税されますが、新NISA口座内で受け取る配当は非課税です。配当利回りは預金金利や債券利回りと比較でき、インカム収益を重視する長期投資家が銘柄や高配当ETFを選ぶ際の判断材料となります。
配当(配当金)
配当とは、会社が得た利益の一部を株主に分配するお金のことをいいます。企業は利益を出したあと、その一部を将来の投資に使い、残った分を株主に還元することがあります。このときに支払われるお金が配当金です。株を持っていると、持ち株数に応じて定期的に配当金を受け取ることができます。多くの場合、年に1回または2回支払われ、企業によって金額や支払い時期は異なります。配当は企業からの「お礼」のようなもので、株を長く持ち続ける理由の一つになることがあります。
キャピタルゲイン(売却益/譲渡所得)
キャピタルゲインとは、株式や不動産、投資信託などの資産を購入した価格よりも高く売却したことによって得られる利益のことです。一般的な経済用語としては「売却益」と呼ばれ、資産運用における収益のひとつとして広く使われています。日本の税法においては、このキャピタルゲインは「譲渡所得」として分類され、確定申告などで所得として扱われます。つまり、経済的な意味ではキャピタルゲインと譲渡所得は同様の概念を指しますが、前者が広義の利益、後者が課税対象としての所得という違いがあります。投資の成果を判断したり、税金を計算したりするうえで、両者の使われ方を正しく理解することが大切です。
含み損益
含み損益とは、保有している資産をまだ売却していない段階で発生している、見かけ上の利益や損失のことを指します。たとえば、購入時よりも価格が上がっている株を持っていれば「含み益」、逆に価格が下がっていれば「含み損」となります。 これはあくまで現在の評価額と購入額の差であり、実際に売却して現金化しない限り、確定した損益とはなりません。そのため、「含み」とは「まだ確定していない」という意味を含んでいます。 投資判断をする際には、この含み損益をもとに、売却のタイミングや資産配分の見直しを検討することがあります。また、税金は原則として実際に売却して利益が確定した時点で課税されるため、含み益があるだけでは課税対象にはなりません。資産運用において、現在の状況を把握する重要な指標のひとつです。
トータルリターン
トータルリターンとは、株式や債券、投資信託などの資産から得られる利益を、値上がり益(キャピタルゲイン)と分配金・利息・配当金などのインカムゲインを合わせて総合的に捉えた指標です。配当や利息をその都度再投資すると仮定して計算するのが一般的であり、単に価格変動だけを追う「価格リターン」と比べ、投資の実質的な運用成果をより正確に示します。このため、長期投資のパフォーマンス評価や異なる資産クラスの比較を行う際には、トータルリターンで見ることが重要です。
実質利回り
実質利回りとは、資産運用において、名目上の利回りから運用コストや税金、インフレの影響を差し引いた後の、実際に得られる利益率を示す指標です。金融資産や不動産など、さまざまな資産運用の分野で活用され、投資の収益性をより正確に評価するために重要な役割を持ちます。 金融資産においては、債券や定期預金などの固定利回りの金融商品では、インフレ率が名目利回りを上回ると実質利回りがマイナスになり、資産価値が目減りするリスクがあります。そのため、投資家は名目利回りだけでなく、インフレ調整後の実質利回りを確認することで、資産の購買力を維持しながら運用することができます。 不動産投資では、実質利回りは単なる表面利回りとは異なり、賃貸収入から管理費、修繕費、固定資産税、ローンの利息などのコストを差し引いた後の利益をもとに算出されます。さらに、インフレによって家賃が上昇すれば実質利回りが向上する一方で、維持費の増加によって利回りが低下する可能性もあります。そのため、不動産投資では、地域の経済成長や賃料の上昇余地を考慮しながら、実質利回りを長期的に評価することが求められます。 資産運用全体において、実質利回りを考慮することで、単なる表面上の収益ではなく、実際に資産を増やすための正確な指標を得ることができます。運用コストや税金、インフレといった要素を踏まえて投資判断を行うことが、資産の成長と保全のために不可欠です。