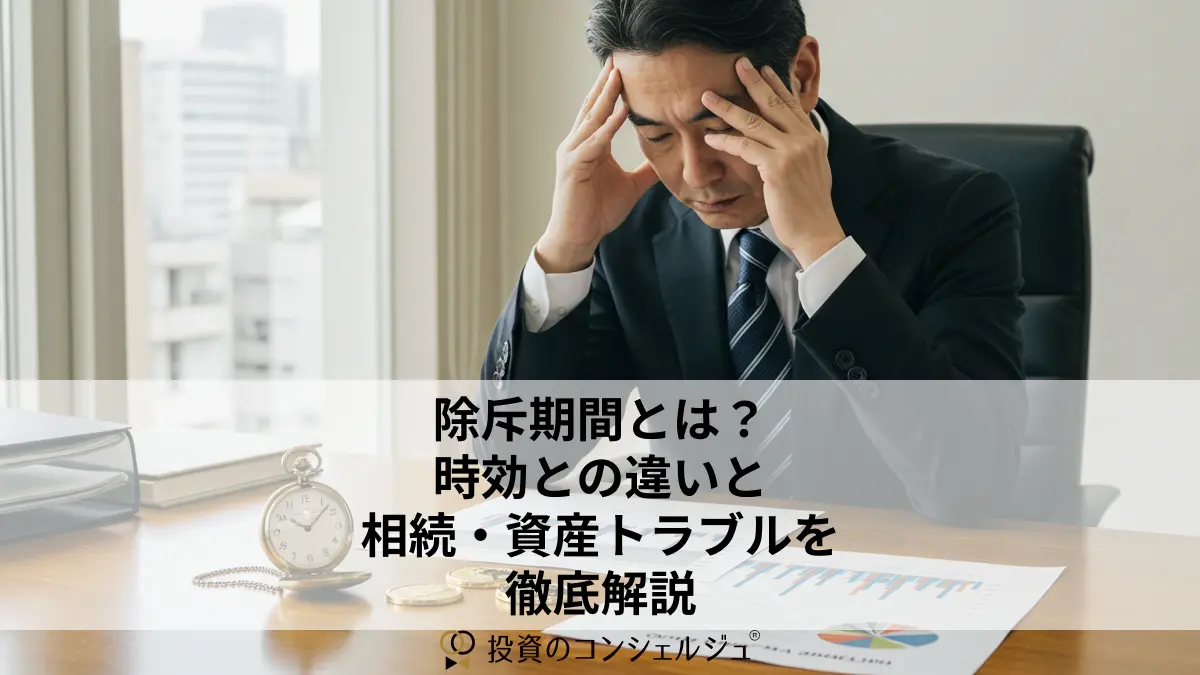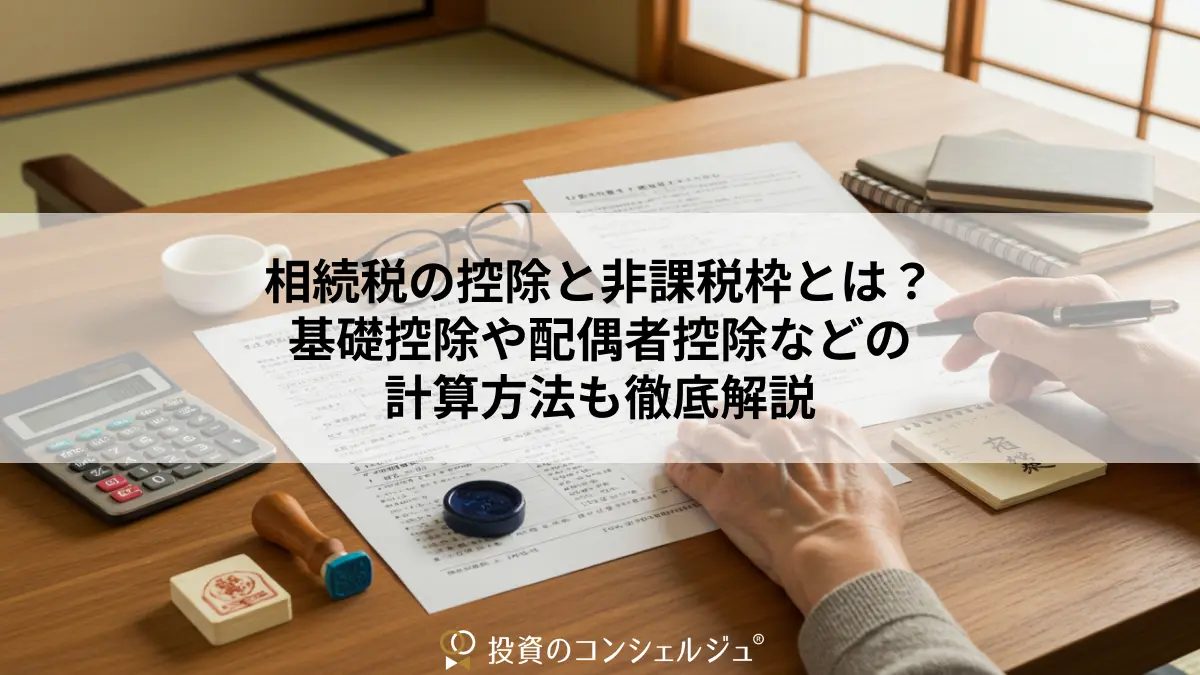亡くなった親が連帯保証人となっていた借金の相続でも時効の援用はできますか?
回答受付中
0
2025/08/09 08:19
男性
30代
亡くなった親が知人の借金の連帯保証人になっていたと聞きました。遺産分割協議も済んでいない段階ですが、突然保証債務の請求書が届き、不安です。このような場合でも、時効の援用をして支払い義務を免れることはできるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
亡くなった親が連帯保証人となっていた借金についても、一定の条件を満たせば、相続人が「時効の援用」によって返済義務を免れることが可能です。具体的には、消滅時効の期間がすでに経過しており、その間に裁判所での手続きや債務の承認など、時効を中断・更新させるような行為がなかった場合に限られます。
保証債務の消滅時効期間は、契約の時期や内容によって異なります。2020年4月1日以降に成立した貸金契約では、原則として「権利行使ができることを知った時から5年」または「最長10年」で消滅します。個人間の貸し借りか、金融機関との契約かによっても異なるため、まずは契約書や返済履歴などの資料を確認することが重要です。
援用に向けては、次のようなステップを踏むのが一般的です。まず、連帯保証契約書や督促状などの資料を集め、時効が完成しているかを確認します。次に、債権者に対して内容証明郵便で時効援用の意思を通知します。これは、文面に「連帯保証債務について消滅時効を援用します」と明記し、配達証明付きで送付することが必要です。また、信用情報機関(CICやJICCなど)に情報開示を請求し、自分の信用情報に延滞や債務が記録されているかも確認しておきましょう。
ただし、注意すべき点もあります。たとえば、債権者からの督促に対して「支払います」と返事をしてしまうと、債務の承認と見なされて時効がリセットされてしまうことがあります。また、裁判所から支払督促や訴状が届いた場合、それを無視してしまうと時効中断が成立してしまうこともあるため、すぐに専門家に相談することが大切です。
なお、相続開始後6か月以内に時効が完成する場合には、民法160条により時効完成が6か月猶予される特例もあります。相続人の保護のための制度ですので、この点も踏まえて判断すべきでしょう。
時効援用が成功すれば、債務は法的に消滅し、債権者は以後請求できなくなります。信用情報についても、援用自体は事故情報として登録されないことが多いですが、過去の延滞記録が残る可能性はあります。そのため、住宅ローンや新たな借り入れを希望する場合は、一定期間不利になることもあります。
また、時効援用ができれば、相続財産の負債として保証債務を計上する必要がなくなるため、遺産分割協議がスムーズに進むという副次的なメリットもあります。
最後に、判断が難しい場合や書類が揃わない場合、あるいは3か月の相続放棄期間が迫っているような状況では、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。内容証明の作成だけであれば3〜5万円ほど、訴訟対応まで依頼する場合には10万円以上かかるケースもありますが、確実な解決のためには有効な手段です。
このように、連帯保証債務であっても時効の援用が可能なケースはありますので、まずは落ち着いて状況を整理し、法的な時効期間が経過しているかを確認することが出発点となります。
関連記事
関連する専門用語
時効の援用
時効の援用とは、一定期間が経過したことで法律上の権利や義務が消滅する時効制度を、自らの利益のために正式に主張することをいいます。たとえば借金の返済義務は、法律で定められた期間が過ぎれば時効によって消滅する可能性がありますが、その効力は自動的には発生せず、本人が「時効を援用します」と意思表示をすることで初めて成立します。資産運用においては、直接的な投資商品の仕組みというよりも、金融取引や債務整理、相続などに関わる法的リスク管理の一環として理解しておくことが重要です。
消滅時効
消滅時効とは、一定の期間が経過すると、法律上の権利が行使できなくなる制度のことです。たとえば、お金を貸した場合、一定の年数が過ぎてしまうと、原則として裁判などで返済を請求する権利が消滅します。これは、時間の経過とともに事実関係が不明確になることを避け、社会的な安定と公平を図るために設けられている制度です。 民法では、原則として権利を行使できることを知ったときから5年(または権利が発生してから10年)という期間が定められています。資産運用や金融の分野でも、貸付債権、未払いの配当金、保険金請求などにおいて消滅時効のルールが適用され、時効を過ぎると本来受け取れるはずだった資産を失う可能性があります。したがって、請求や権利行使のタイミングには注意が必要であり、時効制度の理解は金融実務において極めて重要です。
連帯保証人
連帯保証人とは、主たる借主と同じ立場で返済義務を負う保証人のことです。通常の保証人と異なり、債権者は借主に請求する前に、いきなり連帯保証人へ全額請求することができます。また、連帯保証人は「自分の負担分だけ払えばよい」という考え方は通用せず、借主が支払えない場合は全額を肩代わりしなければなりません。 資産運用や家計管理の観点では、連帯保証人になることは大きなリスクを伴い、自分の信用情報や将来の資金計画にも直接影響するため、慎重な判断が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どんな内容の文書を送ったのかを、日本郵便が証明してくれる特別な郵便のことです。たとえば、お金の返済を正式に請求したり、契約の解除を通知したりする場合に使われます。普通の手紙とは違い、郵便局が内容を記録・保管し、あとから「確かにこの文書を送りました」と証明してくれるため、トラブルが起きたときに自分の主張を裏付ける証拠として使えます。資産運用や相続の場面でも、貸付金の返還請求や相続放棄の意思表示など、法的に重要なやりとりを確実に記録に残したい場合に活用されることがあります。慎重に相手に伝えたい意思があるときに、非常に役立つ手段です。