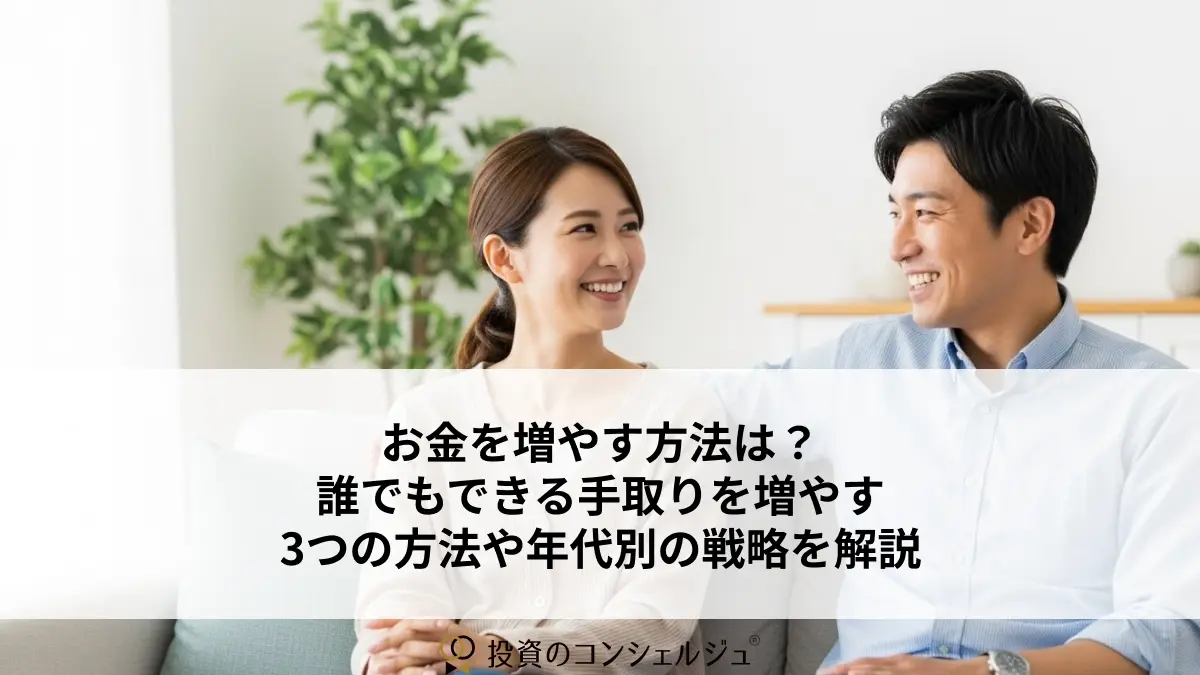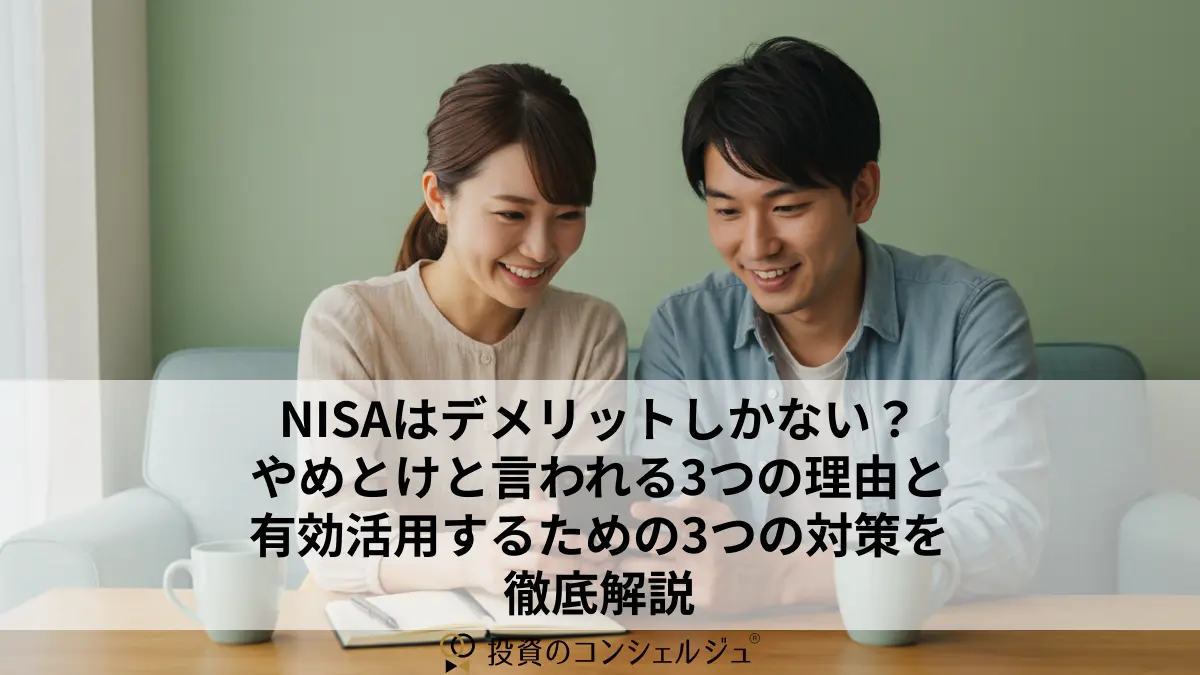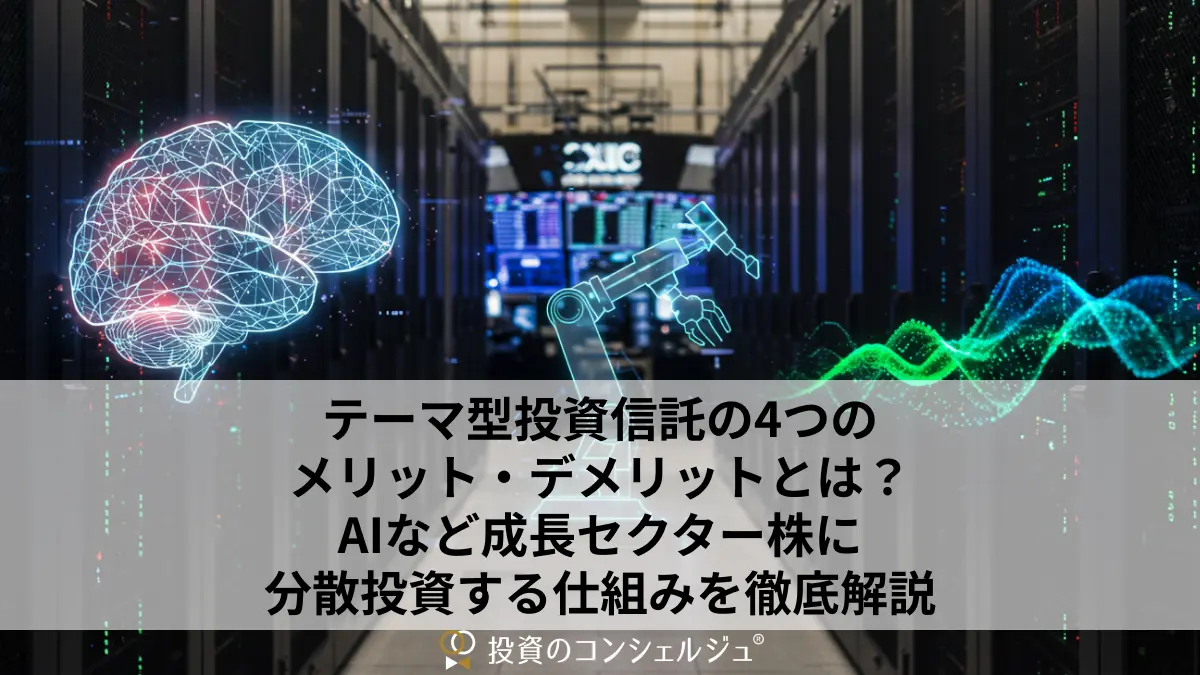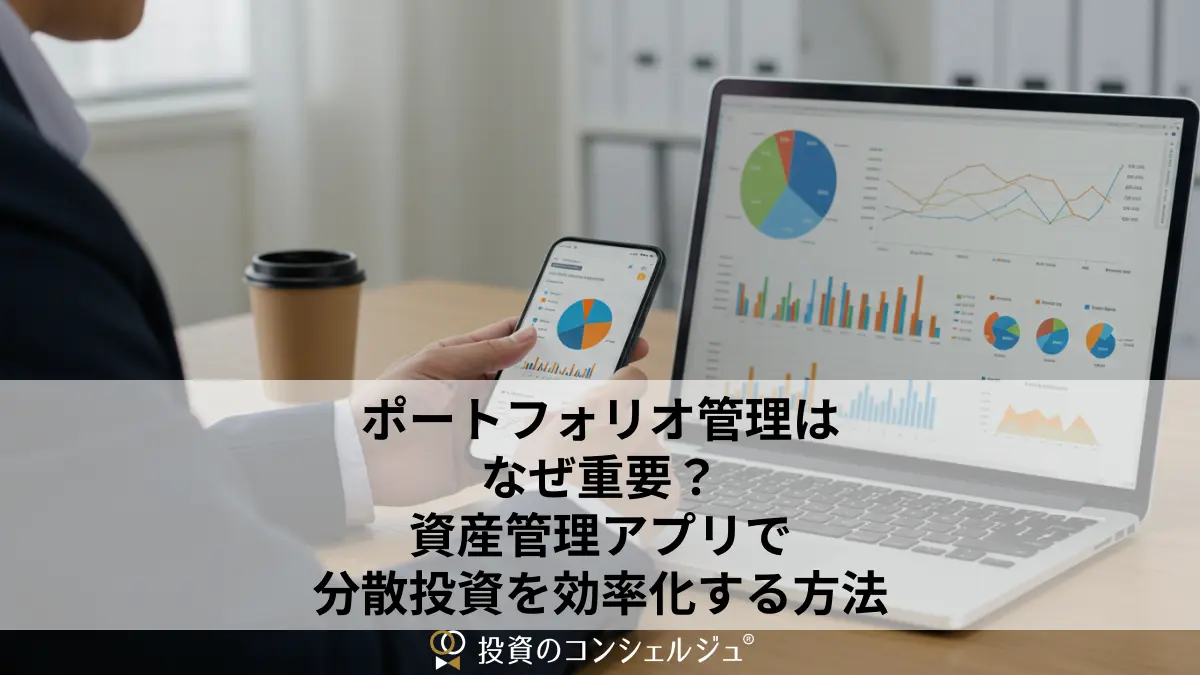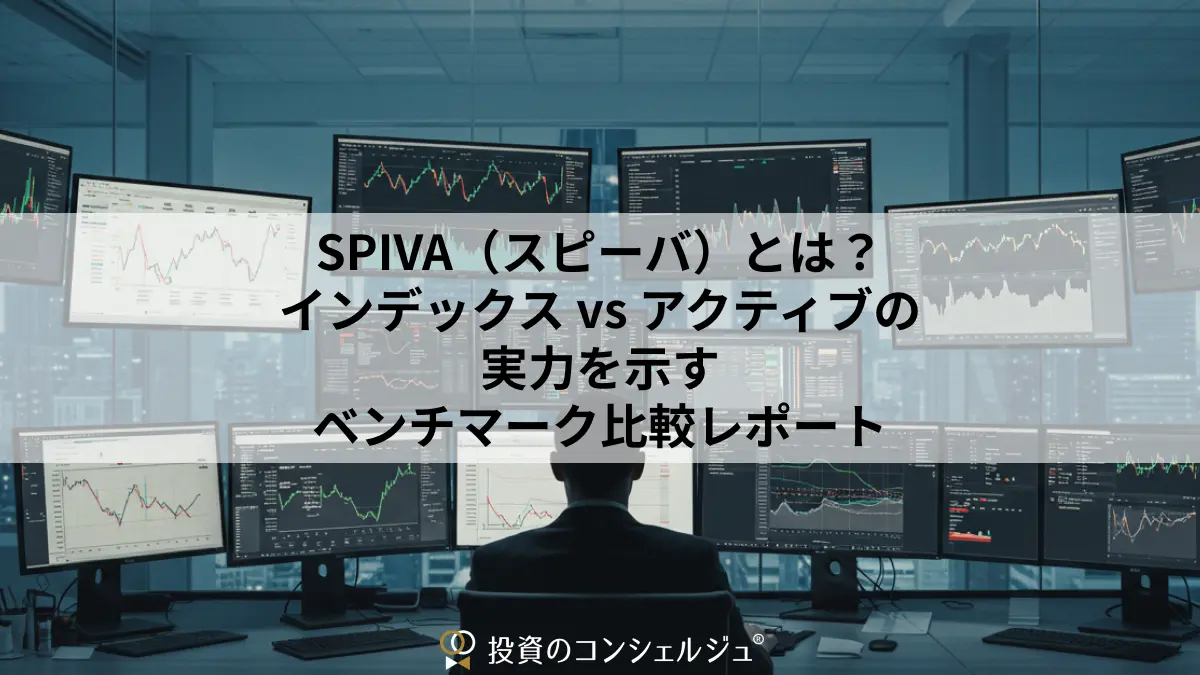コアサテライト戦略とは?守りと攻めの組み合わせで実現する安定と成長両取りの投資術
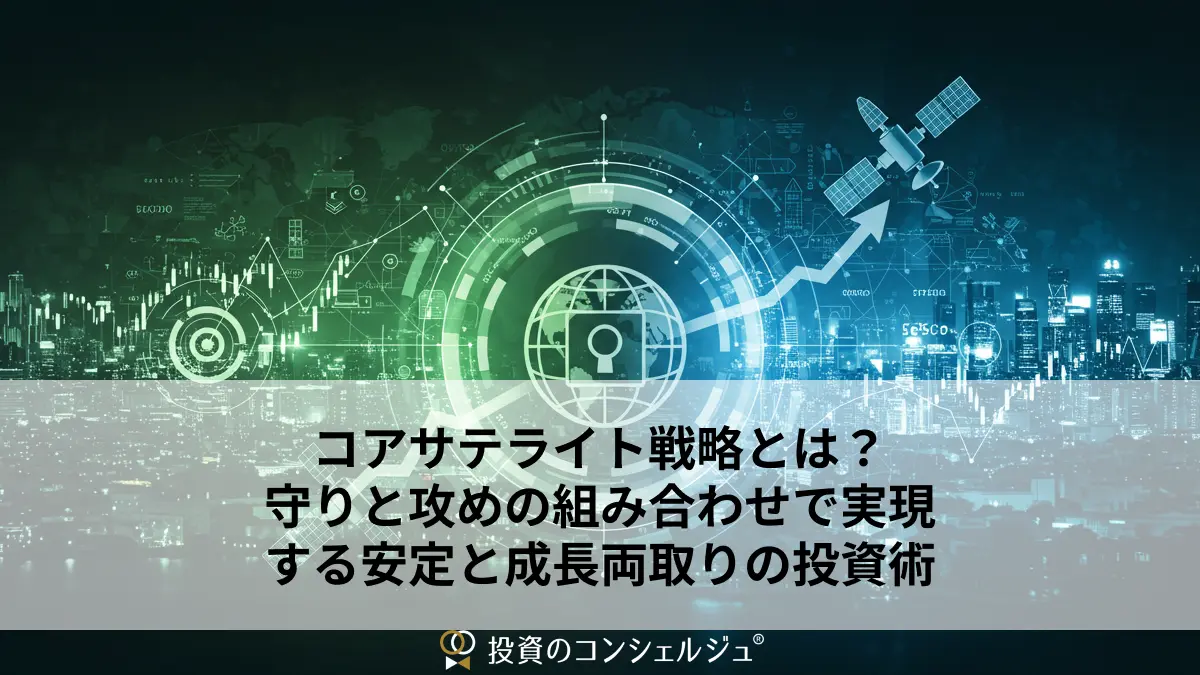
コアサテライト戦略とは?守りと攻めの組み合わせで実現する安定と成長両取りの投資術
難易度:
執筆者:
公開:
2025.09.25
更新:
2025.11.07
コアサテライト戦略は、資産を「守りのコア」と「攻めのサテライト」に分け、安定性と成長性を両立させる手法です。もともと機関投資家が実践してきた考え方ですが、個人投資家にも応用できます。ただし、役割を混同したり、サテライトに比重を置きすぎたりすると、想定以上のリスクを抱える可能性があります。本記事では、基本概念や比率の考え方、商品選びやリバランスの方法までを整理し、実践に必要なステップをわかりやすく解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、資産を「守りのコア」と「攻めのサテライト」に分けて運用する考え方を理解し、自分に合った最適な比率を設定できるようになります。
一般的な目安「コア70〜90%/サテライト10〜30%」を踏まえ、リスク許容度や年齢、資産状況に応じた調整の方法も学べます。また、商品選定の基準やリバランスの実践法、初心者が陥りやすい注意点まで体系的に整理されており、今日から実装可能な戦略を自分の資産形成に落とし込めるようになります。
目次
コアサテライト戦略の基本:「守り」と「攻め」で資産を育てる考え方
本質はインデックスかアクティブかではなく「守り×攻め」の役割分担
コア資産の役割:ポートフォリオの土台として長期・安定を支えるもの
一般的な配分の目安:「コア70〜90%、サテライト10〜30%」が基本
最適な比率を決めるには:リスク許容度・年齢・運用期間を基準に
メリット1:分散効果でポートフォリオ全体のリスクを抑えやすい
メリット3:サテライトで市場平均以上のリターンを狙う余地がある
初心者でも簡単!コアサテライト戦略を始める6つの実践ステップ
STEP1:自分のリスク許容度を把握し、運用目標を明確にする
STEP3:サテライト資産を選ぶ|テーマやアクティブで“攻め”を少額配分
STEP4:新NISAとiDeCoをフル活用し、税負担を軽くする
STEP6:管理ツールと記録で“見える化”し、運用を継続する
ケース1.30代・投資初心者Aさん:「コア9割」で堅実にスタート
ケース2.60代・リタイア準備層Bさん:「コア7割」で安定収入と成長を両立
ケース3.30代・子育て世帯Cさん:「コア8割」で手間なく計画的に資産形成
コアサテライト戦略の基本:「守り」と「攻め」で資産を育てる考え方
コアサテライト戦略は、資産を「守りのコア」と「攻めのサテライト」に分けて設計する手法です。全体の安定性を確保しつつ、一部で超過リターンを狙います。もともと機関投資家が実践してきた考え方ですが、個人でも同じ発想で再現できます。ここでは、その基本的な概念と、役割分担がなぜ効果的なポートフォリオにつながるのかを解説します。
「コア」で守り、「サテライト」で攻めるポートフォリオ戦略
ポートフォリオの大半を占めるコア資産は、広く分散され、低コストな商品を長期保有することを軸に、全体の安定性を担います。一方、残りのサテライト資産は、全体の配分を小さく保ちながら、テーマ性や成長性の高い商品へ機動的に投資し、超過リターンを追求します。この二層構造により、過度なリスクを避けつつ、安定と成長の両立を目指すことができます。
プロの考え方を個人投資に活かす3つの原則
このプロの設計思想は、以下の3つの原則に集約できます。
第一に、土台となるコア資産は徹底して広く分散させます。世界株式や先進国債券などでポートフォリオの基礎を築き、価格変動に耐える安定性を確保します。
第二に、「攻め」を担うサテライト資産の配分は小さく保ち、機動的に管理します。テーマ株や新興国株、アクティブファンドなどを活用し、高いリターンを狙います。
第三に、それぞれの役割を混同しないことが重要です。コアはあくまで「守り」、サテライトは「攻め」です。目的が異なるため、評価基準や売買のルールも分けて考えましょう。
この3点を守ることで、プロの戦略を個人の資産運用に無理なく取り入れられます。
本質はインデックスかアクティブかではなく「守り×攻め」の役割分担
重要なのは、商品の種類よりもまず役割で考えることです。コアは「広く、低コストで、長期保有」、サテライトは「狭く、高リスクで、機動的」なものと定義します。
王道は、コアに全世界株式や先進国債券のインデックスファンドを据え、サテライトでテーマ株やアクティブファンドなどを少額配分するという形です。ただし、この役割さえ守れるなら、例えばコアにアクティブ運用の債券ファンドを、サテライトに新興国株のインデックスファンドを組むといった構成も合理的と言えます。「インデックスかアクティブか」という二者択一に縛られず、役割を基準に柔軟に設計しましょう。
コアとサテライトの最適な比率は?役割と配分の考え方
コア資産とサテライト資産には明確な役割があり、その最適な配分比率は投資目的やリスク許容度によって異なります。ここでは、両者の役割を深く理解し、ご自身の状況に合った資産配分を見つけるための具体的な考え方を解説します。
コア資産の役割:ポートフォリオの土台として長期・安定を支えるもの
コア資産とは、ポートフォリオの安定性を確保するための「土台」となる部分です。家を建てる際の基礎や柱のように、市場の変動にも耐えられる強さを持たせる役割を担います。コア資産の主な特徴は、以下の3点に集約されます。
- 長期保有が前提:短期的な値動きに一喜一憂せず、数年〜数十年のスパンで保有することで、複利効果などを期待します。
- リスク抑制が目的:ポートフォリオ全体への影響を抑えるため、比較的価格変動の小さい資産(債券や全世界株式インデックスファンドなど)を中心に組み入れます。
- 徹底した分散:特定の国や資産が不調でも他でカバーできるよう、国・地域・資産クラスを幅広く分散させます。
このように、コア資産はポートフォリオの「守り」として、安定した収益基盤を築く上で最も重要な部分です。
サテライト資産の役割:超過リターンを狙う「攻め」の部分
サテライト資産は、コア部分だけでは得にくい追加的なリターン(超過リターン)を狙う「攻め」の部分です。コア資産よりもリスクは高くなりますが、うまく活用すれば資産の成長を加速させる可能性を秘めています。サテライト資産の主な性質は以下の通りです。
- 成長性を重視:将来の成長が期待されるテーマ株、新興国株、特定技術分野のアクティブファンドなどが投資対象になりやすいです。
- 価格変動が大きい:値動きが激しいものが多く、短期的には大きな損失を出すリスクも伴います。
- 全体の期待リターン向上:コアで安定を確保した上で、サテライトで全体のパフォーマンス向上を目指します。
堅固なコアという土台があるからこそ、サテライト部分ではより挑戦的な投資が可能になる、と理解しておきましょう。
一般的な配分の目安:「コア70〜90%、サテライト10〜30%」が基本
最適な資産配分に絶対の正解はありませんが、多くの専門家や金融機関が示す一般的な目安は存在します。
基本的な考え方として、「コア70〜90%、サテライト10〜30%」の範囲を基準とします。これは、資産の大部分で安定を確保しつつ、一部で成長を狙うというバランスの取れた比率です。
ご自身の考え方に応じて、この基準から調整します。例えば、リスクをより抑えたい方や退職が近い方はコアの比率を90%に近づけ、逆にリスクを取れる若年層や余裕資金の多い方は、サテライトの比率を30%に近づけるといった判断が考えられます。
最適な比率を決めるには:リスク許容度・年齢・運用期間を基準に
ご自身にとって最適な比率を見つけるには、以下の要素を総合的に判断することが大切です。
リスク許容度:価格変動への心の耐性
資産が値下がりした際に、冷静でいられるか、不安で眠れなくならないか、といったご自身の性格を考慮します。許容度を超えたリスクを取ると、冷静な判断ができなくなり、投資の継続が困難になります。
運用目的と期間:いつまでに、いくら必要か
「30年後の老後資金」と「5年後の教育資金」では、取れるリスクが全く異なります。運用期間が長いほど短期的な下落から回復する時間があるため、サテライトの比率を高める余地が生まれます。
年齢とライフステージ:回復できる時間の長さ
一般的に、若いうちは収入を得られる期間が長いため、リスクを取っても挽回しやすいと言われます。一方、年齢を重ねて退職が近づくと、資産を守る必要性が高まるため、コア比率を高めるのが堅実です。
資産状況:他の安全資産の有無
すでにある程度の預貯金や不動産といった安全資産を確保できている場合は、投資に回すお金でよりリスクを取る余裕が生まれます。逆に、安全資産が少ないうちは、まずコア資産の形成を優先すべきでしょう。
これらの基準を元に自分だけの資産配分を決め、市場の状況に応じて定期的に見直す(リバランスする)ことが、戦略を成功に導く鍵となります。
コアサテライト戦略の3つのメリット|安定性とリターンを両立
コアサテライト戦略は、「リスク分散による安定性の向上」「運用コストの最適化」「市場平均を超えるリターンの追求」という主に3つの点で効果を発揮します。ここでは、それぞれのメリットについて、なぜそう言えるのかという理由まで踏み込んで解説します。
メリット1:分散効果でポートフォリオ全体のリスクを抑えやすい
資産を「守りのコア」と「攻めのサテライト」に分けることで、ポートフォリオのリスクとリターンの役割を明確に分担できます。コア部分で世界株式や債券など値動きの異なる資産を広く組み合わせることで、資産全体の価格変動(ボラティリティ)を緩和します。これにより、相場が大きく荒れた局面でもコア資産がクッションとして機能し、サテライト部分の失敗がポートフォリオ全体に与える致命的な影響を防ぎやすくなります。
メリット2:低コストなコア中心で「手数料負け」を避けやすい
資産の大部分を占めるコア部分に低コストなインデックスファンドなどを採用するため、ポートフォリオ全体の運用コストを低く抑えやすい点も大きなメリットです。全体のコストは、各資産のコストをその配分比率に応じて平均したものになります。
そのため、仮に資産の8割を占めるコアの信託報酬が非常に低ければ、残り2割のサテライトのコストが多少高くても、全体として見れば手数料は低水準に保たれます。これにより、長期運用でじわじわと響いてくる「手数料負け」のリスクを避けやすくなります。
メリット3:サテライトで市場平均以上のリターンを狙う余地がある
コアで安定した土台を固めているからこそ、サテライト部分ではテーマ株や新興国株、アクティブファンドといった資産を少額配分し、市場平均を上回るリターン(アルファ)を積極的に狙うことができます。
相場環境の変化に応じて機動的に資産を入れ替えることで、市場全体が横ばいの局面でも、ポートフォリオ全体の成績を押し上げる効果が期待できます。ただし、このメリットを活かすには、サテライトはあくまで少額で、かつ事前に決めたルールに従って運用することが大前提です。この明確な役割分担が、安定性とリターンの両立を支えます。
コアサテライト戦略の3つのデメリットと注意点
コアサテライト戦略には多くのメリットがある一方、注意すべきデメリットも存在します。特に「管理の複雑さ」「サテライト部分の高いリスク」「運用成績のブレ」という3つの課題は、事前に理解しておくことが重要です。これらを把握せずに始めると、期待外れの結果につながりかねません。
デメリット1:複数商品を管理する手間が増え、やや複雑になる
資産を複数の商品に分散するため、ポートフォリオの管理はシンプルではなくなります。単一の商品であればその値動きを追うだけで済みますが、この戦略では複数の商品の状況を把握し、定期的に全体のバランスを調整(リバランス)する必要があります。
特に資産クラスが異なる場合、市場動向に応じた判断が求められるため、初心者にとっては管理の難易度が上がります。「分散効果の分だけ手間も増える」と念頭に置いておきましょう。
デメリット2:サテライト資産は大きな価格変動リスクを伴う
サテライト資産には高リスク商品が含まれるため、大きな値上がりの可能性がある一方、大幅な値下がりのリスクも伴います。サテライト部分が成功すれば全体の成績を押し上げますが、失敗するとポートフォリオ全体の足を引っ張る要因になり得ます。
特にボラティリティの高い資産を組み入れた場合、短期間での急落リスクを十分に認識しておく必要があります。損失の影響を限定するため、事前に損失許容範囲を決め、「何%下落したら損切りする」といったルールを設けて備えましょう。
デメリット3:サテライトの成否で運用成績がブレやすくなる
サテライト部分の成否によって、年ごとの運用成果がブレやすくなる点もデメリットと言えます。コア資産だけであれば市場平均並みの安定した成績に落ち着きやすいですが、サテライトの良し悪しでリターンに大きな差が出ることがあります。
サテライト運用は手間と時間がかかるため、中途半端な知識で臨むと失敗につながる恐れがあります。多忙な方や自信がない方は、無理にサテライト運用を行わずコア部分に集中するのも有効な選択です。管理できる範囲を超えると逆効果になるため注意しましょう。
初心者でも簡単!コアサテライト戦略を始める6つの実践ステップ
はじめに、コアサテライト戦略を今日から実装できるよう、6つの手順をチェックリスト形式で整理します。読み終えた時点で「配分比率の決定」「口座・枠の使い分け」「運用ルールの設定」まで一気通貫で決められる状態を目指します。
STEP1:自分のリスク許容度を把握し、運用目標を明確にする
まずは「どの程度の価格変動に耐えられるか(リスク許容度)」を把握します。収入・資産余力・性格・家計の安定度を踏まえ、証券会社の診断ツール等で自己チェックしましょう。
次に、目的と期限を伴う数値目標を設定します(例:20年で1,000万円、年平均リターン◯%を想定)。高リターンは高リスクを伴うため、許容度の範囲内に収めることが重要です。ここで決めた目標が、この後の資産配分と商品選定の“基準線”になります。
STEP2:コア資産を選ぶ|低コストなインデックスを土台に
コア資産は「広く・安く・長く」を合言葉に、長期で安定性を担う商品を選びます。代表的な選択肢は次の4つです。
株式インデックスファンド(ETF)
全世界や先進国などに幅広く分散し、世界経済の成長を取り込む土台になります。信託報酬が低く、長期保有に適します。
債券ファンド(ETF)
株式より値動きが小さく、ポートフォリオのクッション役です。通貨ヘッジありは為替の振れを抑えやすい一方、ヘッジコストで利回りが低下する場合があります。デュレーション(価格の金利感応度)は短いほど安定し、長いほどリターンもリスクも増えます。
債券ファンドやETFについては以下Q&Aでも説明しています。
バランスファンド
株式・債券などを自動分散。1本で手軽ですが、商品ごとにリスク水準が異なるため中身の配分・コストを確認しましょう。
ロボアドバイザー・ラップ口座
リスク許容度に合わせて国際分散を自動実行。手間は少ない反面、手数料はやや高め(概ね年率1%前後が目安)です。
コアは運用全体の土台です。つみたてNISAやiDeCoと組み合わせ、広く分散された低コスト商品を長期で保有しましょう。
STEP3:サテライト資産を選ぶ|テーマやアクティブで“攻め”を少額配分
サテライトは、コアよりも高いリスクを取り、超過リターンを狙う領域です。配分は事前に決めた枠(例:全体の10〜20%)に収め、複数の投資アイデアに分散させるのが基本です。また、売買ルールは「サテライト限定」で明確に設定しましょう(例:含み損20%で機械的に損切り/想定シナリオ崩れで撤退)。一方でコア資産は積立とリバランスを軸とし、頻繁な売買は避けることが安定的な運用につながります。
個別株投資
特定の企業の株式を直接購入する方法です。企業の成長性や業績に応じて大きなリターンを得られる可能性がありますが、同時にその企業特有のリスク(業績不振、経営不祥事、規制変更など)を抱える点には注意が必要です。
サテライトにおける個別株投資は、全体資産の一部を「攻め」の領域として活用するのに適しています。銘柄選定では、自分が理解しやすい業界や強みを持つ企業に絞ることが望ましく、複数銘柄に分散することでリスクを抑える工夫が欠かせません。また、投資する際はテーマやトレンドに左右されすぎず、業績や財務基盤といったファンダメンタルズの確認も大切です。
アクティブファンド
市場平均超えを目指す投信。コストは高めですが、優れた運用なら指数超えの可能性があります。
アクティブファンド投資の詳細はこちらの記事をご参照ください。
オルタナティブ投資
REIT、不動産、金・原油などのコモディティ、その他非伝統的資産を含みます。株式・債券と異なる値動きをするため、分散効果を高めやすいのが特徴です。ただし、暗号資産のように極めて高リスクなものは少額にとどめましょう。
オルタナティブ投資に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。
テーマETF・投資信託
特定テーマをまとめて保有できる商品です。個別株よりも分散は効きますが、テーマ自体の盛衰に大きく左右されます。
テーマ型投資信託・ETFについての詳細はこちらの記事をご参照ください。
STEP4:新NISAとiDeCoをフル活用し、税負担を軽くする
税制優遇は長期運用の成果を左右します。制度の「枠」を役割で使い分けましょう。
新NISA:「つみたて投資枠」でコア、「成長投資枠」でサテライト
新NISAは年間360万円(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)、生涯非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)。非課税保有期間は無期限です。基本は「つみたて枠=コアの積立」「成長枠=サテライト」で割り当て、不足分は課税口座で補います。
iDeCo:長期のコア形成に最適
iDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに、掛金が全額所得控除。超長期のコア資産向きです(上限額は職業区分で異なるため各自確認)。流動性を重視するなら新NISA優先、節税を厚くするならiDeCo併用が目安です。
iDeCoについては以下Q&Aでも説明しています。
STEP5:定期的なリバランスで配分を最適に保つ
運用を続けると比率は崩れます。ルールを先に決め、機械的に戻します。
閾値法:ずれ幅で調整
許容幅の目安は株式±5%、債券±3%。閾値を超えたら自動的に元の目標比率へ戻します。
リバランスの方法や頻度については以下Q&Aでも説明しています。
定期法:時期を決めて調整
年1回など、タイミングを固定して見直す方法です。
まずは新規入金や分配金で比率を戻す“入金リバランス”を優先し、売買回数と課税コストを抑えましょう。定期法に閾値法を補助的に組み合わせると、過不足が出にくくなります。
STEP6:管理ツールと記録で“見える化”し、運用を継続する
複数の商品を組み合わせて運用するこの戦略では、ポートフォリオ全体を「見える化」し、一貫したルールで運用を継続できるかが成果を大きく左右します。そのための具体的な方法を3つ紹介します。
お金を増やすには、資産運用だけでなく収入を増やしたり支出を減らしたりするアプローチも有効です。具体的な方法については、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。
ポートフォリオ管理ツールの活用
証券会社のアプリや資産管理アプリを活用すれば、複数の口座を横断して資産配分や損益を把握できます。これは、リバランスのタイミングを客観的に判断する上でも役立ちます。
ポートフォリオ管理の重要性とツールについては以下記事で詳しく解説しています。
定期チェックリストの作成
「毎月末に資産状況を確認する」「年に一度リバランスを行う」など、ご自身の行動を簡単なルールとして明文化しておくと、運用に一貫性が生まれます。
記録と振り返り
投資した理由や売買の根拠などを簡潔に記録し、定期的に振り返る習慣も有効です。あわせて、ポートフォリオ全体の運用コストも把握しておきましょう。各商品の信託報酬とその配分比率から全体の費用は算出でき、これを意識することで「手数料負け」を防ぐことにつながります。
コアサテライト戦略のポートフォリオ運用例3選
最後に、読者の参考となるよう3つのペルソナ別にコアサテライト戦略のシナリオ例を紹介します。それぞれ異なる年齢・状況のケースで、どのようにコアとサテライトを配分・運用するかを見ていきましょう。
ケース1.30代・投資初心者Aさん:「コア9割」で堅実にスタート
Aさんは35歳の会社員。貯金はそこそこありますが、本格的な投資は初めてです。独身で身軽なものの投資経験が浅いため、大きなリスクは避けたいと感じています。将来的にはマイホーム購入も視野に、長期での資産形成を希望しています。
戦略方針:コア9割で土台を固め、サテライトは少額から
Aさんの場合、まずはコア資産を重視した「コア9割:サテライト1割」程度の配分でスタートするのが無難でしょう。投資初心者で知識が十分でない間は、思い切ったサテライト運用は控え、資産の大半を堅実なインデックス投資に充てます。例えば「つみたてNISA」で全世界株式インデックスファンドを毎月積み立て、ボーナスで先進国債券ETFを買い増すことでコア資産を形成します。全体の約1割に設定したサテライト枠では、ご自身の興味関心に応じて少額から試してみましょう。趣味でテクノロジーに詳しければ、話題の国内IT企業の個別株を数万円分購入するのも一案です。
成功の鍵:焦らず、まずは守りを固める運用を徹底
Aさんは投資初心者なので、最初はコア資産100%から始めても良いくらいです。重要なのは、サテライトへの投資は万が一ゼロになっても生活に支障のない金額に抑えること。投資に慣れて知識がついてきた段階で、興味の持てる分野にサテライト投資を広げていきましょう。「守り8割、攻め2割」程度のバランス感覚で、焦らず続けることが大切です。
ケース2.60代・リタイア準備層Bさん:「コア7割」で安定収入と成長を両立
Bさんは60歳の創業経営者。自社株の売却益などでまとまった資産はありますが、公的年金は多くありません。リタイア後も資産を成長させつつ、安定した収入源も確保したいと考えています。
戦略方針:コア7割で安定収入を確保し、サテライトで資産成長を狙う
Bさんはリスク耐性が比較的高くても、60歳という年齢を考慮し、コア資産重視の運用へシフトすべき時期です。コアとサテライトの比率は約70:30に見直します。まずコア資産には、国内外の債券ETFや高配当株ETFなど、価格変動が比較的小さく、定期的な配当収入が見込める資産を組み入れます。一方、サテライト資産では経営者としての知見を活かし、ベンチャー企業へのエンジェル投資や未公開株ファンドへの出資も選択肢となります。ただし、いずれも高リスクなため、サテライト資産は全体の30%以内に収めるのが鉄則です。
成功の鍵:人生100年時代を見据えたバランス感覚
Bさんの場合、人生100年時代を見据えれば運用期間はまだ20〜30年あります。安全一辺倒ではなく一定のリスク資産を持ち続ける方が、資産寿命を延ばすことにつながります。コア部分からの安定収入で生活費を補い、サテライト部分は余裕資金で将来の資産成長を狙う、という戦略が描けます。
ケース3.30代・子育て世帯Cさん:「コア8割」で手間なく計画的に資産形成
Cさんは32歳の銀行員で、配偶者と小さなお子さんがいる共働き世帯です。金融リテラシーは比較的高めですが、本業が多忙で投資に割ける時間は限られています。将来の教育資金やマイホーム資金を計画的に準備したいと考えています。
戦略方針:コア8割を自動積立で形成し、サテライトは手間なく
Cさんの場合、金融知識はあっても時間に制約があるため、シンプルかつ自動化された運用を目指すと良いでしょう。コア資産を80%程度に設定し、積立投資で半自動的に運用。サテライトは20%程度とし、興味のあるテーマや得意な分野に限定して取り組みます。コア資産は、夫婦それぞれのつみたてNISAやiDeCoをフル活用し、手間なく分散投資を実現します。サテライト資産は、限られた時間で効率よく運用するため、個別銘柄の分析が不要なテーマ型ETFなどを活用するのが有効です。
成功の鍵:家計全体でポートフォリオを設計し、夫婦で協力
Cさんファミリーでは、夫婦の口座を合算するなど、家計全体でコアサテライト戦略を設計する視点が有効です。これにより、全体のバランスが「コア8割:サテライト2割」になっていれば問題ありません。忙しい中でも運用を継続できるよう、積立や自動化の仕組みを積極的に活用しましょう。
コアサテライト戦略で失敗しないための2つの重要ポイント
最後に、コアサテライト戦略で初心者が陥りがちな誤解と、成功のために押さえておくべき重要な注意点を整理します。この戦略のメリットを最大限に活かすためにも、以下の2つのポイントを必ず心に留めておきましょう。
「サテライトで一発逆転」は狙わない|あくまで「プラスアルファ」と心得る
コアサテライト戦略の考え方を誤解し、サテライト部分で「一発逆転」を狙うのは非常に危険です。例えば「資産の10%を仮想通貨に投じ、それが10倍になれば全体も倍増する」と考えてしまうことがあります。しかし実際には、仮にサテライト資産が10倍になっても、ポートフォリオ全体では+90%の上昇にとどまります。そもそも、そのような急騰が起こる確率は極めて低いのが現実です。サテライト部分はあくまで「スパイス」であり、コアという土台があってこそ活きるもの。夢を見すぎず、現実的なバランス感覚を持つことが大切です。
コア資産は頻繁に乗り換えない|長期的な視点で土台を固める
「もっと良いファンドが出た」「最近リターンが振るわない」といった理由で、コア資産を頻繁に入れ替えるのは避けましょう。コア資産は、長期でじっくりと保有してこそ土台として機能するからです。頻繁な売買は、長期投資の複利効果を損なうだけでなく、手数料や税金で資産を目減りさせます。これは「家の基礎を何度も工事し直す」ようなもので、ポートフォリオ全体の安定性を損なう行為です。コア部分は一度決めたら腰を据えて付き合い、運用の軸をブラさないことが肝心です。
この記事のまとめ
コアサテライト戦略の要点は、コアで長期安定を確保し、サテライトで少額の成長余地を追う役割分担にあります。一般的な目安は「コア70〜90%/サテライト10〜30%」ですが、自身のリスク許容度やライフステージに応じて調整することが大切です。運用を継続するには、あらかじめルールを定め、定期的なリバランスで軸を維持することが欠かせません。まずは目標額や期限を明確にし、コア資産の商品を決め、サテライトの範囲と管理方法をルール化することから始めましょう。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
コアサテライト戦略
コアサテライト戦略とは、資産運用において「コア資産」と「サテライト資産」を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを最適化する投資手法のことを指す。ポートフォリオの大部分を安定したコア資産で構成し、長期的な市場の成長に連動するリターンを確保する一方で、残りの一部をサテライト資産として運用し、高いリターンの可能性を追求する。これにより、安定性を維持しながら市場環境の変化に柔軟に対応し、資産の成長を図ることができる。
コア資産
コア資産とは、長期的な資産運用の中核を成す安定的な資産のことを指す。主にインデックスファンドや大型株、債券など、リスクが比較的低く、安定したリターンを期待できる資産が含まれる。運用の基本方針として、市場の長期的な成長を享受しながら、大きなリスクを取らずに資産を増やすことを目的とする。ポートフォリオの大部分をこのコア資産で構成し、安定した資産形成を目指す。
サテライト資産
サテライト資産とは、資産運用においてコア資産を補完し、高いリターンを狙うために組み入れる資産のことを指す。具体的には、新興国株式、個別株、テーマ型ファンド、ヘッジファンド、コモディティ、暗号資産など、リスクは高いが成長の可能性がある投資対象が含まれる。サテライト資産は、ポートフォリオの一部に限定して保有し、コア資産の安定性を損なわない範囲で積極的な運用を行うことが推奨されます。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産運用における投資対象の組み合わせを指します。分散投資を目的として、株式、債券、不動産、オルタナティブ資産などの異なる資産クラスを適切な比率で構成します。投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを設計し、リスクとリターンのバランスを最適化します。また、運用期間中に市場状況が変化した場合には、リバランスを通じて当初の配分比率を維持します。ポートフォリオ管理は、リスク管理の重要な手法です。
超過リターン(超過収益/エクセスリターン)
超過リターン(エクセスリターン)とは、投資の成果が基準となる指標(ベンチマーク)をどれだけ上回ったかを示すものです。 たとえば、株式市場全体の動きを表す指標である「日経平均株価」や「S&P500」が年間5%上昇したとします。このとき、あなたが投資している商品が7%のリターンを得た場合、その差の2%が超過リターンです。この指標は、投資の「成果が良かったかどうか」を客観的に判断する基準になります。特にアクティブ運用(市場平均を上回ることを目指す投資)の成果を評価する際に重要です。ただし、超過リターンを得るためにはリスクを取る必要がある場合が多いので、投資初心者は自分のリスク許容度をよく考えることが大切です。
インデックスファンド
インデックスファンドとは、特定の株価指数(インデックス)と同じ動きを目指して運用される投資信託のことです。たとえば「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」などの市場全体の動きを示す指数に連動するように設計されています。この仕組みにより、個別の銘柄を選ぶ手間がなく、市場全体に分散投資ができるのが特徴です。また、運用の手間が少ないため、手数料が比較的安いことも魅力の一つです。投資初心者にとっては、安定した長期運用の第一歩として選びやすいファンドの一つです。
アクティブファンド
アクティブファンドとは、運用のプロであるファンドマネージャーが、市場の平均を上回るリターンを目指して積極的に銘柄を選んで運用するタイプの投資信託のことです。 具体的には、独自の分析や調査にもとづいて、将来性があると見込まれる企業や、割安と判断される株式などに投資を行います。こうした運用には高度な専門知識と時間が必要となるため、同じ投資信託でも市場平均への連動を目指す「パッシブファンド」より運用コスト(信託報酬など)が高めになる傾向があります。しかし、その分大きなリターンを狙える可能性もある点が魅力です。 ただし、アクティブファンドだからといって必ずしも市場平均を上回るとは限らないことに注意が必要です。投資判断がうまくいかなかった場合は、損失が出たり、パッシブファンドに劣る成績となったりすることもあります。 投資初心者の方は、ファンドマネージャーの運用実績やファンドの方針、運用コストなどをよく調べたうえで、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことが大切です。購入前に「過去の運用成績」や「運用レポート」を確認し、アクティブファンドの特徴を理解してから投資を始めましょう。
リスク許容度
リスク許容度とは、自分の資産運用において、どれくらいの損失までなら精神的にも経済的にも受け入れられるかという度合いを表す考え方です。 投資には必ずリスクが伴い、時には資産が目減りすることもあります。そのときに、どのくらいの下落まで冷静に対応できるか、また生活に支障が出ないかという観点で、自分のリスク許容度を見極めることが大切です。 年齢、収入、資産の状況、投資経験、投資の目的などによって人それぞれ異なり、リスク許容度が高い人は価格変動の大きい商品にも挑戦できますが、低い人は安定性の高い商品を選ぶほうが安心です。自分のリスク許容度を正しく理解することで、無理のない投資計画を立てることができます。
分散投資
分散投資とは、資産を安全に増やすための代表的な方法で、株式や債券、不動産、コモディティ(原油や金など)、さらには地域や業種など、複数の異なる投資先に資金を分けて投資する戦略です。 例えば、特定の国の株式市場が大きく下落した場合でも、債券や他の地域の資産が値上がりする可能性があれば、全体としての損失を軽減できます。このように、資金を一カ所に集中させるよりも値動きの影響が分散されるため、長期的にはより安定したリターンが期待できます。 ただし、あらゆるリスクが消えるわけではなく、世界全体の経済状況が悪化すれば同時に下落するケースもあるため、投資を行う際は目標や投資期間、リスク許容度を考慮したうえで、計画的に実行することが大切です。
ボラティリティ
ボラティリティは、投資商品の価格変動の幅を示す重要な指標であり、投資におけるリスクの大きさを測る目安として使われています。一般的に、値動きが大きい商品ほどそのリスクも高くなります。 具体的には、ボラティリティが大きい商品は価格変動が激しく、逆にボラティリティが小さい商品は価格変動が穏やかであることを示します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティを標準偏差という統計的手法で数値化し、それを商品のリスク度合いとして評価するのが一般的です。このため、投資判断においては、ボラティリティの大きい商品は高リスク、小さい商品は低リスクと判断されます。
リバランス
リバランスとは、ポートフォリオを構築した後、市場の変動によって変化した資産配分比率を当初設定した目標比率に戻す投資手法です。 具体的には、値上がりした資産や銘柄を売却し、値下がりした資産や銘柄を買い増すことで、ポートフォリオ全体の資産構成比率を維持します。これは過剰なリスクを回避し、ポートフォリオの安定性を保つためのリスク管理手法として、定期的に実施されます。 例えば、株式が上昇して目標比率を超えた場合、その一部を売却して債券や現金に再配分するといった調整を行います。なお、近年では自動リバランス機能を提供する投資サービスも登場しています。
信託報酬
信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。
オルタナティブ投資
オルタナティブ投資とは、伝統的な投資対象である株式や債券以外の資産への投資を指します。主な投資対象には、不動産、インフラ、プライベートエクイティ(未公開株式)、コモディティ(商品市場)、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、貴金属、仮想通貨などが含まれます。 この投資手法の主な特徴として、伝統的な市場との相関が低いため、ポートフォリオ全体のリスク分散効果が期待できることが挙げられます。また、投資対象や手法の選択肢が広がることで、より柔軟な投資戦略を構築することが可能になります。 ただし、オルタナティブ投資には留意点もあります。一般的に流動性が低い場合が多く、また専門的な知識が必要とされることから、長期的な投資視点を持って取り組む必要があります。
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)とは、証券取引所で株式のように売買できる投資信託のことです。日経平均やS&P500といった株価指数、コモディティ(原油や金など)に連動するものが多く、1つのETFを買うだけで幅広い銘柄に分散投資できるのが特徴です。通常の投資信託に比べて手数料が低く、価格がリアルタイムで変動するため、売買のタイミングを柔軟に選べます。コストを抑えながら分散投資をしたい人や、長期運用を考えている投資家にとって便利な選択肢です。
新NISA
新NISAとは、2024年からスタートした日本の新しい少額投資非課税制度のことで、従来のNISA制度を見直して、より長期的で柔軟な資産形成を支援する目的で導入されました。この制度では、投資で得られた利益(配当や売却益)が一定の条件のもとで非課税になるため、税負担を気にせずに投資ができます。新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が用意されており、年間の投資可能額や総額の上限も大幅に引き上げられました。 また、非課税期間が無期限となったことで、より長期的な運用が可能となっています。投資初心者にも利用しやすい仕組みとなっており、老後資金や将来の資産形成の手段として注目されています。
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。
デュレーション
デュレーションは、債券価格が金利変動にどれほど敏感かを示す指標で、同時に投資資金を回収するまでの平均期間を意味します。 一般に「Macaulay デュレーション」を年数で表し、金利変化率に対する価格変化率を示す「修正デュレーション」は Macaulay デュレーションを金利で割って算出します。 数値が大きいほど金利 1 %の変動による価格変動幅が大きく(例:修正デュレーション 5 年の債券は金利が 1 %上昇すると約 5 %値下がり)、金利リスクが高いと判断できます。一方で金利が低下すれば同じ倍率で価格は上昇します。デュレーションを把握しておくことで、ポートフォリオ全体の金利感応度を調整したり、将来のキャッシュフローと金利見通しに応じて保有債券の残存期間やクーポン構成を選択したりする判断材料になります。特に金利の変動が読みにくい局面や長期安定運用を重視する場面では、利回りだけでなくデュレーションを併せて確認することが重要です。
通貨ヘッジ
通貨ヘッジとは、海外の資産に投資をする際に為替相場の変動による損失を抑えるための仕組みのことです。たとえば、日本円で生活している投資家が米ドル建ての投資信託や債券を購入すると、資産の値動きだけでなく円とドルの為替レートによっても利益や損失が変わってしまいます。このリスクを軽減するために、あらかじめ為替取引を組み合わせて、一定の為替レートに固定することを通貨ヘッジと呼びます。通貨ヘッジを利用すれば、為替相場の影響を小さくすることができるため、投資対象そのものの値動きに集中できるメリットがあります。ただし、ヘッジのためのコストがかかるため、その分リターンが減少する場合がある点にも注意が必要です。