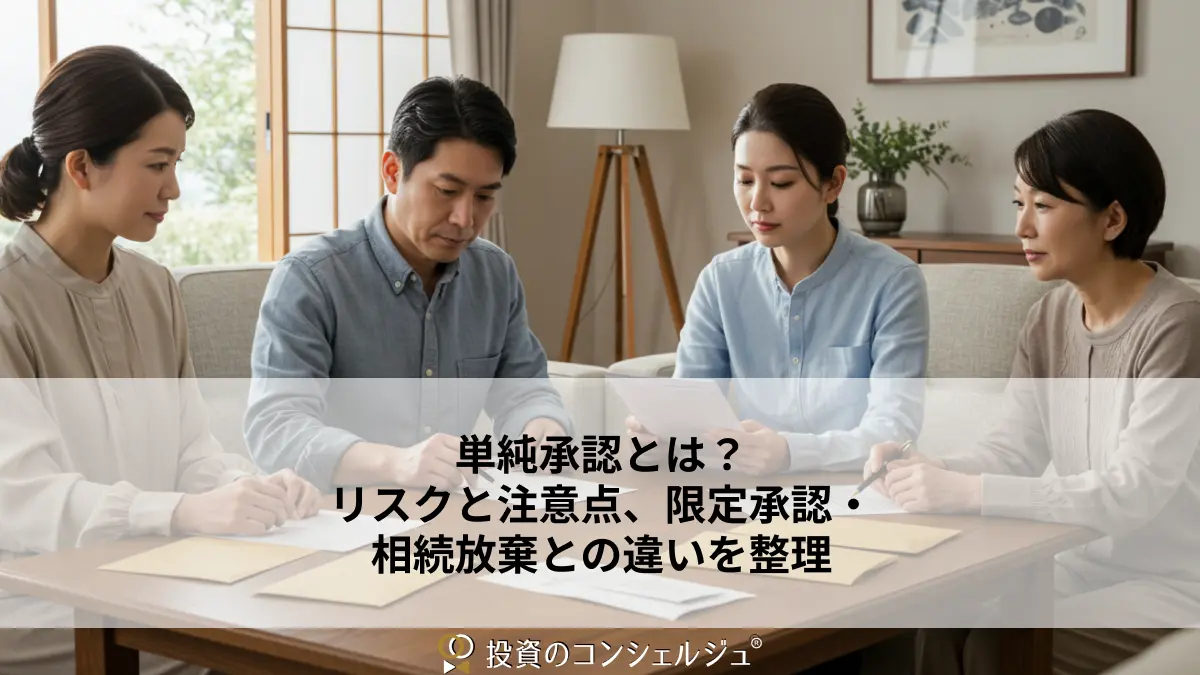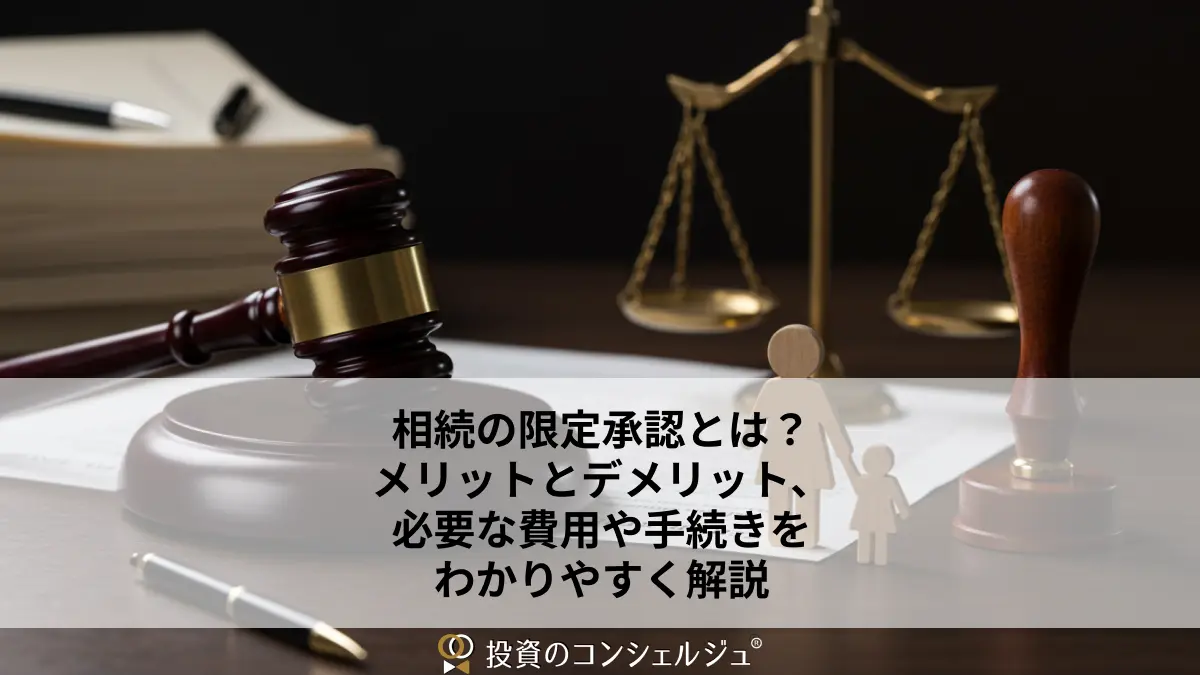遺言信託とは?仕組みやメリット・デメリットと遺言代用信託との違いを解説
難易度:
執筆者:
公開:
2024.11.25
更新:
2025.09.24
そろそろ相続について考えなければならないけれど、
「何から手を付けてよいかわからない。」「できるだけ相続人の負担を減らしたいけれど1人で準備するのは大変。」と思うことはありませんか。
「遺言信託」や「遺言代用信託」を活用することで相続準備や相続手続きがスムーズにいく場合があります。
この記事では「遺言信託」と「遺言代用信託」のメリット・デメリットや、活用されるケース、また両者にどういった違いがあるのかを解説しています。ぜひ、最後までお読みください。
目次
遺言信託とは?信託銀行が遺言書に関するサポートを提供
「遺言信託」という言葉は主に信託銀行が提供しているサービス商品名のことを指し、遺言書作成サポート、保管、執行を一貫して行ってくれるサービスです。
遺言者は金融機関と「どのような財産があるか」、「万が一の際に誰にどのくらいの遺産を相続するのか」などを話し合い、遺言書の内容を決めます。
遺言書の内容が決まると、遺言者は公証役場で公正証書遺言を作成し、万が一の際に遺言の執行を行う遺言執行者に信託銀行等の金融機関を指定します。
遺言書の作成後、遺言者は遺言執行者とした金融機関と遺言信託の契約をすることで、万が一の際には、金融機関が遺言執行を行うという仕組みです。

ちなみに「遺言信託」という言葉には、二種類の異なる意味があります。ひとつは、信託法などの法律で規定されている「遺言による信託」という意味で、遺言によって信託するという法律行為を指します。
もうひとつは信託銀行などが提供する「サービス商品名としての遺言信託」という意味で、金融機関が提供するサービスを指します。
一般的に「遺言信託」という言葉は、後者の「サービス商品名としての遺言信託」を指すことが多く、広く利用されています。
遺言信託のメリット
遺言信託は、相続に関する様々な手続きを金融機関に任せることで、遺言者や相続人の負担を軽減するサービスです。この章では遺言信託を利用するメリットについて詳しく解説します。
1.遺言執行を金融機関が代行し、相続人の負担が減らせる
遺言信託では、遺言者が万が一の際には遺言書で指定した金融機関が遺言執行者となり、遺言執行を行います。遺言執行とは相続時に遺言書に書かれている内容を実現することです。遺言執行者は、遺言書の内容に基づいて、財産の管理・処分、預貯金口座の解約や不動産の名義変更などを行います。
書類作成などの手間が省けることはもちろん、相続人への遺言書の披露も金融機関が行うため、相続人の負担を大幅に減らすことができます。
2.遺言書の保管を金融機関に任せられるため安全
遺言書には個人情報や財産の詳細などが記載されており、第三者に悪用や盗難をされないように気をつける必要があります。保管を金融機関にまかせることで安全に遺言書を保管でき、本人が万が一の際には、保管された遺言書をもとにスムーズに相続手続きを行うことが可能です。
3.生前の権利移転が不要
遺言信託は遺言者の万が一の際に効力が発生する信託で、生前に相続人に権利が移転することはありません。遺言者の存命中は、遺言者の意思で財産を管理することができ、いつでも遺言書の内容を書き換えたり、撤回することができます。
遺言信託のデメリット
遺言信託は便利なサービスですが、利用する場合には何点か注意が必要です。この章では遺言信託を利用するデメリットについて詳しく解説しています。
1.遺言信託にかかるトータルの手数料が安くない
遺言信託を契約し、執行業務が終わるまでにかかる費用として契約時手数料、遺言書の保管料(毎年)、遺言執行報酬などの手数料がかかります。
遺言書の変更手数料や公的書類の取得費用などが別でかかる場合もあり、最低でも数十万円、場合によっては数百万円以上の費用が発生する可能性があります。
2.遺言信託の引受内容は一定の「型」に限られることがある
金融機関では遺言信託で扱える内容に限りがあり、オーダーメイドで契約するのが難しい場合がほとんどです。
一般的には、相続人の廃除や子の認知に関する手続きなどの身分に関する執行や、相続人同士が争うことが予見される場合などは金融機関では取り扱われません。
遺言信託がよく使われるケース
遺言信託は、相続時の煩雑な事務手続きを減らしたい場合や、スムーズな事業承継を希望する場合、財産を寄付したい場合によく利用されます。
財産が多いと遺産分割や名義替えなどの相続手続きが煩雑です。また、相続が発生した時から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。10ヵ月以内に遺産分割協議を終え申告をしないと、相続税の減税に繋がる税額控除や特例が受けられなくなる可能性もあるためスムーズに相続手続きを終える必要があります。
遺言代用信託とは?
遺言代用信託とは信託銀行等に特定の財産を信託し、生存中は本人のために管理・運用してもらい、本人が万が一の際には事前に指定した受取人に財産が引き渡される仕組みです。
この章では遺言代用信託について解説します。
遺言代用信託の仕組み
本人が委託者となり預金など特定の財産を信託銀行等の受託者へ信託し、本人の存命中は受託者となった信託銀行等が財産の管理・運用を行います。
また、典型的には本人が運用益などの利益を得る受益者となり、本人の万が一の際には、あらかじめ指定した人が受益者となります。

遺言代用信託のメリット
遺言代用信託は、特定の財産をスムーズに相続するための有力な手段として注目されています。この章では遺言代用信託のメリットについて詳しく説明します。
1.遺産の受取人を指定できる
遺言代用信託は本人の万が一の際に、あらかじめ指定した受取人に特定の財産を引き渡すことができます。
2.遺産分割を待たずにお金が引き出せる
一般的に銀行口座などの口座は本人の万が一の際には、凍結され、遺産分割協議後まで引き出すことができません。ところが、遺言代用信託で信託された財産は遺産分割協議の対象外となり、指定された受取人は、遺産分割協議前に財産を引き出すことができます。
3.子から孫への相続内容も決められる
遺言代用信託では世代を超えた相続が可能です。
本人から子供へ相続するだけでなく、孫の代の遺産配分も決めることができ、長期的に家族の財産管理が可能になります。
遺言代用信託のデメリット
遺言代用信託には多くのメリットがある一方で、いくつかの制約や注意点も存在します。この章では遺言代用信託のデメリットについて詳しく説明します。
1.信託できる財産が限定されている
遺言代用信託は財産の全てを信託するのではなく、特定の財産を信託するサービスです。取り扱う金融機関によっては金銭のみしか信託していないなど、信託できる財産が限定されている場合があります。
2.手数料が一律でなく、費用の体系が難しい
受託者となる金融機関によって費用が異なりますが、一般的に契約時手数料、信託契約期間中の事務・管理手数料、運用報酬などの費用がかかります。
遺言代用信託の場合、信託財産の運用益からそれらの費用をまかなっている場合が多く、信託する金額によって手数料が変わる場合があります。
遺言代用信託は、特定の財産をあらかじめ指定した人に確実に相続するための有力な手段として注目されている一方で、機能性や費用面で注意が必要です。しっかり理解したうえで契約を進めるようにしましょう。
遺言代用信託がよく使われるケース
遺言代用信託は、相続時にすぐ引き出したい資金がある場合や、代を超えて相続したい場合、経営に空白期間を生じさせたくない場合などに活用されることが多いです。
遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託は、信託銀行等が遺言書の作成サポート、保管、執行を一貫して行うサービスです。本人の生存中は信託銀行等が財産の管理・運用を行い、万が一の際に効力が発生します。
一方、遺言代用信託は、信託銀行に特定の財産を信託し、本人のために管理・運用をしてもらいます。本人の存命中から効力が発生し、万が一の際には指定された受取人に特定の信託財産が引き渡されるサービスです。
| コスト | 汎用性 | 対象資産 | |
|---|---|---|---|
| 遺言信託 | △ | 〇 | 〇 |
| 遺言代用信託 | 〇 | △ | △ |
「相続の相談は誰にすればよいのかわからない」という方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
遺言信託と遺言代用信託の選び方と活用方法
遺言信託と遺言代用信託、どちらを選ぶか、というのは悩みどころです。ここでは、それぞれ活用するのに向いている人や例をご紹介します。
遺言信託が有効な例
遺言信託は財産が多く、専門家のサポートを受けながら遺言書を作成したい人や、相続時に発生する事務的な負担を減らしたい人に向いています。
- 複数の銀行口座や不動産、有価証券があり、金額が大きく、遺産分割時の計算や名義変更手続きなどが煩雑な場合
- 複数の銀行口座や不動産、有価証券があり、金額が大きく、自分1人では整理できず、専門家のサポートを受けながら相続財産の整理をしたい場合
- 財産を残す人がおらず、特定の団体や機関に寄付したい場合
遺言代用信託が有効な例
遺言代用信託は、存命中から特定の財産の管理・運用を信託銀行等に任せ、相続時には指定した承継者に確実に承継したい人に向いています。
- 万が一の際に預金を数百万円だけ特定の承継者に渡したい場合
- 万が一の際に会社をスムーズに承継したい場合
- 相続時のことも見据え、生前から特定の財産の管理・運用を信託銀行等にまかせたい場合
まとめ
遺言信託や遺言代用信託を活用することで相続に関する負担や不安を軽減することができます。ただし、遺言信託と遺言代用信託は似て非なるものです。それぞれの違いをしっかりと理解したうえで契約を進める必要があります。
遺言信託は、複数の銀行口座や不動産、有価証券を持つ場合など、遺産分割時の手続きが煩雑で専門家のサポートが必要な場合に役立ちます。遺言書作成のサポートや相続人の負担軽減を希望する人におすすめです。また、財産を残す人がいない際には特定の団体や機関への寄付手段としても利用できるため、財産を寄付したい人にもおすすめです。
遺言代用信託は、信託銀行に特定の財産を管理・運用してもらい、将来的に指定した承継者に確実に財産を承継するために活用されます。決まった額の財産や特定の財産、会社をスムーズに承継したい場合や、相続時を考慮して生前から特定の財産の管理・運用を信託銀行に任せたい人におすすめです。
遺言信託も遺言代用信託も金融機関によってサービス内容に差があり、ご自身や残される方に沿った内容のサービスを選択する必要があります。あとから「思っていたサービスとは違っていた。」とならないためにも、契約内容や費用などもしっかりと確認したうえで契約するようにしましょう。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
遺言信託
遺言信託とは、被相続人(故人)が自分の財産を誰にどのように分配するかを定めた遺言書の作成や執行を、信託銀行などの専門機関に依頼するサービスのことです。遺言の作成支援から保管、そして死亡後の遺言執行までを一貫して対応するため、相続に関する手続きの煩雑さを軽減でき、専門的な判断が必要な場面でも安心して任せられます。 特に、複数の相続人がいたり、不動産や非上場株式など評価が難しい資産を含む場合には、第三者の介在によって円滑な資産分配が行える利点があります。遺言信託を活用することで、相続トラブルの予防や、被相続人の意思の尊重が実現しやすくなりますが、信託銀行等に支払う手数料が発生する点には注意が必要です。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。