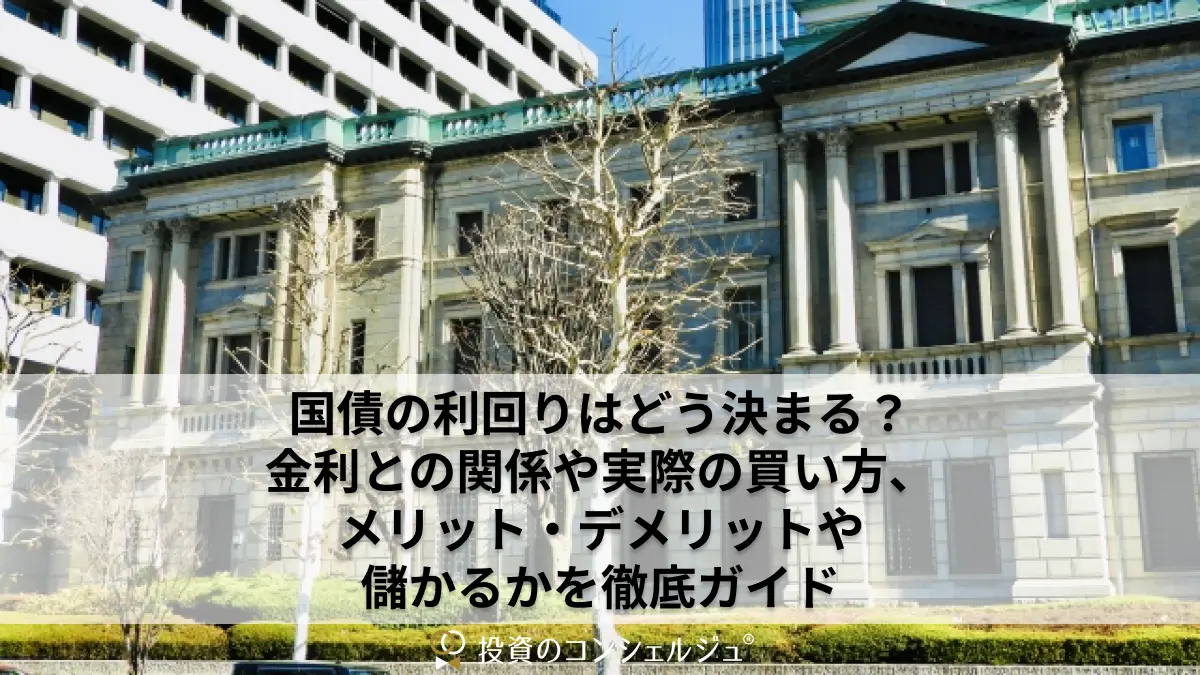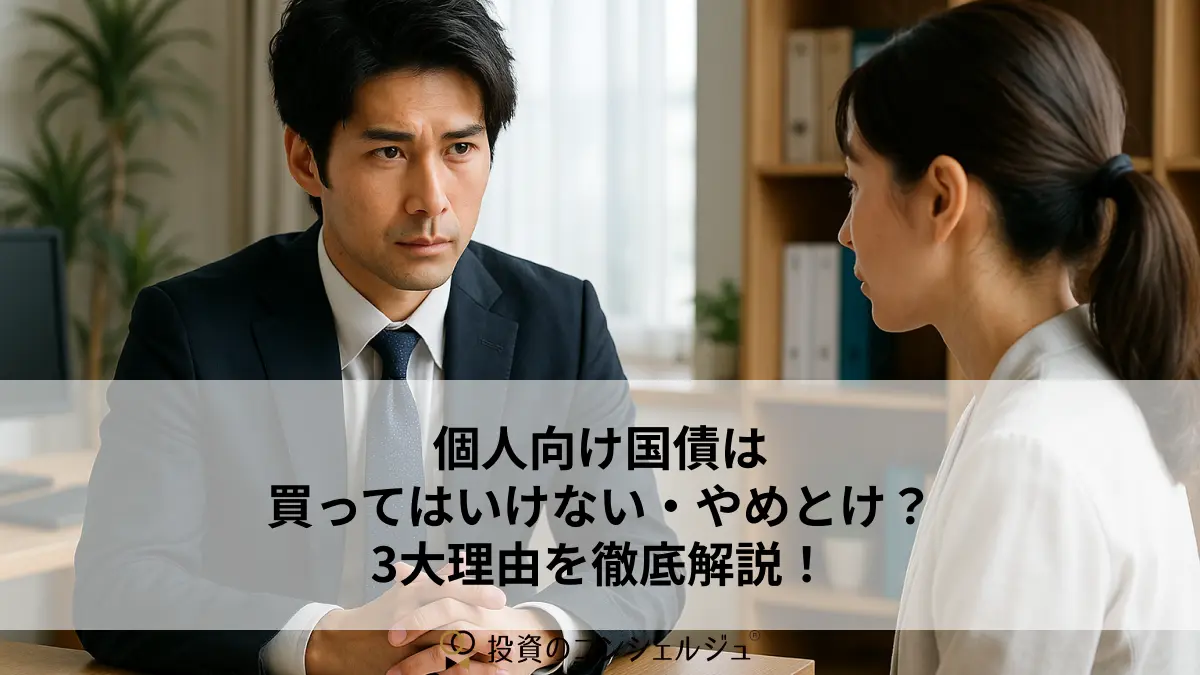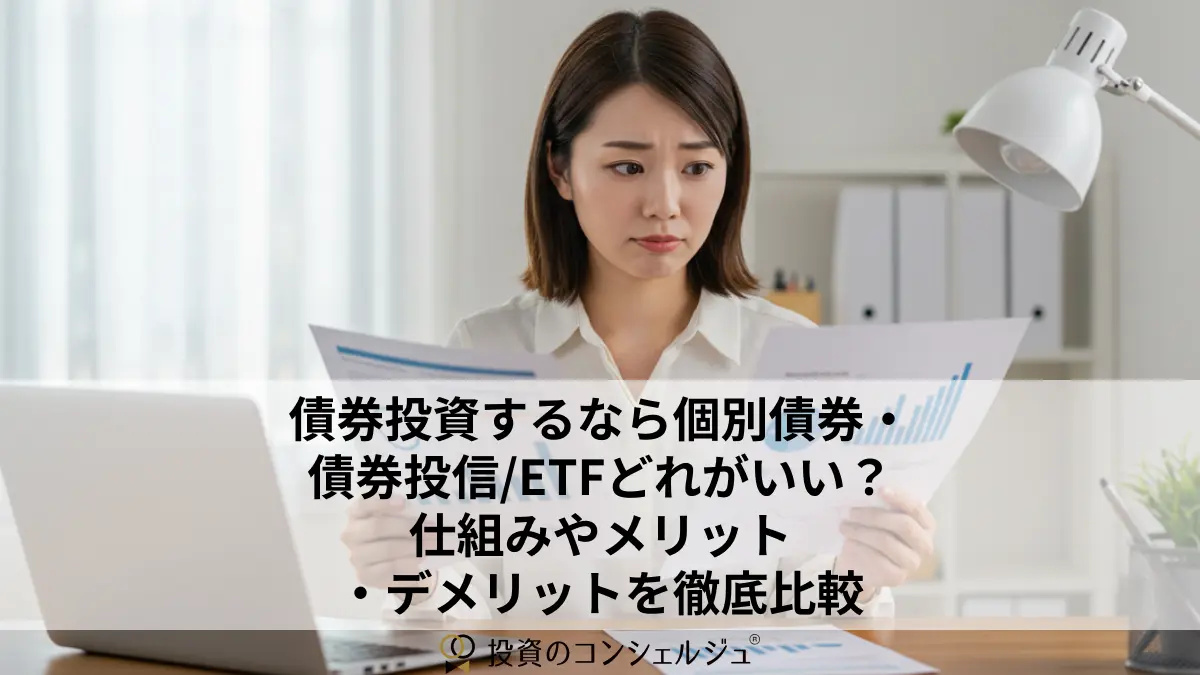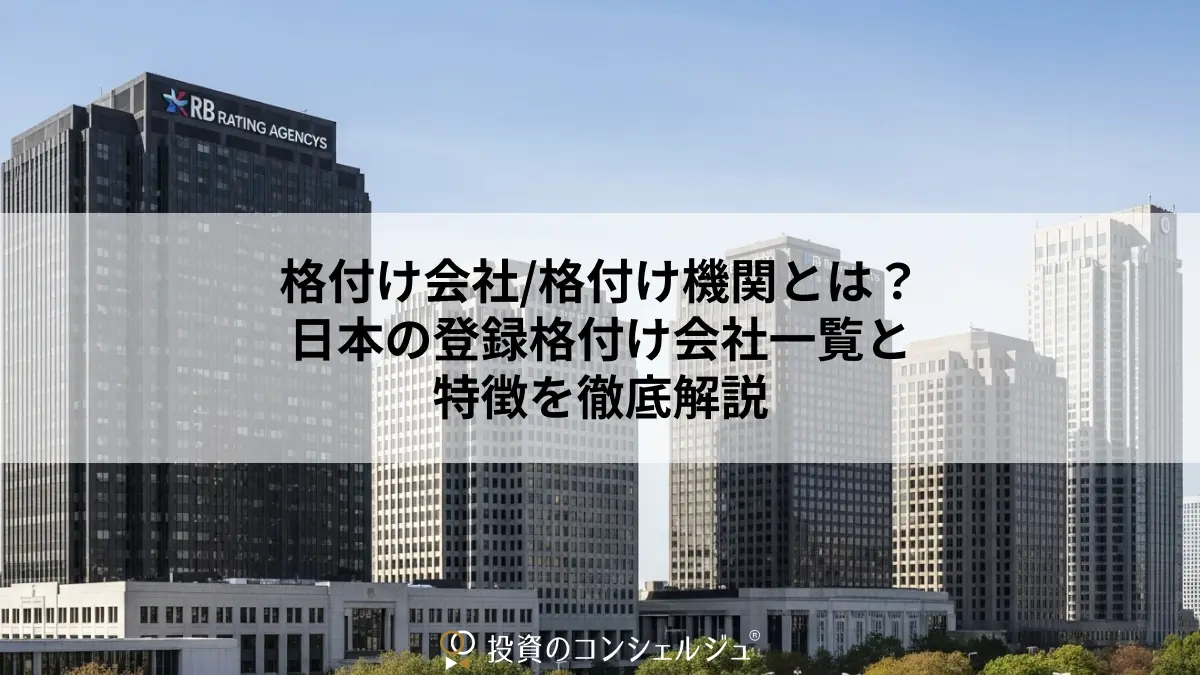債券投資入門~債券投資の仕組みや気をつけるポイント
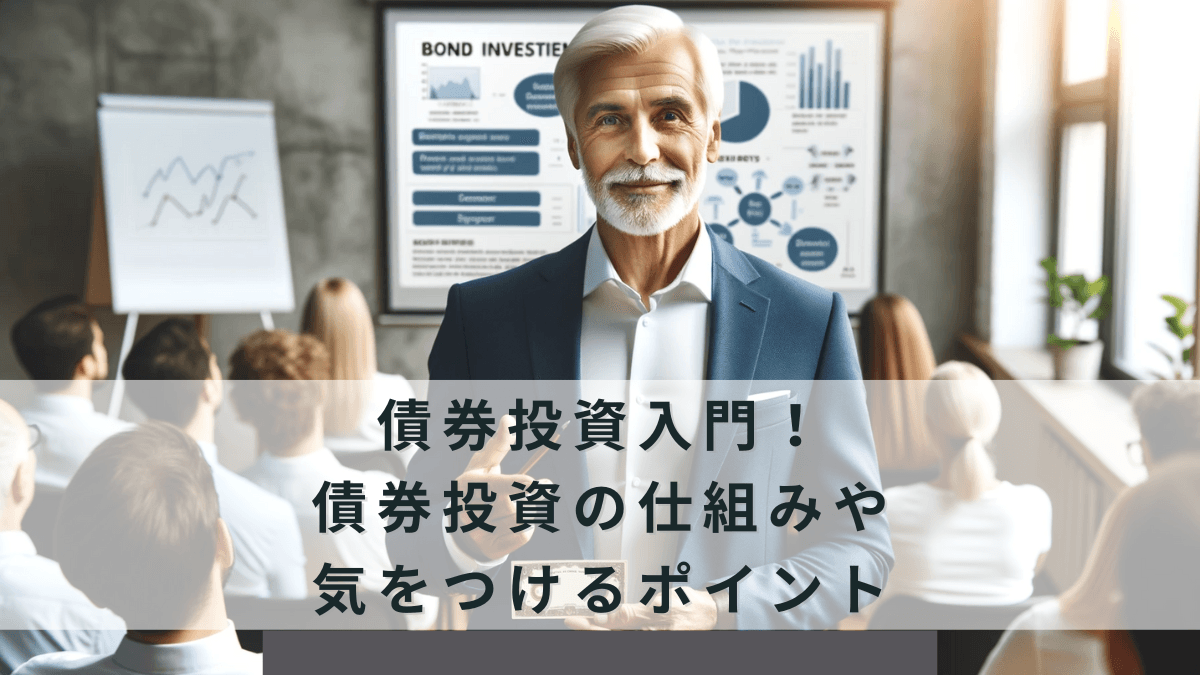
債券投資入門~債券投資の仕組みや気をつけるポイント
難易度:
執筆者:
公開:
2023.12.19
更新:
2025.06.27
「投資=株」というイメージが強い中で、「債券って難しそう」と感じていませんか?でも実は、債券は初心者にも取り入れやすい“安定志向”の資産運用のひとつ。元本が戻ってくる仕組みや、利息収入の見通しが立てやすい点から、長期的な資産形成に役立つ選択肢です。本記事では、債券の仕組みからメリット・注意点までを丁寧に解説。これから投資を始めたい方や、リスクを抑えた運用を考えている方におすすめの入門ガイドです。
サクッとわかる!簡単要約
本記事を通じて、債券投資の基本的な仕組みや特徴を体系的に理解できます。具体的には、債券の定義、種類(国債、社債など)、利回りの計算方法、リスク要因(信用リスク、金利変動リスクなど)について詳しく解説されています。また、債券投資のメリットとして、安定した利息収入や元本の返済が期待できる点が挙げられています。一方で、デメリットや注意点についても触れられており、投資判断の参考になります。これにより、自身の投資目的やリスク許容度に応じた適切な資産運用戦略を立てるための知識が得られるでしょう。
債券投資をする前に、債券の基本を理解しよう
債券投資を行う際は、債券の特徴やリスクなどを把握する必要があります。
下記では「債券とは?」といった基本的な内容から、債券の種類や特徴やデメリットなど、債券投資を始めるにあたり、最初に知るべき基本的な内容を解説しています。
- 代表的な債券は国債と社債だが、その中でも様々な種類がある
- 債券投資には「信用リスク」、「金利変動リスク(価格変動リスク)」など6つのリスクがある
- 債券投資には「資産保全」と「安定したキャッシュフロー」が期待できるメリットがある
債券の定義と目的
債券は、企業や政府といった発行体から見ると借用証書に近い存在の一方で、投資家から見ると金融商品として認知される存在です。
企業が事業を展開するには、資金が必要不可欠です。企業による資金調達手段としては、銀行からの借入や株式の発行による増資に加えて、債券(社債)の発行という手段があります。また債券の発行は企業のみならず、政府や自治体などでも行われています。2023年度予算では、日本政府は政府予算の約3割を、債券=国債の発行により賄う状態です。
株式の発行で調達した資金は返済の必要はありません。しかし、債券の発行は簡単にいえば、投資家からの借金です。よって、銀行からの借入と同様、債券の発行で調達した資金は利息を付けて返済する必要があります。
債券の発行者(発行体と呼ばれます)から見れば、債券の発行は銀行融資と同様の借入による資金調達の手段です。例えば、債券は「1000万円を年利3%の利息で借りて5年後に返済する」と書かれた借用証書に近い存在となります。
一方、投資家の側から債券を見ると、債券の保有者は上記の場合「1000万円の貸付に対し年利3%の金利を受け取り5年後に返済される」ことになります。また債券は、投資家間での売買が可能です。よって、債券は返済が約束されており、返済までは年間3%の利息が得られる金融商品としての側面が非常に大きくなります。
以下では投資家から見た、金融商品としての債券を中心に解説します。
債券の主な特徴 ~ 社債、国債、通貨、発行地域
主な国債や社債などは電子化されており、現在は債券そのものを見る機会がほとんどありません。しかし過去は紙の債券が発行されており、紙の債券には様々な事項が記載されていました。
債券の主な特徴は「額面」「利率」「満期」の3点です。なお、紙の債券を見る機会は無くなりましたが、紙の債券をイメージすることで債券の理解が進みやすくなります。この3点はいずれも紙の債券に記されていた事項です。

債券の発行体は、債券の保有者に資金を返済する必要があります。債券には「額面(価格)」が記載されており、その「額面(価格)」が債券の満期時に発行体から債券の保有者に返済される金額です。取引市場で売買される債券には価格変動があります。よって売買のタイミングによっては、損失や利益が発生します。しかし、満期日には額面金額が、発行体から債券の保有者に支払われます。100万円の貸し出しに対して満期日に100万円が返済されるのは当たり前です。しかしこの当たり前が、金融商品として債券が取引される際に大きな意味を持ちます。
お金を借りる際は、借り手は貸し手に対し一定の利息を支払う必要がありますが、債券には額面金額に対して支払われる利率が記載されています。額面金額100万円で年間の利率が3%の債券の保有者は、年間3万円の金利収入を得ることができます。金利収入=利子により安定的な収入を得られる点も債券投資の特徴です。なお、紙の時代の債券には、債券保有者が受け取りできる利子も債券の端に切り取り可能な紙(利札と呼ばれた)が付いており、利払い日に利札を金融機関などに持ち込めば利子を受けることができました。
「満期」について、借金には返済日があります。債券発行による借入は、返済の期日到来で一度に返済(一括返済)されることがほとんどです。借金の返済日が「満期」に相当します。また債券の満期日が来て、投資家に対し資金が返済されることは「償還」とも呼ばれます。債券の満期は債券の種類によって様々ですが、10年満期の国債が債券の代表的な存在です。
債券の種類1:国債と社債について
債券の主な発行体は政府と企業です。下記で「政府が発行する債券」=国債、と「企業が発行する債券」=社債について詳細を解説します。
国債について(発行体、通貨、発行地域による分類と特徴)
国が発行する債券が国債です。日本を始め様々な国が国債を発行しています。国が利子の支払いと償還を行うため、国債は基本的には高い信用力を持つ存在です。ただしアルゼンチンの様に過去9度もデフォルト(債務不履行)に陥り、2022年には90%を超える物価上昇を見せ財政・経済状態の悪い国の場合、国債であっても信用力は投機的と位置付けられる低い債券もあります。
世界を代表する国債は、アメリカが発行するドル建ての「米国債」、日本が発行する日本円建ての「日本国債」、ドイツやフランスといったユーロ圏の国が発行するユーロ建て国債です。

ドル建てで発行される米国債は、世界最大発行額を誇る金融商品で、2023年10月時点で約42.8兆ドルです。その中でも、米国債の中心となる10年債は世界の金利動向を左右する存在です。米国債の金利動向は株式市場を始め、様々な金融市場に大きな影響を与えるため、機関投資家は米国国債の金利動向を注視しています。
日本国債は、日本政府が発行する国債です。円建てで発行されており、10年満期の10年債中心ながら、最短2ヵ月の国庫短期証券から最大40年の超長期国債までが存在します。機関投資家中心に保有や売買がなされていますが、個人投資家向けには、3・5・10年満期の個人向け国債が発行されています。
通貨ユーロの採用国は、ユーロ建てで国債を発行しています。ドイツ・フランス・イタリアなど経済規模の大きい国も、ギリシャなどの経済規模の小さい国も同様にユーロ建てで国債を発行しています。ただし国の信用力により利率が異なります。ユーロで様々な国の債券に投資できる反面、2010年以降に発生したギリシャ危機の際は、ギリシャ国債の暴落に連動する形で信用力の高いドイツ国債の価格も急落しました。ユーロ危機といわれる金融危機を招いた経緯があり、制度的に不安定な一面を有しています。
社債について
企業が発行する債券は社債と呼ばれています。国内の会社法上では、手順を踏めばどの企業でも社債の発行自体は可能です(会社法676~742条に規定)。しかし国内では、銀行などの融資審査よりも社債の引受審査のほうが審査は厳しい状態にあります。よって、社債を発行して資金調達ができるのは、上場する信用力の高い有力企業に実質的に限られています。一方、米国では鉄道の敷設資金を債券や株式の発行により調達した歴史的経緯もあり、信用力の低い企業の債券の発行も活発に行われています。
なお、国内で発行される社債の多くは、機関投資家向けに発行されます。よって、個人投資家が社債投資を行う機会は限られますが、ソフトバンクグループや楽天グループのように個人向け社債を定期的に発行する企業もあります。
また、社債は発行体となる企業の本社所在地において現地通貨での発行が基本ですが、米国現地法人などが発行体となり日本本社の企業ながらドル建てで社債を発行するケースもあります。多国籍企業は様々な国で事業を展開しており、決済などで様々な国の通貨を必要とすることから、社債の発行で現地通貨を調達することも珍しくありません。実際に2023年4月には日本の商社株にも投資するアメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社米バークシャー・ハザウェイが、1,600億円の円建て債を発行しました。
また海外企業などが資金調達コストを抑えるために、低金利の日本において円建てで債券(サムライ債と呼ばれます)を発行するケースもあります。
債券の種類2:様々な債券について
以下では、様々な種類の債券について概要を説明します。
シニア債(社債)
シニア債は優先債とも呼ばれる債券です。社債が発行される際に、リスクや金利などの条件が異なる複数の債券が発行される場合がありますが、リスクの度合いを三分類した際に、シニア債は最も低リスクの債券となります。
劣後債(社債)
劣後債は、通常の社債に比べ元本や利息の支払い順位の低い社債です。発行体企業が倒産した場合、一般債券に比べ弁済順位が劣る反面、利回りは通常の社債に比べて高めに設定されます。なお、金融機関が発行する劣後債は、一定の制限があるものの自己資本への参入が認められており、金融機関が自己資本充実の手段として発行するケースもあります。
物価連動債(国債)
物価連動債は、債券の元本や利率をインフレ率に応じて調整する仕組みを持った債券です。通常の国債は、元本と利率が固定されており、インフレなどの影響を受けて物価が上昇すれば、実質的な債券の価値や利率は低下が避けられません。物価連動債は、物価上昇に応じて元本部分が調整されます。また利率は元本額に乗じて計算されるため、元本部分が増加すれば利子の額も増加します。
ハイイールド債(国債、社債)
ハイイールド債とは、高い利回りが特徴の債券です。債券の発行体の信用力が低くデフォルト(債務不履行)のリスクが高い反面、利回りが高く設定されています。債券ながらハイリスク・ハイリターンの投資対象です。また社債のみならず、信用力の低い国の国債もハイイールド債に位置付けられます。なお、ジャンク債、高利回り債とも呼ばれています。
債券投資のリスク
債券投資には、主に下記6つのリスクがあります。
1.信用リスク(クレジットリスク)
信用リスクとは、一般的に貸したお金が約束通りに返ってこないリスクを指します。ただし債券では、利息や償還金が事前に決められた条件で支払われないリスク、を指します。
2.金利変動リスク(価格変動リスク)
債券価格は、金利の動きと逆相関の関係にあります。よって、金利が上昇すると債券価格が下落するため、時価で売却を行うと売却損が生じるリスクがあります。
3.流動性リスク
債券を売りたい時に売れず、買いたい時に買えないリスクを指します。取引が少なく流動性の低い債券の場合、損失となる価格まで下落して売る判断をしても、買い手不在で売却ができず損失が膨らみ続けるリスクがあります。
4.途中償還リスク
債券の中には、発行体の都合で途中償還される事が定められているものがあります。その場合、投資家は本来受け取りできた利子を満額受け取ることができません。途中償還で額面割れとなることはほとんどないものの、予定していた利回りが得られないことに加え、売却と同時に円に換えてしまうと、海外の債券の場合は為替での損益が自動的に確定してしまいます。
5.為替変動リスク
海外債券は、債券価格の変動とは別に為替変動でも価値が上下します。特に円安が進むと、円換算での債券の価値が低下するため、為替変動リスクが表面化します。
6.カントリーリスク
国の信用リスクを指します。開発途上国などではクーデターなどの発生を契機に、為替の急変や債券の利払い停止・国債の償還見送りなどが発生するリスクがあります。
「信用リスク」と「金利変動リスク(価格変動リスク)」が債券投資の2大リスクといえますが、特に海外債券へ投資を行う際は他のリスクも充分理解した上で取り組みましょう。
債券投資はどんな人におすすめ?
金融商品としての債券投資のメリットは、以下の2点の特徴があります。
- 満期時の額面償還(高い資産保全性)
- 安定的な金利収入(安定したキャッシュフローの獲得)
まず①について、債券の発行時に額面100万円で投資すれば、満期時に通常は100万円で償還され、投資元本が回収できます。よって、資産保全に優れた金融商品です。このためリスクの低い債券なら、比較的大きな資金を投じても投資元本が毀損するリスクは低いといえるでしょう。
次に②について、債券の保有者は基本的に年1度以上の金利収入が得られます。発行体に問題が生じない限り満期まで金利は定期的に支払われるため、債券の保有で安定したキャッシュフローが得られます。株式の配当は企業業績に大きく左右され、また確定的な収入ではありません。債券は発行時点で金利が決められており、債券の保有者は事前に決められた安定的な金利収入=リターンが得られます。
上記2点の特徴があることから、債券はある程度まとまった資金を持ち、安定的なキャッシュフローを得たい方におすすめの金融商品です。
また、まとまった資金がなくとも、保有する資金をリスク回避して保守的に運用する際も、資産保全の観点から債券は有力な選択肢です。
さらに積極的に株式投資を行うリスク許容度の高い投資家であっても、一定の資産を債券に充当することで、株式市場の急落時であっても、一定の資産の保全及び安定的なキャッシュフローが得られます。このため比較的リスクを取れる投資家であっても、ポートフォリオの一部に債券を充当することは有効です。
このように投資元本の「資産保全」と「安定したキャッシュフロー」が期待できる債券は、長期視点での資産増加を目指す際に、欠かすことのできない金融商品といえるでしょう。
この記事のまとめ
債券投資は、比較的リスクを抑えつつ安定した収益を目指せる選択肢の一つです。ただし、金利や信用リスクといった債券特有の注意点もあるため、投資全体のバランスを考えるうえで、自分に合った使い方を見極めることが大切です。今回の記事を通じて基礎を押さえたうえで、もう少し具体的に「自分ならどう使えるか」を考えるには、信頼できる情報源や第三者の視点を取り入れるのも良い方法です。専門家への相談はその一つであり、必要に応じて活用することで、より納得感のある運用プランが描けるようになるでしょう。
金融・投資ライター
大手証券グループ投資会社への勤務を経て、個人投資家・ライターに。株式関連、為替関連、資産運用関連を中心に執筆中。Yahoo!トップページに掲載実績あり。第一種証券外務員資格保有。
大手証券グループ投資会社への勤務を経て、個人投資家・ライターに。株式関連、為替関連、資産運用関連を中心に執筆中。Yahoo!トップページに掲載実績あり。第一種証券外務員資格保有。
関連記事
関連する専門用語
国債
発行体が各国中央政府の債券を国債といいます。発行目的や利払い方式などで種類が分別されます。中央政府に資金需要が発生した際に、国債を発行して資金の調達を行うことがあります。 投資家は国債を購入することで、発行体である中央政府へ資金を提供し、その見返りとして半年に1回などのペースで、中央政府から利子を受け取ります。償還期限までに中央政府の財政が悪化するなど、債務が履行されない状況に陥らなければ、満期には額面どおりの金額が投資家へ償還される仕組みです。 国債には、固定利付国債、変動利付国債、物価連動国債などがあります。
社債
社債とは、企業が事業資金を調達するために発行する「借金の証書」のようなものです。投資家は社債を購入することで企業にお金を貸し、その見返りとして、あらかじめ決められた利息(クーポン)を一定期間ごとに受け取ることができます。満期が来れば、企業は投資家に元本を返済します。 銀行からの融資とは異なり、社債は不特定多数の投資家から直接資金を集める方法であり、企業にとっては柔軟かつ効率的な資金調達手段です。 投資家にとって社債の魅力は、株式に比べて価格の変動が小さく、定期的な利息収入が得られる点にあります。一方で、発行体である企業が経営破綻した場合、元本が戻らないリスクがあるため、信用格付けや業績などを十分に確認することが重要です。 安定的な収益を目指しつつ、リスク管理も重視する投資家にとって、社債はポートフォリオの中核を担いうる資産クラスのひとつです。
劣後債
劣後債とは、企業や金融機関が資金調達のために発行する債券の一種で、通常の社債(シニア債)よりも弁済順位が低い(劣後する)債券のことです。発行体が破綻した場合、一般の債券や他の債権者への支払いが優先され、劣後債の保有者への弁済はその後に行われるため、元本や利息の支払いリスクが相対的に高くなります。 このリスクの高さを補うため、劣後債は通常の社債よりも利回りが高めに設定されており、リスクプレミアムが反映されたハイリスク・ハイリターンの投資対象として位置づけられます。劣後債には、シニア劣後債とジュニア劣後債があり、ジュニア劣後債の方がさらに弁済順位が低いため、リスクが高くなる傾向にあります。 特に、金融機関が発行する劣後債の一部(例:AT1債やTier 2債)は、国際的な銀行規制であるバーゼル規制に基づき、一定の条件を満たせば自己資本として算入できるため、自己資本比率を向上させる手段として利用されています。ただし、AT1債(追加的Tier 1債)は発行体の財務状況によって利息の支払いが停止される可能性もあるため、リスクが高くなります。 投資家にとっては、高い利回りの魅力がある一方で、発行体の信用リスクや市場環境を十分に考慮した慎重な判断が求められる金融商品です。また、流動性が低く、満期前に売却が難しい場合がある点にも注意が必要です。
インカムゲイン(インカム)
インカムゲイン(インカム)とは、株式や債券、不動産などの資産を保有していることで定期的または継続的に得られる収益のことを指します。具体的には、株式の配当金、債券の利息、不動産の家賃収入などが代表的な例です。一方で、資産の売買差益から生まれるキャピタルゲインとは異なり、保有し続けることで一定のペースで収入を得る点が特徴です。 インカムゲインを重視する投資では、安定したキャッシュフローを得られることが大きな魅力となります。例えば、株式の配当金は企業の利益から支払われますが、企業の業績や配当方針に応じて増減があるため、定期的なチェックが必要です。債券の利息は発行体の信用力や金利情勢に大きく左右され、金利が上昇すると既存債券の価格が下落するリスクがあります。不動産投資では家賃収入がインカムゲインとなりますが、空室が続いたり修繕費がかさんだりするリスクがあるほか、売却時の価格も景気や立地に左右されるため、投資額の回収が遅れる可能性があります。 これらのリスクを考慮する一方で、インカムゲインには安定性というメリットがあります。資産を保有しているだけでも定期的に資金が手に入り、再投資や生活費に回すことで資産形成を円滑に進めやすい面があります。また、いざ急に資金が必要になった場合には、すぐに売却しなくても配当金や利息で一定の収入を得られる可能性があるため、心理的な安心感につながることもあります。 ただし、インカムゲインを得ようとするあまり、高配当や高利回りをうたう投資商品ばかりに偏ると、発行体の信用リスクや価格変動リスクが高まるケースも考えられます。特に、株式の配当は企業の業績が悪化すれば減配や無配となる恐れがあり、債券の場合でも発行体の破綻リスクや金利上昇リスクが存在します。不動産投資では物件管理の手間や費用が大きく、地方物件などでは買い手が少なく流動性リスクも高くなるため、分散投資の観点で他の資産とバランス良く組み合わせるのが望ましいでしょう。 総じて、インカムゲインは、投資から生まれる継続的な収益を得るための有力なアプローチです。特に、キャピタルゲインだけに頼らず、配当や利息、家賃収入などの定期的な収入源を得ることでリスクを分散しながら安定した資産運用を目指すことができます。ただし、投資対象の選定やリスク管理は欠かせないポイントであり、投資する資金やライフプラン、リスク許容度に応じて最適なバランスを見極める必要があります。
金利(利率)
金利(利率)とは、お金を貸したり預けたりしたときに発生する利息の割合を表す言葉です。たとえば、銀行にお金を預けると一定の利息がもらえますが、そのときの利息の割合を金利または利率と呼びます。一般的には「金利」が金融機関との貸し借りに使われることが多く、 「利率」は投資商品の収益率などに使われる傾向がありますが、日常的にはほぼ同じ意味で使われています。資産運用の場面では、金利の動きが預金、ローン、債券などの価格や収益に影響を与えるため、金利や利率に注目することはとても大切です。特に経済状況や中央銀行の政策によって金利は変動するため、それを理解しておくことでより良い投資判断につながります。
利回り
利回りとは、投資で得られた収益を投下元本に対する割合で示し、異なる商品や期間を比較するときの共通尺度になります。 計算式は「(期末評価額+分配金等-期首元本)÷期首元本」で、原則として年率に換算して示します。この“年率”をどの期間で切り取るかによって、利回りは年間リターンとトータルリターンの二つに大別されます。 年間リターンは「ある1年間だけの利回り」を示す瞬間値で、直近の運用成績や市場の勢いを把握するのに適しています。トータルリターンは「保有開始から売却・償還までの累積リターン」を示し、長期投資の成果を測る指標です。保有期間が異なる商品どうしを比べるときは、トータルリターンを年平均成長率(CAGR)に換算して年率をそろすことで、複利効果を含めた公平な比較ができます。 債券なら市場価格を反映した現在利回りや償還までの総収益を年率化した最終利回り(YTM)、株式なら株価に対する年間配当の割合である配当利回り、不動産投資なら純賃料収入を物件価格で割ったネット利回りと、対象資産ごとに計算対象は変わります。 また、名目利回りだけでは購買力の変化や税・手数料の影響を見落としやすいため、インフレ調整後や税控除後のネット利回りも確認することが重要です。複利運用では得た収益を再投資することでリターンが雪だるま式に増えますから、年間リターンとトータルリターンを意識しながら、複利効果・インフレ・コストを総合的に考慮すると、より適切なリスクとリターンのバランスを見極められます。
劣後債
劣後債とは、企業や金融機関が資金調達のために発行する債券の一種で、通常の社債(シニア債)よりも弁済順位が低い(劣後する)債券のことです。発行体が破綻した場合、一般の債券や他の債権者への支払いが優先され、劣後債の保有者への弁済はその後に行われるため、元本や利息の支払いリスクが相対的に高くなります。 このリスクの高さを補うため、劣後債は通常の社債よりも利回りが高めに設定されており、リスクプレミアムが反映されたハイリスク・ハイリターンの投資対象として位置づけられます。劣後債には、シニア劣後債とジュニア劣後債があり、ジュニア劣後債の方がさらに弁済順位が低いため、リスクが高くなる傾向にあります。 特に、金融機関が発行する劣後債の一部(例:AT1債やTier 2債)は、国際的な銀行規制であるバーゼル規制に基づき、一定の条件を満たせば自己資本として算入できるため、自己資本比率を向上させる手段として利用されています。ただし、AT1債(追加的Tier 1債)は発行体の財務状況によって利息の支払いが停止される可能性もあるため、リスクが高くなります。 投資家にとっては、高い利回りの魅力がある一方で、発行体の信用リスクや市場環境を十分に考慮した慎重な判断が求められる金融商品です。また、流動性が低く、満期前に売却が難しい場合がある点にも注意が必要です。
リスク許容度
リスク許容度とは、自分の資産運用において、どれくらいの損失までなら精神的にも経済的にも受け入れられるかという度合いを表す考え方です。 投資には必ずリスクが伴い、時には資産が目減りすることもあります。そのときに、どのくらいの下落まで冷静に対応できるか、また生活に支障が出ないかという観点で、自分のリスク許容度を見極めることが大切です。 年齢、収入、資産の状況、投資経験、投資の目的などによって人それぞれ異なり、リスク許容度が高い人は価格変動の大きい商品にも挑戦できますが、低い人は安定性の高い商品を選ぶほうが安心です。自分のリスク許容度を正しく理解することで、無理のない投資計画を立てることができます。
ハイブリッド証券
ハイブリッド証券とは、債券と株式の両方の特徴を併せ持つ金融商品で、資金調達の柔軟性を高めるために企業が活用することが多いです。債券のように定期的な利払いがある一方で、株式のように返済義務が劣後したり、発行企業の業績によって利払いが変動することがあります。 また、一定の条件下で株式に転換できるものもあり、投資家にとってはリターンが見込める一方で、リスクも高めです。企業にとっては、通常の借入や株式発行では対応しにくい状況でも、信用力や資本性を維持しながら資金を調達できる手段として重宝されます。とくに金融機関や格付機関の評価において、自己資本として一部認められるケースがあり、財務体質の強化にもつながります。
新株予約権付社債
新株予約権付社債とは、企業が資金を調達するために発行する社債(借金)に、「あらかじめ決められた価格でその企業の株式を買う権利(新株予約権)」が付いている金融商品です。投資家はこの社債を保有している間、一定の利息を受け取ることができるだけでなく、将来的にその企業の株価が上がった場合には、新株予約権を使って割安で株式を購入することができます。 このように、債券としての安定性と、株式のような値上がり益を狙える「両方のメリット」を持つのが特徴です。ただし、株価があまり上がらなかった場合は新株予約権を使わずに社債としての利息だけを受け取ることになります。また、新株予約権が行使されると、発行会社の株式数が増えるため、既存の株主にとっては「株の価値が薄まる(希薄化する)」可能性もある点に注意が必要です。資産運用においては、成長性のある企業への投資をしつつ、ある程度の安定収益も確保したいと考える投資家にとって魅力的な選択肢となることがあります。