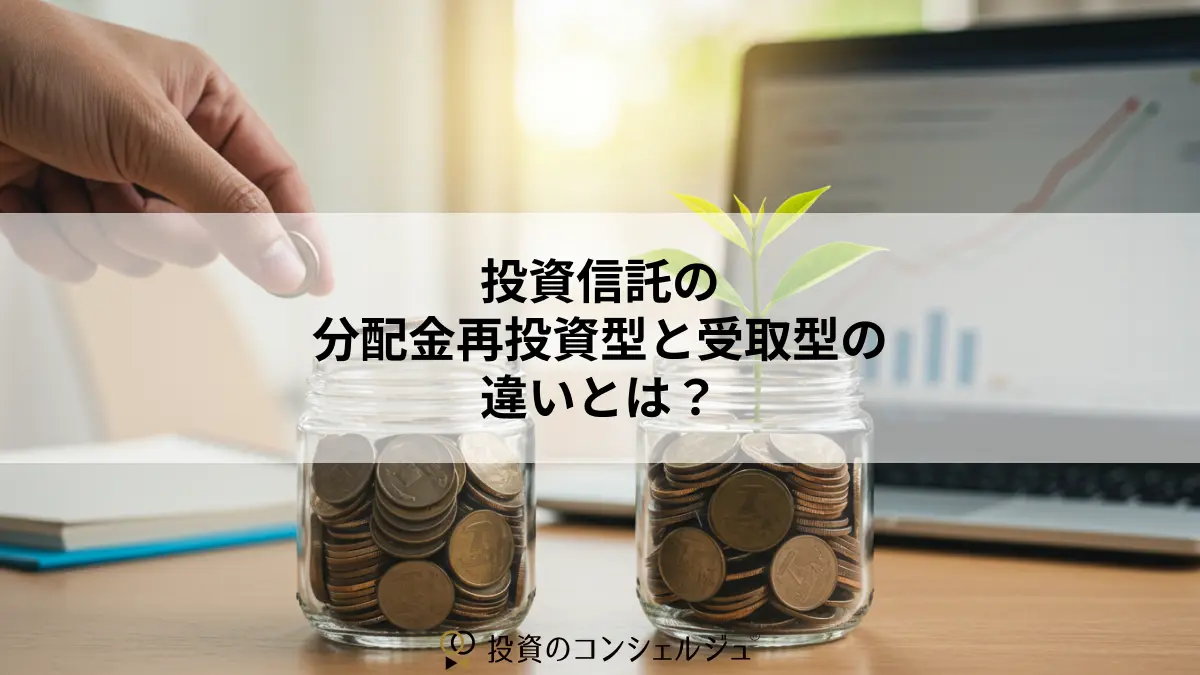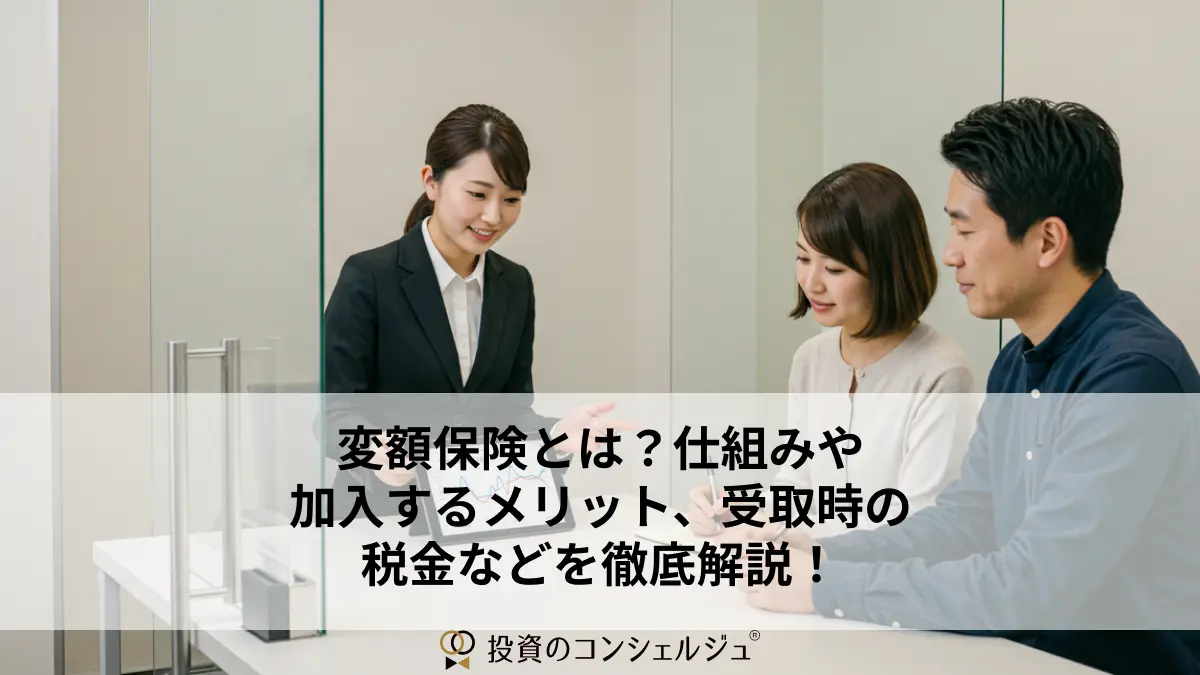ブラックロックのゴールドファンドの特徴は?
回答受付中
0
2025/08/09 08:19
男性
30代
最近、金(ゴールド)に投資する人が増えていると聞きました。中でもブラックロックのゴールドファンドが注目されているようですが、他の金関連ファンドと比べてどのような特徴やメリットがあるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
ブラックロック・ゴールド・ファンド(愛称:Gold Rush)は、南アフリカやカナダ、米国など世界の金鉱株に投資する追加型投資信託です。金そのものではなく「金を掘る企業」の株価上昇を取り込む設計で、外貨建て資産への為替ヘッジは原則行いません。そのため、基準価額は金価格と円相場の両方の影響を受けます。
本ファンドの強みは大きく三つあります。第一に、金価格と連動性の高い金鉱株に集中投資することで、金価格上昇時に株価がそれ以上に伸びる“レバレッジ効果”を狙える点です。第二に、金鉱株は一般の株式や債券と値動きの相関が低く、ポートフォリオ全体のリスク低減に寄与しやすい点です。第三に、ブラックロックの資源専門チームが世界規模で調査してアクティブに運用し、市場平均を上回る超過リターン(α)を目指している点が挙げられます。
一方でコストはやや高めです。販売手数料は最大3.3%、信託報酬(運用管理費用)は年率2.2%程度で、解約時には0.5%の信託財産留保額もかかります。インデックス型ETFの金投資商品と比べると、保有コストは10倍近くになるケースもあるため「リターンで費用を上回れるか」が重要な判断ポイントです。
リスク面では、金価格の下落に株価の変動が掛け算的に効くため値動きが大きくなりがちです。加えて、政治情勢や採掘コスト高騰など個別企業リスク、為替変動による円高リスクも避けられません。過去1年の標準偏差はおおむね20%超と、一般的な株式ファンドより高い水準です。
ファンドは新NISAの「成長投資枠」に対応しているため、長期の資産形成にも組み込めます。ただしポートフォリオ全体の5〜10%程度の“スパイス枠”にとどめ、残りは低コストの株式・債券インデックスファンドや現物金ETFなどで守りを固めるバランス運用が現実的です。
参考までに代表的な現物金ETF「iShares Gold Trust(IAU)」と比べると、IAUは金地金を100%裏付けとするパッシブ運用で信託報酬は年0.25%程度と低コストです。金価格を純粋に追いたい人にはIAUが向き、一方で金価格上昇時により大きな値上がり益を狙いたい人にはブラックロック・ゴールド・ファンドが選択肢となります。
総じて、本ファンドは「金価格の上昇局面で株価が跳ねる攻めの金投資」を求める中長期投資家向けの商品です。高コスト・高ボラティリティを許容でき、資産全体に占める割合を抑えたうえでポートフォリオの分散とリターン拡大を狙う――そんな使い方が初心者にも無理のない現実解と言えるでしょう。
関連記事
関連する専門用語
ブラックロック
ブラックロックとは、アメリカに本社を置く世界最大級の資産運用会社の名前です。個人投資家から年金基金、政府系ファンドに至るまで、世界中の幅広い顧客の資産を運用しています。取り扱う資産の総額は数千兆円規模にのぼり、株式や債券、インデックスファンド、ETF(特にiシェアーズというブランド)など、多様な金融商品を提供しています。長期的で安定した運用を重視しており、インデックス連動型の商品を多数展開していることでも知られています。また、AIを活用したリスク管理システム「アラディン(Aladdin)」を開発・活用するなど、最先端のテクノロジーを取り入れた運用体制も特徴のひとつです。個人投資家にとっても、ブラックロックの商品は信頼性が高く、低コストで分散投資が可能な手段としてよく利用されています。
レバレッジ
レバレッジとは、借入金や証拠金取引など外部資金を活用して自己資本以上の投資規模を実現する手法です。利益の拡大が期待できる一方、市場の下落や金利の変動で損失が膨らみやすく、追加証拠金(追証)が必要になる場合やロスカットが発生するリスクも高まります。 また、借入金利や手数料などのコストが利益を圧迫する可能性があるため、ポジション管理やヘッジ手法を含めたリスク管理が不可欠です。レバレッジによる損益変動幅が大きくなることで精神的な負担も増えやすい点にも注意が必要です。最終的には、投資目的やリスク許容度を考慮し、適切なレバレッジ水準を設定することで、資産運用の効率を高めつつリスクを抑えることが重要となります。
信託報酬
信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。
ボラティリティ
ボラティリティは、投資商品の価格変動の幅を示す重要な指標であり、投資におけるリスクの大きさを測る目安として使われています。一般的に、値動きが大きい商品ほどそのリスクも高くなります。 具体的には、ボラティリティが大きい商品は価格変動が激しく、逆にボラティリティが小さい商品は価格変動が穏やかであることを示します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティを標準偏差という統計的手法で数値化し、それを商品のリスク度合いとして評価するのが一般的です。このため、投資判断においては、ボラティリティの大きい商品は高リスク、小さい商品は低リスクと判断されます。
為替リスク
為替リスクとは、異なる通貨間での為替レートの変動により、外貨建て資産の価値が変動し、損失が生じる可能性のあるリスクを指します。 たとえば、日本円で生活している投資家が米ドル建ての株式や債券に投資した場合、最終的なリターンは円とドルの為替レートに大きく左右されます。仮に投資先の価格が変わらなくても、円高が進むと、日本円に換算した際の資産価値が目減りしてしまうことがあります。反対に、円安が進めば、為替差益によって収益が増える場合もあります。 為替リスクは、外国株式、外貨建て債券、海外不動産、グローバルファンドなど、外貨に関わるすべての資産に存在する基本的なリスクです。 対策としては、為替ヘッジ付きの商品を選ぶ、複数の通貨や地域に分散して投資する、長期的な視点で資産を保有するなどの方法があります。海外資産に投資する際は、リターンだけでなく、為替リスクの存在も十分に理解しておくことが大切です。
分散投資
分散投資とは、資産を安全に増やすための代表的な方法で、株式や債券、不動産、コモディティ(原油や金など)、さらには地域や業種など、複数の異なる投資先に資金を分けて投資する戦略です。 例えば、特定の国の株式市場が大きく下落した場合でも、債券や他の地域の資産が値上がりする可能性があれば、全体としての損失を軽減できます。このように、資金を一カ所に集中させるよりも値動きの影響が分散されるため、長期的にはより安定したリターンが期待できます。 ただし、あらゆるリスクが消えるわけではなく、世界全体の経済状況が悪化すれば同時に下落するケースもあるため、投資を行う際は目標や投資期間、リスク許容度を考慮したうえで、計画的に実行することが大切です。