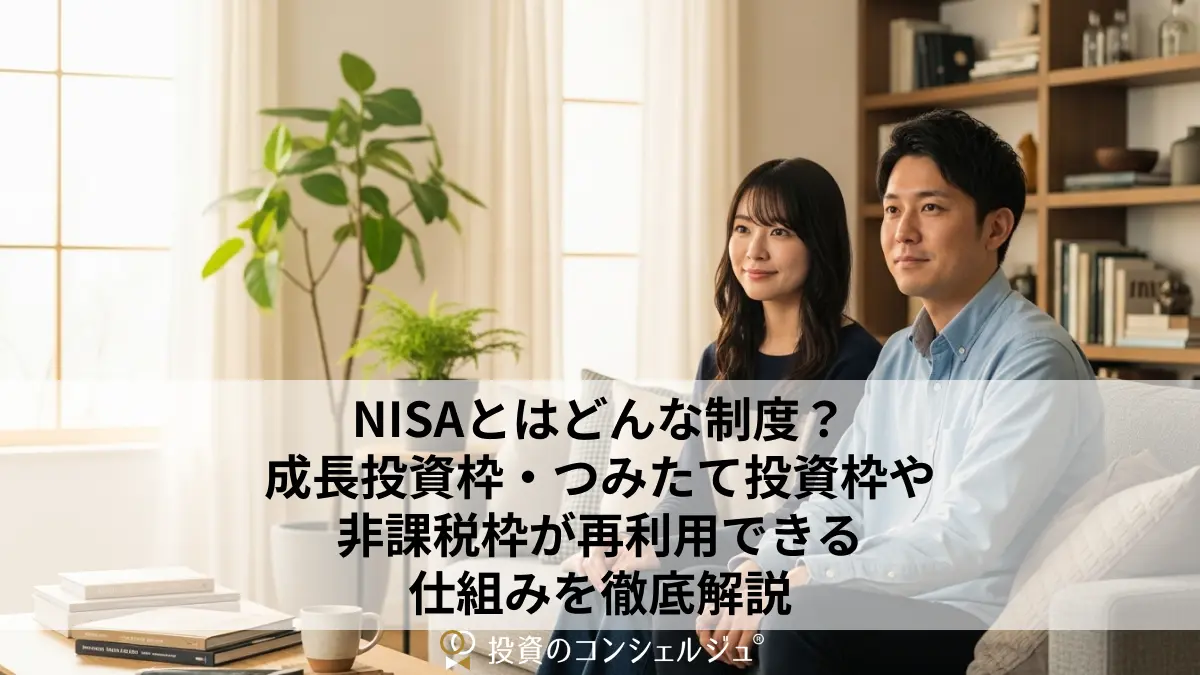eMAXIS Slimとは?:全世界株式や米国S&P500などラインナップや選び方と活用法を徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.09.26
更新:
2025.09.27
この記事を読むと、eMAXIS Slimシリーズの低コスト方針の背景や資産クラスごとの違いが短時間で整理できます。指数との乖離や実質コストの見方、為替リスクや集中リスクの捉え方が自然に身につき、表面的な人気や評判に流されない判断ができるようになります。
また、信託報酬・実質コスト・純資産規模・連動性といった評価軸で比較しながら、「重複のない組み合わせ方」と「積立の始め方」が具体的に理解できます。特に投資家が迷いやすい「全世界株式かS&P500か」という選択も、自信を持って決められるようになります。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、eMAXIS Slimシリーズの低コスト方針の背景や資産クラスごとの違いが短時間で整理できます。指数との乖離や実質コストの見方、為替リスクや集中リスクの捉え方が自然に身につき、表面的な人気や評判に流されない判断ができるようになります。
また、信託報酬・実質コスト・純資産規模・連動性といった評価軸で比較しながら、「重複のない組み合わせ方」と「積立の始め方」が具体的に理解できます。特に投資家が迷いやすい「全世界株式かS&P500か」という選択も、自信を持って決められるようになります。
目次
eMAXIS Slimとは?|業界最安水準コストを目指す投信シリーズ
1. 全世界株式(オール・カントリー):これ1本で世界中に分散投資したい人向け
2. 米国株式(S&P500・全米株式):米国の成長に期待してリターンを狙いたい人向け
3. 国内株式(TOPIX/日経平均):円資産として日本株にも投資したい人向け
4. 先進国株式・新興国株式:投資する国・地域を自分で調整したい人向け
5. 債券(国内/先進国):株式の値動きリスクを抑えたい人向け
6. REIT(リート:国内/先進国):不動産にも分散投資したい人向け
7. バランス(8資産均等型):おまかせで安定運用を目指したい人向け
8. 特殊型(除く日本/3地域均等):特定の投資方針を実現したい上級者向け
NISA・iDeCoでのeMAXIS Slim活用法|制度の基本と選び方
2. iDeCo:老後資金作りで税金のメリットを最大限に活用
3. 取扱金融機関:どこで買う?手数料とポイントがお得なネット証券が基本
迷ったらこの3択!eMAXIS Slimのおすすめ王道シナリオ
シナリオ1. 「全世界株式」1本集中:手間なく世界経済の平均点を狙う
シナリオ2. 「米国株式(S&P500)」集中:リスクを取って高いリターンを狙う
シナリオ3. 「バランス型」中心:安定感を重視して長く続けたい
eMAXIS Slimのコストは本当に安い?手数料を確認する2つのポイント
2. リターンに影響する「分配金」と「為替」の仕組みを理解する
eMAXIS SlimとSBI・Vシリーズ等はどっちがいい?比較と組み合わせのコツ
eMAXIS Slimとは?|業界最安水準コストを目指す投信シリーズ
eMAXIS Slimは、三菱UFJ国際投信が運用するインデックスファンドシリーズです。「業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指す」という方針のもと、長期・積立・分散投資に適した商品を多数ラインナップしています。
NISA等の制度と組み合わせて、低コストで市場平均への長期投資を実践したい投資初心者〜中級者に支持されています。
eMAXIS Slimの3つの特徴
eMAXIS Slimは①低コスト追求の方針(競合動向に応じた信託報酬の見直し)②指数連動の設計(市場平均に沿う成果を目指す)③幅広いラインナップ(株式・債券・REITなど)を特徴とします。コストや実質コスト、連動性(後述)といった評価軸を最新の目論見書・運用報告書で確認しながら選べます。
1. 徹底した低コストへのこだわり
同シリーズは「業界最低水準の運用コストを目指す」と明示し、競合に応じた信託報酬の見直し実績があります。コストは時点で変動するため、最新の目論見書の信託報酬と運用報告書の実質コストの双方を確認して判断しましょう。
2. 市場平均を目指す「指数連動」
eMAXIS Slimは、日経平均株価やS&P500といった、あらかじめ定められた指数(ベンチマーク)に連動する成果を目指すインデックスファンドです。特定の銘柄を選ばず、市場全体の動きに連動させることで、世界経済や各国の市場全体の成長を効率よく自分の資産に取り入れることができます。運用コストが低いほど、長期的には指数に近い成果になりやすくなります(短期の乖離は生じ得ます)。
3.充実のラインナップと規模:複数資産・地域を網羅し、シリーズとしての純資産規模も拡大
eMAXIS Slimは、全世界株式のような定番商品から、債券やリート(REIT)まで、多様な資産クラスを網羅しています。投資家は自分のリスク許容度や方針に合わせて、これらのファンドを自由に組み合わせることが可能です。シリーズの純資産総額は直近まで増加傾向が続いています(時点で変動するため最新データ要確認)。規模の拡大は一般に運用の安定性やコスト効率に寄与し得ます。
「Slim」に込められた意味とは?
eMAXIS Slimの「Slim」はコストのスリム化を志向するブランド方針を示します。信託報酬だけでなく、売買委託手数料や監査費用等を含む実質コスト(年1回の運用報告書で判明)も低水準を目指す設計です。
信託財産留保額の有無・水準はファンドごとに異なるため、目論見書での確認が必要です。
「eMAXIS」と「eMAXIS Slim」の違いは?
両者はコスト設計と販売チャネルに違いがあります。
Slimは低コスト追求を前面に、主にネット証券経由での販売が中心です。
eMAXISはチャネルやコスト水準がファンドにより異なるため、同一指数連動の候補が複数ある場合は、各ファンドの信託報酬・実質コスト・連動性を比較して選ぶのが合理的です。
eMAXIS Slimはどんな人におすすめ?
eMAXIS Slimは、NISAなどを活用して「長期・積立・分散」を実践したい投資初心者や中級者に幅広くおすすめできます。ただし、投資スタイルによっては他の選択肢が合う場合もあります。
おすすめな人
低コストで、手間をかけずに市場全体の成長に沿ったリターンを目指したい人に向いています。特に、つみたて投資枠でコツコツ積立投資をする場合、その低コストと分散効果は非常に有効です。難しい銘柄選びも不要なため、投資経験が浅い方でも安心して始められます。
おすすめでない人
一方で、以下のような場合はミスマッチになる可能性があります。
- 特定地域への集中投資をしたい人:「新興国の比率をもっと高めたい」など、自分で資産配分を細かく調整したい場合、全世界株式ファンドでは物足りなく感じるかもしれません。
- 為替の変動リスクを避けたい人:海外資産に投資するファンドは原則として為替ヘッジを行わないものが多く、為替変動の影響を受けます。円高局面では円換算の評価額が下がる可能性があるため、為替感応度を受け入れにくい方は国内資産比率を高める・ヘッジ型商品を検討する等の対策が必要です。
- 市場平均を上回るリターンを狙いたい人:eMAXIS Slimはアクティブ運用ではなく、あくまで市場平均を目指すパッシブ運用です。より高いリターンを求めて積極的に銘柄を選びたい人には不向きです。
eMAXIS Slimの主なラインナップと特徴
eMAXIS Slimシリーズには、株式、債券、REIT(不動産投資信託)など、様々な資産に投資する合計15本(2025年9月時点)のファンドがあります。
「どの資産」に「どの地域」へ投資するかという観点で、自分の考えに合った商品を選ぶことができます。ここでは、代表的なファンドをカテゴリー別に解説します。
1. 全世界株式(オール・カントリー):これ1本で世界中に分散投資したい人向け
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、通称「オルカン」は、これ1本で日本を含む全世界の株式に分散投資できるファンドです。世界の株式市場の動きを示す指数に連動するため、世界経済全体の成長をリターンとして狙えます。投資先に迷ったらまず検討したい、シンプルで王道の商品です。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 約0.05775% | ○(つみたて/成長) | コア | 日本含む先進国+新興国の世界株を1本で時価総額加重で分散(通称オルカン)。超低コストで王道のコア。 |
メリット:手間いらずで理想的な国際分散が実現できる
最大のメリットは、1本で理想的な国際分散投資が実現できる手軽さです。国や地域の配分は市場の規模に応じて自動で調整されるため、自分でメンテナンスする手間がかかりません。
留意点:米国株比率の高さと市場全体の下落リスク
世界の時価総額に応じて自動で配分され、米国の比率は概ね6割台となるのが一般的です。新興国比率は相対的に小さく、「新興国株式」を上乗せして好みに調整する方法もあります。
2. 米国株式(S&P500・全米株式):米国の成長に期待してリターンを狙いたい人向け
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、米国の代表的な約500社にまとめて投資するファンドです。過去の実績や今後の成長性から、世界経済を牽引する米国に集中投資したいと考える人に人気があります。全世界株式よりも高いリターンを期待できる可能性がある一方、リスクも大きくなる点には注意が必要です。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 約0.0814% | ○(つみたて/成長) | サブコア(成長寄り) | 米国大型株約500社に連動。長期で人気の集中投資先。2025年時点の最新料率は0.0814%水準。 |
メリット:高い成長期待と過去の優れたリターン実績
最大の魅力は、高い成長期待です。イノベーションを牽引するIT企業などが含まれており、過去のリターンは全世界株式を上回る期間が多くありました。
留意点:米国への集中投資と円高による為替リスク
投資先が米国に集中するため、米国経済が不調になると大きな影響を受けます。また、資産は米ドル建てなので、円高になると円換算での価値が下がる「為替リスク」があります。
3. 国内株式(TOPIX/日経平均):円資産として日本株にも投資したい人向け
「eMAXIS Slim 国内株式」には、市場全体の値動きを示す「TOPIX」に連動するものと、主要225社の値動きを示す「日経平均株価」に連動するものの2種類があります。為替リスクがなく、日本経済の成長に期待する人や、円建ての資産を手厚くしたい人に適しています。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 約0.143% | ○(つみたて/成長) | 日本株エクスポージャー | 東証株式の広範をカバー。円建てで為替リスクなし、全世界×日本の比率調整に。 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 約0.143% | ○(つみたて/成長) | 日本株サブコア | 代表225銘柄に連動。指数の設計が異なるためTOPIXと組み合わせの考慮も。 |
メリット:為替リスクがなくポートフォリオの安定に貢献
為替変動の影響を受けない円建て資産であるため、ポートフォリオの安定につながります。また、「全世界株式」ファンドの日本株比率は比較的小さいため、日本への投資比率を高めたい場合に活用できます。
留意点:国際分散の効果はなく、リターンは米国株等に劣後する可能性
日本市場だけに投資するため、国際分散の効果は得られません。過去の長期的なリターンは米国株などに劣後してきた歴史もあります。全世界株式などと組み合わせて持つのがおすすめです。
4. 先進国株式・新興国株式:投資する国・地域を自分で調整したい人向け
「全世界株式」を地域ごとに分解したファンドです。「先進国株式」は日本を除くアメリカやヨーロッパなどの先進国に、「新興国株式」は中国やインドといった今後高い成長が期待される国々に投資します。これらを組み合わせることで、自分好みの配分で国際分散投資を設計できます。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 約0.09889% | ○(つみたて/成長) | サブコア | MSCIコクサイ連動(日本除く主要先進国)。オルカンを自分で分解したい人向け。 |
| eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 約0.09889% | ○(つみたて/成長) | サブコア | 先進国を日本も含めてカバー(シリーズ内の“先進国(含む日本)”の新設系ライン)。配分を日本含みにしたい人向け。 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 約0.1518% | ○(つみたて/成長) | サテライト | MSCIエマージング連動。成長余地は大きいが、ボラティリティ・政策/通貨リスクも相応。 |
| eMAXIS Slim 全米株式 | 約0.0814% | ○(つみたて/成長) | サブコア(米国広域) | 米国の広範な株式(トータルマーケット)を対象。S&P500より裾野の広い米株エクスポージャーに) |
メリット:自分好みの比率で国・地域をカスタマイズできる
「全世界株式では新興国の比率が物足りない」と感じる場合などに、新興国株式ファンドを買い足すことで、自分なりの比率調整が可能です。
留意点:管理の手間と新興国特有の価格変動リスク
全世界株式1本に比べて管理がやや複雑になります。また、新興国は経済や政治が不安定な場合もあり、先進国よりも大きな価格変動リスクを伴います。
5. 債券(国内/先進国):株式の値動きリスクを抑えたい人向け
債券は、株式と並ぶ代表的な資産です。一般的に株式とは異なる値動きをする傾向があるため、ポートフォリオに組み入れることで、資産全体の値動きを安定させる効果が期待できます。「国内債券」と、日本を除く先進国の債券に投資する「先進国債券」の2種類があります。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 約0.132% | ○(つみたて/成長) | ディフェンシブ(円建て) | 国内公社債に分散。為替リスクなしで値動きは株式より穏やか。 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 約0.154% | ○(つみたて/成長) | ディフェンシブ(分散) | 日本を除く先進国の公社債に広く分散。株式と異なる値動きでクッション役。2025/7に名称を「(除く日本)」へ変更。 |
債券の役割:株式とは異なる値動きで資産全体の安定性を高める
株式市場が下落する局面でも、債券価格は安定していたり、逆に上昇したりすることがあります。このように、資産全体のクッション役として価格変動リスクを和らげるのが主な役割です。
留意点:大きなリターンは期待できず、外国債券には為替リスクがある
大きなリターンを狙う資産ではありません。「先進国債券」は為替リスクを伴います。「国内債券」は為替リスクはありませんが、リターンも非常に低くなる傾向があります。
6. REIT(リート:国内/先進国):不動産にも分散投資したい人向け
REIT(リート)は、オフィスビルや商業施設などの不動産に投資する商品です。株式や債券とは異なる値動きをすることが期待されるため、分散投資の選択肢の一つとなります。「国内リート」と、日本を除く先進国のリートに投資する「先進国リート」の2種類があります。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 約0.22% | ○(つみたて/成長) | 代替資産(サテライト) | 先進国REIT(不動産)に分散。配当(分配)原資となる賃料収入等に期待。価格変動は株式並みも。 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 約0.187% | ○(つみたて/成長) | 代替資産(サテライト) | 日本のREITに分散。金利や不動産市況に敏感。ポートフォリオの不動産エクスポージャー付与に。 |
リートの特徴:賃料収入などを源泉とする比較的高い分配金が魅力
不動産の賃料収入などがリターンの源泉であり、比較的高い分配金が期待できるのが特徴です。株式や債券だけでなく、不動産にも資産を分散させたい場合に活用できます。
留意点:価格変動は株式並みに大きく、安全資産ではない
不動産市況や金利の動向に影響を受けやすく、価格変動は株式並みに大きいことがあります。決して安全資産ではないため、ポートフォリオのアクセントとして、一部を組み入れるのがおすすめです。
7. バランス(8資産均等型):おまかせで安定運用を目指したい人向け
「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は、国内外の株式、債券、REITの8つの資産に1本で均等に投資できるファンドです。自分で資産配分を考える必要がなく、自動でリバランス(配分調整)もしてくれるため、手間をかけずに安定的な運用を目指したい人に適しています。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 約0.143% | ○(つみたて/成長) | おまかせ分散(コア候補) | 国内外の株・債券・REITの8資産へ均等配分&自動リバランス。手間をかけずに広く分散。 |
メリット:自動リバランス機能付きで安定した値動きが期待できる
様々な資産に分散されているため、株式100%のファンドに比べて価格変動が緩やかになる傾向があります。値動きの安定は、長期投資を続ける上での安心材料になります。
留意点:リターンは株式中心ファンドに劣り、配分は固定
安定を重視する分、株式中心のファンドに比べてリターンは控えめになる可能性があります。資産配分は固定されているため、市場の状況に合わせた柔軟な変更はできません。
8. 特殊型(除く日本/3地域均等):特定の投資方針を実現したい上級者向け
基本のラインナップに加え、「全世界株式(除く日本)」や「全世界株式(3地域均等型)」といった、特定の投資方針を持つ人向けのファンドも用意されています。ポートフォリオをより細かく自分好みに調整したい場合に活用できる、やや上級者向けの選択肢です。
| 商品名 | 信託報酬(目安) | NISA対応 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 約0.05775% | ○(つみたて/成長) | コア(日本株を別で保有する人向け) | 日本を除く全世界株。日本株を自前で持つ/増やす設計と相性◎。 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 約0.05775% | ○(つみたて/成長) | コア〜サブコア | 日本・先進国(除く日本)・新興国を1/3ずつ均等配分。時価総額比でなく地域を意図的にフラット化。 |
NISA・iDeCoでのeMAXIS Slim活用法|制度の基本と選び方
eMAXIS Slimシリーズは、NISAやiDeCoといった税制優遇制度と非常に相性が良い商品です。ここでは、これらの制度を使ってeMAXIS Slimを活用する際の具体的な方法や注意点を解説します。制度のルールは変更されることがあるため、実際に始める際は必ず公式サイトなどで最新情報を確認してください。
1. 新NISA:2つの非課税枠を使い分けるのが基本戦略
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれの特徴に合わせてeMAXIS Slimのファンドを選ぶのが効果的です。基本は長期的な資産形成を目指し、腰を据えて運用することが非課税メリットを最大限に活かすコツです。
NISAについて詳しくは以下の記事で解説しています。
つみたて投資枠:王道は「全世界株式」か「S&P500」の自動積立
つみたて投資枠は、毎月コツコツと長期で積立投資を行うのに適しています。
つみたて投資枠は金融庁の基準を満たす長期・積立・分散向け商品に限定されます。対象可否は商品ごとに異なるため、購入画面や商品ページの「つみたて枠対象」表示を必ず確認してください。
この枠では、1本で世界中に分散投資できる「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」か、米国の成長に期待する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を自動で積み立てるのが王道パターンです。どちらを選ぶか迷う場合は、より分散効果の高い「全世界株式」から始めるのが無難でしょう。
成長投資枠:つみたて投資枠の「上乗せ」や「補完」に活用
成長投資枠は、つみたて投資枠よりも自由度の高い投資が可能です。
例えば、つみたて投資枠と同じファンドを追加購入して非課税投資額を増やす「上乗せ」や、異なる特徴を持つファンド(例:「S&P500」に「新興国株式」をプラス)を組み合わせて弱点を補う「補完」といった使い方が考えられます。
2. iDeCo:老後資金作りで税金のメリットを最大限に活用
iDeCoは、掛金が所得控除の対象になるなど、老後資金作りに特化した強力な税制優遇制度です。ただし、原則60歳まで資金を引き出せないという制約があるため、長期的な視点で商品を選ぶ必要があります。
iDeCoについては以下の記事で詳しく解説しています。
金融機関選び:取扱商品と口座管理手数料の確認が必須
iDeCoは、利用する金融機関によって選べる商品や手数料が異なります。希望するeMAXIS Slimのファンドがラインナップに含まれているか、また口座管理手数料が安いかを事前にしっかり確認することが、長期的な運用成果に大きく影響します。
運用時の注意点:60歳まで引き出せないことを前提に計画を
iDeCoは原則60歳まで換金不可です。スイッチング(預け替え)は手数料無料の商品が多い一方、口座管理手数料は別途発生します。ライフイベントに合わせ、年1回程度の見直しを基準に無理のない範囲で調整しましょう。
3. 取扱金融機関:どこで買う?手数料とポイントがお得なネット証券が基本
eMAXIS Slimシリーズは多くの金融機関で購入できますが、販売手数料が無料で、クレジットカード積立などでポイントが貯まるネット証券が最もおすすめです。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などが代表的で、それぞれポイント還元率やサービスに特徴があります。
ネット証券を基本に、クレカ積立の還元率、投信保有ポイント、積立設定の柔軟性(毎日/毎週)、入金のしやすさ(即時入金)などを比較しましょう。長期ではポイント還元と手数料構造の差が効いてきます。
迷ったらこの3択!eMAXIS Slimのおすすめ王道シナリオ
eMAXIS Slimには多くのファンドがあり、どれを選べば良いか迷うかもしれません。ここでは、投資初心者から中級者向けに、代表的な3つの運用シナリオを紹介します。
3つのシナリオに優劣はありません。期待リターンと価格変動(下落時の耐性)のバランス、そして続けやすさで選ぶのが実務的です。ご自身のリスク許容度や投資方針に合わせて、最適なプランを見つける参考にしてください。
シナリオ1. 「全世界株式」1本集中:手間なく世界経済の平均点を狙う
投資の判断や手間をできるだけ省きたい人向けの、最もシンプルな戦略です。「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」1本だけをコツコツ積み立て、世界経済全体の成長をリターンとして狙います。どの国が成長するかを予測する必要がなく、投資先の選択に迷うことがありません。
こんな人におすすめ
とにかくシンプルに始めたい、細かいことは気にせず世界経済全体に投資したいという方に向いています。投資の王道であり、大きな失敗をしにくい選択肢です。
メリット:判断ストレスがなく、自動で国際分散が維持される
投資先の配分は市場の規模に応じて自動で調整されるため、自分でメンテナンスする必要がありません。一部の国が停滞しても、他の国々の成長でカバーできる安心感があります。
デメリット:リターンが物足りなく感じる可能性
米国株式など、特定の地域への集中投資に比べると、リターンは穏やかになる傾向があります。爆発的な成長は期待しにくい反面、安定感のある運用が可能です。
シナリオ2. 「米国株式(S&P500)」集中:リスクを取って高いリターンを狙う
今後も米国の高い成長が続くと信じ、集中的に投資することで大きなリターンを狙う戦略です。「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を中心にポートフォリオを組みます。リターンを最大化できる可能性がある一方、リスクも相応に高くなる点を理解しておく必要があります。
投資はS&P500だけでいい?という疑問に対しては以下Q&Aでも説明しています。
こんな人におすすめ
米国の将来性を信じ、多少の価格変動は許容できるという方に向いています。資産が大きく増える可能性がありますが、相応のリスク耐性が求められます。
メリット:高いリターンが期待できる
イノベーションを牽引するグローバル企業が多く含まれ、過去の実績でも全世界株式を上回るリターンを上げてきました。資産をスピーディーに増やせる可能性があります。
デメリット:米国経済の動向と為替リスクに大きく左右される
投資先が米国に集中するため、米国景気・金利・為替(円高)の影響を同時に受けやすく、短期的な評価額ブレは大きくなります。また、円高になると円換算での資産価値が減少する為替リスクも伴います。
長期で取り組む前提と下落時のルール(積立継続等)を決めておきましょう。
シナリオ3. 「バランス型」中心:安定感を重視して長く続けたい
価格の変動をできるだけ抑え、精神的な負担を減らしながら長期的に投資を継続したい人向けの戦略です。「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」を中心に、安定したポートフォリオを構築します。特に、価格の下落に不安を感じやすい投資初心者におすすめです。
こんな人におすすめ
最大リターンより継続のしやすさを重視し、下落時に積立を止めにくい設計を求める人に向いています。値動きが緩やかで心理的負担を抑えやすいのが利点です。
メリット:価格変動が緩やかで精神的な負担が少ない
株式だけでなく債券やREITにも分散されているため、株式市場が大きく下落した際も、資産全体への影響を和らげる効果が期待できます。
デメリット:リターンは株式中心のポートフォリオに劣る
安定性を重視する分、リターンは株式100%のポートフォリオに比べて控えめになります。長期的に見ると、その差は大きくなる可能性があります。
eMAXIS Slimのコストは本当に安い?手数料を確認する2つのポイント
インデックスファンドの運用において、コストは長期的なリターンに直接影響する重要な要素です。eMAXIS Slimシリーズは業界最低水準のコストを掲げていますが、具体的にどのような費用がかかるのか、そしてなぜ安さを維持できるのかを理解しておくことが大切です。
1. 「信託報酬」だけでなく「実質コスト」も確認しよう
投資信託のコストを見る際は、カタログに表示されている「信託報酬」だけでなく、実際に運用でかかった全ての費用を含む「実質コスト」を確認することが重要です。
実質コストとは、信託報酬に加え、売買委託手数料・保管費用・監査費用など運用で実際に発生した費用の合計(年次の運用報告書で判明)です。表示の信託報酬とあわせて比較しましょう。
eMAXIS Slimシリーズは、この実質コストも低く抑えられているのが特徴です。
2. なぜ安さを維持できる?純資産の拡大が低コストの鍵
eMAXIS Slimが低コストを実現し、さらに継続的に信託報酬を引き下げられる背景には、ファンドに集まる資金の大きさ、つまり「純資産総額の拡大」があります。
資産規模が大きいほど運用効率が上がる
一般的に、投資信託は純資産総額が大きくなるほど、運用にかかる固定費の割合が下がり、効率的な運営が可能になります。多くの投資家から資金が集まることでスケールメリットが働き、信託報酬を引き下げる余力が生まれるのです。
継続的な信託報酬引き下げの実績
eMAXIS Slimは「業界最低水準のコストを目指し続ける」という方針を掲げ、実際に競合ファンドの動向に合わせて何度も信託報酬を引き下げてきました。純資産総額の増加がさらなるコスト低下につながるという、投資家にとって好ましい循環が生まれています。
運用成果のチェック方法|基準価額・利回り・分配金の仕組み
インデックスファンドの成績は、目標とする指数(ベンチマーク)にどれだけ忠実に連動できているかで評価されます。ここでは、その連動性を確認するための「基準価額」の見方や、リターンに影響を与える「分配金」「為替」といった要素の仕組みについて、分かりやすく解説します。
1. 「基準価額」とベンチマークのズレで連動性を確認する
基準価額とは、投資信託の値段のことで、日々変動します。インデックスファンドでは、この基準価額が目標とする指数の動きとほぼ一致することが理想です。
指数との連動の度合いは、日々のブレをトラッキングエラー(TE)、累積の差をトラッキングディファレンス(TD)と呼び、数値が小さいほど指数に忠実と評価されます。
eMAXIS Slimシリーズは、このズレが小さいことで知られています。
2. リターンに影響する「分配金」と「為替」の仕組みを理解する
ファンドの最終的なリターンには、信託報酬以外にも分配金の方針や為替の変動が影響します。これらの仕組みを理解しておくことで、より正確に運用成果を把握できます。
分配金は出さずに再投資するのが基本方針
eMAXIS Slimシリーズは、投資先から得られた配当などを投資家に分配せず、そのままファンド内で再投資する方針をとっています。これにより、税金の支払いを繰り延べながら、複利効果で効率的に資産を成長させることができます。
為替ヘッジは行わず、為替変動をそのままリターンに反映
海外の資産に投資するファンドは、為替レートの変動によって円換算での価値が変わります。eMAXIS Slimシリーズでは、この為替変動のリスクを抑える「為替ヘッジ」を行いません。為替ヘッジにはコストがかかるため、長期的なリターンを優先する方針だからです。
為替ヘッジを判断するための基準は以下Q&Aでも説明しています。
eMAXIS SlimとSBI・Vシリーズ等はどっちがいい?比較と組み合わせのコツ
eMAXIS Slimの他に、SBI・Vシリーズなど低コストの競合ファンドも人気です。ここでは、自分に合ったファンドを選ぶための比較ポイントと、複数のファンドを効果的に組み合わせる際の注意点を解説します。ファンド選びの最終的な判断材料としてご活用ください。
1. 競合ファンドとの比較:コスト、規模など4つのポイントで選ぶ
同じ指数に連動するファンドを比較する際は、以下の4つのポイントを確認しましょう。
- コスト:カタログに記載の「信託報酬」だけでなく、運用報告書で確認できる「実質コスト」まで含めて比較します。わずかな差でも、長期ではリターンに大きく影響します。
- 純資産規模:ファンドに集まっている資金の大きさも重要です。規模が大きいほど運用が安定し、繰上償還(ファンドが運用を終了してしまうこと)のリスクが低くなります。
- 運用会社の方針:「業界最低水準コストを目指し続ける」といった、投資家に利益を還元する方針を明確に示しているかは、信頼性を測る上で大切な指標です。
- 指数との連動性:目標とする指数にどれだけ忠実に連動できているか、過去の実績を確認します。ズレが小さいほど、運用が優れていると言えます。
これらの点を総合的に見ると、各ファンドに決定的な優劣はなく、僅差であることが多いです。eMAXIS Slimは実績と運用方針の明確さで安心感がありますが、SBI・Vシリーズなども非常に優秀です。最終的には、ご自身が利用する証券会社のポイント制度なども考慮して選ぶと良いでしょう。
2. 効果的な組み合わせ方:投資先の「重複」を避けて分散効果を高める
複数のファンドを組み合わせて運用する場合、まず避けたいのは「同じ中身の二重保有」です。
例えば、全世界株式(オルカン)と米国株式(S&P500)を両方購入すると、オルカンに含まれる米国株と合わせて、ポートフォリオに占める米国株の比率が8割を超えてしまうことがあります。これでは分散効果が薄れてしまい、かえってリスクを高める結果になりかねません。
組み合わせが有効なのは、お互いを補完し合う関係の場合です。「先進国株式」に「国内株式」を加えて先進国全体をカバーしたり、「米国株式」に「新興国株式」を加えて成長地域を補ったりするのが良い例です。
基本は1本、多くても補完関係にある2から3本程度に絞り、シンプルな構成で運用するのが長期的に成功しやすいでしょう。
以上、eMAXIS Slimシリーズの特徴から活用法までを解説しました。超低コストでインデックス投資の王道を行くこれらのファンドは、初心者から中級者まで、多くの方にとって強力な資産形成のツールとなるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、ご自身の資産運用計画に役立ててください。
この記事のまとめ
eMAXIS Slimは低コストと指数連動性で、長期積立の土台になり得るシリーズです。選定は信託報酬だけでなく実質コスト、純資産規模、ベンチマーク乖離、為替・集中リスクを軸に、重複を避けて2〜3本に絞るのが要点です。次の一歩は、全世界株式かS&P500のいずれかで少額積立を開始し、年1回の見直しで配分を整えること。新NISAでは成長投資枠とつみたて枠の役割を分け、iDeCoは長期拘束を前提に税制メリットを確認しましょう。迷いが残る場合は、中立的な専門家に家計全体のリスク許容度と併せて相談し、判断の確度を高めてください。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。
インデックスファンド
インデックスファンドとは、特定の株価指数(インデックス)と同じ動きを目指して運用される投資信託のことです。たとえば「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」などの市場全体の動きを示す指数に連動するように設計されています。この仕組みにより、個別の銘柄を選ぶ手間がなく、市場全体に分散投資ができるのが特徴です。また、運用の手間が少ないため、手数料が比較的安いことも魅力の一つです。投資初心者にとっては、安定した長期運用の第一歩として選びやすいファンドの一つです。
為替ヘッジ
為替ヘッジとは、為替取引をする際に、将来交換する為替レートをあらかじめ予約しておくことによって、為替変動のリスクを抑える仕組み。海外の株や債券に投資する際は、その株や債券の価値が下がるリスクだけでなく、為替の変動により円に換算した時の価値が下がるリスクも負うことになるので、後者のリスクを抑えるために為替ヘッジが行われる。
繰上償還(投資信託)
繰上償還とは、投資信託や債権などにおいて、運用資産が少なくなり一定規模を下回った場合に運用会社が効率的な運用をすることが難しくなったと判断して、償還期日(あらかじめ設定されていた期限)を繰り上げて、償還期日よりも前に償還することをいう。投資目的を早期に達成した場合にも行われることがある。
実質コスト
実質コストとは、投資信託を1年間保有した場合に投資家が実際に負担する全ての費用を合計し、期中の平均純資産総額で割って割合として示したものです。信託報酬のほかに売買委託手数料や監査費用、保管費用など運用に付随する細かな経費も含まれるため、名目の信託報酬より高くなるのが一般的です。多くの場合、決算後に運用報告書で公表されるため事前に完全な数値を知ることはできませんが、同じカテゴリのファンド同士を費用面で比較する際に最も実態に近い指標として役立ちます。
純資産総額(Net Asset Value, NAV)
純資産総額とは、投資信託(ファンド)が保有しているすべての資産から、負債を差し引いた実質的な価値の合計を指します。これは、そのファンド全体の規模や健全性、人気度を測る指標としてよく使われます。一般的に、投資家がファンドに多くのお金を預ければ預けるほど、この純資産総額は大きくなります。また、運用成績が良くて利益が出ているファンドほど、純資産総額が増加する傾向にあります。資産運用の観点では、ファンド選びの際にこの数字を確認することで、流動性の高さや安定した運用体制があるかどうかの目安になります。ただし、金額が大きいからといって必ずしも運用成績が良いとは限らないため、他の指標と合わせて判断することが大切です。
信託報酬
信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。
スイッチング
スイッチングとは、確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)でよく使われる用語で、すでに保有している運用商品を売却し、その資金で別のファンドに乗り換えることを指します。たとえば、安定重視の債券型ファンドから、成長を狙った株式型ファンドに変更するなど、市場環境やライフプランの変化に応じて資産配分を見直すための重要な手段です。 確定拠出年金の仕組みでは、このスイッチングは同一制度内で完結するため、多くの場合、売却や購入に手数料がかからず、非課税で実行できます。ただし、ファンドによっては信託財産留保額やスプレッドなど、乗り換え時にコストが発生する場合もあるため、注意が必要です。 投資初心者にとっては、「口座の中で資産を入れ替える仕組み」と理解するとイメージしやすく、自分の年齢やリスク許容度に応じて運用を柔軟に調整できる便利な機能です。長期的な資産形成を続けるうえで、定期的な見直しとスイッチングの活用は大きな効果を発揮します。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
パッシブ運用
パッシブ運用とは、投資信託を選ぶ際の運用手法の一つ(対義語:アクティブ運用)。比較のために用いる指標であるベンチマーク(日経平均やNASDAQなど)と同様の動きを目標とする運用手法で、組み入れ銘柄数は多くなる傾向がある。パッシブ運用はアクティブ運用に比べて販売手数料や信託報酬などのコストは安くて済むが、リスクが分散される分、リターンも小さくなるという特徴がある。
バランスファンド
バランスファンドとは、株式と債券などの固定収入資産を組み合わせた投資ファンドです。このタイプのファンドは、成長の機会を追求する一方で、リスクを分散し安定した収益を目指します。投資の比率は通常、ファンドの投資方針に基づき、アクティブに管理されます。 バランスファンドの主な魅力は、一つのファンド内で異なる資産クラスへの露出を確保できる点にあります。市場の変動に対する耐性を高めるために、株式の成長性と債券の安定性を兼ね備えています。このため、市場の状況に応じて、ファンドマネージャーは資産配分を調整し、リスクを管理しながらリターンを最適化することが可能です。 投資家にとって、バランスファンドは多様な投資ポートフォリオを持つことなく、一定のリバランスを通じて市場の機会を捉えつつ、下落リスクを抑制できる手段を提供します。特に長期投資や退職資金の積立に適しており、安定した運用成績を求める投資家に人気があります。
ベンチマーク
ベンチマークとは、特定の目標や標準として用いる指標のことを指し、ビジネス、金融、技術など様々な分野で利用されます。この指標を用いて、パフォーマンスの測定や戦略の効果を評価し、改善点を見つけることができます。特に投資分野においては、ベンチマークはポートフォリオのパフォーマンスを評価するための基準点として活用され、特定の市場指数や同業他社の成績などが用いられます。 たとえば、投資ファンドの管理者は、自身のファンドのパフォーマンスをS&P 500やナスダックなどの市場指数と比較して評価することが多いです。この比較によって、ファンドの戦略が市場全体と比べてどの程度効果的であるか、またはリスクが適切に管理されているかを判断します。 ベンチマークは、透明性と目標設定を促進し、継続的な改善を目指すための重要なツールです。しかし、ベンチマークを選定する際には、その適切性や関連性を慎重に評価する必要があります。適切でないベンチマークを選ぶと、誤った方向性を示すことがあり、結果的にパフォーマンスの誤解を招くことになるためです。したがって、目標とする成果と密接に関連する、かつ実現可能なベンチマークを設定することが極めて重要です。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産運用における投資対象の組み合わせを指します。分散投資を目的として、株式、債券、不動産、オルタナティブ資産などの異なる資産クラスを適切な比率で構成します。投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを設計し、リスクとリターンのバランスを最適化します。また、運用期間中に市場状況が変化した場合には、リバランスを通じて当初の配分比率を維持します。ポートフォリオ管理は、リスク管理の重要な手法です。
リバランス
リバランスとは、ポートフォリオを構築した後、市場の変動によって変化した資産配分比率を当初設定した目標比率に戻す投資手法です。 具体的には、値上がりした資産や銘柄を売却し、値下がりした資産や銘柄を買い増すことで、ポートフォリオ全体の資産構成比率を維持します。これは過剰なリスクを回避し、ポートフォリオの安定性を保つためのリスク管理手法として、定期的に実施されます。 例えば、株式が上昇して目標比率を超えた場合、その一部を売却して債券や現金に再配分するといった調整を行います。なお、近年では自動リバランス機能を提供する投資サービスも登場しています。
REIT(Real Estate Investment Trust/不動産投資信託)
REIT(Real Estate Investment Trust/不動産投資信託)とは、多くの投資家から集めた資金を使って、オフィスビルや商業施設、マンション、物流施設などの不動産に投資し、そこで得られた賃貸収入や売却益を分配する金融商品です。 REITは証券取引所に上場されており、株式と同じように市場で売買できます。そのため、通常の不動産投資と比べて流動性が高く、少額から手軽に不動産投資を始められるのが大きな特徴です。 投資家は、REITを通じて間接的にさまざまな不動産の「オーナー」となり、不動産運用のプロによる安定した収益(インカムゲイン)を得ることができます。しかも、実物の不動産を所有するわけではないので、物件の管理や修繕といった手間がかからない点も魅力です。また、複数の物件に分散投資しているため、リスクを抑えながら収益を狙える点も人気の理由です。 一方で、REITの価格は、不動産市況や金利の動向、経済環境の変化などの影響を受けます。特に金利が上昇すると、REITの価格が下がる傾向があるため、市場環境を定期的にチェックしながら投資判断を行うことが重要です。 REITは、安定した収益を重視する人や、実物資産への投資に関心があるものの手間やコストを抑えたい人にとって、有力な選択肢となる資産運用手段の一つです。