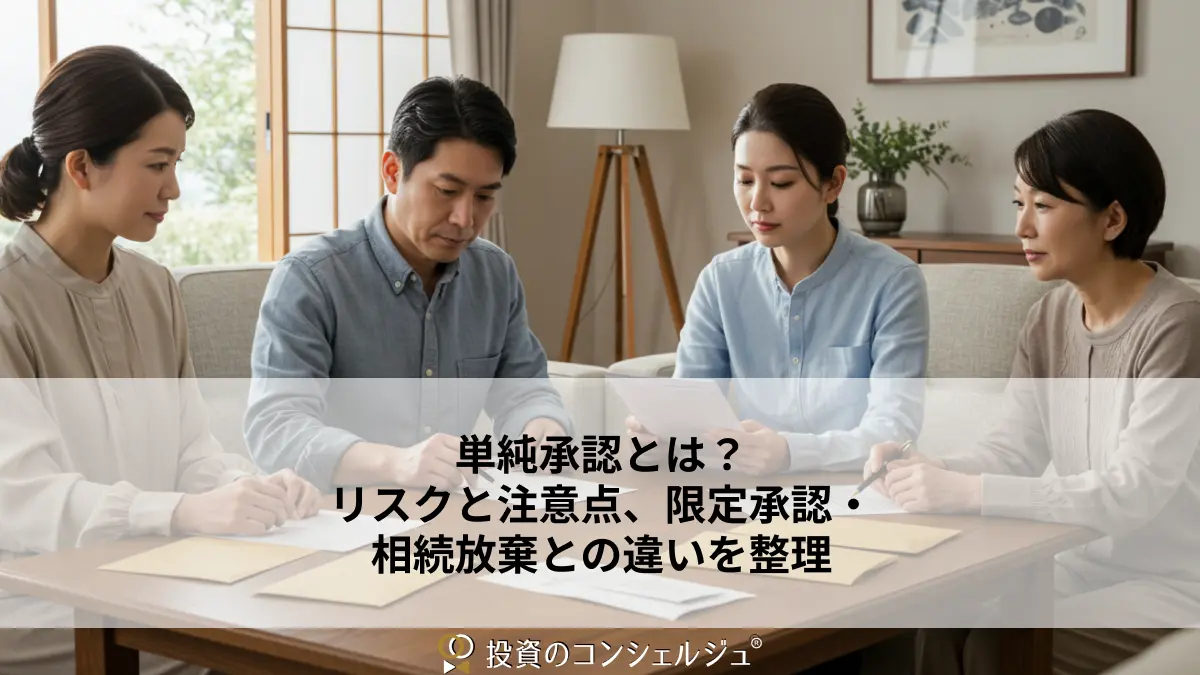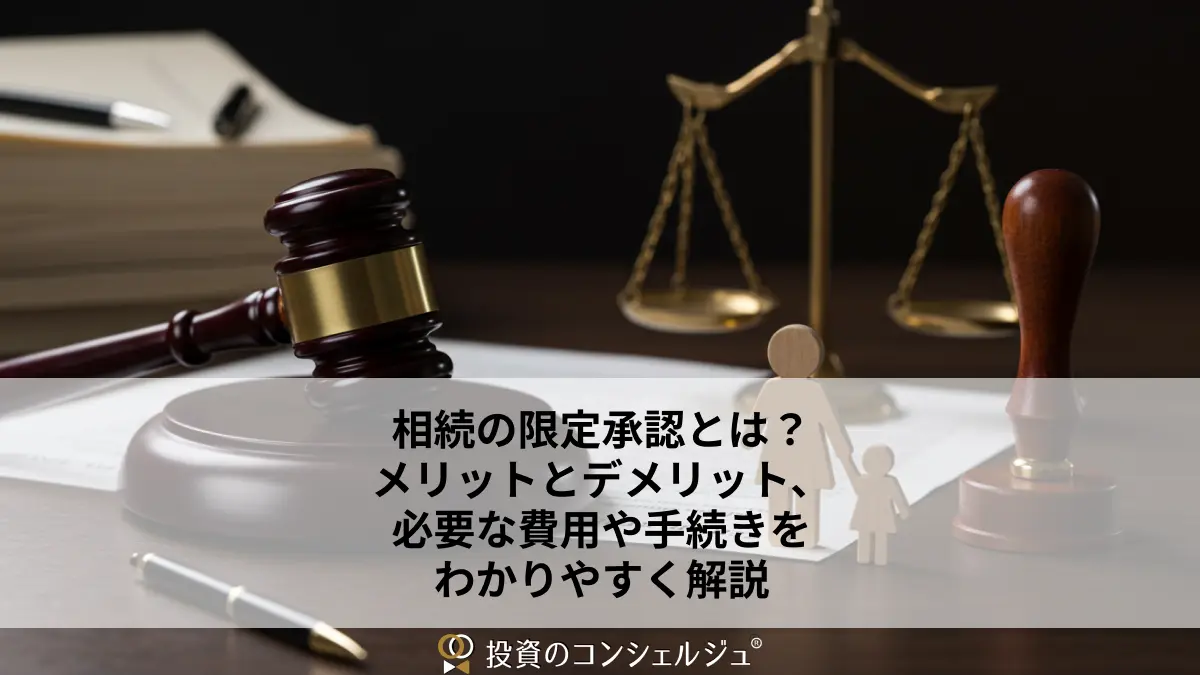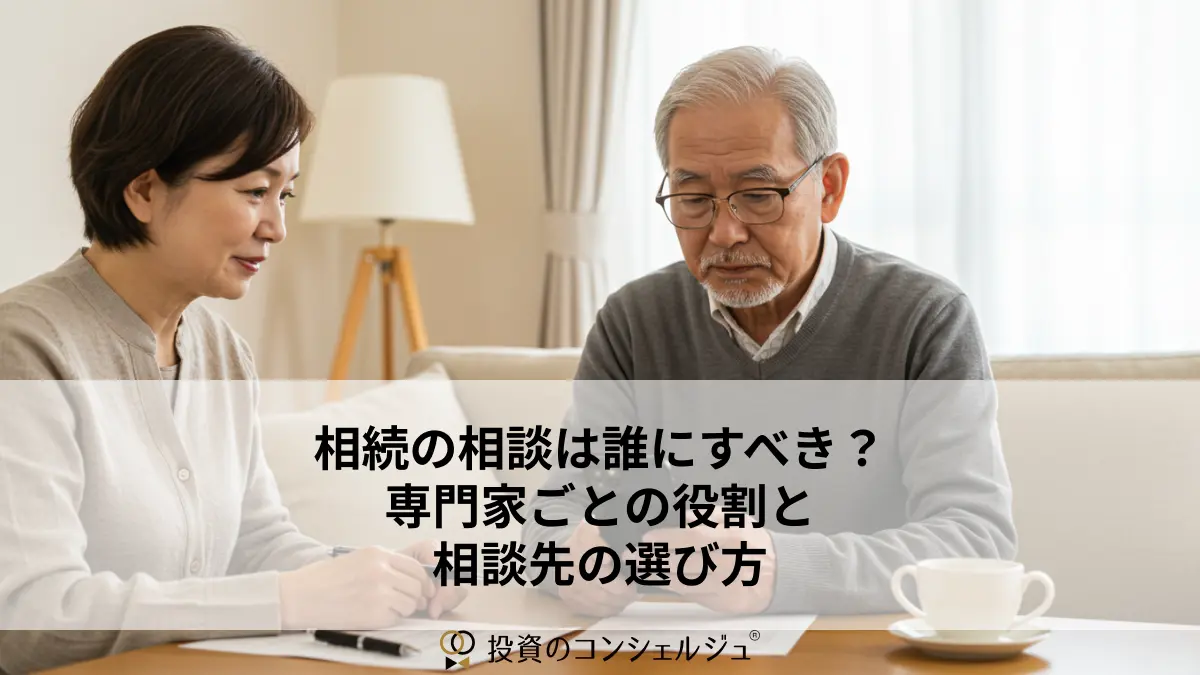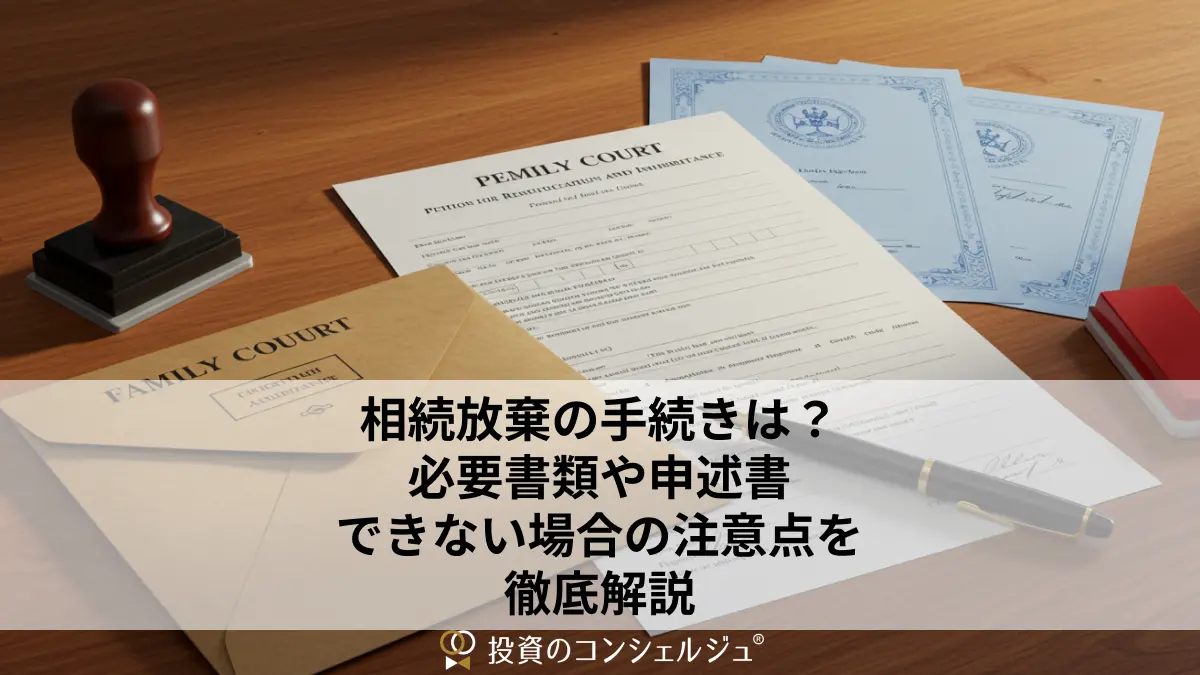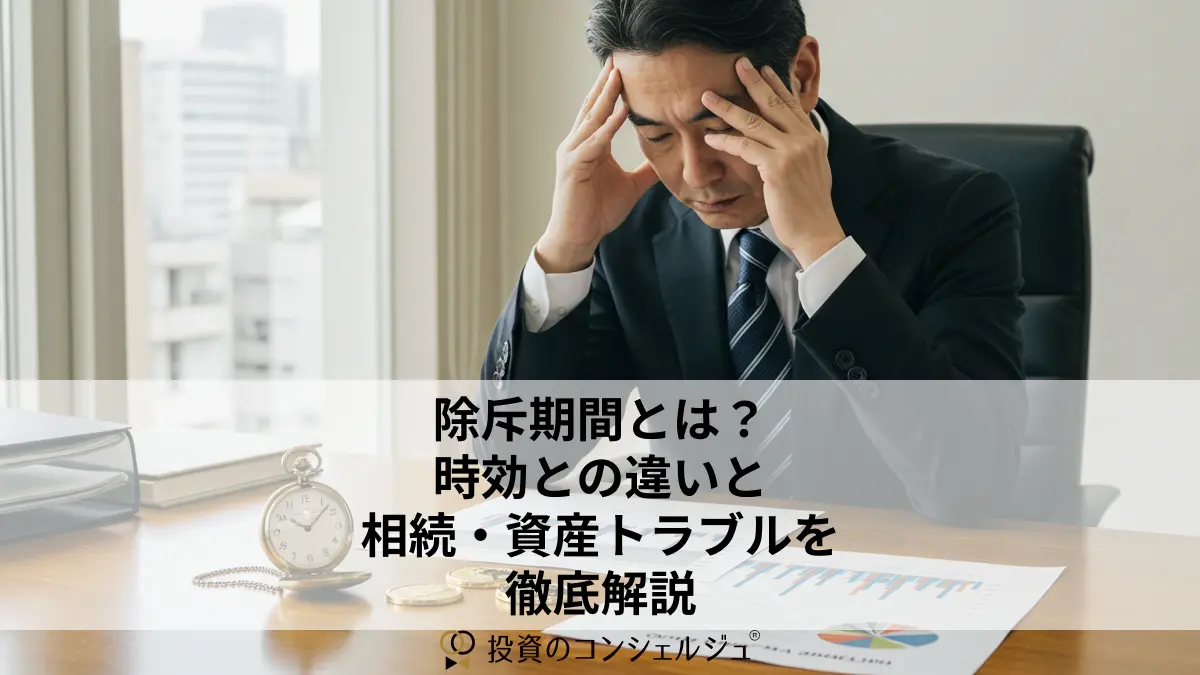相続における消滅時効の援用とは?仕組みや条件、メリット・デメリットを徹底解説
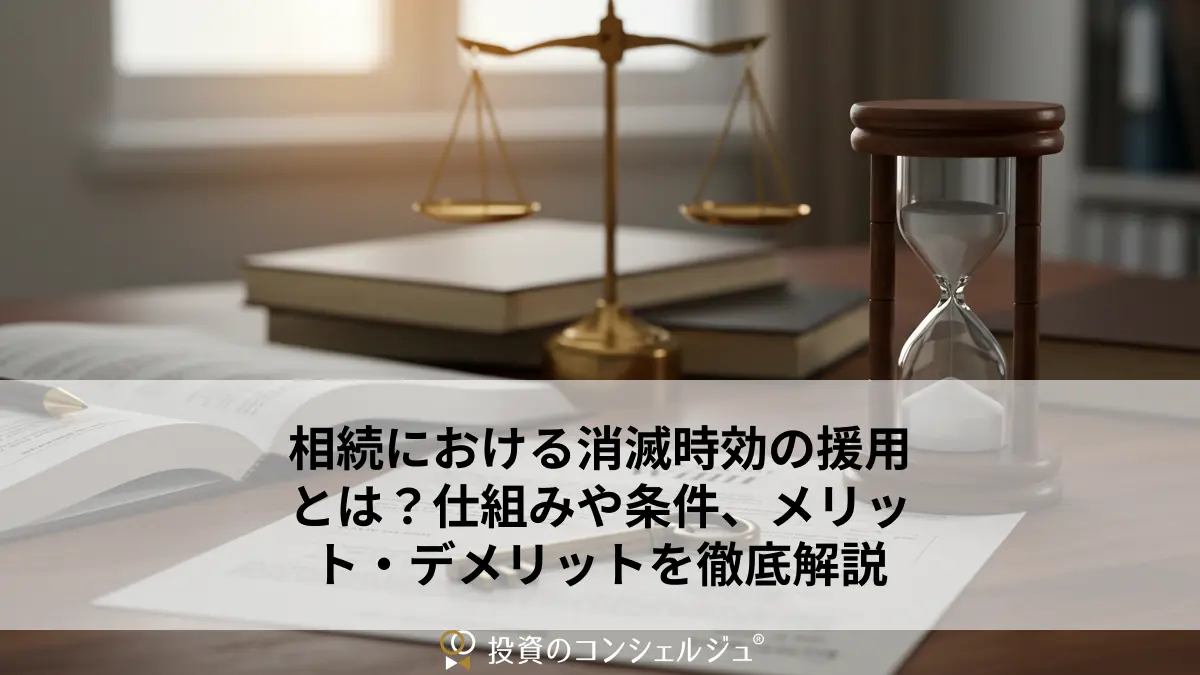
相続における消滅時効の援用とは?仕組みや条件、メリット・デメリットを徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.08.11
更新:
2025.09.24
「相続した借金は時効で消える」と耳にして、安心してしまう人がいます。しかし実際には、ただ時間が過ぎるのを待つだけで借金が自動的になくなるわけではありません。民法が定める「時効の援用」という正式な意思表示を行わない限り、金融機関や債権者からの請求が再開し、返済義務が復活するリスクもあります。
特に相続時には時効期間の引き継ぎや更新(リセット)要因など複雑な問題が絡み、安易な対応は危険です。本記事を読めば、相続した借金を時効で確実に消すための条件、手順、注意点が明確になり、リスクを最小化する判断軸が得られます。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、相続した借金を時効で確実に消すために必要な「時効の援用」の条件や手続きが明確になります。「時効援用」とは、時効が成立したことを明確に主張する法的な手続きであり、「ただ待つだけ」では借金は消えません。時効期間(原則5年)の計算方法や、時効が訴訟や一部返済で簡単にリセットされる仕組み、相続人特有の「6ヶ月完成猶予」などの複雑なルールについても詳しく解説。また援用する際のメリットやデメリット、相続放棄・限定承認との比較まで網羅しているため、財産を守りながら負債のリスクを回避するための具体的な判断材料が手に入ります。
時効の援用とは?「待つだけ」で借金が消えない理由
「時効の援用」と聞くと難しく感じるかもしれません。ここでは、援用がどのような制度で、なぜ「時効が過ぎるのを待つだけ」では借金がなくならないのか、その基本的な仕組みと法律上の理由を分かりやすく解説します。
援用とは「時効の完成」を主張する重要な意思表示
援用とは、法律上「自分に有利な事実を主張すること」を指し、特に時効(一定期間の経過で権利が消滅する制度)の完成を主張する場合に使われます。
この援用が大きく関わるのが、借金の返済義務などが時間の経過で消滅する「消滅時効」です。消滅時効を援用することで、法的に返済義務を免れることが可能になります。
時効を過ぎていても「援用」しない限り、借金の返済義務は残ったまま
時効期間が過ぎても、何もしなければ返済義務は消えません。その根拠は民法145条に定められています。
日本の民法第145条は「時効は当事者が援用しなければ、裁判所はそれによって裁判できない」と定めています。これは、たとえ法律で定められた期間が経過しても、本人が「時効を使います」と明確に主張しない限り、その効果が生じないことを意味します。
もし援用をしなければ、時効期間が過ぎても借金の返済義務は残ったままです。そのため、裁判になったとしても裁判所が自動的に時効を考慮することはありません。このように、援用は自らの権利を守るために不可欠な意思表示なのです。
特に相続の場面では、被相続人(亡くなった方)が残した借金や、逆に他人に貸していたお金の回収において、この援用が問題となる典型的なケースと言えます。
時効援用が成立するための2つの必須条件
時効の援用を成功させるには、法律で定められた2つの条件を満たす必要があります。ここでは「時効期間の満了」と「時効の更新(中断)がないこと」という、それぞれの条件の具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
条件1:時効期間が満了していること(借金は原則5年)
第一の条件は、法律で定められた時効期間が満了していることです。現行民法では、債権の消滅時効期間は原則として5年(一部の場合は最長10年)と定められています。
具体的には「権利を行使できると知ったときから5年」または「権利を行使できるときから10年」のいずれか早い方とされており、通常の借金であれば短い方の5年が適用されます。例えば銀行や貸金業者からの借入金は、最後の返済日(または契約上の返済期限)の翌日から5年間支払いがなければ時効成立の可能性があります。
個人間の貸し借りなどでは10年が適用される場合もありますが、2020年の民法改正以降に発生した債権については、原則5年と考えて差し支えありません。
時効と除斥期間の違いについては以下の記事で詳しく説明しています。
条件2:時効の進行をリセットする「更新(中断)」事由がないこと
第二の条件は、時効の進行を途中でリセットしてしまう「更新(中断)」事由が発生していないことです。たとえ期間が経過していても、特定の行為があると時効は振り出しに戻ってしまうため、注意が必要です。
2020年の民法改正で「中断」は「更新」と「完成猶予」に再編されましたが、時効の進行がゼロから再スタートするという基本的な考え方は同じです。時効期間中に、以下のような事由が発生すると時効は更新されます。
更新事由の例1:訴訟や差押えなどの「裁判上の請求」
債権者が裁判所に訴えを起こして請求してきた場合、時効はその時点で更新されます。単なる督促状や催告書だけでは更新されませんが、6ヶ月以内に正式な裁判手続きが取られると時効の更新事由となります。また、給与や財産の差押えといった強制執行も同様です。
更新事由の例2:一部返済などの「債務の承認」
債務者(借りている側)が債権の存在を認める行為をした場合も、時効は更新されます。具体的には、借金の一部でも返済したり「返済を待ってほしい」と伝えたりすると、その時点で時効期間はリセットされます。口頭の約束でも証拠が残れば承認とみなされる可能性があります。
このように、更新事由が一度でも発生すると、その時点から再び5年または10年が経過しなければ時効は完成しません。そのため、長期間返済も請求もないまま時効が自然に完成するのは稀であり、時効の完成を安易にあてにすることは非常にリスクが高いと言えます。
相続時の注意点:時効期間は引き継がれるが、6ヶ月の猶予期間がある
相続が発生した場合、時効の扱いはどうなるのでしょうか。期間がリセットされることはありませんが、相続人保護のための特別なルールが定められています。
相続そのものは、時効をリセットする更新事由にはなりません。例えば、被相続人が亡くなった時点で借金の最後の返済から3年が経過していた場合、相続人は残りの2年という時効期間をそのまま引き継ぎます。
しかし、民法160条により、相続の発生から6ヶ月間は時効が完成しない「完成猶予」の期間が設けられています。これは、相続人が状況を把握し対応を検討するための配慮ですが、猶予期間が過ぎれば再び時効の進行が始まるため、早めの対応が求められます。
相続における時効援用例|こんな時、どうすればいい?
相続と援用が深く関わる典型的なケースとして、被相続人の借金と被相続人の貸付金という、立場が逆の2つのケースを紹介します。
ケース1.借金の時効援用:亡父のカードローン督促状が届いた
被相続人にカードローンや消費者金融からの借入金があったケースです。親などが亡くなった後、突然届いた請求書で初めて借金の存在を知ることは少なくありません。
もし、最後の返済から5年以上が経過しているなど、長期間返済が滞っていた場合、その借金は消滅時効が成立している可能性があります。金融機関からの借入金の時効期間は、民法上原則5年とされているためです。
このような状況で、相続人が債権者に対して「時効を援用します」と通知すれば、法的に借金の支払いを拒むことができます。援用が認められると返済義務はなくなり、債権者も回収できなくなります。
親の借金の相続放棄する場合の注意点については以下Q&Aで説明しています。
ケース2.債権回収と逆援用:被相続人が貸したお金が返ってこない
被相続人が生前に誰かにお金を貸しており、その貸付金(債権)を相続するケースです。相続人は貸主の地位を引き継ぎ、借主に返済を請求できます。
しかし、その貸付金が長期間返済されないまま時効期間が経過していると、借主側から時効を援用される可能性があります。借主が「時効なので支払いません」と主張(援用)すると、その主張は法的に有効となります。
その結果、相続人は期待していた貸付金を回収できなくなってしまいます。
このように、相続では借金の返済義務をなくすために援用するケースもあれば、逆に貸付金の回収を相手に援用されて阻まれるケースもあります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産や債権の状況もしっかりと確認することが重要です。
相続人が時効を援用する4ステップ
それでは、消滅時効が成立した借金について、実際に「時効援用」をするための手続き手順を具体的に見ていきましょう。基本的な流れは以下のとおりです。
Step1:時効が成立しているか?を最終確認する
まず、相続した債務について、最終返済日や請求の有無を確認し、時効期間が満了しているか計算します。借金の契約書類や取引履歴、債権者からの通知などを調べ、「最後の返済から5年以上経っているか」「その間に裁判を起こされていないか」といった点をチェックします。
次に、専門家の助言も得ながら時効成立の確実性を高めます。時効期間ギリギリの場合や、すでに裁判で判決が出ている可能性も考えられます。「一度でも時効の更新事由があれば成立しない」ため、不安な場合は司法書士や弁護士に相談し、手続きを進めるのが賢明です。
Step2:「時効援用通知書」を作成する
時効の成立を確信したら、債権者宛に「時効援用通知書」を作成します。書式に決まりはありませんが、以下の事項は必ず盛り込みましょう。
- 相続人であることの明示:自分が債務者である被相続人の相続人である旨(例:「被相続人〇〇の子として相続人になりました」)。
- 時効が成立している事実:借金の最終弁済日から所定の年数(5年など)が経過し、消滅時効が完成していること。
- 時効を援用する意思表示:「時効を援用します」という明確な意思表示は、通知書の核となる部分ですので、絶対に記載を忘れないでください。
- 債権の特定情報:債務者氏名、債権者名、契約番号や金額など。
- その他:通知日付、自署押印など。
Step3:証拠が残る「内容証明郵便」で送付する
作成した時効援用通知書は、必ず内容証明郵便(配達証明付き)で発送します。内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。これにより、債権者から「通知は受け取っていない」と主張されるリスクを防ぎ、援用の意思表示をした強力な証拠を残すことができます。
Step4:送付後の債権者の反応を確認し、対応する
通知書が相手に届いた後、債権者の反応を確認します。多くの場合、時効援用を受け入れる旨の連絡が来るか、何も反応がありません。万一、時効の成立を認めず支払いを求めてくる場合でも、適切に援用ができていれば法的な支払義務はありません。不安な場合は専門家に対応を相談しましょう。重要なのは、援用の意思表示を証拠として記録に残すことです。
相続に関する専門家選びは、こちらの記事も参考にしてみてください。
時効援用のメリット・デメリットを比較|信用情報(ブラックリスト)への影響は?
時効を援用することには、相続人にとってさまざまなメリットとデメリットがあります。ここでは経済的・心理的な両側面から、それぞれを具体的に見ていきましょう。
5つのメリット:借金返済を免れ、プラスの遺産(不動産・預金)は相続できる
時効援用には、主に5つのメリットが考えられます。相続放棄と比較しながら、その利点を確認しましょう。
相続放棄については以下の記事で詳しく解説しています。
メリット1:借金の返済義務が法的に消滅する
最大のメリットは、法律に則って借金の返済をしなくて済む点です。時効援用が成功すれば、相続した債務は法的に消滅します。これにより、返済の経済的負担から解放され、手元の財産を守ることができます。
メリット2:プラスの遺産はそのまま相続できる
時効援用は、借金のためにプラスの財産まで手放す「相続放棄」とは異なります。負債だけを事実上消滅させ、現金や不動産といったプラスの遺産はそのまま相続できる点が大きな利点です。
メリット3:相続放棄のような3ヶ月の期限がない
相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期限がありますが、時効援用にはそのような期限はありません。条件さえ満たせば、相続発生から何年後でも手続きが可能です。この柔軟性は、借金の発見が遅れた場合に特に有効です。
相続放棄の3ヶ月ルールについては以下Q&Aで説明しています。
メリット4:他の相続人や親族に迷惑がかからない
相続放棄をすると、放棄した負債の返済義務が次順位の相続人(他の親族など)に移ってしまいます。一方、時効援用で借金を解決すれば、自分一代で問題を完結させることができ、他の親族に負担をかける心配がありません。
メリット5:信用情報(ブラックリスト)が回復する場合がある
「時効援用をすると信用情報に傷がつくのでは?」と心配する方もいますが、新たなペナルティはありません。むしろ、時効成立で債務契約が終了するため、信用情報機関の事故情報(延滞履歴)が抹消される場合があります。結果として、信用状態が改善される可能性も期待できます。
5つのデメリット:失敗時のリスクと「寝た子を起こす」可能性を理解する
一方で、時効援用には注意すべきデメリットも存在します。安易に判断せず、リスクもしっかりと把握しておきましょう。
デメリット1:手続きに失敗すると返済義務が確定する
時効期間の計算ミスや時効更新事由の見落としなど、手続きに不備があると援用は失敗します。失敗した場合、相続人はその債務の支払義務を負うことになり、後から相続放棄をすることもできなくなるという深刻な状況に陥るリスクがあります。
デメリット2:時効が未完成だと「寝た子を起こす」ことになる
もし時効が完成していないのに援用通知を送ると、債権者に借金の存在を知らせることになり、本格的な請求や訴訟を誘発する可能性があります。いわゆる「寝た子を起こす」リスクです。
デメリット3:債権者が複数いる場合は個別に対応が必要
負債が複数ある場合、それぞれの債権者に対して個別に時効援用の手続きが必要です。相続放棄のように一度の手続きで全ての負債から解放されるわけではないため、債権者が多いと手間がかかり、見落としのリスクも高まります。
デメリット4:道義的な葛藤を覚える可能性がある
法律で認められた正当な権利行使ですが、「借金を返済しない」という選択に心理的な抵抗を感じる方もいます。特に故人がお世話になった相手からの借金などの場合、道義的な面で悩むかもしれません。
デメリット5:専門家に依頼すると費用がかかる
自身で手続きを行えば費用は郵送代程度で済みますが、手続きの確実性を期して専門家に依頼する場合は報酬が発生します。ただし、専門家は債権者との窓口にもなってくれるため、費用とメリットを比較して検討することが大切です。
相続対策を進めたい方は、生前に推定相続人を調査しておきましょう。詳細は、こちらの記事で解説しています。
時効の援用ができない・失敗するケースと注意点
時効の援用は強力な手段ですが、常に最善策とは限りません。援用が適さないケースや、他の選択肢である「相続放棄」「限定承認」との違いを知ることが重要です。ここでは、3つの手続きを比較し、状況に応じた最適な選び方を解説します。
選択肢1:相続放棄―資産も負債もすべて手放す
相続放棄とは、プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)のすべてを相続する権利を手放す手続きです。家庭裁判所への申述により、初めから相続人ではなかったことになります。
この手続きのメリットは、どんなに多額の負債があっても一切の返済義務を免れ、後から未知の借金が見つかっても影響を受けない点です。また、債権者が多くても一度に解決できます。一方で、価値のあるプラスの財産もすべて手放さなければならず、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期限があります。さらに、放棄した負債は次順位の相続人に移ってしまう点にも注意が必要です。
選択肢2:限定承認―プラスの財産の範囲で返済する
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金などを返済する条件付きで相続する方法です。「相続財産を超える借金は支払わない」と意思表示する手続きと言えます。
主なメリットは、借金を返済してもプラスの財産が残る場合にそれを確保できる点や、手放したくない特定の財産がある場合に有効なことです。しかし、相続放棄と同じく「3ヶ月以内」の期限があり、相続人全員が共同で手続きを行う必要があるため、一人でも反対すると利用できません。また、手続きが非常に複雑で、専門家のサポートがほぼ必須となる点がデメリットです。
限定承認や単純承認の仕組みについては、こちらの記事で解説しています。あわせて参考にしてみてください。
時効援用・相続放棄・限定承認の選び方
では、これら3つの手続きをどのように使い分ければよいのでしょうか。
まず、時効援用が適しているのは、相続した借金の大部分が時効を迎えており、他に大きな負債がなくプラスの財産を守りたい場合や、相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合です。
次に、相続放棄を選ぶべきなのは、明らかに負債がプラスの財産を上回っている場合や、時効になっていない借金が多数ある、または負債の全体像が不明な場合です。手続きを迅速かつ確実に終わらせたい時にも向いています。
最後に、限定承認は、負債はあるものの自宅などどうしても手放したくない財産があり、かつプラスの財産が負債を上回る可能性がある場合に検討すべき選択肢となります。
なお相続の単純承認、限定承認、相続放棄の違いについては以下Q&Aで説明しています。
この記事のまとめ
相続した借金を時効で消すには、「時効の援用」という法的な意思表示が不可欠です。援用の成功には、時効期間(原則5年)の経過と、時効がリセットされる「更新(訴訟や一部返済など)」がないことを慎重に確認する必要があります。援用に成功すれば借金の返済義務が消え、プラスの遺産を守ることも可能ですが、時効成立前に援用すると、逆に債権者からの強い請求を誘発するリスクがあります。相続放棄や限定承認など、他の選択肢とも比較し、プラスの財産の規模、債務総額、手続きの手間、信用情報への影響を総合的に考慮して最適な方法を選びましょう。必要に応じて専門家に相談するのも選択肢です。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
時効の援用
時効の援用とは、一定期間が経過したことで法律上の権利や義務が消滅する時効制度を、自らの利益のために正式に主張することをいいます。たとえば借金の返済義務は、法律で定められた期間が過ぎれば時効によって消滅する可能性がありますが、その効力は自動的には発生せず、本人が「時効を援用します」と意思表示をすることで初めて成立します。資産運用においては、直接的な投資商品の仕組みというよりも、金融取引や債務整理、相続などに関わる法的リスク管理の一環として理解しておくことが重要です。
消滅時効
消滅時効とは、一定の期間が経過すると、法律上の権利が行使できなくなる制度のことです。たとえば、お金を貸した場合、一定の年数が過ぎてしまうと、原則として裁判などで返済を請求する権利が消滅します。これは、時間の経過とともに事実関係が不明確になることを避け、社会的な安定と公平を図るために設けられている制度です。 民法では、原則として権利を行使できることを知ったときから5年(または権利が発生してから10年)という期間が定められています。資産運用や金融の分野でも、貸付債権、未払いの配当金、保険金請求などにおいて消滅時効のルールが適用され、時効を過ぎると本来受け取れるはずだった資産を失う可能性があります。したがって、請求や権利行使のタイミングには注意が必要であり、時効制度の理解は金融実務において極めて重要です。
民法第145条
民法145条は、日本の民法において時効の完成猶予や更新に関する基本的な規定を定めた条文です。この条文では、裁判上の請求や差押えなどの一定の行為が行われた場合に、時効の完成が猶予されたり、更新されることが規定されています。つまり、権利を守るために法的手段を取ったとき、時効がそのまま進行して権利が消えてしまうのを防ぐ役割を持っています。資産運用や金融契約においては、債権の回収や契約上の権利保全を行う際、この条文の理解が時効管理の基本となります。
時効期間
時効期間とは、ある権利を行使できる、または義務を履行させられる法的な有効期間のことです。この期間が過ぎると、原則としてその権利は消滅したり、義務を免れることができます。 例えば、貸したお金の返済請求には一定の時効期間があり、それを過ぎると債務者は「時効の援用」を主張することで支払い義務を免れることができます。時効期間は権利や義務の種類によって異なり、数年から十年以上に及ぶ場合もあります。資産運用や金融取引では、契約や債権管理の際にこの期間を正確に把握することが、権利を守るうえで非常に重要です。
時効の更新
時効の更新とは、進行中の時効期間をいったん終わらせ、新たにゼロから時効期間を数え直すことをいいます。例えば、貸したお金の返済を長期間受けていない場合でも、債務者が返済の一部を支払ったり、債務を認める発言をしたり、債権者が裁判で請求を行った場合などには、時効が更新されます。 これにより、本来であれば間もなく権利が消滅するはずだったものが、新たな期間分だけ延び、権利行使の機会を確保できます。資産運用や金融取引では、貸付金や契約上の権利を守るために、時効の更新をうまく活用することが重要です。
完成猶予
完成猶予とは、法律で定められた時効の完成を一時的に止める制度のことです。本来、時効は一定期間が経過すると権利や義務が消滅したり発生したりしますが、特定の事情が生じると、その期間のカウントが中断される場合があります。 例えば、債権者が債務者に請求を行ったり、裁判を起こしたりした場合、時効の完成が一定期間猶予されます。資産運用や金融取引においては、貸付金の回収や契約上の権利保全のために、この制度を理解しておくことで、思わぬ権利消滅を防ぐことができます。
債務の承認
債務の承認とは、借金やその他の支払い義務が自分にあることを、債務者本人が認める行為のことです。これは口頭での発言や書面での確認だけでなく、一部の返済や利息の支払いなど、行動によって示す場合も含まれます。 債務の承認が行われると、進行中だった時効が更新され、そこから新たに時効期間が数え直されます。資産運用や金融取引の場面では、貸付金や契約上の請求権を維持するために、この制度を理解し活用することで、権利消滅のリスクを回避できます。
裁判上の請求
裁判上の請求とは、裁判所を通じて正式に相手方へ権利の履行を求める手続きのことです。例えば、貸したお金が返ってこない場合に、債権者が裁判所に訴えを起こして返済を求める行為がこれにあたります。この手続きが行われると、進行中の時効は更新され、新たにゼロからカウントし直されます。また、時効完成間近の権利を守る有効な手段としても利用されます。資産運用の分野では、貸付金や契約上の権利を確実に守るために、裁判上の請求が時効管理の重要な手段となります。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
時効援用通知書
時効援用通知書とは、権利や義務が時効によって消滅したことを正式に主張するために、相手方へ送る書面のことです。例えば、借金の返済義務が法律で定められた期間を過ぎている場合、この通知書を送付することで「もう支払い義務はありません」と法的に意思表示します。 この書面は、後々のトラブルを防ぎ、証拠として残すために内容証明郵便で送るのが一般的です。資産運用や金融の場面では、債務整理や相続に関連して使われることがあり、法的権利を守るための重要な手段となります。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どんな内容の文書を送ったのかを、日本郵便が証明してくれる特別な郵便のことです。たとえば、お金の返済を正式に請求したり、契約の解除を通知したりする場合に使われます。普通の手紙とは違い、郵便局が内容を記録・保管し、あとから「確かにこの文書を送りました」と証明してくれるため、トラブルが起きたときに自分の主張を裏付ける証拠として使えます。資産運用や相続の場面でも、貸付金の返還請求や相続放棄の意思表示など、法的に重要なやりとりを確実に記録に残したい場合に活用されることがあります。慎重に相手に伝えたい意思があるときに、非常に役立つ手段です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
限定承認
限定承認とは、相続人が引き継ぐ財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を支払うことを条件に、相続を受ける方法のことです。つまり、相続によって得られる資産が借金を上回っている場合にはその差額を受け取ることができますが、もし借金が多くても、自分の財産を使ってまで返済する必要はありません。 この方法を使えば、相続することで損をするリスクを減らすことができます。ただし、限定承認を行うには、相続の開始を知ってから原則として3か月以内に、他の相続人全員と一緒に家庭裁判所に申立てをする必要があるため、手続きがやや複雑です。
信用情報
信用情報とは、個人や企業の過去から現在までの借入や返済、クレジットカード利用履歴、ローン契約状況などを記録した情報のことです。これらは信用情報機関という専門の機関に集められ、金融機関は新たな融資やクレジット契約の審査を行う際に参照します。 たとえば住宅ローンを申し込むとき、過去の延滞や借入残高などがチェックされ、返済能力の判断材料となります。資産運用を行ううえでも、信用情報が良好であれば低い金利で融資を受けられる可能性が高まり、投資計画の選択肢が広がります。逆に信用情報が傷つくと、資金調達が難しくなり運用戦略にも影響します。