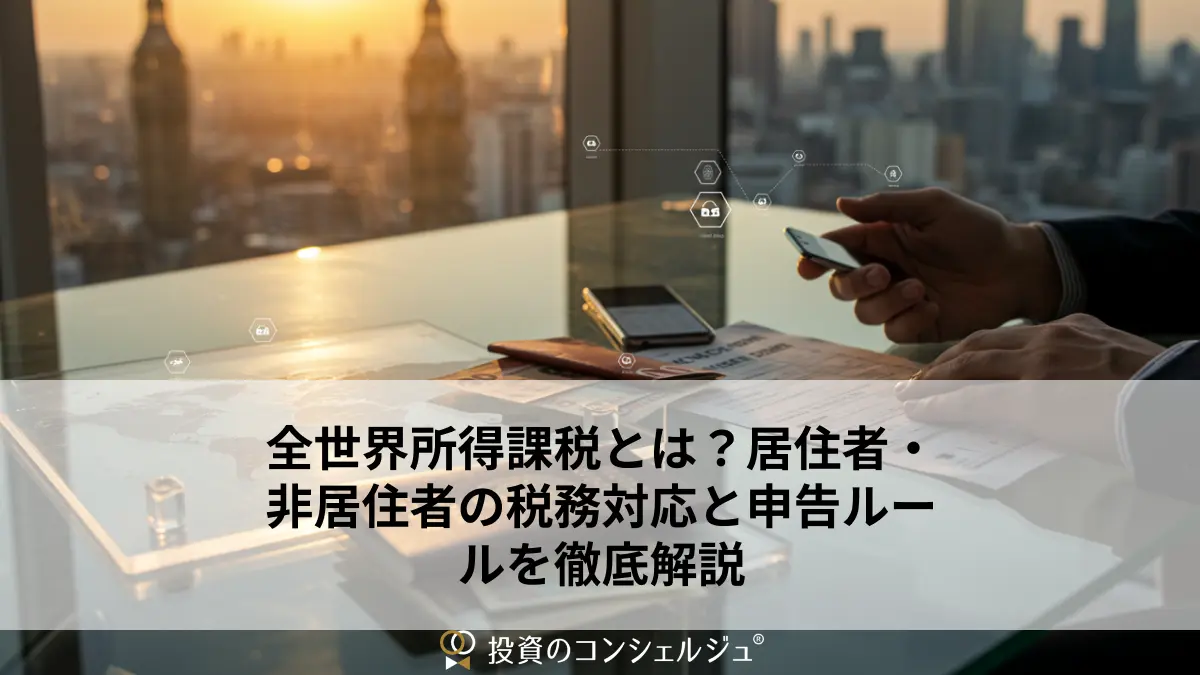高配当ETFのVYMはおすすめしないってなぜ?4つの弱点やデメリット・配当金や利回りを徹底解説!
難易度:
執筆者:
公開:
2025.06.26
更新:
2025.08.27
VYMは「安定配当・低コスト・広い分散」といった強みで人気の米国高配当ETFですが、一方で「おすすめしない」と言われる理由も確かに存在します。
配当利回りは中程度で物足りなく感じやすく、金融セクター偏重や景気敏感性、さらに為替リスクや二重課税といった課題も避けられません。魅力ばかりに注目すると投資目的とのミスマッチを招きかねないのです。
本記事では、VYMの強みと弱点を整理し、他のETFとの比較を通じて「なぜおすすめされないことがあるのか」、そしてどんな投資家に適しているのかを判断できる軸を提示します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むと、VYMが「おすすめしない」と言われる理由と、その背景を整理できます。VYMは低コストで分散性が高く安定配当を狙える一方、配当利回りは中程度で金融セクター偏重や為替・二重課税といった弱点も抱えています。
SPYD・HDV・VIG・SCHDとの比較を通じて、利回り・増配・安定性などの評価軸が明確になり、自分の投資目的やリスク許容度にVYMが合うのかを判断できる知識が得られます。
VYMとは?米国高配当ETFの基本と3つの強み
VYMは、Vanguard社が提供する米国高配当株式ETF(正式名称:Vanguard High Dividend Yield ETF)です。2006年11月に設定され、米国株式市場の中から「平均以上の配当を出す大型株」へ幅広く投資します。「FTSEハイディビデンド・イールド指数」をベンチマークとし、不動産(REIT)を除外した約500銘柄で構成。直近の分配利回りは約2.6~3.0%、経費率はわずか0.06%と非常に低コストです。分配金は年4回支払われ、楽天証券やSBI証券など主要ネット証券で、新NISAの成長投資枠でも購入できます。
VYMが多くの投資家から支持される背景には、以下の3つの強みがあります。
強み1. 運用方針:FTSE High Dividend指数で大型バリューに分散
VYMは、予想配当利回りが市場平均を上回る米国大型株(REITを除く)で構成される「FTSEハイディビデンド・イールド指数」に連動します。約500銘柄に幅広く分散しているのが最大の特徴で、上位10銘柄の比率も低く、特定銘柄への集中リスクを抑えています。
セクター構成は金融が約23%と最も高いものの、産業、ヘルスケア、生活必需品など他の主要セクターにも10%前後で分散されています。市場平均(S&P500)と比べても、金融の比率が高く、情報技術の比率が低いため、景気後退期には注意が必要ですが、ディフェンシブセクターも多く含むため下落相場での底堅さも期待できます。
総じて、高配当ETFの中では癖が少なく、長期保有しやすいポートフォリオです。
ETFについては、以下の記事で詳しく解説しています。
強み2. 経費率0.06%:圧倒的な低コスト
VYMの経費率は年0.06%と、競合するSPYD(0.07%)やHDV(0.08%)より低く、業界最安水準です。長期投資ではコストの差がリターンに直接影響するため、この低コストは大きな利点です。純資産総額も約509億ドル(約7.2兆円)と巨大で流動性も高いため、安心して取引できます。
強み3. 四半期分配と増配実績:安定した配当の積み上げ
VYMは年4回(3月・6月・9月・12月)に分配金を支払い、その額は長期的に増加傾向にあります。金融危機後、2010年から13年連続で増配を達成し、年間分配金は14年で2倍以上になりました。近年の平均増配率も年5~7%と安定しており、コロナショック時にも減配しなかった実績は、インカム投資家にとって大きな安心材料です。
VYMはおすすめしないと言われる4つの弱点
多くの魅力を持つVYMですが、「おすすめしない」という声があるのも事実です。これはVYM自体の欠陥というより、他のETFとの比較や投資目的とのミスマッチが原因であることがほとんどです。
ここでは代表的な4つの弱点を率直に検証します。これらを正しく理解することが、ご自身の投資方針にVYMが合うかどうかの判断材料になります。
弱点① 配当利回りが“中間レンジ”
VYMの分配利回りは約2.6~3.0%台で、SPYD(4~5%台)やHDV(3.5%以上)といった他の高配当ETFと比較すると見劣りします。「とにかく高い利回りが欲しい」という投資家には物足りなく映る可能性があります。
これは、VYMが極端な高利回り銘柄に集中せず、ポートフォリオの安定性とのバランスを取った設計になっているためです。
弱点② 増配ペースがVIGやSCHDに劣る
VYMは安定増配の実績がありますが、近年の増配ペースは年5%前後に落ち着いており、過去よりは鈍化傾向にあります。
特に、SCHD(シュワブ米国配当株ETF)が記録する年平均10%超のような高い配当成長率と比較すると、将来のインカム(配当収入)の伸びしろという点で見劣りします。
弱点③ 金融セクター偏重と景気敏感性
VYMは構成比率の20%超を金融セクターが占めており、景気後退局面では株価や配当が打撃を受ける可能性があります。
また、GAFAに代表されるような高成長ハイテク株をほとんど含まないため、ハイテク株が市場を牽引するような強気相場では、S&P500などの市場平均リターンに後れを取りがちです。
弱点④ 為替リスクと二重課税
日本の投資家にとって、VYMは海外ETFならではの2つの課題があります。
1.為替リスク:ドル建て資産のため、円高が進むと円換算でのリターンが目減りします。
2.二重課税:分配金には、まず米国で10%の源泉税が課されます。NISA口座を利用すれば日本国内の約20%の課税は非課税になりますが、この米国源泉税は還付されません。そのため、額面の利回りよりも手取り額は低くなります。
海外ETF配当の二重課税を防ぐにはこちらのQ&Aもご参照ください。
為替リスクの影響についてはこちらのQ&Aをご参照ください。
デメリットを踏まえてVYMを活用できる3つのシナリオ
VYMの弱点を理解した上で適切に位置付ければ、VYMは資産運用の心強い武器となります。ここでは、具体的な3つの活用シナリオを提案します。
シナリオ① コア資産として配当と値上がり益を両取りする
VYMをポートフォリオの「コア(中核)」に据え、受け取った配当を再投資することで、「配当+値上がり益」による複利効果を狙う戦略です。
VYMは高配当ETFの中では値動きが比較的安定しており、長期のトータルリターンも良好です。配当を再投資し続けることで、将来の配当額そのものを増やしながら、着実な資産成長を目指せます。
シナリオ② S&P500/オルカンと組み合わせるコア・サテライト戦略
S&P500や全世界株式(オルカン)といった市場全体に連動するインデックスファンドを「コア(主軸)」とし、VYMを「サテライト(衛星)」として組み合わせる戦略です。
狙いは、市場全体の成長性を享受しつつ、VYMでポートフォリオ全体の配当利回りを底上げし、下落相場でのクッション効果(下値抵抗力)を得ます。
期待される効果は、「攻め(S&P500等の成長性)」と「守り(VYMの安定性・インカム)」のバランスが取れた、より強固なポートフォリオを構築できます。
シナリオ③ NISA非課税枠で退職後のインカム源を確保する
新NISAの非課税メリットを最大限に活用し、VYMからの分配金を老後の生活費にあてる、インカム重視の戦略です。
このシナリオのメリットは、NISA口座なら国内課税(約20%)がかからず、より多くの分配金を手元に残せます。元本を取り崩すことなく、「配当金で生活を補う」という理想的な形を実現しやすくなります。
例えば、仮に1,000万円分のVYMをNISA口座で保有した場合、年間で約27万円(税引後利回り2.7%で計算)の非課税収入が期待でき、年金の心強い上乗せになります。
新NISAでETFを選ぶコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。
米国高配当ETF比較:VYMとSPYD・HDV・VIG・SCHDどっちを選ぶべき?
高配当ETFを選ぶ上では、「いま受け取れる配当(利回り)」、「将来の配当成長(増配)」、そして「下落相場での粘り(安定性)」という3点が大切な軸となります。
ここでは、VYMを基準として、SPYD、HDV、VIG、SCHDを個別に比較します。各ETFの設計思想や採用指数、最新の利回り、経費、安定性を示す各種指標を整理し説明します。
主要ETFの比較表
| ETF | 特徴 | 配当利回り | 増配トレンド | 安定性(暴落耐性) |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 分散型のバランス重視 | 中(2.9〜3.1%) | 安定増配(2〜4%) | 高い(-8〜10%) |
| SPYD | 利回り特化・リスク高 | 高い(4.3%) | 横ばい・不安定 | 低い(-15〜18%) |
| HDV | 財務健全性重視の守備型 | やや高(3.4%) | 比較的安定(2〜4%) | 高い(-8〜10%) |
| VIG | 増配重視の成長型 | 低め(1.8〜2.0%) | 高い(10〜12%) | 普通(-10〜12%) |
| SCHD | 利回り・成長・安定の「三拍子」型 | 高い(3.8%) | 高め(約6%) | 比較的高い(-10〜12%) |
安定配当のVYMと高利回り特化のSPYDの比較ポイント
両者の最初の違いは、VYMが「広く分散し不動産投資信託(REIT)を除外する」のに対し、SPYDは「S&P500の中から配当利回りが高い上位80銘柄に均等な比率で投資する」という設計にあります。
VYMはFTSE High Dividend Yield指数に連動し、セクターの偏りを抑えつつ、大型の配当株へ幅広く投資します。一方、SPYDは指数の特性上、不動産や公益事業の比率が高くなりやすく、金利や景気の動向に影響を受けやすいポートフォリオになる傾向があります。
配当利回りの違い:中配当で安定したVYMと高配当で景気に左右されやすいSPYD
VYMの直近30日SEC利回りは2.57%(2025年7月31日)と中程度の水準で、分散性の高さも相まって持続性を重視した設計です。
対するSPYDは4.69%(2025年6月30日)と、現時点で受け取れる金額は大きいものの、その利回り水準は景気や金利の変動で振れやすい特性を持っています。利回りは常に市況により変動します。
暴落耐性の違い:分散に強みのあるVYMと、セクター偏重で下落幅が大きくなりやすいSPYD
VYMは500を超える銘柄を保有することで、特定の企業やセクターが不調なときのリスクを和らげます。また、REITを含まない指数設計は、金利が上昇する局面での価格変動を緩和しやすい構造です。
一方でSPYDは、構成する全銘柄に均等に投資するため、不動産が23%、公益事業が18%といった金利の動きに敏感なセクターへの比重が高く、相場の下落時には値下がり幅が大きくなる可能性に注意が必要です。
投資家タイプ:総合バランスのVYM、分配金の大きさを優先するならSPYD
将来を見据えつつ安定した配当を積み上げたい長期投資家にはVYMが適しています。一方で、「毎年のインカム額をできるだけ大きくしたい」という明確な目的がある場合にはSPYDが選択肢になるでしょう。
ただし後者は、利回りが高い分、市場の状況に価格が左右されやすいため、資産全体での分散や現金管理と組み合わせて活用することが現実的です。
分散型のVYMと守備型のHDVの比較ポイント
VYMは市場平均以上の配当を狙う大型株に幅広く投資し、約580銘柄という厚い分散によって安定性を確保します。
対照的にHDVは、モーニングスターの配当フォーカス指数を採用し、「財務健全性」といった品質基準をクリアした約75銘柄に絞り込む、守りを重視した手法です。
この設計思想の違いが、利回りの水準や値動きの大きさの差として表れています。
利回りと増配傾向の違い:安定増配のVYMと、やや高利回りで品質重視のHDV
VYMの直近30日SEC利回りは2.57%(2025年7月31日)です。一方、HDVは3.33%(2025年6月30日)とやや高めで、指数の品質審査により配当の持続可能性に重点を置いています。
増配率は年や市場の状況で変動しますが、VYMは広い分散で、HDVは銘柄選別で、それぞれ配当の安定を追求する点が異なります。
下落局面での違い:広い分散のVYMと、低ベータ・低ボラティリティを志向するHDV
VYMは保有銘柄数が多いため、個別企業の問題が全体に与える影響を軽減します。
HDVの特長は、過去3年のベータ値が0.64、標準偏差が14.16%と、市場平均(S&P500)に比べて値動きが抑えられてきた点です。
品質を重視するがゆえに上昇相場では物足りなさを感じる場面もあり得ますが、下落局面に強い点を評価するなら有力な選択肢です。
投資家タイプ:幅広い市場配当を取り込みたいならVYM、守備力を厚くしたいならHDV
配当と分散をバランス良く取り入れたい場合はVYMが使いやすく、景気減速や金利変動といった局面での粘り強さを重視するならHDVが適しています。
HDVは銘柄数が少ないものの、品質を重視した採用ルールが値動きのブレを抑える設計になっており、ポートフォリオ全体の守りを固めるのに向いています。
安定配当のVYMと増配成長に強いVIGの比較ポイント
VIGは「連続増配」を重視する指数(S&P U.S. Dividend Growers)を採用し、少なくとも10年以上連続で配当を増やしている企業群に投資します。現時点での利回りは控えめでも、長期的な配当の成長力に期待するのがその設計思想です。これは、現在の受取配当額と分散を重視するVYMとは異なる考え方に基づいています。
配当と増配率の違い:いまの受け取り重視のVYMと、将来の伸びを狙うVIG
VYMの直近30日SEC利回りは2.57%(2025年7月31日)という中程度の水準です。
対するVIGは1.65%(2025年7月31日)と低めですが、10年以上の連続増配という厳しい条件を満たす銘柄で構成されており、将来的に受け取る配当が増えていくことを目指します。
この目的の違いが、現在の配当水準の差に表れています。
リターンの源泉の違い:インカム中心のVYMと、配当成長が牽引するVIG
VYMは、受け取った配当を再投資することで資産を増やしていく複利効果が主な原動力となります。
一方VIGは、連続増配という企業の優れた収益基盤に投資し、時間の経過とともに配当額そのものが増えることを期待する設計です。
同じ配当系ETFでも、「現在の受け取り」と「将来の伸び」で担う役割が全く異なります。
投資家タイプ:安定キャッシュフローのVYM、配当成長の長距離走を狙うならVIG
安定的な収入源として配当を重視するならVYMが、長期的な視点で配当の成長を原動力とした総リターンを狙うならVIGが選びやすいでしょう。VIGは短期的に受け取る配当は控えめですが、その増配傾向が総合的な資産成長に寄与しやすい点が核心です。
バランス型のVYMと三要素が揃ったSCHDの比較ポイント
SCHDは配当の「質」にこだわるDow Jones U.S. Dividend 100指数を採用しています。10年以上の配当実績や、ROE(自己資本利益率)、フリーキャッシュフローと負債の比率といった品質指標を総合的に評価して構成銘柄を決めるため、利回り、増配、安定性という三つの要素をバランスさせた設計です。
VYMは、より広く市場の高配当銘柄を捉える普遍的なアプローチと言えます。
利回りと増配の違い:VYMは中配当、SCHDはやや高めで質に裏打ち
VYMは2.57%(2025年7月31日)の中配当水準です。一方SCHDは、30日SEC利回りが3.74%(2025年8月25日)、過去12カ月分配利回りが3.87%(2025年7月31日)と、受け取れる配当水準は相対的に厚めです。
品質基準を組み込むことで、単に利回りだけを追求しない点が設計上の強みです。
安定性の違い:VYMは広い分散、SCHDは品質スクリーニングと市場連動性の両立
VYMの強みは、広い分散によって個別銘柄が不調な際のリスクを抑える点にあります。
SCHDは、過去3年のベータ値が1.00、標準偏差が15.12%と、市場全体とほぼ同じような値動きをする中で、質の高い銘柄を選び出すという特徴を加えています。これにより、上昇相場に大きく遅れることなく、下落局面では銘柄の質の高さが支えとなるような、中庸の安定性を目指します。
投資家タイプ:広く堅実な受け皿のVYM、三要素の均衡を求めるならSCHD
「配当、増配、安定」という三つの要素を一つのETFで実現したい投資家にはSCHDが合っています。
まずは王道である分散投資と低コストで配当を得たいと考えるなら、VYMが軸にしやすい選択です。
この二つは補完的な関係も築きやすく、組み合わせて保有することも現実的な戦略です。
VYMと各ETFに共通する実用性の比較
どのETFも、経費率が非常に低く、資産規模が大きく、年4回の分配金支払いがあるという点で共通しており、長期投資の土台に据えやすい設計です。コストの差はわずかでも、10年、20年という期間で見ると複利効果に影響してきます。利回りを比較する際は、指標の定義が異なる場合があるため、同じ種類の指標で比べることが実務上のコツです。
経費率の実態:0.05〜0.08%の最安水準で長期コストに効く
VYM 0.06%、VIG 0.05%、SCHD 0.06%、SPYD 0.07%、HDV 0.08%と、いずれも業界で最も低い水準の経費率です。長期の複利運用では0.01%単位の差も無視できません。
商品選択で迷ったら、ご自身の運用方針に合っているかを最優先しつつ、同水準ならより低コストなものを選ぶのが合理的です。
利回り指標の扱い:SEC利回りとTTM分配利回りを混同しない
利回りには、直近30日間の収益を年率換算した「30日SEC利回り」や、過去1年間の分配金実績に基づく「TTM分配利回り」など複数の指標があります。
比較する際は、同じ指標でそろえ、いつの時点のデータかも確認することが重要です。この記事の表では、可能な限りSEC利回りで統一しています。
規模・流動性:どれも十分大きく日常の売買で困りにくい
各ETFは純資産規模が大きく、取引量も潤沢な部類に入ります。例えばSCHDの純資産は約720億ドル(2025年8月26日)と規模が大きく、日常的な売買で不便を感じることは少ないでしょう。
これは実務的な取引コストの面でも安心材料になります。VYMなども同様に、市場で広く取引されています。
VYMがおすすめできる人・できない人
これまでの分析を基に、VYMがどのような投資家に適しているか、その逆にあまり向いていないタイプは何かを具体的に解説します。安定したインカム収入や暴落耐性を重視するディフェンシブな投資家には最適な一方、より高い利回りや株価の大きな成長を狙う攻撃的な投資家には物足りないかもしれません。
VYMが向いている人
YMは、守りを固めつつ着実に資産を育てたい投資家と好相性です。長期的な視点で安定した配当収入を狙う方、市場の変動リスクを抑えたい方、そして既存ポートフォリオに安定感を加えたい方にとって、VYMがなぜ魅力的な選択肢となるのかを具体的に解説します。
1.安定志向の長期投資家
VYMは景気に左右されにくい大型優良株で構成され、安定した株価と増配実績が魅力です。NISA口座でコツコツ買い増せば、非課税の配当収入が着実に積み上がります。短期的な値動きに一喜一憂せず、じっくりとインカム資産を育てたい長期投資家にとって、心強い味方となるでしょう。
2.暴落耐性を重視する人
約500銘柄への分散と不況に強いセクター構成により、VYMは市場全体の下落局面で底堅さを発揮します。大きな値崩れをしにくい実績は、投資家の精神的安定にも貢献します。相場の変動に動じず、どっしりと構えたいディフェンシブな投資家にとって、理想的な守りの資産と言えるでしょう。
3. バランスを求める人
S&P500など成長資産を主軸とする投資家にとって、VYMは最適な補強役です。コア資産の低い配当利回りを補い、ポートフォリオ全体のインカムを向上させます。また、成長株(グロース)と割安株(バリュー)のバランスを取ることで、より安定した資産構成を目指す方に適しています。
VYMが向いていない人
一方で、VYMの安定志向な特性が投資目的と合わないケースもあります。より高い利回りを追求する方、株価の大きな成長を狙う方、またはハイリスクな投資を好む方にとって、なぜVYMが物足りなく感じる可能性があるのか。そのミスマッチの理由を具体的に解説します。
1.利回り最優先の人
VYMの利回り約3%は安定的ですが、インカムの最大化を目指すには物足りない水準です。利回り4%超を狙えるSPYDや高配当個別株の方がキャッシュフローは大きくなります。VYMの分散性よりも、現在の配当金の高さを最優先する投資家には、より利回りに特化した商品が適しているでしょう。
2.値上がり益を重視する人
VYMは成熟した大型バリュー株が中心のため、株価が数倍になるような急成長は期待しにくい構成です。資産を大きく増やすことが目標なら、ハイテク株ETFや個別グロース株が適しています。安定配当よりも、株価の値上がり益(キャピタルゲイン)で積極的に資産を拡大したい投資家には不向きでしょう。
3.攻めの投資を好む人
VYMの堅実で安定した値動きは、裏を返せば「退屈」とも言えます。新興国株や小型株、短期的なテーマ株などで高いリスクを取り、大きなリターンを狙う投資家には刺激が足りないでしょう。「資産を守り育てる」ことより「積極的に増やしにいく」ことを重視する、リスク許容度の高い方には不向きです。
VYMとは弱点を理解し、賢く付き合う
VYMは、「突出した魅力はないが、大きな欠点もない優等生」なETFです。その性質を正しく理解すれば、堅実なインカム(配当収入)と適度な成長を両立できる、非常に優秀な投資対象と言えます。
特に新NISA制度が始まった今、非課税で安定したキャッシュフローを生み出すVYMの価値は、これまで以上に高まっています。ご自身のポートフォリオに「安定した配当」という軸を加えたいなら、VYMは最初に検討すべき、心強いパートナーとなってくれるでしょう。
この記事のまとめ
VYMは「安定配当・低コスト・広い分散」を兼ね備えた王道ETFであり、長期投資の軸になり得ますが、利回りは中程度にとどまり、金融セクター偏重や為替・二重課税といった注意点もあります。
SPYD・HDV・VIG・SCHDなどと比較することで、自分が重視すべき評価軸が利回りなのか増配なのか、あるいは守備力なのかが明確になります。投資判断の際にはリスク許容度や資産全体のバランスを照らし合わせることが重要です。必要に応じて専門家に相談するのも選択肢です。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)とは、証券取引所で株式のように売買できる投資信託のことです。日経平均やS&P500といった株価指数、コモディティ(原油や金など)に連動するものが多く、1つのETFを買うだけで幅広い銘柄に分散投資できるのが特徴です。通常の投資信託に比べて手数料が低く、価格がリアルタイムで変動するため、売買のタイミングを柔軟に選べます。コストを抑えながら分散投資をしたい人や、長期運用を考えている投資家にとって便利な選択肢です。
VYM
VYMとは、バンガード社が提供する「Vanguard High Dividend Yield ETF」の略称で、米国の大型株を中心に配当利回りの高い企業に投資する上場投資信託です。このETFは約440〜590銘柄に分散投資し、高配当銘柄を広くカバーしつつ、費用率は0.06%と非常に低いため、コストパフォーマンスにも優れています。 年間配当利回りは2.7%前後で、四半期ごとの配当支払いが行われています。長期保有による安定的なインカムゲインと株価上昇の両方を狙いたい投資家に向いた商品です。
配当利回り
配当利回りは、株式を1株保有したときに1年間で受け取れる配当金が株価の何%に当たるかを示す指標です。計算式は「年間配当金÷株価×100」で、株価1,000円・配当40円なら4%になります。 指標には、実際に支払われた金額で計算する実績利回りと、会社予想やアナリスト予想を用いる予想利回りの2種類があります。株価が下がれば利回りは見かけ上上昇するため、高利回りが必ずしも割安や安全を意味するわけではありません。 安定配当の見極めには、配当性向が30~50%程度であること、フリーキャッシュフローに余裕があることが重要です。また、権利付き最終日の翌営業日には理論上配当金相当分だけ株価が下がる「配当落ち」が起こります。 日本株の配当は通常20.315%課税されますが、新NISA口座内で受け取る配当は非課税です。配当利回りは預金金利や債券利回りと比較でき、インカム収益を重視する長期投資家が銘柄や高配当ETFを選ぶ際の判断材料となります。
FTSE High Dividend Yield指数
FTSE High Dividend Yield指数とは、英国のFTSE社が算出・公表している株価指数で、米国市場に上場している中から配当利回りが市場平均よりも高い大型株を選定し構成されています。 この指数は、高配当を安定的に出している企業に注目し、収益性と健全性を兼ね備えた銘柄群を反映しています。代表的なETFであるVYM(Vanguard High Dividend Yield ETF)はこの指数に連動しており、配当収入を重視する長期投資家のベンチマークとして広く利用されています。
経費率
経費率(Expense Ratio)は、投資信託やETF(上場投資信託)などの運用にかかる年間コストを、運用資産総額に対する割合で示した指標です。投資家はこの経費率を負担するため、経費率が低いほど投資のコストが抑えられ、リターンが高まりやすくなります。 例えば、あるETFの経費率が0.2%の場合、年間で運用資産の0.2%が管理費用などに充てられます。経費率には、ファンドの管理費用、売買手数料、監査費用などが含まれます。 一般的に、インデックス型ETFは経費率が低く(0.1%~0.5%程度)、アクティブ運用のファンドは高くなる(1%~2%程度)傾向があります。経費率が高すぎると、長期的に資産が目減りする可能性があるため、投資先を選ぶ際は経費率の低い商品を選ぶことが重要です。
コア・サテライト戦略
コア・サテライト戦略とは、資産運用において「コア資産」と「サテライト資産」を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを最適化する投資手法のことを指す。ポートフォリオの大部分を安定したコア資産で構成し、長期的な市場の成長に連動するリターンを確保する一方で、残りの一部をサテライト資産として運用し、高いリターンの可能性を追求する。これにより、安定性を維持しながら市場環境の変化に柔軟に対応し、資産の成長を図ることができる。
セクター分散
セクター分散とは、資産運用において特定の業種や産業(セクター)に偏らず、複数の分野にわたって投資先を分けることで、リスクを軽減する投資手法のことです。たとえば、情報技術、医療、金融、消費財といった異なるセクターに株式を分散させることで、ある業種に不測の事態が起きた場合でも、他のセクターで損失をカバーできる可能性があります。 これは、値動きの傾向が異なる業種を組み合わせることで、全体のポートフォリオの安定性を高めるための戦略です。資産運用の基本である「分散投資」の中でも、地域や資産クラスの分散と並んで重要な考え方の一つです。特に株式投資においては、セクターごとの経済環境の影響が大きいため、この分散の工夫が成果に直結します。
大型株
大型株とは、時価総額が大きく、安定した業績や財務基盤を持つ上場企業の株式のことを指します。一般的には、国内外で広く知られた大企業が該当し、取引量も多く流動性が高いため、売買がしやすい特徴があります。代表的な例として、日本ではトヨタ自動車やソニーグループ、アメリカではアップルやマイクロソフトなどが挙げられます。 大型株は、中小型株に比べて値動きが比較的穏やかで安定しており、長期投資や年金運用などで重視されます。一方で急激な成長はあまり期待できないこともありますが、その分、経済全体の動向に連動しやすい傾向があります。
バリュー株
バリュー株とは、企業の財務状況や資産価値と比較して割安に取引されている株式を指します。一般的に、成長が鈍化した企業や市場から注目されていない企業に多く、配当利回りが高い傾向にあります。投資家は、企業価値が市場に正しく評価されることで株価が上昇し、利益を得ることを期待して投資します。
リバランス
リバランスとは、ポートフォリオを構築した後、市場の変動によって変化した資産配分比率を当初設定した目標比率に戻す投資手法です。 具体的には、値上がりした資産や銘柄を売却し、値下がりした資産や銘柄を買い増すことで、ポートフォリオ全体の資産構成比率を維持します。これは過剰なリスクを回避し、ポートフォリオの安定性を保つためのリスク管理手法として、定期的に実施されます。 例えば、株式が上昇して目標比率を超えた場合、その一部を売却して債券や現金に再配分するといった調整を行います。なお、近年では自動リバランス機能を提供する投資サービスも登場しています。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
二重課税
二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。
外国税額控除
外国税額控除とは、日本に住んでいる個人や法人が、海外で所得を得てその国で税金を支払った場合に、同じ所得に対して日本でも課税される「二重課税」を避けるために、日本で支払う税金からその分を差し引くことができる制度のことをいいます。たとえば、外国株式の配当金を受け取った際に、外国で源泉徴収された税金がある場合、その金額を一定の計算に基づいて日本の所得税や法人税から控除することができます。この制度を利用することで、国際的な投資やビジネスを行う際の税負担を適正に調整できるようになります。ただし、控除できる金額には上限があり、正確な申告と証明書類の提出が必要です。資産運用や海外取引を行ううえで、知っておきたい重要な税務上の仕組みです。
ドルコスト平均法
ドルコスト平均法とは、一定の金額を定期的に投資する方法です。価格が高いときは少なく、価格が低いときは多く買えるため、購入価格が平均化され、リスクを分散できます。市場のタイミングを読む必要がないため、初心者に最適な方法とされています。長期投資で効果を発揮し、特に投資信託やETFで利用されることが多い手法です。
ボラティリティ
ボラティリティは、投資商品の価格変動の幅を示す重要な指標であり、投資におけるリスクの大きさを測る目安として使われています。一般的に、値動きが大きい商品ほどそのリスクも高くなります。 具体的には、ボラティリティが大きい商品は価格変動が激しく、逆にボラティリティが小さい商品は価格変動が穏やかであることを示します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティを標準偏差という統計的手法で数値化し、それを商品のリスク度合いとして評価するのが一般的です。このため、投資判断においては、ボラティリティの大きい商品は高リスク、小さい商品は低リスクと判断されます。
トータルリターン
トータルリターンとは、株式や債券、投資信託などの資産から得られる利益を、値上がり益(キャピタルゲイン)と分配金・利息・配当金などのインカムゲインを合わせて総合的に捉えた指標です。配当や利息をその都度再投資すると仮定して計算するのが一般的であり、単に価格変動だけを追う「価格リターン」と比べ、投資の実質的な運用成果をより正確に示します。このため、長期投資のパフォーマンス評価や異なる資産クラスの比較を行う際には、トータルリターンで見ることが重要です。
配当(配当金)
配当とは、会社が得た利益の一部を株主に分配するお金のことをいいます。企業は利益を出したあと、その一部を将来の投資に使い、残った分を株主に還元することがあります。このときに支払われるお金が配当金です。株を持っていると、持ち株数に応じて定期的に配当金を受け取ることができます。多くの場合、年に1回または2回支払われ、企業によって金額や支払い時期は異なります。配当は企業からの「お礼」のようなもので、株を長く持ち続ける理由の一つになることがあります。
為替リスク
為替リスクとは、異なる通貨間での為替レートの変動により、外貨建て資産の価値が変動し、損失が生じる可能性のあるリスクを指します。 たとえば、日本円で生活している投資家が米ドル建ての株式や債券に投資した場合、最終的なリターンは円とドルの為替レートに大きく左右されます。仮に投資先の価格が変わらなくても、円高が進むと、日本円に換算した際の資産価値が目減りしてしまうことがあります。反対に、円安が進めば、為替差益によって収益が増える場合もあります。 為替リスクは、外国株式、外貨建て債券、海外不動産、グローバルファンドなど、外貨に関わるすべての資産に存在する基本的なリスクです。 対策としては、為替ヘッジ付きの商品を選ぶ、複数の通貨や地域に分散して投資する、長期的な視点で資産を保有するなどの方法があります。海外資産に投資する際は、リターンだけでなく、為替リスクの存在も十分に理解しておくことが大切です。
信託報酬
信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。
分配金
分配金とは、投資信託やREIT(不動産投資信託)などが運用によって得た収益の一部を、投資家に還元するお金のことです。これは株式でいう「配当金」に似ていますが、分配金には運用益だけでなく、元本の一部が含まれることもあります。そのため、分配金を受け取るたびに自分の投資元本が少しずつ減っている可能性もあるという点に注意が必要です。分配金の有無や頻度は投資信託の商品ごとに異なり、毎月、半年ごと、年に一度などさまざまです。投資初心者にとっては、「お金が戻ってくる」という安心感がありますが、長期的な資産形成を考えるうえでは、分配金の出し方やその内容をしっかり理解することが大切です。
再投資
再投資とは、株式や投資信託などの運用から得られた配当金・利息・分配金などを現金化せず、再び同じ資産や他の金融商品に振り向けることを指します。たとえば、受け取った配当金で同じ株式を買い増したり、投資信託の分配金を再度そのファンドに組み入れるような方法です。 この再投資によって、得られた収益が次の投資原資となり、元本が増加することでさらに多くの収益を生み出す「複利効果」が働きます。特に長期的な資産形成を目指す場合、複利の積み上げはリターンの差を大きく左右する重要な要素です。 また、再投資は相場のタイミングに依存しない「継続的・機械的な投資行動」でもあるため、長期的な投資規律を保ちやすく、感情的な売買を避ける上でも有効です。インデックス投資や積立投資においても再投資の活用は基本戦略のひとつであり、資産運用の効率性と安定性を高めるために欠かせない視点と言えるでしょう。