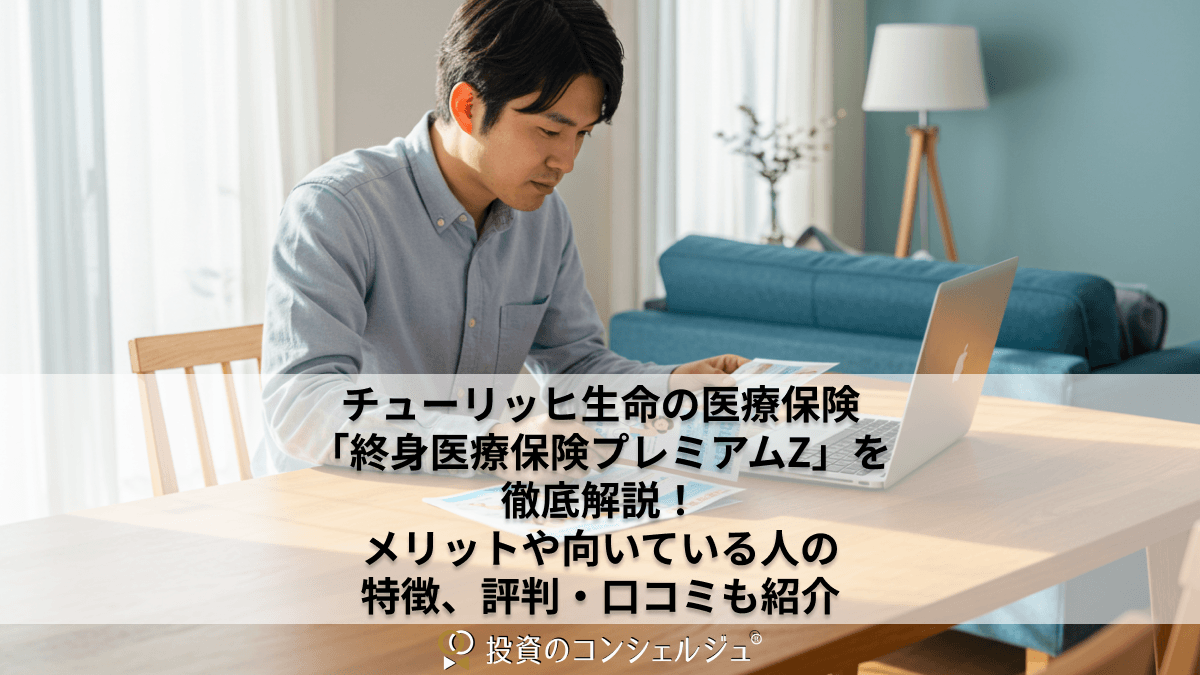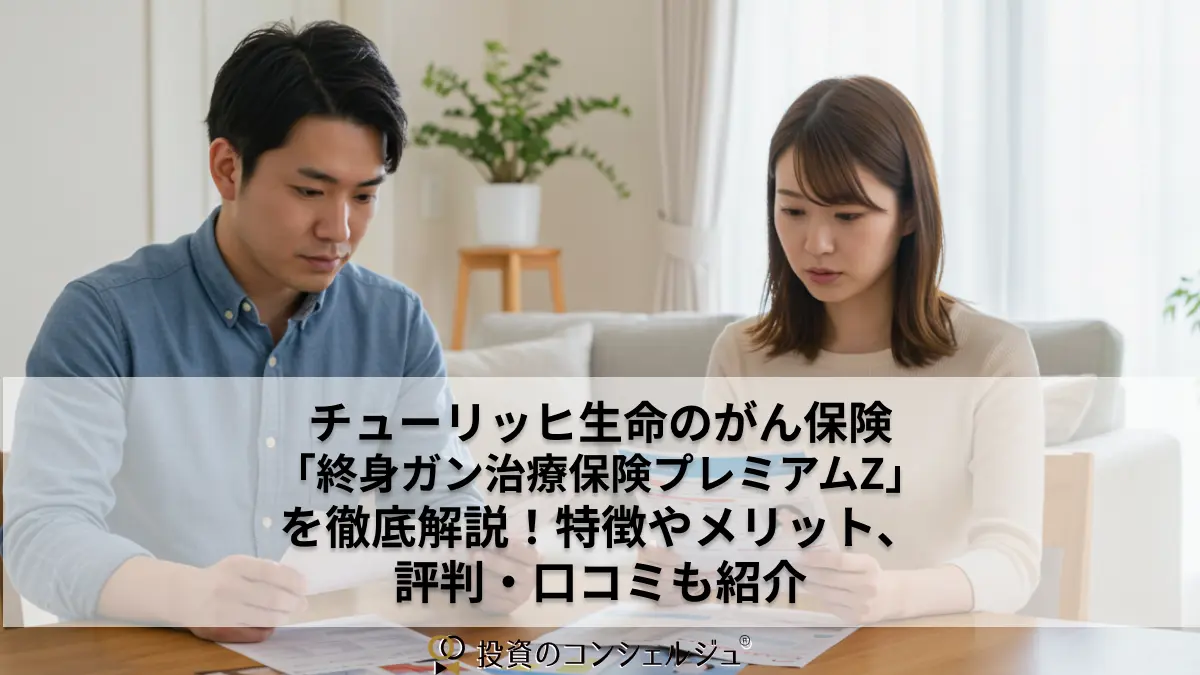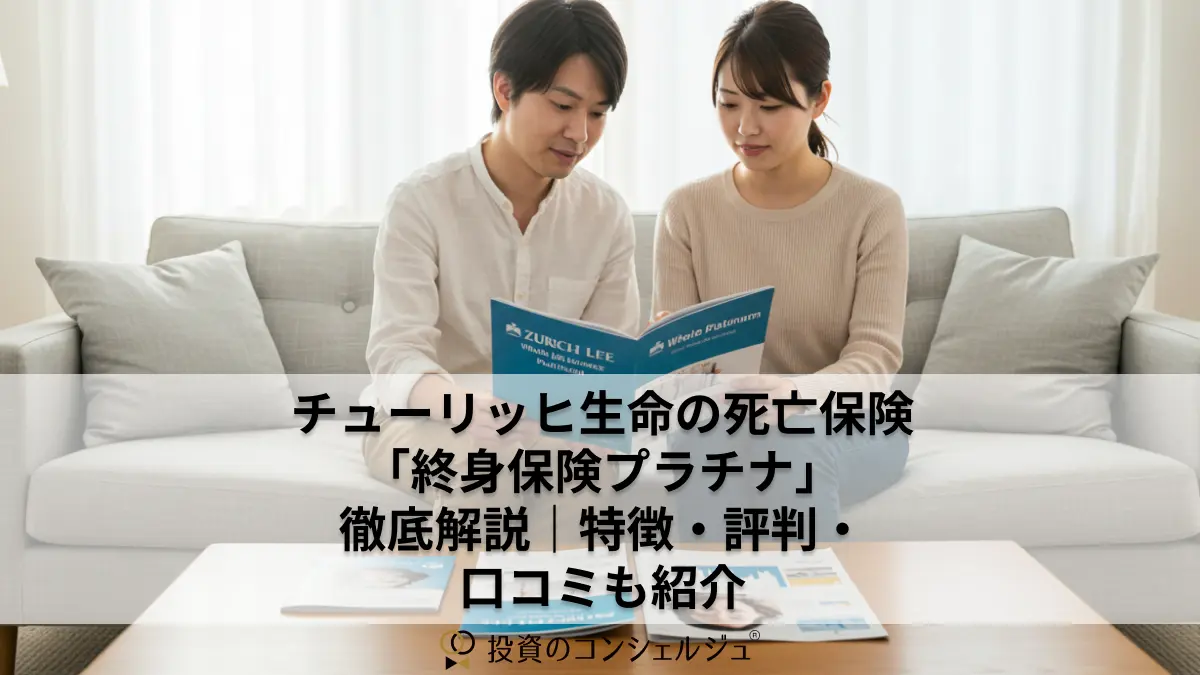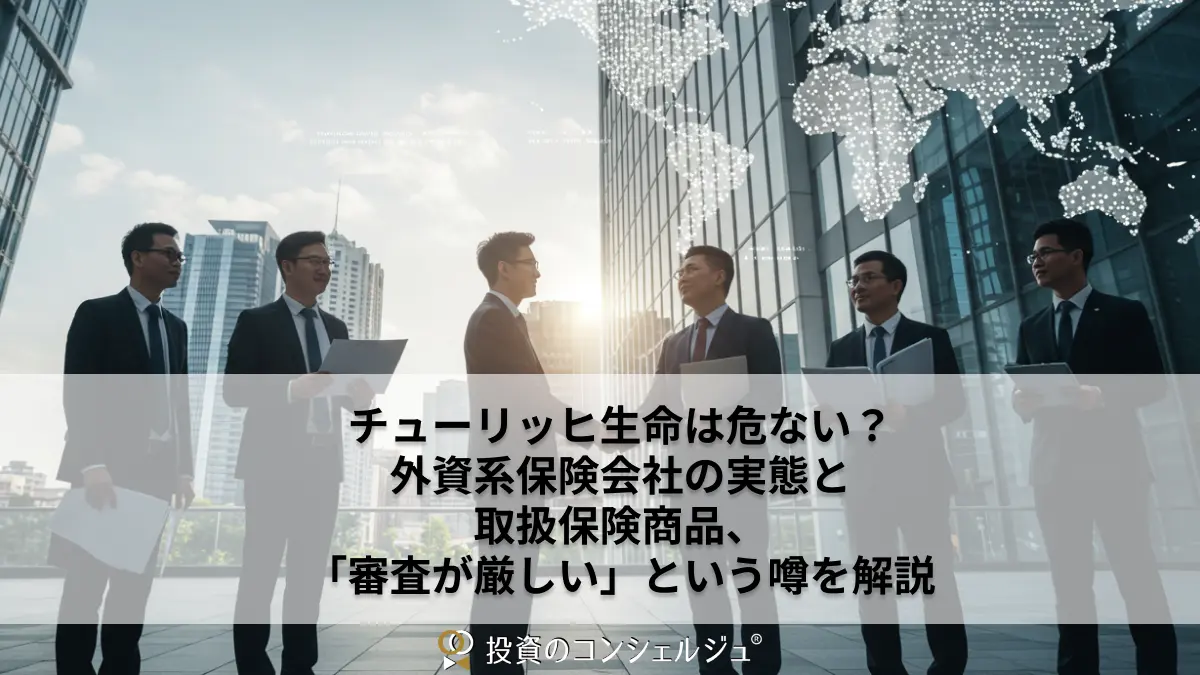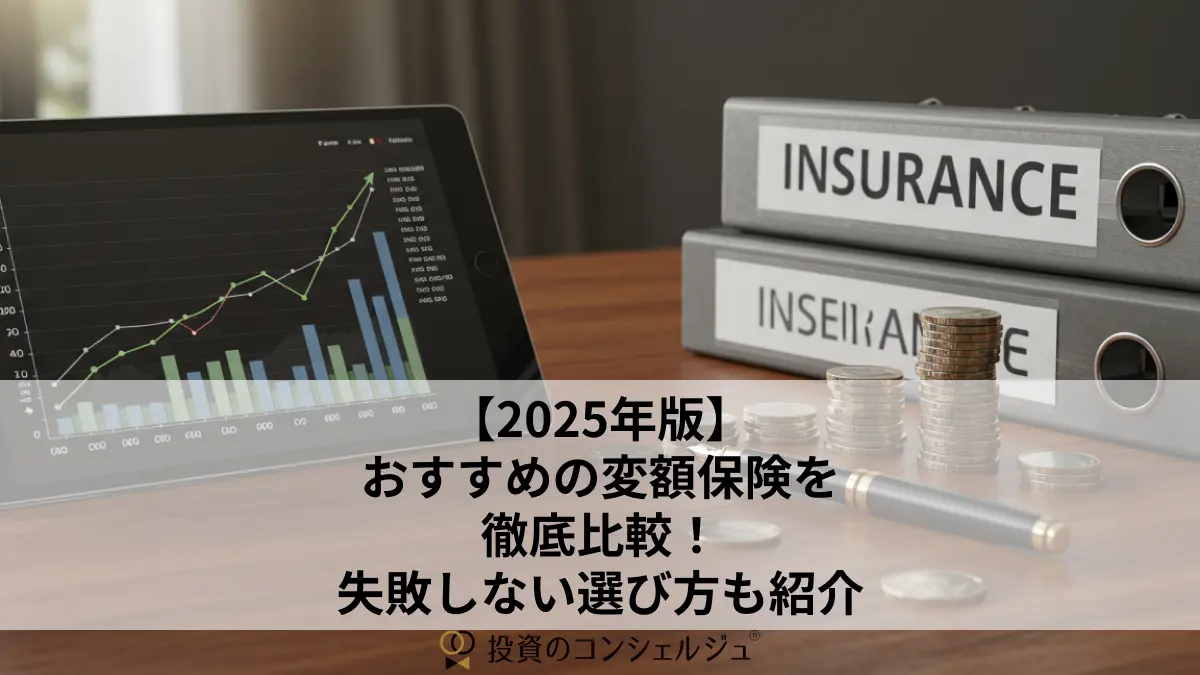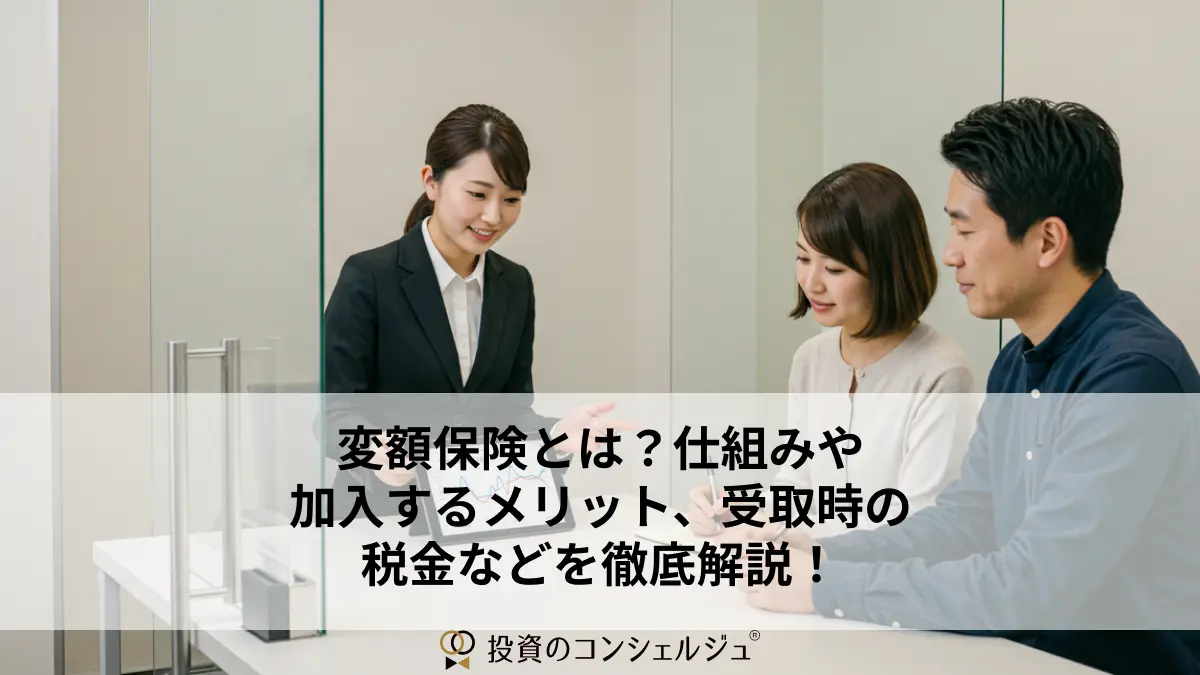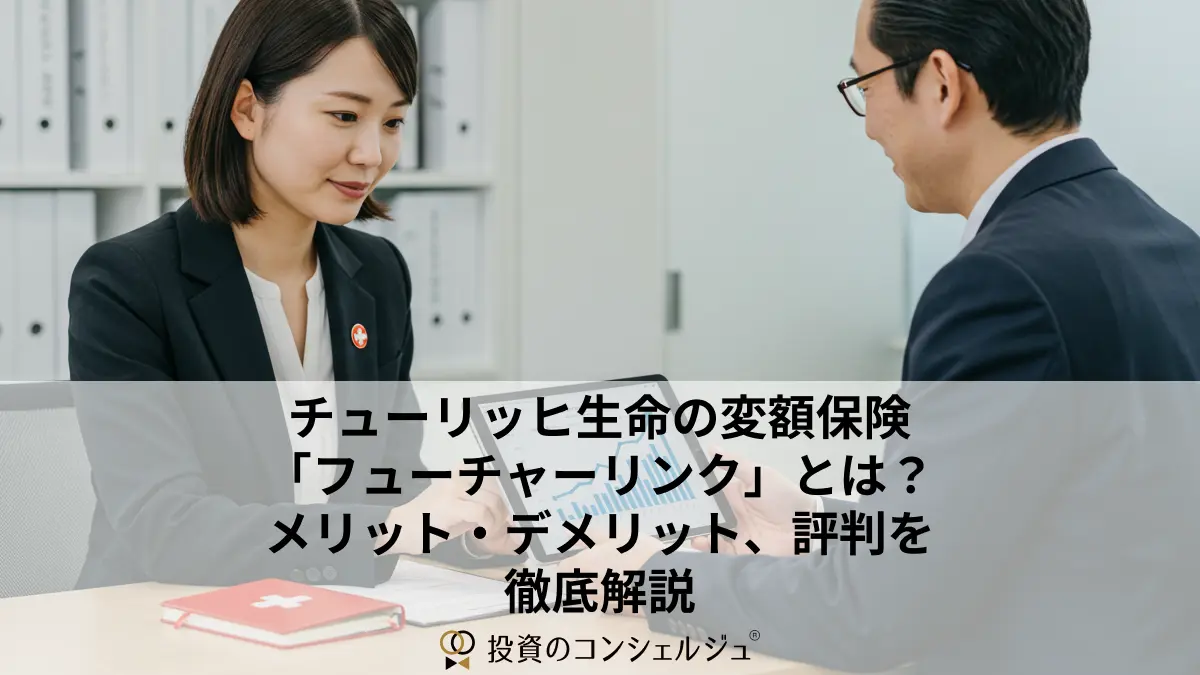
チューリッヒ生命の変額保険「フューチャーリンク」とは?メリット・デメリット、評判を徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.07.08
更新:
2025.09.26
金利上昇とインフレが進む今、保障と資産運用を同時にかなえたい層が注目するのが2025年4月に登場したチューリッヒ生命の変額保険「フューチャーリンク」です。本商品は死亡保障と特別勘定運用を一本化し、年に12回までの無料スイッチングなど、柔軟性の高さが魅力です。一方で、信託報酬や解約控除などコスト要因と元本割れリスクがある点には注意が必要です。
本記事では商品仕様をひもとき、メリットとデメリット、サービスの活用方法などを解説します。向いている人の特徴も解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読めば、チューリッヒ生命が販売している「フューチャーリンク」が提供する死亡保障と特別勘定運用をワンストップで活用する具体像を把握できます。3大疾病保険料払込免除特約の内容や、年金移行機能を活用するメリットなど、実用的なメリットも紹介。
フューチャーリンクならではの特徴やサービスを把握し、他社の変額保険との違いを理解できます。
さらに、発生する手数料や10年以内に解約するデメリットなど、加入にあたって抑えておくべき注意点も紹介。読後にはあなたのライフプランに合うかどうか、本当に合っている保険なのかを客観的に分析できます。
変額保険の特徴
変額保険とは、死亡・高度障害などを保障しつつ保険料の一部を株式や債券で運用し、その成果に応じて解約返戻金や死亡保険金が増減する商品です。
保険会社は元本や利回りを保証しないため運用リスクは契約者負担ですが、長期的には市場成長の恩恵を享受できます。払込保険料は生命保険料控除の対象になるため、所得税・住民税を抑えられます。また、死亡保険金は「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用でき、相続税対策にも有効です。
一般の終身保険よりインフレ耐性がある一方で、運用不振による元本割れや高めの保険関係費用、短期解約時の解約控除などに注意が必要です。
フューチャーリンクの基本スペック
まずは、フューチャーリンクの基本的な情報から見ていきましょう。
商品概要
フューチャーリンクは、2025年4月にチューリッヒ生命が発売した有期型の変額保険です。変額保険とは、保険料の一部を株式や債券を中心とした特別勘定で運用し、その運用成果に応じて解約返戻金や死亡保険金が増減する仕組みを持つ商品です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約年齢 | 満0歳~満70歳 |
| 基本保険金額 | 100万円~3億円 |
| 特別勘定 | 9種類(日本株式型、世界株式型、外国債券型、バランス型など)から選択・配分比率指定可能 |
| 保険期間 | 歳満了:50 歳・55 歳・60 歳・65 歳・70 歳・75 歳・80 歳満了 年満了:10 年・15 年・20 年・25 年・30 年満了 |
| 保障内容 | 死亡保険金:被保険者が保険期間中に死亡したとき 高度障害保険金:被保険者が保険期間中に高度障害状態に該当したとき 満期保険金:被保険者が保険期間満了時に生存しているとき |
| 特約 | 3大疾病保険料払込免除特約(がん・心疾患・脳血管疾患、上皮内新生物含む)付加可能 |
保険料の一部を運用する特性上、運用成績が良ければ受け取り額が増えるメリットがあります。一方で、運用成績が悪ければ受け取り額が減少するリスクもあります。
保障内容
フューチャーリンクの保障内容について、主契約と特約にわけて見ていきましょう。
主契約
| 区分 | 支払事由・内容 | 保険金額・取扱い |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 基本保険金額と「支払事由発生日の積立金額」のいずれか大きい額を支払い |
| 高度障害保険金 | 責任開始後の傷病が原因で所定の高度障害状態に該当したとき | 上記と同じ算定方法 |
| 保険料払込免除 | 所定の払込免除事由に該当した場合 | ただし 地震・噴火・津波、および 戦争・変乱 に起因する場合は免除しない |
特約
| 特約名 | 主な保障・機能 | 免除対象/移行条件など |
|---|---|---|
| 3大疾病保険料払込免除特約(変額保険用) | 3大疾病に該当すると、保険料払込が免除 | ・事故による身体障害(事故日から180日以内) ・初回診断確定のガン(上皮内含む/責任開始90日経過後)・急性心筋梗塞など心疾患、脳卒中など脳血管疾患で所定の入院または手術 |
| 年金支払特約 | 受取保険金等を一括ではなく 年金方式で受け取れるよう変更 | 年金支払期間中に年金管理費(年金額の1.0%上限)が控除される |
| 年金移行特約 | 将来、契約の全部または一部を 死亡保障等に代えて年金へ移行 | 年金額・移行時期は契約者申出により設定 |
3大疾病に備えたい方は「3大疾病保険料払込免除特約」を付加すれば、健康リスクにも備えられます。保険金を年金形式で受け取りたいと考えている方は、年金支払特約または年金移行特約の付加を検討するとよいでしょう。
特別勘定ラインナップと運用方針
フューチャーリンクの特別勘定は、全部で9種類です。国内外株式や債券、バランス型などの多彩な運用テーマが揃っています。
| 運用コース名 | 特徴・概要 |
|---|---|
| 日本株式型(アクティブ) | 日本株式を積極運用 |
| 日本株式型(インデックス) | 日本株式の指数連動型 |
| 世界株式型(アクティブⅠ) | 世界の株式を積極運用 |
| 世界株式型(アクティブⅡ) | 世界の株式を積極運用(運用方針が異なる2タイプ) |
| 外国株式型(インデックス) | 海外株式の指数連動型 |
| 日本債券型 | 日本の債券を中心に運用 |
| 外国債券型 | 海外の債券を中心に運用 |
| バランス型(マルチアセット) | 複数資産に分散投資(積極的な資産配分) |
| バランス型(インデックス) | 複数資産に分散投資(指数連動型) |
契約中のスイッチング(ファンド変更)は、年12回まで無料です(13回目以降は有料)。ライフステージや経済状況の変化に合わせて、リスクを調整できる制度設計となっています。
フューチャーリンクのメリット──保障と資産運用を両立する仕組み
具体的に、フューチャーリンクにはどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。以下で解説する内容に魅力を感じる場合、相性が良い可能性が考えられます。
3大疾病保険料払込免除特約を付加できる
チューリッヒ独自の「3大疾病保険料払込免除特約」は、がん(上皮内新生物含む)・急性心筋梗塞・脳卒中・脳血管疾患で所定状態になれば、それ以降の保険料が免除されます。
保険料の払込が免除されても、保障や資産形成はそのまま継続されるため、将来のさまざまなリスクに備えられます。
「変額保険に加えて、医療保険の機能の一部を上乗せしている」というイメージです。大きな病気による経済的な負担を軽減しつつ、安心して資産形成を継続するうえで、有用な特約です。
リスク許容度に応じて9種類の特別勘定を選べる
フューチャーリンクで選択できる9つの特別勘定は、リスクレベルで分類されています。初心者向けの「インデックス型」「バランス型」はもちろん、積極的にリターンを狙う「アクティブ型」まで用意されています。
国内外の株式・債券に加え、機動的に資産配分を変えるマルチアセット型まで、ワンストップで選択可能です。相場観やライフステージの変化に合わせて、自由に組み合わせ・スイッチングしながら長期ポートフォリオを構築できるメリットがあります。
また、スイッチングは年12回までは無料で行えるため、不況時にはバランス型への切替も可能です。
クレジットカード払い対応のキャッシュフロー柔軟性
チューリッヒ生命では、保険料の払込方法として口座振替に加えクレジットカード決済を選べます。これにより、カード利用でポイントやマイルを獲得できる副次的なメリットを得られます。
年払を選択した場合でも、保険料は自動的に月次で特別勘定へ振り分けられる特則が適用されるため(いわゆる月次ドルコスト運用)、積立投資のタイミング分散効果の両方を享受できます。
「年金支払特約」+「年金移行特約」で年金受け取りも可能
フューチャーリンクの特約には、以下のような特約が用意されています。
| 特約名 | 機能 |
|---|---|
| 年金支払特約 | 満期や途中の任意のタイミングで、死亡保障などを確定年金に変更する |
| 年金移行特約 | 契約の全部または一部を年金に切り替える |
これにより、運用フェーズで積み上げた積立金を、退職後は定期的な年金収入へスムーズにシフトできます。外部の年金保険へ乗り換える手間や新規契約コストをかけずに、「保障重視」から「生活設計重視」への切り替えが可能です。
心身の健康サポートを受けられる
チューリッヒ生命では、契約者に向けて心身の健康サポートのサービスを提供しています。
| サービス名 | 主な内容 | 対応時間 | 相談方法 | 相談相手・専門家 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| メディカルサポート | 健康・医療・介護などの相談、夜間・休日診療機関案内、セカンドオピニオン(医師紹介) | 24時間365日 | 電話 | 看護師・医師等 | ご契約者・被保険者とその家族 |
| Doctors Me | オンライン健康相談(文章・写真で相談可能) | 24時間365日 | PC・スマートフォン(Web) | 医師・歯科医師・薬剤師・栄養士等 | ご契約者・被保険者 |
両サービスとも無料で利用可能で、メディカルサポートは電話中心、Doctors Meはオンライン中心という違いがあります。24時間365日対応しており、健康面で不安があればいつでも相談できます。
より良い医療や納得のいく治療方法を選ぶためのセカンドオピニオンも可能です。「主治医以外の医師に意見を聞きたい」というときに、有用なサービスです。
些細なことでも、何度でも相談できる点は契約者にとって安心につながります。夜中に医療機関が閉まっている時間でも相談できるため、健康面で気になることがあれば有効活用しましょう。
「特別勘定とは何か?」という疑問を感じた方は、以下のFAQを参考にしてみてください。
フューチャーリンクのデメリットや注意点
メリットがある一方で、契約前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。契約後に後悔する事態を防ぐためにも、商品の内容をきちんと確認しておきましょう。
契約時費用・保険関係費・信託報酬の全体コストが高め
フューチャーリンクの費用構造は複雑で、以下のようなコストがかかります。
| 費用の名称 | 料率・計算方法 | 控除されるタイミング・対象 |
|---|---|---|
| 保険契約の締結・維持および保険料収納費 | ―(比率の明示なし) | 保険料を特別勘定へ繰り入れる際に保険料から控除 |
| 基本保険金額保証費 | 年率0.05 % | 毎月の契約応当日始に積立金から控除 |
| 死亡保障などに必要な費用(危険保険料) | 年齢・性別等に応じた危険保険料 | 毎月の契約応当日に積立金から控除 |
| 特別勘定管理費 | 年率0.7% | 毎月の契約応当日始に積立金から控除 |
| 保険料払込免除費 | 保険料×0.2 % | 保険料を特別勘定へ繰り入れる際に保険料から控除 |
これらのコストは保険料から自動的に差し引かれるため、手数料を支払っている実感は得づらいかもしれません。しかし、一連の手数料は契約者にとって確実なマイナスリターンであるため、できるだけ抑えるに越したことはありません。
さらに、特別勘定ごとに運用関係費(信託報酬)が定められています。投資信託の純資産総額から毎日控除されるコストであるため、あわせて押さえておきましょう。
解約控除と短期解約リスク
フューチャーリンクでは、契約から10年未満で解約した場合は、積立金額から解約控除額が差し引かれます。解約控除とは短期間で保険を解約したときのペナルティで、控除額は基本保険金額・保険料払込年月数・契約年齢・保険期間などによって異なります。
早期解約ほど控除率が高く、解約返戻金が少なくなる、またはゼロになる場合もあります。無計画に契約すると、せっかく資産を増やそうとしたのにもかかわらず、結果的に資産を減らしてしまう結果になりかねません。
変額保険に関するコストは、以下のFAQで詳しく解説しています。
3大疾病払込免除特約を付加する場合は保険金額の上限に注意
3大疾病保険料払込免除特約を付加すると、基本保険金額は「1被保険者あたり総払込保険料1,080万円」が上限という制限が掛かります。すでに1,080万円超の保険料設計を希望する場合は、基本保険金額を減額するか、あるいは特約を付けずに契約する必要があります。
フューチャーリンクに向いている人──メリットを最大化できる3タイプ
具体的に、どのような人がフューチャーリンクに向いているのかを解説します。あなたの状況に近いケースがあるか、参考にしてみてください。
死亡保障・医療保障・運用を一本化したい人
教育費のピークと住宅ローン返済が重なる中で、個別に保険や投資商品を管理するのが負担に感じられる世帯には、保障と資産運用が一体となったフューチャーリンクが適している可能性があります。
住宅ローンに関しては、団信(団体信用生命保険)でカバーできます。しかし、教育費は保険や貯蓄などの手段で、自力で用意しなければなりません。
3大疾病保険料払込免除特約を付ければ、がん(上皮内を含む)・心疾患・脳血管疾患で所定の状態になったとき、保険料の支払いが免除されます。もし大病を患っても、保障と資産形成を途切れさせません。
フューチャーリンクは、死亡保障と三大疾病保障を確保しつつ、解約返戻金を教育費や住宅繰上げ返済資金として活用できます。元本割れのリスクには注意が必要ですが、家計の柔軟性を高めるうえで、有用な保険商品といえるでしょう。
なお、チューリッヒ生命では終身保険や医療保険も販売しています。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
保険金の受取り方法を一時金か年金から選びたい人
フューチャーリンクは、受取方法を「まとまった一時金」か「分割の年金」へ自在に切り替えが可能です。契約の途中でも、「年金支払特約」を付加することにより、積立金の全部または一部を死亡保障から年金受取に移行できます。
退職のタイミングや公的年金の開始時期に合わせ、必要額だけを年金化することも可能です。保険金受取時における資金ニーズに応じて、適した方法を選択できます。
「相続対策として一時金を選ぶか、生活費として年金化するかを後で決めたい」「公的年金の繰下げ受給を予定し、その空白期間だけ私的年金でカバーしたい」のようなニーズに対して、柔軟に対応できます。
健康や介護に関する不安がある人
フューチャーリンクでは、契約者向けに日々の健康相談や介護・医療の情報収集などのサービスを提供しています。
「メディカルサポート」では、24時間365日、看護師など専門スタッフが電話で健康・医療・介護の悩みに対応しています。夜間・休日に受診できる医療機関案内や、専門医によるセカンドオピニオン手配も可能です。家族も利用対象に含まれるため、介護を抱える世帯や遠方の親の体調が気になる人に心強いサービスです。
「Doctors Me(ドクターズミー)」では、PCやスマホから文章・写真を送って医師・薬剤師・栄養士など各分野の専門家にオンライン相談できます。こちらも24時間365日利用でき、仕事や子育てで病院へ行く時間が取りづらいときの“すき間相談窓口”として有効活用できるでしょう。
なお、以下の記事ではおすすめの変額保険をまとめて紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
フューチャーリンクが向いていない人──別手段を検討すべき3タイプ
以下に該当する方は、フューチャーリンクが向いていない可能性があります。
手数料を徹底的に抑えて資産運用をしたい人
低コストインデックスファンドに長期投資している人にとって、フューチャーリンクの信託報酬や保険関係費は相対的に高コストです。コスト意識が高く、運用効率を無駄に下げたくない人にとって、フューチャーリンクは向きません。
変額保険は、保険会社を介して投資信託を購入している構図です。間に保険会社が入る分、手数料が高くなってしまうのです。運用期間が長期になるほど、手数料の差が大きな差につながります。
つまり、死亡保障や払込免除特約などの付加価値を求めず、「純粋に運用効率を追求したい」という方には不向きです。自分の判断で投資ができる方は、あえて変額保険を活用して運用する必要性は乏しいでしょう。
10年以内に教育費・住宅取得などの大きな出費を予定している人
保険契約から10年未満で解約すると、解約控除により返戻金が大きく目減りします。近い将来に資金需要がある人にとって、フューチャーリンクは適していません。
資金拘束が長い変額保険は流動性に欠け、柔軟な資金運用が困難です。たとえば5年後に住宅購入や教育資金が必要と分かっている場合、流動性の高い投資信託や定期預金などの方が適しています。
生活費や近い将来に使う予定のお金は、「減らさないような運用」が求められます。リスクを取って運用した結果、資産を減らしてしまうのは問題です。そのため、きちんと「安全に運用するお金」「運用に回してもよいお金」は、必ず分けて管理しましょう。
頻繁にスイッチングをする可能性がある人
フューチャーリンクでは、積立金を別の特別勘定へ移す「スイッチング」は保険年度内で12回までは無料で行えます。ただし、13回目以降は1回あたり800円(書面の場合は2,000円)の手数料がかかります。
細かくポートフォリオを動かしたい人は、年間13回を超えるたびにコストを負担しなければならない可能性があります。長期運用で積み上げたリターンを削るリスクがあるため、向かない可能性が考えられるでしょう。
相場に合わせて頻繁にスイッチングしたい場合は、保険を通じて運用しないほうがよいでしょう。手数料無料で売買できる証券口座を解説し、自分の判断で柔軟に運用できるほうが向いています。
実際の加入者からの評判や口コミ
実際に、フューチャーリンクに契約している人からの評判や口コミを見てみましょう。チューリッヒ生命の公式サイトと、投資のコンシェルジュが独自に集計したアンケート調査を紹介します。
良い評判・口コミ
初めての保険金請求で少し不安でしたが、保険金請求書送付の申請から請求書の記入、入金の確認まで、想像以上にスムーズに進めることができたと高く評価しています。申請から入金までの期間もすこぶる早く、現在の状況も逐一SMSで報告していただけるので、「今どうなってんの?」、「放置されているのでは?」という不安もゼロでした。請求書の記入例もわかりやすく、記入に詰まることなく申請できたのも高評価です。(40代 男性)
引用:チューリッヒ生命
乳ガンになってしまい元気を失いましたが、いただいた保険金のお陰で治療や胸の再建費に充てることができました。特に胸の再建に関しては脂肪注入という先進医療を選択することができ、これ以上心と体に傷をつけることなく本当に感謝しております。(40代 女性)
引用:チューリッヒ生命
保険金や解約返戻金の支払いがスムーズである点を、高く評価する声が見られました。万が一の保険金や、生活に必要な資金を受け取るまでに時間がかかると、さまざまな不安がよぎります。
しかし、チューリッヒ生命では迅速な対応を行っているため、保険金や解約返戻金を請求するときにストレスを感じずに済むでしょう。
女性の加入者からは、乳がんの治療費を用意できた点を評価する声が見られました。がんの診断を受けると、健康面だけでなく経済的な不安も感じるものですが、フューチャーリンクの3大疾病保険料払込免除特約を付加すればリスクに備えられます。
悪い評判・口コミ
死亡保障があるので保険料控除を利用できるのはメリットですが、信託報酬を含む諸費用はネット証券の投資信託より高いと感じます。(40代 男性)
子どもの教育資金を目的に契約したが、途中で住宅ローンの頭金が必要になり解約を検討したところ、解約控除が予想以上に大きく元本割れが確定すると分かった。流動性を重視する家庭には向かない商品だと感じる。(40代 男性)
変額保険の諸費用は、自分で直接投資信託を購入するよりも高くなります。変額保険には契約関係費や特別勘定の信託報酬など複数の費用が内包され、相対的に高コストです。
純粋に運用効率を重視する方は、NISAやiDeCoで低コストのファンドを活用し、死亡保障を掛け捨て定期保険で確保する組み合わせも検討すべきです。
変額保険の解約控除は契約後10年程度まで段階的に発生し、特に前半は高率です。ライフプランの変化で早期解約を余儀なくされると、元本割れのリスクが高くなります。
契約前には、保険期間中に大きな資金需要が生じる可能性をシミュレーションし、解約控除率の推移を確認しておくことが重要です。流動性を重視する家庭は、解約控除のない投資信託や流動性の高い債券ファンドで教育資金を準備し、保障部分を定期保険でカバーするほうが柔軟性を確保できます。
なお、チューリッヒ生命の基本的な情報や強みなどはこちらの記事で解説しています。
この記事のまとめ
フューチャーリンクは死亡保障と長期運用を一契約で実現できる一方、信託報酬や解約控除がリターンを削るため、契約前に費用と運用リスクを数字で把握することが欠かせません。
教育費や老後資金など10年以上先の目的に向けて計画的に積み立てたい人、三大疾病リスクを家計から切り離したい人には有力な選択肢です。反対に、近い将来の資金需要や低コスト運用を重視する場合は投資信託と掛け捨て保険の組み合わせを検討しましょう。
不安が残るときは専門家にシミュレーションを依頼し、コストとリスクを見える化してから意思決定することが安心への近道です。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
関連記事
関連する専門用語
変額保険
変額保険とは、死亡保障を持ちながら、保険料の一部を投資に回すことで、将来受け取る保険金や解約返戻金の金額が運用成績によって変動する保険商品です。 保険会社が提供する複数の投資先から自分で選んで運用することができるため、運用がうまくいけば受け取る金額が増える可能性があります。 ただし、運用がうまくいかなかった場合は、受け取る金額が減ることもあります。保障と資産運用の両方を兼ね備えた商品ですが、元本保証がない点には注意が必要です。投資初心者の方には、仕組みを十分に理解したうえで加入することが大切です。
特別勘定
特別勘定とは、主に保険会社が提供する変額保険や年金商品などで使われる仕組みで、契約者から預かったお金を、会社の他の資産とは分けて管理するための専用の勘定のことです。 この仕組みにより、運用による損益は契約者に直接反映され、保険会社の経営状況とは切り離して資産が守られる仕組みになっています。 たとえば、変額保険では、特別勘定の中で株式や債券などの資産を運用し、その運用結果によって将来受け取る金額が変動します。初心者にとっては、特別勘定は「自分のお金がどのように運用されているかが見える透明な箱」とイメージすると理解しやすいです。
運用関係費用
運用関係費用とは、金融商品を保有している間に日々差し引かれるコストの総称です。投資信託なら信託報酬(運用会社・販売会社・受託銀行の報酬)が代表的ですが、購入時手数料や信託財産留保額、売買委託手数料も含めて把握する必要があります。 変額保険では特別勘定の運用管理費に加え、死亡保障コストや契約管理費が控除されるため、表面利回りと実質利回りの差が大きくなりがちです。商品選定では、目論見書や契約概要で「いつ・いくら差し引かれるか」を必ず確認しましょう。
スイッチング
スイッチングとは、確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)でよく使われる用語で、すでに保有している運用商品を売却し、その資金で別のファンドに乗り換えることを指します。たとえば、安定重視の債券型ファンドから、成長を狙った株式型ファンドに変更するなど、市場環境やライフプランの変化に応じて資産配分を見直すための重要な手段です。 確定拠出年金の仕組みでは、このスイッチングは同一制度内で完結するため、多くの場合、売却や購入に手数料がかからず、非課税で実行できます。ただし、ファンドによっては信託財産留保額やスプレッドなど、乗り換え時にコストが発生する場合もあるため、注意が必要です。 投資初心者にとっては、「口座の中で資産を入れ替える仕組み」と理解するとイメージしやすく、自分の年齢やリスク許容度に応じて運用を柔軟に調整できる便利な機能です。長期的な資産形成を続けるうえで、定期的な見直しとスイッチングの活用は大きな効果を発揮します。
三大疾病保険
三大疾病保険とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかと医師に診断されたとき、あるいは所定の状態に該当したときに、一時金が支払われる保険です。治療費はもちろん、仕事を休むことで減少する収入や、介護・生活環境の整備などの費用にも充てられるため、医療保険や公的医療保障を補完しながら家計への影響を抑える役割を果たします。保険会社や商品によって給付条件や支払上限、診断後の免責期間に違いがありますので、契約前に内容をよく確認し、自分のライフプランや貯蓄状況に合った保障額を選ぶことが大切です。
死亡保険金
死亡保険金とは、生命保険契約において、被保険者が死亡した際に受取人に支払われる保険金のことを指す。受取人や契約形態によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの課税対象となる場合がある。
解約返戻金
解約返戻金とは、生命保険などの保険契約を途中で解約したときに、契約者が受け取ることができる払い戻し金のことをいいます。これは、これまでに支払ってきた保険料の一部が積み立てられていたものから、保険会社の手数料や運用実績などを差し引いた金額です。 契約からの経過年数が短いうちに解約すると、解約返戻金が少なかったり、まったく戻らなかったりすることもあるため、注意が必要です。一方で、長期間契約を続けた場合には、返戻金が支払った保険料を上回ることもあり、貯蓄性のある保険商品として活用されることもあります。資産運用やライフプランを考えるうえで、保険の解約によって現金化できる金額がいくらになるかを把握しておくことはとても大切です。
元本割れリスク
元本割れリスクとは、投資した資金(元本)の価値が減少し、最終的に投資額を下回る可能性があるリスクを指します。株式や投資信託、債券、不動産などの金融商品は市場環境や企業業績、金利動向などの影響を受けるため、価格が変動し、元本を下回ることがあります。特に、株式市場の暴落や景気後退時には元本割れのリスクが高まります。 このリスクを抑えるためには、分散投資や長期投資を活用し、リスク許容度に応じた運用を行うことが重要です。また、定期預金や個人向け国債などの元本保証型の商品と、リスク資産を組み合わせることで、資産全体のリスクを軽減することが可能です。投資を行う際には、元本割れリスクを十分理解し、自身のリスク許容度に合った商品選びを行うことが求められます。
信託報酬
信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。
解約控除
解約控除とは、保険や一部の投資商品を契約期間の途中で解約した場合に、契約者が受け取る解約返戻金などから差し引かれる手数料のことをいいます。特に契約から数年以内など、早い段階で解約した際に高めに設定されていることが多く、実際に受け取れる金額が大きく減ってしまうことがあります。 この制度は、販売時にかかった初期費用や運用の準備にかかるコストを回収するために設けられていますが、契約者にとっては思ったよりも少ない金額しか戻ってこないというリスクにつながります。そのため、商品選びの際には解約控除の有無やその金額、期間などをよく確認し、「途中で解約したらどうなるか」をあらかじめ理解しておくことがとても大切です。長期での運用を前提とした商品には特に注意が必要です。
インデックスファンド
インデックスファンドとは、特定の株価指数(インデックス)と同じ動きを目指して運用される投資信託のことです。たとえば「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」などの市場全体の動きを示す指数に連動するように設計されています。この仕組みにより、個別の銘柄を選ぶ手間がなく、市場全体に分散投資ができるのが特徴です。また、運用の手間が少ないため、手数料が比較的安いことも魅力の一つです。投資初心者にとっては、安定した長期運用の第一歩として選びやすいファンドの一つです。
アクティブファンド
アクティブファンドとは、運用のプロであるファンドマネージャーが、市場の平均を上回るリターンを目指して積極的に銘柄を選んで運用するタイプの投資信託のことです。 具体的には、独自の分析や調査にもとづいて、将来性があると見込まれる企業や、割安と判断される株式などに投資を行います。こうした運用には高度な専門知識と時間が必要となるため、同じ投資信託でも市場平均への連動を目指す「パッシブファンド」より運用コスト(信託報酬など)が高めになる傾向があります。しかし、その分大きなリターンを狙える可能性もある点が魅力です。 ただし、アクティブファンドだからといって必ずしも市場平均を上回るとは限らないことに注意が必要です。投資判断がうまくいかなかった場合は、損失が出たり、パッシブファンドに劣る成績となったりすることもあります。 投資初心者の方は、ファンドマネージャーの運用実績やファンドの方針、運用コストなどをよく調べたうえで、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことが大切です。購入前に「過去の運用成績」や「運用レポート」を確認し、アクティブファンドの特徴を理解してから投資を始めましょう。
団体信用生命保険(団信)
団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んだ人が亡くなったり高度障害になったりした場合に、その時点のローン残高が保険金で返済される保険です。多くの場合、住宅ローンを借りる際に金融機関が加入を条件とすることがあり、略して「団信(だんしん)」とも呼ばれます。 この保険に加入しておけば、万が一のことがあった際に遺族がローンを引き継ぐ必要がなくなり、家に住み続けることができるため、大きな安心材料になります。保障の範囲は、死亡や高度障害に限らず、がんや三大疾病、就業不能までカバーするタイプもあり、ライフスタイルに応じて選ぶことができます。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。
保険金
保険金とは、生命保険や損害保険などの保険契約に基づき、あらかじめ決められた事由が発生したときに保険会社から受取人へ支払われるお金を指します。 たとえば死亡や入院、事故による損害などが起こると、契約内容に応じた金額が支払われます。これは万一の経済的損失を補うために設計されており、受け取った人は生活費や治療費、修理費などに充てることができます。
市場価格調整
市場価格調整は、利率があらかじめ保証されている終身保険・養老保険・個人年金保険などで途中解約や減額、繰上げ受取を行う際に適用される仕組みです。保険会社は契約者から預かった保険料を長期債券などで運用しているため、解約時点の市場金利と契約時(または利率更改時)の市場金利との差によって債券価格が変動します。この価格変動による損益を契約者にも反映させ、公平性を保つのが市場価格調整の目的です。 具体的には、解約時点で残存期間に相当する市場金利を取り、契約時との金利差と残存期間を掛け合わせた調整率を計算し、その分だけ解約返戻金を増減させます。金利が下がっていれば債券価格は上昇するため返戻金が増え、金利が上がっていれば返戻金は減ります。同じ金利差でも残存期間が長いほど増減幅が大きくなるのが特徴です。 なお、市場価格調整はあくまで途中解約や減額などに限定して適用され、満期保険金や死亡保険金、予定利率の更改時点での年金原資などには掛からないのが一般的です。また、契約初期費用を回収する目的で設定される「解約控除」とは仕組みも趣旨も異なりますが、多くの商品で両方が併用されています。 保険会社側にとっては、途中解約による資産売却損を契約者とシェアできるため、長期運用前提の商品でも予定利率を比較的高めに設定しやすくなるメリットがあります。一方、契約者側には、金利上昇局面で早期解約すると返戻金が大きく目減りするリスクがあるため、資金の流動性を重視する場合には不向きです。したがって、市場価格調整付きの商品は「長期にわたり保有する資金で加入する」という前提で検討することが重要です。
上皮内新生物
上皮内新生物とは、体の表面や粘膜を覆っている「上皮」という薄い層の内部だけにとどまり、まだ周囲の組織へ浸潤していないごく早期のがん細胞を指します。 臨床上は「ステージ0」や「上皮内がん」とも呼ばれ、病変が上皮の境界を越えていないため、転移リスクが極めて低い段階です。医療保険やがん保険では、従来の「悪性新生物」と区別して保険金額や給付条件が設定されることが一般的で、診断給付金や手術給付金が減額されたり、別建てで保障される場合があります。 そのため、資産運用を目的に保険を選ぶ際には、上皮内新生物がどこまで保障対象か、給付金額はいくらかを確認しておくことが、安心とコストのバランスを測るうえで大切です。
主契約
主契約とは、生命保険や医療保険などの保険商品において、基本となる保障内容を規定する中心的な契約部分を指します。投資型保険でも、まず主契約が土台となり、そのうえで必要に応じて追加保障やサービスを付加する「特約」を組み合わせる仕組みが一般的です。 主契約があることで保険としての骨格が成立し、保険料の算定や契約期間、解約返戻金の有無などの重要な条件が定められます。投資初心者の方にとっては、特約に目が行きがちですが、まず主契約が何を保障し、どのような運用や保障期間になっているかを理解することが、資産運用として保険を活用するうえでの第一歩となります。