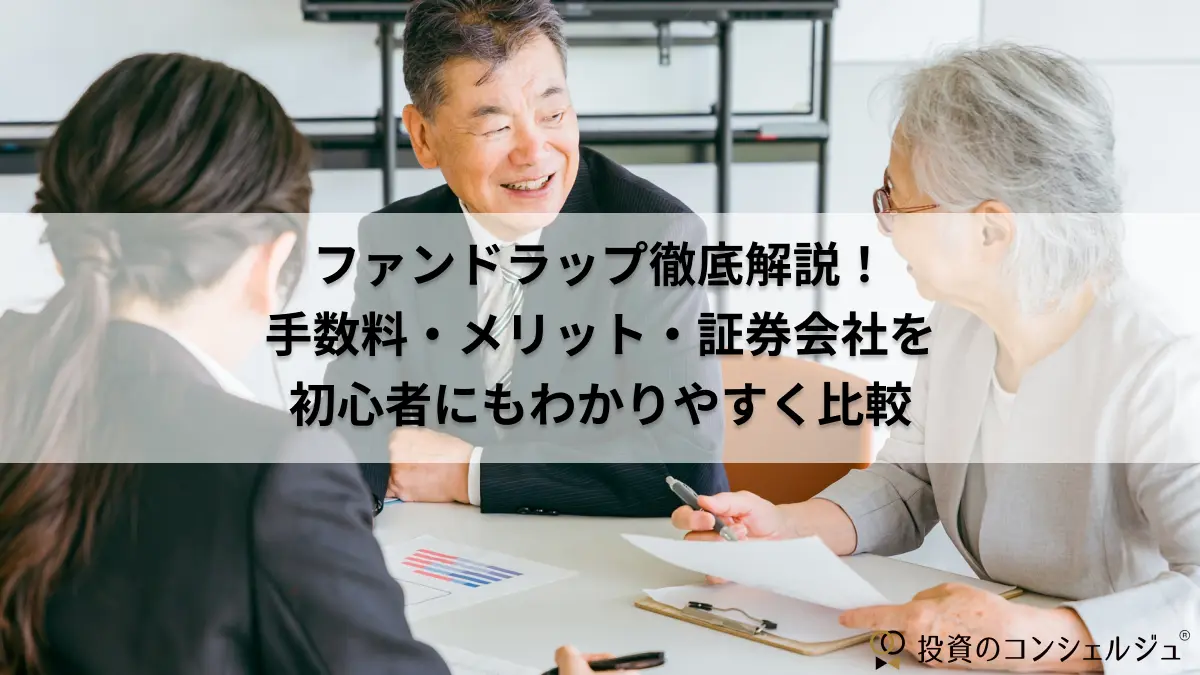富裕層が注目する「ダイレクト・インデックス」とは?カスタマイズ運用の最前線
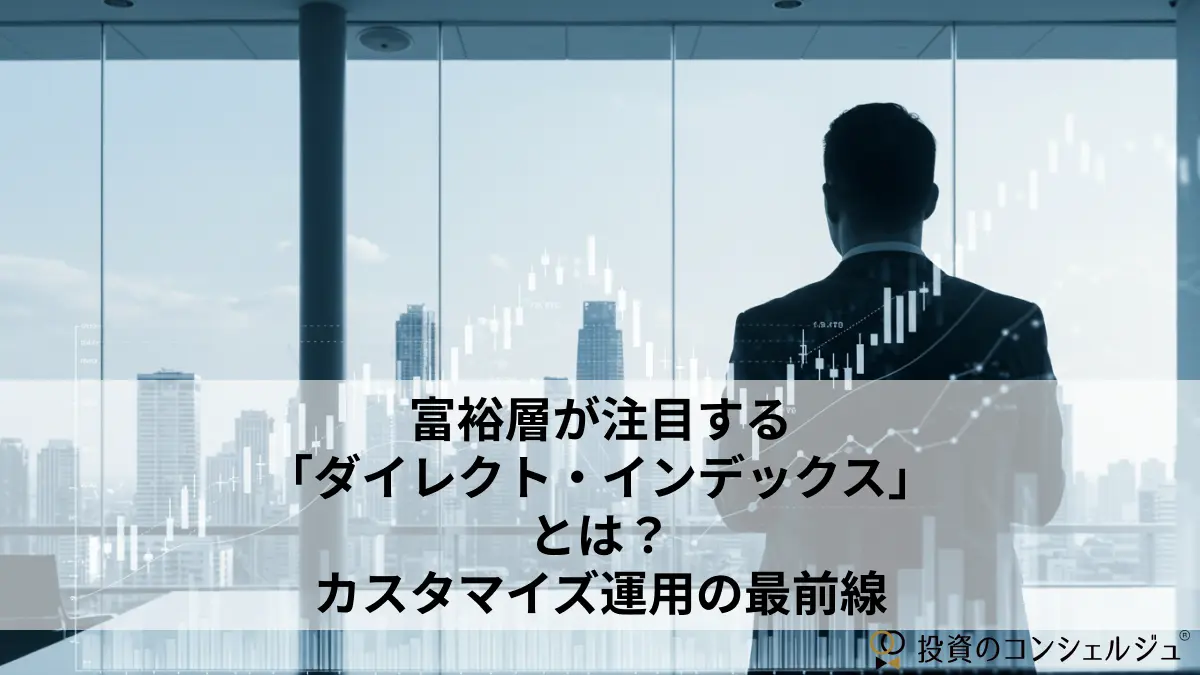
富裕層が注目する「ダイレクト・インデックス」とは?カスタマイズ運用の最前線
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.04
更新:
2025.06.02
いま富裕層の間で注目を集めているのが、「ダイレクト・インデックス」。従来のインデックスファンドとは一線を画し、節税・柔軟性・透明性を兼ね備えたカスタマイズ可能な運用手法です。アメリカで急成長中の手法を簡単にそのポイントを解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むことで、これまでインデックス投資に満足していた投資家も、新たな可能性に気づくことができます。特に、損出しによる節税効果や、ESGやファクター戦略などによるカスタマイズ性の高さに驚くはずです。さらに、実際に米国での導入事例(WealthfrontやParametric)や、日本での実践方法(ファンドラップやSMAの活用)まで網羅しており、すぐにでも行動に移せる知見が得られます。加えて、個人と法人での活用の違いも丁寧に整理されているため、読者の立場に合わせた応用が可能。読後には「これは単なる流行ではなく、次の運用戦略の柱になり得る」と確信できるでしょう。
目次
ダイレクト・インデックスとは何か
ダイレクト・インデックス(Direct Indexing)とは、日経平均やS&P500といった株価指数に似た運用を目指すときに、インデックスファンドやETF(上場投資信託)などを買うのではなく、その指数に含まれる株を自分で直接買って運用する方法です。
この方法を使うと、たとえば値下がりした株を売って損失を出すことで、税金を減らす(節税する)ことができたり、自分の好みや投資方針に合わせてポートフォリオを自由にカスタマイズできるというメリットがあります。
「ダイレクト・インデックス」という名前は最近よく聞くようになりましたが、考え方自体は30年ほど前から存在しています。ただし、これまでは売買や管理の手間やコストがかかるため、主に超富裕層向けの特別なサービスとして提供されてきました。
しかし近年では、テクノロジーの進歩や株式取引の手数料が無料となる「ゼロコミッション」の広がりにより、一般の投資家にとっても利用しやすい環境が整いつつあります。
実際、アメリカでは2020年以降、大手の証券会社や資産運用会社がこの分野のスタートアップや専門企業を次々に買収しており、モルガン・スタンレーによるParametric社、ブラックロックによるAperio社の買収などが話題になっています。このような動きから、ダイレクト・インデックスは「資産運用の次なるフロンティア」として大きな注目を集めています。
ダイレクト・インデックスのメリット
ダイレクト・インデックスがもたらす主なメリットは、大きく「税制上の利点」と「ポートフォリオ構築の柔軟性」の二点にまとめられます。
税制メリット(税負担の最適化)
ダイレクト・インデックスの大きな魅力のひとつは、税金を減らせるチャンスがあるという点です。
株の値動きはバラバラなので、全体の株価指数が上がっている年でも、いくつかの銘柄は値下がりしていることがあります。ダイレクト・インデックスでは、そのような値下がりしている株をわざと売って損失を確定させ、他の利益と相殺して税金を減らすという工夫ができます。
このやり方は「タックス・ロス・ハーベスティング(Tax-loss Harvesting)」、日本語で言うと「損出し」と呼ばれていて、ダイレクト・インデックスの中心的な戦略です。
たとえば2023年、S&P500指数は26%以上も上がりましたが、その中の171社は1年を通してマイナスでした。また、全銘柄の7割以上が一時的に15%以上も下落しています。つまり、指数が好調な年でも損失を出している株はあるということです。ダイレクト・インデックスでは、そうした銘柄をうまく活用して節税することができます。
損失を出した株を売った後は、代わりに似た動きをする別の銘柄を買うことで、ポートフォリオの形(指数との連動性)を保つのが一般的です。
一方、インデックスファンドやETFでは、ファンドの中で損失が出ていても、投資家自身がその損失を税金対策に使うことはできません。ダイレクト・インデックスなら、投資家が個別株を直接持っているため、自由に損失を活用できるのです。
このような損出しを年間を通じて計画的に行うことで、最終的に手元に残るお金(アフター税リターン)を増やすことが期待できます。実際、専門機関の分析によると、1〜2%ほどリターンが増える可能性があるとされています。これは手数料の差を上回る効果であり、特に高い税率の人にとっては非常に大きなメリットです。
もちろん、株の売買を頻繁に行うために、指数とのズレ(トラッキングエラー)や売買コストが増える可能性もありますが、その分のデメリットを上回るだけの節税効果が見込めるとされています。
ポートフォリオ構築の柔軟性(自由にカスタマイズできる)
ダイレクト・インデックスのもう一つの大きな魅力は、ポートフォリオを自由にカスタマイズできるという点です。
ふつうのインデックスファンドは、指数に合わせた「決まった形」で運用されますが、ダイレクト・インデックスでは投資家ごとに細かく中身を調整できるため、より自分に合った運用ができます。たとえば、次のような調整が可能です。
ESGや価値観に沿った調整
「この業界の企業には投資したくない」「環境に悪影響のある会社は除きたい」といった考えがある場合、その企業の株を外すことができます。たとえば、化石燃料関連やタバコ産業など、自分の価値観に合わない銘柄を指数から除外または割合を減らすことができます。
ファクター投資を取り入れる
「割安株(バリュー)を多めに入れたい」「最近伸びている企業(モメンタム)を重視したい」といった要望にも対応できます。スマートベータETFのようにあらかじめ決まった枠組みに頼らず、個別に銘柄を調整することで、自分好みの投資スタイルを反映させることが可能です。
特定リスクの回避
たとえば、自分の勤務先の株をすでにたくさん持っている人や、ある業種に資産が偏っている人の場合、ポートフォリオの中でその銘柄や業種を除外することができます。これにより、資産の偏り(リスク)を避けて、バランスの取れた分散投資ができます。
このように、ダイレクト・インデックスは「ただ指数に合わせる」だけではなく、投資家の価値観・目的・リスクに合わせて、自由に調整できるオーダーメイドの運用が可能です。
だからこそ、特に富裕層など個別のニーズが大きい投資家にとって、非常に魅力的な新しい選択肢となっています。
ダイレクト・インデックスのデメリット
ここまで、ダイレクト・インデックスのメリットを紹介してきましたが、すべての投資家にとって完璧な手法というわけではありません。実際には、以下のようなデメリットや注意点も存在します。
運用・管理の手間がかかる
インデックスファンドやETFであれば、1つの商品を保有するだけで指数に連動する投資ができますが、ダイレクト・インデックスでは多数の個別株を自分で保有・管理する必要があります。定期的なリバランスや損出しを行うためには、日常的にポートフォリオをチェックし、売買の判断を行う手間がかかります。
特に自力で運用する場合、構成銘柄の入れ替えや市場変動への対応など、ある程度の知識やツールが求められる点にも注意が必要です。
トラッキングエラーの発生リスク
税金対策のために一部の銘柄を売却し、似た動きをする別の銘柄に入れ替えるといった操作を行うことで、元の指数との乖離(トラッキングエラー)が発生する可能性があります。特に節税を優先する運用では、指数との連動性が犠牲になることもあります。
売買コストや税務管理の複雑さ
頻繁に個別株を売買するため、取引手数料やスプレッド(買値と売値の差)が累積すると、運用コストがかさむ場合があります。また、日本では損出しを行った場合でも確定申告が必要になることが多く、税務処理の手間が増えるという課題もあります。自動化されたサービスを使わない場合は、こうした管理を自分で行う必要があります。
ある程度の資産規模が求められる
ダイレクト・インデックスでは、指数に含まれる多数の銘柄に分散投資することが基本となるため、ある程度まとまった運用資産がないと十分な効果を得るのが難しいという側面があります。たとえば、S&P500やTOPIXのような指数を再現するには、数十銘柄以上を保有する必要があり、数十万円〜数百万円単位の資金が必要になることもあります。
ファンドやETFのように1本で手軽に分散できる商品と比べると、少額投資との相性はあまり良くないというのが実情です。もちろん、自分で銘柄数を絞って応用することも可能ですが、その分指数との乖離や分散効果の低下には注意が必要です。
どんな投資家に向いているか?
以上のような特徴を踏まえると、ダイレクト・インデックスは次のような投資家に特に向いているといえます。
一定以上の資産を持ち、長期的な視点で節税メリットを最大化したい人
年間を通じたタックス・ロス・ハーベスティングを戦略的に行うことで、アフター税リターンの向上が見込めるため、所得税や住民税の負担が大きい富裕層に特に適しています。
投資の透明性やコントロールを重視する人
どの銘柄をどの比率で保有しているかを自分で把握・調整できるため、投資対象の見える化や、ESGなど個別の価値観に合わせた運用を求める人に向いています。
ある程度の運用知識があり、カスタマイズ性を重視する人
スマートベータ的な戦略やファクター投資を組み合わせたり、業種の偏りを調整したりといった、柔軟な設計が可能な投資スタイルを志向する人には大きなメリットがあります。
米国におけるダイレクト・インデックスの先進事例
アメリカでは、ダイレクト・インデックスを活用した資産運用サービスが、主に富裕層を中心に広がっており、金融業界でも注目を集めています。ここでは、ロボアドバイザーのWealthfront社と、富裕層向け運用の先駆者Parametric社の事例を紹介します。
Wealthfront社:テクノロジーで低コスト自動運用
Wealthfront(ウェルスフロント)は、アメリカの大手ロボアドバイザーです。10万ドル以上の口座残高がある顧客には、米国株の個別銘柄で構成された自動ポートフォリオを提供しています。
Wealthfront社の特徴
- S&P500などの指数構成銘柄を個別に保有し、値下がりした銘柄は自動的に売却して、損出し(タックス・ロス・ハーベスティング)を行います。
- 小型株はETFで補完し、市場全体に近い動きを再現します。
- 残高が50万ドルを超えると、ファクター戦略(スマートベータ)も自動で適用され、より高度な運用になります。
- これらの高度な機能があっても、年0.25%の低コストで利用可能です。
この仕組みは、少額でもテクノロジーの力で本格的なダイレクト・インデックス運用が可能になった好例です。
Parametric社:富裕層向けカスタム運用のパイオニア
Parametric(パラメトリック)は、30年近く前からダイレクト・インデックスを提供してきた老舗企業です。特に富裕層向けにオーダーメイドのポートフォリオ設計を行っており、以下のような特徴があります:
Parametric社の特徴
- 投資家の価値観(例:ESG)や保有資産に応じて個別にポートフォリオを調整。
- 税金面でも、損出しや、含み益株の寄付による節税などの高度な戦略を活用。
- こうした柔軟性と実績により、「ダイレクト・インデックス=Parametric」と評価されるほどの評価。
2020年には、Parametricの親会社がモルガン・スタンレーに買収され、この分野の重要プレイヤーとして注目されました。
従来は最低でも25万ドル程度の資産が必要でしたが、現在はオンラインプラットフォームの活用などで、より多くの富裕層投資家に門戸が開かれつつあります。
この2社の事例からも、ダイレクト・インデックスはテクノロジーと金融の融合により、柔軟かつ効率的な運用を実現する新しい形であることがわかります。
日本におけるダイレクト・インデックスの活用可能性と実践方法
日本でも、ダイレクト・インデックスの考え方は徐々に広がりつつあります。 米国ほど一般的ではないものの、税金対策や柔軟なポートフォリオ構築の手段として、富裕層投資家にとって有望な選択肢となっています。
日本でも節税効果は期待できる
日本では、株式や投資信託で得た利益には約20%の税金がかかりますが、損失が出た場合には、利益と相殺する「損益通算」や、損失を翌年以降3年間繰り越せる制度もあります。
そのため、アメリカで広く行われている損出し(節税目的での損失確定)は、日本でも十分に活用可能です。
また、アメリカでは「ウォッシュセール規則」という制度があり、同じ銘柄を30日以内に買い戻すと損失が認められないという制限がありますが、日本にはこのような規則はありません。 ただし、短期間で同じ銘柄を何度も売買することには、市場取引上の注意点もあるため、同じような値動きをする他の銘柄やETFに乗り換える方法が、より実践的だといえます。
実践方法①:ファンドラップや投資一任口座を活用
証券会社のファンドラップや投資一任サービス(SMA)を使って、担当アドバイザーにポートフォリオのカスタマイズを依頼する方法があります。 特定の銘柄を除外したり、ESGや業種への比重を調整したりと、ダイレクト・インデックスと同じような運用が可能です。
実践方法②:自分で構成銘柄を買って運用
TOPIXや日経平均の構成銘柄を自分で分散して保有し、定期的にリバランス(資産配分の調整)や損出し(節税目的での損失確定)を行う運用方法もあります。 近年はネット証券の進化により、少額でも多くの銘柄を売買できるようになっており、このような運用も現実的になってきました。
ただし、銘柄の管理や調整には一定の手間や知識が必要となるため、専門家のサポートを受けたり、専用のツールを活用したりすることで、より効率的な運用が可能になります。
法人でも損出しは可能?個人との違いと注意点
ダイレクト・インデックスを法人名義で活用し、損出しによる節税を狙うことも理論上は可能です。日本の法人税制でも、有価証券の売却による損益は他の利益と損益通算できるため、決算期前に含み損のある株式を売却し、税負担を圧縮するという戦略が取られることがあります。
ただし、個人投資家とは異なり、法人には以下のような注意点があります。
- 取得原価の管理や会計処理が厳密に求められる:法人では、移動平均法や総平均法に基づいた帳簿処理が必要で、売却時の損益計算が複雑になるケースがあります。
- 決算期直前の売買は税務上リスクがある:節税目的が明確すぎると、税務調査で否認されるリスクがあるため、売買の合理性や目的の説明が重要です。
- 一部の税制優遇が適用されない場合もある:たとえば、みなし配当課税など、法人独自の課税ルールが適用され、期待した節税効果が得られないことがあります。
- 顧問税理士との連携が必須制度上可能であっても、実務上は税務戦略全体の中での位置づけや書類対応が問われるため、専門家のサポートは欠かせません。
このように、法人においてもダイレクト・インデックスを活用した損出しは選択肢の一つになりますが、個人投資家と同じような感覚で運用することはできず、より高い制度理解と体制整備が求められます。
この記事のまとめ
ダイレクト・インデックスは、ただの「高度な投資手法」ではありません。特に節税や分散投資の最適化、さらには自身の価値観や事業構造に合わせた資産設計までを可能にする、いわば「運用のオーダーメイド」。しかしその一方で、トラッキングエラーや税務処理、法人活用の難しさなど、専門的な知識が求められる領域でもあります。もしあなたが、高所得者層や法人経営者として、次の一手を考えているのなら、プロの視点とサポートは不可欠です。信頼できる資産運用の専門家とともに、自分に最適なダイレクト・インデックス戦略を設計してみてはいかがでしょうか。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
ダイレクト・インデックス
ダイレクト・インデックスとは、特定の株価指数(インデックス)に連動するように、自分でその指数に含まれる個別の銘柄を直接保有する投資手法のことです。たとえば、日経平均株価やS&P500といった代表的な指数の構成銘柄を自分の証券口座でひとつひとつ購入して、全体としてインデックスと同じような値動きを目指します。インデックスファンドとは異なり、自分で銘柄を細かく調整できるため、税金対策を行ったり、自分の価値観に合わない企業を除外したりといった柔軟な運用ができるのが特徴です。ただし、ある程度の資金や管理の手間がかかるため、一般的には中上級者向けの運用方法とされています。
インデックスファンド
インデックスファンドとは、特定の株価指数(インデックス)と同じ動きを目指して運用される投資信託のことです。たとえば「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」などの市場全体の動きを示す指数に連動するように設計されています。この仕組みにより、個別の銘柄を選ぶ手間がなく、市場全体に分散投資ができるのが特徴です。また、運用の手間が少ないため、手数料が比較的安いことも魅力の一つです。投資初心者にとっては、安定した長期運用の第一歩として選びやすいファンドの一つです。
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)とは、証券取引所で株式のように売買できる投資信託のことです。日経平均やS&P500といった株価指数、コモディティ(原油や金など)に連動するものが多く、1つのETFを買うだけで幅広い銘柄に分散投資できるのが特徴です。通常の投資信託に比べて手数料が低く、価格がリアルタイムで変動するため、売買のタイミングを柔軟に選べます。コストを抑えながら分散投資をしたい人や、長期運用を考えている投資家にとって便利な選択肢です。
損出し(タックス・ロス・ハーベスティング)
損出し(タックス・ロス・ハーベスティング)とは、保有している投資商品をあえて損が出ているタイミングで売却し、その損失を確定させることで、税金を軽減するための手法です。投資で得た利益には税金がかかりますが、同じ年に出た損失と相殺することで、課税される利益を減らすことができます。たとえば、ある株で10万円の利益が出た場合に、別の株で5万円の損失を損出しすると、実質的に5万円の利益に対してだけ課税される仕組みになります。売却後に同じ銘柄や類似の銘柄を買い直すこともできますが、税務上のルールには注意が必要です。節税を意識した賢い投資戦略のひとつとして活用されています。
トラッキングエラー
トラッキングエラーとは、主にインデックスファンドなどの運用成績が、目標とする指数(たとえば日経平均株価やS&P500など)とどれくらいズレているかを示す指標です。ファンドは基本的に指数に連動するように運用されますが、運用コストや売買のタイミングの違いなどにより、実際の成績が指数と完全に一致することはまれです。 この差が大きいほど、運用が指数とずれていると評価されます。トラッキングエラーが小さいほど、より正確に指数に連動しているとされ、インデックス投資においては重要な確認ポイントとなります。
ESG投資
ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮して行う投資のことです。従来、企業の投資価値は主にキャッシュフローや利益率などの財務情報を基に判断されてきましたが、近年は、環境負荷の低減、社会的責任の遂行、健全な経営体制といった非財務情報も投資判断の重要な指標となっています。 ESGの概念は、2006年に国連が機関投資家向けに「責任投資原則(PRI)」を提唱したことをきっかけに広まりました。ESG要素を投資プロセスに組み込むことで、長期的なリスクを抑えながら持続可能なリターンの向上が期待されます。特に、ESGに積極的に取り組む企業は、規制対応力やブランド価値の向上につながるため、将来的な成長性や安定性の面で投資家の関心を集めています。
ファクター投資(因子投資)
ファクター投資とは、株式などの投資対象を選ぶ際に、特定の「ファクター(要因)」に基づいて投資判断を行う手法です。このファクターとは、過去のデータから長期的にリターンを高めたり、リスクを抑えたりするとされる特徴のことで、代表的なものには「バリュー(割安性)」「モメンタム(勢い)」「サイズ(企業の規模)」「クオリティ(財務の健全性)」などがあります。たとえば、割安な株に投資する「バリュー・ファクター」や、最近値上がりしている株に投資する「モメンタム・ファクター」といった具合です。従来の市場全体に投資する方法よりも、より高いリターンやリスクコントロールを目指せる可能性がある一方で、タイミングや市場環境によって成果が変わるため、しっかりとした理解と戦略が必要です。
スマートベータ指数
スマートベータ指数とは、従来の株価指数のように「時価総額の大きさ」に基づいて銘柄の比重を決めるのではなく、収益性、ボラティリティ(価格変動の大きさ)、配当利回り、バリュエーション(割安度)など、特定の投資戦略やファクター(要因)に基づいて構成される株価指数のことです。これにより、リスクを抑えながら市場平均を上回る成果を目指すことができます。 たとえば、単に大企業が多いというだけで選ぶのではなく、「安定して高配当を出している企業」や「株価の変動が小さい企業」などを組み合わせて、より戦略的なポートフォリオを作るのがスマートベータ指数の考え方です。 初心者の方には、「単なる平均ではなく、ちょっと“かしこく”工夫された指数」とイメージするとわかりやすいでしょう。最近では、ETF(上場投資信託)などでもこの考え方を取り入れた商品が増えており、パッシブ運用とアクティブ運用の中間的な存在として注目されています。
ウォッシュセール規則
ウォッシュセール規則とは、米国の税制において定められているルールで、損失を使った節税(タックス・ロス・ハーベスティング)を制限するための制度です。具体的には、ある投資商品を売却して損失を出したあと、30日以内に同じ銘柄や実質的に同じ銘柄を買い直した場合、その損失は税務上「無効」とみなされ、損失として計上できなくなります。これは、形式的にだけ売買して節税することを防ぐためのルールです。 たとえば、損出しの目的で一度売却してすぐに同じ銘柄を買い戻すような行為がこれに該当します。日本の税制には同様の規則は存在していませんが、米国株など海外資産を運用する場合には注意が必要です。ウォッシュセール規則に違反すると、節税の効果が得られないだけでなく、余計な手間やリスクが発生することもあるため、慎重な取引が求められます。
SMA(投資一任口座)
SMAとは「Separately Managed Account(セパレートリー・マネージド・アカウント)」の略で、日本語では「投資一任口座」と呼ばれます。これは、投資家が証券会社や運用会社などの専門家に運用を一任し、個別に運用してもらう口座のことです。ファンドのように他の投資家と資産をまとめて運用するのではなく、あくまで一人ひとりの投資家の口座単位で運用が行われる点が特徴です。運用方針の設計や銘柄選定などはプロが担当するため、投資の知識や時間がない方でも、本格的な資産運用が可能になります。また、個別運用であることから、資産の透明性が高く、税金対策や柔軟なカスタマイズがしやすいというメリットもあります。その一方で、一定の資産規模が求められることが多く、主に富裕層向けのサービスとされています。
ロボアドバイザー(ロボアド)
ロボアドバイザーとは、投資家のリスク許容度や運用目的に応じて、自動的に資産配分や投資商品を提案・運用するサービスです。利用者は、いくつかの質問に答えるだけで最適なポートフォリオの提案を受けることができ、少額からでも投資を始められるのが特徴です。 ロボアドバイザーには、「提案型(アドバイス型)」と「運用型(投資一任型)」の2種類があります。提案型は、投資家に適したポートフォリオを提案するものの、実際の運用は投資家自身が行います。一方、運用型は、提案だけでなく資産運用もロボアドバイザーが自動で行い、定期的なリバランスも実施します。 主にインデックス運用を中心としたバランス型の商品が提供され、現代ポートフォリオ理論(MPT)を活用した分散投資が行われます。そのため、個別株の選定や細かい資産管理には向いていません。また、投資家の保有資産全体を考慮した包括的なアドバイスを受けることができない点に注意が必要です。 ロボアドバイザーのメリットとして、投資初心者でも簡単に分散投資ができること、感情に左右されない合理的な運用が可能であること、対面の投資アドバイザーと比較して低コストで運用できることが挙げられます。一方で、一定の手数料がかかること、投資家が細かくカスタマイズできないこと、相場急変時の柔軟な対応が難しいことがデメリットとして存在します。 それでも、投資初心者や手間をかけずに資産運用を始めたい人にとって、ロボアドバイザーは手軽に利用できるサービスとして人気を集めています。
ファンドラップ
ファンドラップは、金融機関が顧客から資産運用を一任され、顧客の目標やリスク許容度に応じてポートフォリオを構築・管理するサービスです。顧客の資産を複数の投資信託やETFなどに分散投資し、運用を行います。運用内容や資産配分の調整(リバランス)は専門家が行い、定期的な運用状況の報告も提供されます。 主に、初心者や忙しい投資家が利用することが多く、手数料はファンドラップ・フィーとして一括で支払う形式が一般的です。この手数料には運用管理費やアドバイス料が含まれます。
損益通算
投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産運用における投資対象の組み合わせを指します。分散投資を目的として、株式、債券、不動産、オルタナティブ資産などの異なる資産クラスを適切な比率で構成します。投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを設計し、リスクとリターンのバランスを最適化します。また、運用期間中に市場状況が変化した場合には、リバランスを通じて当初の配分比率を維持します。ポートフォリオ管理は、リスク管理の重要な手法です。