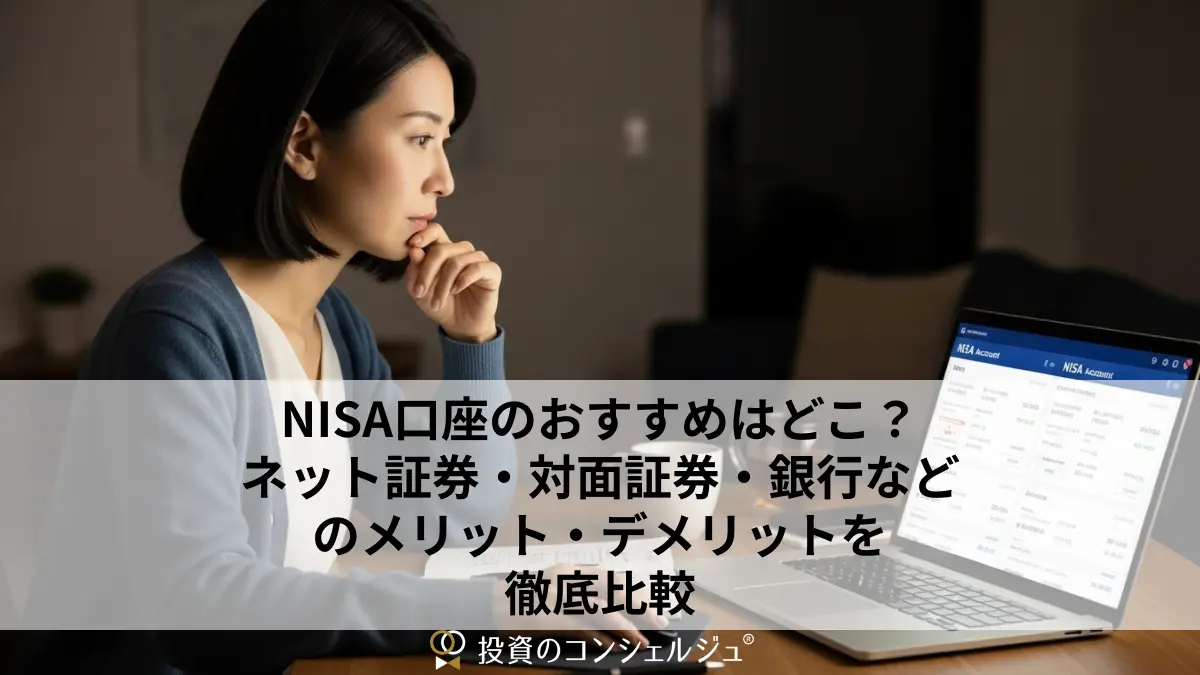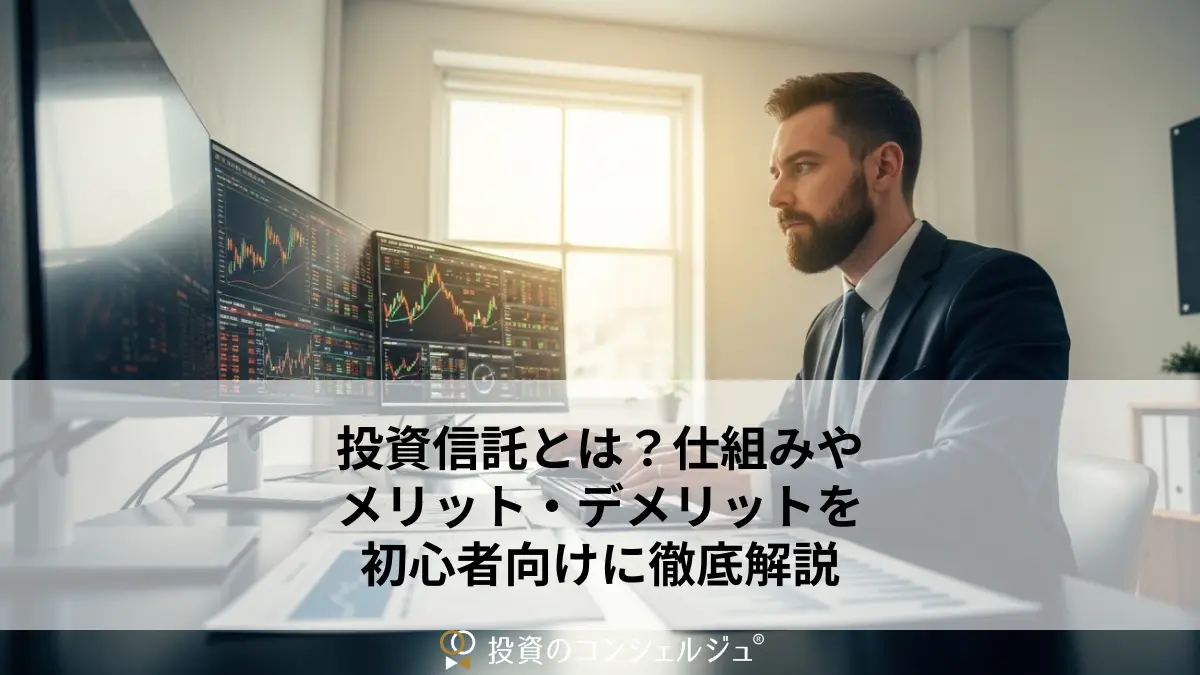資産運用はしないほうがいい?初心者にありがちな3つの失敗例とリスクを踏まえた運用例を徹底解説
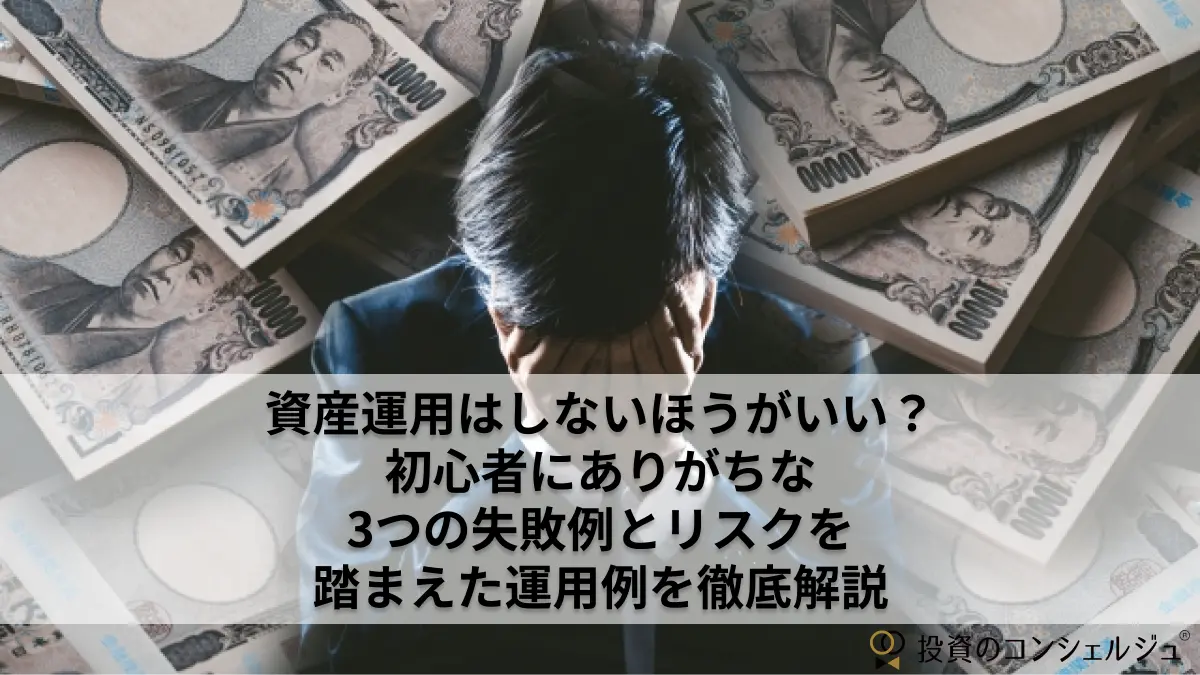
資産運用はしないほうがいい?初心者にありがちな3つの失敗例とリスクを踏まえた運用例を徹底解説
執筆者:
公開:
2025.01.31
更新:
2025.12.09
「資産運用をしないと将来が不安」と言われる一方で、損失が怖くて一歩踏み出せない、あるいは今の投資を続けるべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、資産運用と定期預金の違い、代表的なリスク要因やデメリット、「投資をやめた方がよい・まだ始めない方がよい」ケースを整理し、自分にとって妥当な選択を考えるための視点を解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事では、資産運用の基本と定期預金との違い、代表的なリスク要因・デメリットを体系的に理解できます。自分の収入や貯蓄、リスク許容度を踏まえて「今は資産運用をすべきか/見送るべきか」を冷静に判断し、無理のない運用方針を選べるようになります。結果として、「投資をやめたほうがいい人・続けてもよい人」の違いがわかり、不安に流されない判断軸を持てます。
「資産運用はしないほうがいい」と言われる理由!典型的な失敗例3選
退職金などの資産は、あなたの老後の生活を左右する重要なお金です。そのため、資産運用は慎重に行う必要があります。資産運用を始める前に、よくある失敗例を理解しておけば、典型的な罠を避けることができます。
ここでは、典型的な失敗パターンについて解説します。
失敗例1:一発を狙った過度なリスクの投資
高いリターンを期待するあまり、リスクを過大に取ることは、資産運用でよくある失敗の一つです。ハイリターンな投資先は同様にハイリスクとなり、運用成果が不安定です。
例えば、急成長中の企業の株に資産のほとんどを一点集中するような行動がこれに当たります。こうした行動は、資産運用や投資というよりも、運任せの投機やギャンブルに近いものです。
たしかに、この企業が大きく成長すれば、資産が数年で倍増する可能性はあります。しかし、その確率は高くありません。急成長したベンチャー企業の株価が一時的に上昇しても、その後成長が止まり、株価が急落してしまうケースはよく見られます。
- 大きなリターンの裏には大きなリスクが発生します。リターンに目がくらんだ、過度なリスク取りは、市場の変動によって大きな損失を招く可能性があります。資産運用においてリスクとリターンのバランスを適切に取ることは非常に重要です。自分の考えがバランスの取れているものなのか、資産運用を本格化する前に専門家のアドバイスを求めることはリスク管理において有効な手段となるでしょう。
失敗例2:レバレッジを使った無理な資産運用
レバレッジとは、少ない手持ち資金(証拠金)を担保に、実際の資金の何倍もの金額で取引できる仕組みです。多くの人はレバレッジというとFXを思い浮かべるかもしれませんが、株式や投資信託でもレバレッジを使うことができます。
例えば、100万円の証拠金を使って、300万円分の株を取引する場合、これが「3倍のレバレッジを掛けた状態」です。この場合、株価が1割上昇すると、レバレッジなしでは100万円が110万円(利益10万円)になりますが、3倍のレバレッジを掛けていると300万円の1割、つまり30万円の利益を得られます。
- しかし、逆に株価が1割下落すると、レバレッジなしでは100万円が90万円(損失10万円)で済みますが、3倍のレバレッジでは300万円が270万円に減少し、損失は30万円に拡大します。この損失は証拠金から差し引かれるため、証拠金が70万円に減ってしまいます。
このように、レバレッジは少ない資金で大きな利益を狙える一方、損失もその分大きくなるという特徴があります。投資と投機の違いに関しては、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
失敗例3:SNSや口コミなど誤った情報に基づく投資
誤った情報をもとにした投資は、資産運用でよくある失敗の一つです。不確かな情報や誤解を招く宣伝に惑わされることで、不適切な判断をしてしまうケースがあります。
例えば、証券会社の言われるままに投資を始める、友人や知人の口コミだけで投資先を決める、あるいは「絶対に儲かる」「このチャンスを逃したら損」といった誇大広告に引き込まれることが挙げられます。こうした言葉は、あなたの資産を引き出すことが目的で、あなたの資産を増やすことを保証するものではありません。そのため、リスクを小さく説明し、あたかも成功が確実であるかのように見せかける場合が多いのです。
また、知識が浅い友人や知人から、「この方法で儲かった」と勧められることもあります。しかし、なぜその方法で成功したのかを正確に説明できる人は少なく、その成功が偶然によるものだった場合、あなたが同じように成功する保証はありません。
- 資産運用を成功させるには、信頼できる情報源から正確な情報を集め、冷静に判断することが重要です。また、投資を始める前に、自分の目的やリスク許容度を明確にし、それに合った投資先を選ぶ必要があります。焦って情報に振り回されると、本来の目的を見失い、不要なリスクを背負う原因になりかねません。
信頼できる専門家に相談しつつ、自分自身でも情報を集め、冷静に判断しながら進めることが、安心して資産運用を行うための鍵となります。投資のコンシェルジュでは、資産運用の専門家と無料で相談いただけます。是非お気軽にご利用ください。
投資を始める前に知っておくべき資産運用におけるリスクとは?
通常、「リスク」とは将来的に損をする可能性や危険性のことを指します。しかし、資産運用における「リスク」とは、投資資産の価格が変動する大きさのことを意味します。
例えば、価格変動が大きい「ハイリスク」の資産は、価格が上がれば大きな利益を得られる反面、価格が下がったときの損失も大きくなります。一方、「ローリスク」の資産は、価格の変動が小さいため、利益も損失も少額で安定しています。
資産運用では、この価格変動の要因(リスク要因)を理解することが大切です。投資初心者の方に認識いただきたい主なリスクは以下の5つです。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 価格変動リスク | 投資対象の資産(株式や債券など)の価格が市場の需給や経済状況によって上下するリスクです。価格が下落すれば損失を被る可能性があります。 |
| 金利変動リスク | 金利が変動することで資産の価値や収益に影響を与えるリスクです。例えば、金利が上がると債券の価格が下がることがあります。 |
| 信用リスク | 投資対象の企業や国が財務的な問題に陥り、借金を返せなくなるリスクです。この場合、投資した資産の価値が大きく減少する可能性があります。 |
| 為替変動リスク | 外国通貨建ての資産を持っている場合、通貨の価値が変動することで資産価値が上下するリスクです。例えば、外貨の価値が下がると、その分資産価値も減少します。 |
| カントリーリスク | 投資対象国の政治・経済・社会状況が不安定になることで、資産の価値に影響を与えるリスクです。政策変更や経済危機などが原因で、企業や通貨の価値が変動することがあります。 |
このように、資産運用にはさまざまなリスクが伴います。そのリスクの要因は、国際情勢、各国の政治や経済、企業の経営状況など、複雑に影響し合っています。そのため、安定した資産運用を行うためには、リスクを1つに集中して影響度を大きくしすぎないように分散することが重要なのです。
資産運用を「しないほうがいい」「まだ始めないほうがいい」人つの特徴
資産運用は誰もが今すぐ始めるべきものではありません。家計の土台が整っていない状態で投資をスタートすると、想定外の出費やライフイベントで資金を取り崩さざるを得なくなり、本来得られるはずの長期運用のメリットを失ってしまいます。
以下に挙げる5つの特徴に当てはまる場合は、まず家計の基盤を固めることを優先しましょう。すべてクリアしてから資産運用を検討しても、決して遅くはありません。
生活防衛資金が確保できていない
生活防衛資金とは、失業や病気、災害など予期せぬ事態に備えて確保しておく生活費のことです。この資金がないまま投資を始めると、急な出費が発生した際に運用中の資産を売却せざるを得ず、損失を確定させてしまうリスクがあります。
一般的な目安は「生活費の3〜6ヶ月分」とされています。会社員であれば生活費の3ヶ月〜6ヶ月分、フリーランスや自営業者は6ヶ月〜1年分を確保しておきましょう。
なお、生活防衛資金は家族構成や働き方によっても必要額が異なります。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。
2〜3年以内に使う予定資金で増やそうとしている
結婚式費用、住宅購入の頭金、車の買い替えなど、近い将来に使途が決まっているお金を投資に回すのは避けるべきです。株式や投資信託は短期的に価格が大きく変動する可能性があり、必要なタイミングで元本割れしているケースも珍しくありません。
- 投資の基本原則は「長期運用」です。金融庁のデータでも、保有期間が20年を超えると元本割れのリスクが大幅に低下するとされています。逆に言えば、2〜3年程度の短期間では、相場の波に左右されやすく安定したリターンは期待しにくいのです。
使途と時期が明確な資金は、元本保証のある定期預金や個人向け国債など、安全性の高い商品で管理しましょう。投資に回すのは「10年以上使う予定のないお金」が原則です。
目標・目的がない/勉強・情報収集をまったくしたくない
「なんとなく周りがやっているから」「銀行に勧められたから」という理由だけで投資を始めると、失敗するリスクが高まります。目標がなければ適切な運用期間やリスク許容度を設定できず、相場が下落したときに慌てて売却してしまいがちです。
また、投資には最低限の知識が必要です。信託報酬や為替リスク、複利効果といった基本用語を理解せずに金融商品を購入すると、予想外のコストや損失を被る可能性があります。
「老後資金として65歳までに2,000万円貯めたい」「教育費として15年後に500万円用意したい」など、具体的なゴールを設定しましょう。目標が明確になれば、毎月の積立額や選ぶべき商品も自然と見えてきます。
元本割れが少しでも耐えられず、値動きで生活に支障が出る
投資には必ず価格変動リスクが伴います。株式市場では年に数回、10%以上の下落が起きることも珍しくありません。こうした値動きを見るたびに不安で眠れなくなったり、日常生活に支障が出たりする場合は、投資を始める準備が整っていないといえます。
まずは少額から始めて値動きに慣れるか、元本保証型の商品から検討するのも一つの方法です。心理的な負担なく続けられる範囲で投資することが、長期運用を成功させるカギとなります。
リスク許容度は、年齢や資産額などによっても左右されます。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
資産運用はしない方がいい?失敗例から学ぶなら資産運用したほうが断然いい!3つの理由
「資産運用はしない方がいい?」「資産運用はリスクがあるから、貯金のほうが安心なのでは?」という質問がよくあります。
何も考えずにやる、ギャンブルや投機のようにやってしまうなら、その通りやらないほうがいいです。しかし、資産運用でよくある失敗例を踏まえた上で、リスクとリターンのバランスを考えながら資産運用を行えば、むしろ預貯金だけでお金を管理するよりも大きなメリットと安定性が得られます。
資産運用は、よくある失敗例を踏まえれば、安心して資産を増やし、生活を安定させられる有望な手段です。そのためにも、どのような失敗例があり、小さい成功を積み上げるためにどのようなことを考えればいいのか、ということをデータに基づき親身に相談してくれる専門家に相談してみることがおすすめです。
インフレと増税で現金の実質価値が目減りするから
日本では長らくデフレが続いていましたが、近年は物価上昇が顕著になっています。日本の年間インフレ率は2025年10月に3.0%に上昇し、9月の2.9%から上昇し、7月以来の最高値を記録しました。
また、2024年平均では、生鮮を除く総合が2.5%上昇の107.9だった。3年連続で2%超の水準となるのは1989年〜1992年に4年連続で2%超をつけて以来、約30年ぶりです。
一方、普通預金の金利は依然として0.2%前後にとどまっています。仮にインフレ率が年2%で続くと、100万円の実質的な購買力は10年後に約82万円相当まで目減りする計算です。
- さらに、社会保険料の引き上げや将来的な増税の可能性も考慮すると、預貯金だけでは資産を「守る」ことすら難しくなっています。インフレ率を上回るリターンを目指す資産運用は、お金の価値を維持するための「守りの戦略」ともいえるのです。
ライフイベント資金(住宅・教育・老後)を預貯金だけで賄うのは厳しいから
人生には「住宅資金」「教育資金」「老後資金」という三大支出があります。それぞれの目安金額を見てみましょう。
| ライフイベント | 必要資金の目安 | 出典・補足 |
|---|---|---|
| 住宅購入 | 3,000万〜5,000万円 | 住宅金融支援機構の調査による |
| 教育費(幼稚園〜大学) | 約1,000万〜2,500万円 | 公立/私立によって大きく変動 |
| 老後資金 | 2,000万〜3,000万円 | 年金以外に必要とされる金額 |
これらの資金を預貯金だけで準備しようとすると、毎月の貯蓄額はかなりの負担になります。たとえば、30歳から60歳までの30年間で3,000万円を貯めるには、毎月約8.3万円の積立が必要です。しかし、年利3%で運用できれば、毎月約5.2万円の積立で同じ金額に到達できます。
NISA・iDeCoなど非課税枠を使わないことが大きな機会損失になるから
通常、投資で得た利益には約20.315%の税金がかかります。しかし、NISAやiDeCoといった国の制度を活用すれば、この税金がゼロになるか、大幅に軽減されます。
新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠を合算すると360万円まで投資可能です。生涯の非課税保有限度額は1,800万円に設定されており、この枠内であれば運用益に税金がかかりません。
iDeCoでは運用益の非課税に加え、①掛金が全額所得控除される(所得税・住民税の負担が減ります)、②iDeCo内での運用益は非課税となる、③受け取り時にも控除の対象となります。
たとえば年収500万円の会社員が毎月2万円をiDeCoに拠出した場合、年間で約4.8万円の節税効果が期待できます。30年続ければ、節税だけで約144万円のメリットになる計算です。
これらの制度を使わないことは、国が用意した「お得な枠」をみすみす見逃しているのと同じです。投資を始めるなら、まずNISAやiDeCoの活用を検討しましょう。詳細は、以下の記事もあわせてご覧ください。
資産運用のリスク分散にはグローバル分散投資が初心者におすすめ
「卵を一つのかごに入れない」という言葉の通り、リスク分散は資産運用の基本です。異なる種類の資産や地域に投資を分けることで、特定のリスクに依存せず、資産全体の安定性を高められます。
中でも「グローバル分散投資」は、株式、債券、不動産など複数の資産と、国・地域・通貨の分散を組み合わせることで、リスクを抑えつつ安定した成長を追求できる方法です。これは特に、投資初心者や退職金の運用を検討している方に向いています。
投資の種類は、こちらの記事でまとめて紹介しています。「自分に合った商品がわからない」という方は、参考にしてみてください。
この記事のまとめ
この記事では、資産運用と定期預金の違い、主なリスク要因やデメリット、「投資をやめたほうがよい・見送るべき」ケースを整理してきました。最後は、あなたの収入や貯蓄、家計の安定度、心理的な許容度を一度改めて棚卸しし、「今は守りを重視するのか、少しずつ攻めに転じるのか」を言語化してみてください。不安や迷いが残る場合は、一人で抱え込まず、専門家への相談も検討しましょう。投資のコンシェルジュでは無料で相談できるため、お気軽にご利用ください。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
関連記事
関連する専門用語
リスク
リスクとは、資産運用において、期待している結果とは異なる結果が生じる可能性のことを指します。具体的には、投資による損失が発生するかもしれない不確実性を意味しますが、必ずしも悪い結果だけを指すわけではなく、期待以上の利益が出る可能性もリスクの一部とされます。リスクには、株価の変動、金利の変動、為替レートの変動などさまざまな種類があり、それぞれに応じた対策が求められます。資産運用を行う上では、自分がどの程度のリスクを受け入れられるかを理解し、それに応じた投資戦略を立てることが非常に重要です。
リターン
リターンとは、投資によって得られる利益や収益のことを指します。たとえば、株式を購入して値上がりした場合の売却益(キャピタルゲイン)や、債券の利息、投資信託の分配金(インカムゲイン)などがリターンにあたります。 これらを合計したものは「トータルリターン」と呼ばれ、投資の成果を総合的に示す指標です。リターンは、元本に対してどれだけ増えたかを「%(パーセント)」で表し、特に長期投資では「年率リターン」で比較されることが一般的です。 リターンが高いほど投資先として魅力的に感じられますが、そのぶんリスク(価格変動の可能性)も高くなる傾向があるため、自分の目的やリスク許容度に応じて、適切なリターンを見込むことが大切です。
分散投資
分散投資とは、資産を安全に増やすための代表的な方法で、株式や債券、不動産、コモディティ(原油や金など)、さらには地域や業種など、複数の異なる投資先に資金を分けて投資する戦略です。 例えば、特定の国の株式市場が大きく下落した場合でも、債券や他の地域の資産が値上がりする可能性があれば、全体としての損失を軽減できます。このように、資金を一カ所に集中させるよりも値動きの影響が分散されるため、長期的にはより安定したリターンが期待できます。 ただし、あらゆるリスクが消えるわけではなく、世界全体の経済状況が悪化すれば同時に下落するケースもあるため、投資を行う際は目標や投資期間、リスク許容度を考慮したうえで、計画的に実行することが大切です。
インデックス
インデックス(Index)は、市場の動きを把握するための重要な指標です。複数の銘柄を一定の基準で組み合わせることで、市場全体や特定分野の値動きを分かりやすく数値化しています。 代表的なものには、日本の株式市場を代表する日経平均株価やTOPIX、米国市場の代表格であるS&P500などがあります。これらのインデックスは、投資信託などの運用成果を評価する際の基準として広く活用されており、特にパッシブ運用(インデックス運用)では、この指標と同じような値動きを実現することを目標としています。
レバレッジ
レバレッジとは、借入金や証拠金取引など外部資金を活用して自己資本以上の投資規模を実現する手法です。利益の拡大が期待できる一方、市場の下落や金利の変動で損失が膨らみやすく、追加証拠金(追証)が必要になる場合やロスカットが発生するリスクも高まります。 また、借入金利や手数料などのコストが利益を圧迫する可能性があるため、ポジション管理やヘッジ手法を含めたリスク管理が不可欠です。レバレッジによる損益変動幅が大きくなることで精神的な負担も増えやすい点にも注意が必要です。最終的には、投資目的やリスク許容度を考慮し、適切なレバレッジ水準を設定することで、資産運用の効率を高めつつリスクを抑えることが重要となります。
ドルコスト平均法
ドルコスト平均法とは、一定の金額を定期的に投資する方法です。価格が高いときは少なく、価格が低いときは多く買えるため、購入価格が平均化され、リスクを分散できます。市場のタイミングを読む必要がないため、初心者に最適な方法とされています。長期投資で効果を発揮し、特に投資信託やETFで利用されることが多い手法です。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)とは、証券取引所で株式のように売買できる投資信託のことです。日経平均やS&P500といった株価指数、コモディティ(原油や金など)に連動するものが多く、1つのETFを買うだけで幅広い銘柄に分散投資できるのが特徴です。通常の投資信託に比べて手数料が低く、価格がリアルタイムで変動するため、売買のタイミングを柔軟に選べます。コストを抑えながら分散投資をしたい人や、長期運用を考えている投資家にとって便利な選択肢です。
信用リスク(クレジットリスク)
信用リスクとは、貸し付けた資金や投資した債券について、契約どおりに元本や利息の支払いを受けられなくなる可能性を指します。具体的には、(1)企業の倒産や国家の債務不履行(いわゆるデフォルト)、(2)利払いや元本返済の遅延、(3)返済条件の不利な変更(債務再編=デット・リストラクチャリング)などが該当します。これらはいずれも投資元本の毀損や収益の減少につながるため、信用リスクの管理は債券投資の基礎として非常に重要です。 この信用リスクを定量的に評価する手段のひとつが、格付会社による信用格付けです。格付は通常、AAA(最上位)からD(デフォルト)までの等級で示され、投資家にとってのリスク水準をわかりやすく表します。たとえば、BBB格付けの5年債であれば、過去の統計に基づく累積デフォルト率はおおよそ1.5%前後とされています(S&Pグローバルのデータより)。ただし、格付はあくまで過去の情報に基づいた「静的な指標」であり、市場環境の急変に即応しにくい側面があります。 そのため、市場ではよりリアルタイムなリスク指標として、同年限の国債利回りとの差であるクレジットスプレッドが重視されます。これは「市場に織り込まれた信用リスク」として機能し、スプレッドが拡大している局面では、投資家がより高いリスクプレミアムを求めていることを意味します。さらに、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の保険料率は、債務不履行リスクに加え、流動性やマクロ経済環境を反映した即時性の高い指標として、機関投資家の間で広く活用されています。 こうしたリスクに備えるうえでの基本は、ポートフォリオ全体の分散です。業種や地域、格付けの異なる債券を組み合わせることで、特定の発行体の信用悪化がポートフォリオ全体に与える影響を抑えることができます。なかでも、ハイイールド債や新興国債は高利回りで魅力的に見える一方で、信用力が低いため、景気後退時などには価格が大きく下落するリスクを抱えています。リスクを抑えたい局面では、投資適格債へのシフトやデュレーションの短縮、さらにCDSなどを活用した部分的なヘッジといった対策が有効です。 投資判断においては、「高い利回りは信用リスクの対価である」という原則を常に意識する必要があります。期待されるリターンが、想定される損失(デフォルト確率×損失率)や価格変動リスクに見合っているかどうか。こうした視点で冷静に比較検討を行うことが、長期的に安定した債券運用につながる第一歩となります。
カントリーリスク
カントリーリスクとは、ある国に関連した投資やビジネスを行う際に、その国特有の事情によって損失が生じるおそれのあるリスクのことをいいます。たとえば、政権交代や政治不安、戦争、法制度の変更、為替の急変、債務不履行(デフォルト)など、その国の経済的・政治的な状況によって投資の価値が大きく変動する可能性があります。 特に新興国では、このリスクが高いとされ、投資する際には慎重な情報収集と判断が必要です。カントリーリスクは個別企業の経営状況とは関係なく、その国全体の事情によって発生するため、海外投資や国際分散投資において注意すべき重要な要素です。